C・P・スノー『二つの文化と科学革命』みすず書房
(2013年5月29日)
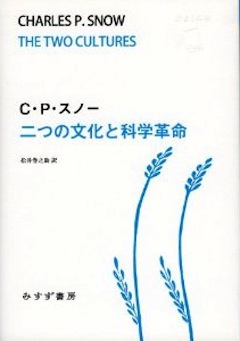 _
_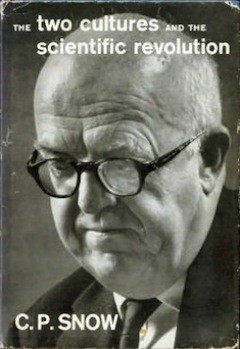
「非科学者たちは、科学者は人間の条件に気がつかず、浅薄な楽天主義者であるという根強い印象をもっている。一方、科学者の信ずるところでは、文学的知識人はまったく先見の明を欠き、自分たちの同胞に無関心であり、深い意味では反知性的で、芸術や思想を実存哲学の契機にだけかぎろうとしている」――1959年の有名な講演「二つの文化と科学革命」において、スノーは科学的文化と人文的文化の深刻な隔絶と対立を問題にし、正常な社会の進歩を阻害しているとする。原子力が産業化されつつあった時代に発表された本著は、文系と理系の分離という現代の問いを端的に示している。
発表者:柴﨑勇人(歴史考古学)、飯澤愁(仏文修士課程)

1章 二つの文化
スノー自身の経験(働く時間は科学者と共有、夜は文学上の友と)【p6-7】⇨「二つの文化」という問題に心を占められるようになる。
Ex)A.L.スミスのケンブリッジでの話【p8-9】
⇩
全西欧社会の人びとの知的生活はますます二つのグループに分かれつつある。【p9】⇨区別できるとは思えない
文学的知識人/科学者(とりわけ物理学者)⇨無理解、敵意、嫌悪、互いに理解しようとしない
文→科
・セッカチでホラ吹きだと考えやすい【p10】
Ex)T.S.エリオット⇨このようなせまく不自然な雰囲気こそが、文学的知識人には気の置けない調子
・浅薄な楽天主義者であるという根強い印象【p12】
科→文
Ex)ラザフォード
・まったくの先見の明を欠き、同胞に無関心であり、深い意味で反知性的であり、芸術や思想を実存哲学の契機にだけかぎろうとしている。【p12】
⇨建設的ではなく、それらの多くは誤解によるもので危険だ
二つの提示
①科学者の楽天主義【p12~p14】⇨個人の体験と社会の体験の混同、人間個人の条件と社会の条件との混同
科学者の大部分→個人の条件が悲劇的であるというそのことだけから社会の条件が悲劇的でなければならないということの理由が出てくるとは思わない⇨希望のきざしといったものが入り込んでくる
人間の孤独の達観→自分自身の悲劇に安心立命し、他人は放っておくという道徳的落とし穴におちいる
⇕
科学者の見届けないではいられない性格 ⇨真の楽天主義→科学者以外の人々が痛切に必要
②文化的知識人への批判【p14~p16】
ある科学者の台詞→ある種の二十世紀の芸術と反社会的なもっとも低俗な表現の間の結びつきを文学的人々がさとるのに非難に値するほど緩慢だったということ
文学は科学とは違い緩やかに変化⇨短い時期(1914年~50年)を取り立てて判断するのは間違い
⇩
現実的な関心を持つ非科学者→これらのことを論ずるには少なくとも三つの文化を考えるべき⇨この議論を尊敬する。

科学的文化=真の文化【p17】
→各領域、お互い同士が完全に理解する必要ない。しかしながら、共通のものが多くある
科学者でたとえ宗教的な人がいても、その人がとる態度は、宗教、政治、階級について同じレッテルを貼られた非科学者よりは、これらを異にする科学者にずっと近い【p18】
⇨科学者は未来を持って生まれている
Ex)J.J.トムスン、リンデマン、アインシュタイン、ブラッケット、コンプトン、バナール、ブローイ、ラッセル、ファラデー、マートン、ロスチャイルドの比較
→同じような反応
⇨「文化」がもっている本当の意味
⇔他の極(文化的知識人)では結局科学の全面的無理解があらゆるものにその影響を与える
→全「伝統的文化」に非科学的な臭気をつけている 一方の極での共感は他方の極の反感を生む
⇨伝統的文化はいまなお西洋世界を支配【p20】
個人としてのわれわれ、人民としてのわれわれ、われわれの社会にとって損失
同時に現実的にも、知識の上でも、創造的な面でも損失
両者における無理解の度合い→ひどい
科学者:伝統的文化との結びつきがか細い(ごく一部のもっともすぐれた科学者を除く)Ex)科学者のディケンズ観【p21】
読書をする科学者が少なく、文学的な人々にとって読んで当たり前の本は皆無
⇨科学者が心理的、道徳的、社会的な生活に関心を持っていないことではない。これもまた伝統的文化によるもの
文学的知識人:みずから自分をむしばんでおり、自尊心が強いため、効果は重大。伝統的文化こそ「文化」のすべてだ
→何も聞き入れない、科学的知識の皆無
他の二律背反→ぶつかり合いにより創造の機会が生まれた ⇔「二つの文化」はその機会さえない
「二つの文化」の分離が英国で際立つ理由【p27】
①教育の専門家についての狂信的ともいえる信頼
②社会の形態を定まったものに固まらせる傾向
→30年近くも話し合いが止まっている状況
⇨抜け出す唯一の方法=教育の再考
教育について【p29~】:英国では教育の再考に半ば諦めムード⇔アメリカ人、ロシア人、スウェーデン人は理解し努力している

2章 生まれながらのラダイトとしての知識人
「二つの文化」の存在→文学知識人は生まれながらのラダイト
伝統的文化→産業革命が豊かなものになるにつれてますますそこから離れた
伝統的文化を永続させるため、科学の大切さを理解しているにもかかわらずアカデミックな人々は何の関係ももたなかった
ラスキン、ウイリアム・モリス、ソロー、エマーソン、ローレンスらさえも恐怖の叫びをあげたにすぎなかった→産業革命を理解した世界で唯一の作家はイプセン
貧しい人々にとっての希望である工業化
貧しい人たちは工場が吸収してくれる限り工場へ行く
⇩
産業革命だけが正しく貧しい人々までに、健康、食糧、教育を拡げた
⇔弊害の一つは全面戦争のために組織されやすい ⇨理解不足が心配

3章 科学革命
[産業革命と科学革命の違い]
○産業革命による変化(18世紀半ば〜20世紀初頭)
・機械化 ・手工業に従事していた女性が工場労働者へ ・農業人口の工業への移行
※ラダイト運動(Luddite movement)… 1811〜1817年ころにイギリス中・北部の織物工業地帯に起こった、工業化による失業への反発としての機械破壊運動
○科学革命…科学の工業への応用→急速で確実
1890年代の大規模な化学・工学工業の時期?
<筆者による定義>
・時期…1920〜30年代→「原始的な粒子が最初に工業的に利用されだした時期」(43頁)
科学革命による産業社会=未曾有の変化
○社会を形成する科学・工業・技術に対する非科学者の無知
神秘的で不可思議な工業製品→科学革命の必要性が理解できなければラダイト運動が起こるのも大いに考えうる
○基礎科学者と応用科学者の差異とお互いに対する無知・誤解
・基礎科学者…左翼的、
・技術者…保守的、「ものをつくることに熱中して、現在の社会秩序というものについては十分満足している」(45頁)
→基礎科学者の矜持…技術や応用科学はスノッブのための二級品
[各国の教育制度の違い]
・イギリス…少数に対する、21歳までのエリート養成→専門教育
・アメリカ…博士課程での厳しい教育
・ソ連…ハイスクールの教育は厳しい→15〜18歳:化学・数学が全員必修
5年制大学の3年次以降での専門的教育→技術者数世界一→ロシア人はイギリス人より科学革命への理解度が高い
e.g. ソ連の小説…技術者への読者の理解を前提としている
○「科学革命の先端に立つために国家が必要とする教育ある男女の数」(52頁)の各国差
ⅰ.「国家が養成できる最高級の科学者」(53頁)…教育に関わらず、自分でやっていくことのできる科学者→米・英・ソの間に差はない
ⅱ.一級の専門家…より広義の専門家。補助的な研究、高級な設計・開発に携わる人々→質では米ソに劣らないが、量はソ連の半分以下
ⅲ.優等卒業試験(tripos=学部・修士試験)程度の水準に教育された層…二級の技術職、行政、人材教育に従事→英国の教育において重視されなかった層
英国においてはこれまで軽視され、劣等と見做されてきたⅲの層が、科学革命が進むにつれ要請されるようになる
・英国人は持ち前の知性で自らを教育し、科学革命を理解し、努力をしてきた→科学革命の潮流においては、それだけでは不十分
凝り固まった教育を打破しなければ、いずれ来る衰亡は免れない

4章 富めるものと貧しいもの
[科学革命の問題]
○科学革命による問題は各国にそれぞれ存在し、他の主要国もその受け入れのために努力をしている→「富めるもの」の中での問題
○科学革命の主たる争点…「富めるものと貧しいもののちがい」→工業国と非工業国の格差=工業化を達成した国はますます豊かになり、それ以外の国は現状維持をするのがやっと
・「貧しいもの」への援助の難しさ…科学革命による社会の変化は西欧の想像力の範疇を超えている
[非工業国の工業化に必要なものは?]
・「明日の楽しみ」(61頁)…人間は皆、明日の楽しみのために驚くほどの勇気でもって努力をする
・「技術とはなにもむずかしいものではなく、人がそれを学んで、結果を予言することのできる人間体験の一分野である」(62頁)
・伝統・技術的背景による西欧諸国のアドバンテージは、西欧諸国のスタートラインでの優位性に加担した→科学の感受性においては、民族の優劣は無い
「貧しいもの」が工業化に必要なのは、科学者・技術者を養成する意志だけである
○「科学革命こそわれわれの行く手に立ちはばかる三つの脅威、水爆戦、人口過剰、貧富の差、から逃れる唯一の方法である」(64頁)→科学革命は資本を必要とするが、「貧しいもの」は資本を蓄積することができない
[工業化に必要な資源]
ⅰ.資金…米ソによる、国家的規模での資金援助
ⅱ.人…ソ連の優位性
ⅲ.教育計画…新しいものを作るための教員(科学・英語)の受け入れ
→欧米諸国が先導し、非工業国の工業化を促さねばならない
○政治的駆け引きに関してどう対処すべきか?
→西欧諸国が先導しなければ共産主義勢力がいずれその役割を担い、世界の覇権を握ることになる

西山雄二
本書は、第二次世界大戦後の冷戦下において、文系と理系の対立を明瞭に宣言した、歴史的資料に値する講演である。ソ連や中国への独特な目配りや進歩主義的楽観論、教育制度への期待などは現在からみると一時代前の話に感じられ、逆に私たち自身の時代状況を内省する材料となる。専門分野に関して言えば、文系と理系の対立は、その後1970年代に「学際性interdisciplinary」が重要視され始める。現代の複合的な課題を解決するためには、あらゆる学問分野を横断する統合的な知が必要であるとされ、現在に至るまでその重要性は増している。また、理系の専門性に関して言えば、科学の専門的知識と市民社会との解離が著しく進展するにつれて、両者の関係を反省的に問い直す試みも洗練される。市民には科学的知識が欠如しているから、彼らを啓蒙することで溝を埋めるという「欠如モデル」は、実は有効ではないことはしばしばある。原発の危険性を正しく認識していても――そもそも、人間の動物的直観によってその危険性は察知されると思うが――、対話の回路がなければ、原発の維持や新設に意思表示し、その展望に参画することはできない。科学者と市民を包括する「社会的文脈」をゆるやかに張り巡らせておくことによってこそ、巨大化して予測不可能な科学技術の方途を適切に統御することができる。
加藤夏海
今回、スノーの『二つの文化と科学革命』の説明を受けてひどく困ってしまいました。理由はこの本が科学的文化と人文学的文化という”二つの文化”について真っ向から問題提起をしていたからです。正直な話をしてしまうと、自分自身理系、文系などという区分になんの興味もおいておらず、一応文系でありますが理系分野(特に建築、土木、農学)にとても関心があり、理系の友人にどんなことを勉強しているのか聞いては一人で楽しんでいるといった次第であるのです。ただ、西山先生もおっしゃったように3.11以降、市民は科学に対し不信感を覚えており、このことは理系に対し関心や憧れを持つ私も含まれています。ここで、スノーの打ち出した二項対立というのは利いてくるのではないかと思います。つまり、科学の対局するものが人文学なのであれば人文学はかなり客観的に科学をとらえることができるのではないかということです。そこで人文学が科学を理解する必要性というものが見えてきますが、おそらく想定できることは人文学者同士の意見の不一致でしょう。この不一致が市民を余計混乱させてしまわないか気になるところですが、意見の不一致というものは多様性とも置き換えられ、トランスサイエンス問題に関してはこうした多様性が重要になってくるだろうと考えます。
川野真樹子(表象修士1年)
大江さんが最後におっしゃっていた「科学の発展は福祉のためになるという考え方は今でもまかり通っている」という言葉が印象に残っている。スノーがこれを書いた時には、先進国である西洋諸国がアジアやアフリカに科学を教えてあげなければいけない、という上からの意識が強かったのではという指摘が多くの方から出ていた。現代では日本や韓国、中国といった国々がその当時の西洋諸国の立ち位置にいるのではないだろうか。これらの国は、技術を中近東やアフリカに輸出しようと競争している。あるいは砂漠化の進む地域に井戸を掘ったり、植林をしたりといった活動を行っている。これらすべてが上から目線で行われる(「教えてあげなきゃ」という意識を持っている)わけではないと思うが、どこかで自分たちのほうが技術が進んでいるという優越感を持っているのではないだろうか。実際に、私自身、後進国に井戸を作ったり植林をしたりするための技術を伝えるのはよいことだと考えていた。しかし、それが自己満足になっていないかどうか、あるいは本当に相手に必要なことなのか、一度立ち止まって考えてみる必要があるのかもしれない。そういう意味で、今回のスノーの文章は現在にも応用できる部分があるのではないだろうか。
倉富聡
ゼミ中にも指摘さていたが、やはり私はC.P.スノーに同意できる点は少ない。たとえ時代的な背景を鑑みても彼の論理はあまりにもイデオロギー的で、素朴すぎる。恐らく彼は自然科学と文学(人文学)の中間的立場として(彼自身はそのように自己を相対化できていると思っているのだろう。)近代化における科学の問題に切り込もうとしたのであろうが、イデオロギー的な観点を見落とした時点で試みとしては失敗ではないだろうか。また、彼が科学と文学の相違を明らかにするために提示した「二つの文化」という概念も、文学も科学も関係なしにあらゆる学問において隣接領域のことすらお互いに理解できていない学問的「分業」が近代化とともに急激に進んでいったことを踏まえられていない。このことに関しては66年も前の1893年に社会学者E.デュルケームが『社会分業論』で指摘している。1959年においては最早自然科学と文学の断絶どころではなかったと推測される。しかし、そのような彼の主張から見えてくることもあった。それは、理解ではなく、想像力の「欠如理論」である。彼が明示した科学者も文化的知識人も、どちらも社会における所与のものへの前提的発想が欠如している、つまり「想像力」が欠如していることである。想像力を理解不可能なものへの志向性、特に「他者」への志向性として想定すると、彼らはどちらも社会的「想像力」が欠如している。我々は他分野への不理解や確執よりも、この社会的「想像力」をいかにして養うかを議論しなければいけないのではないだろうか。
飯澤愁(仏文修士1年)
科学者は民主的であり、人種的な偏見の少ない「人種」であるとし、科学的知識と人間性の連関を素朴に主張するスノーの文章からは、たった半世紀程度前の世界を席巻する進歩主義の風潮が伝わってくる。ではその思想はその時代毎に特有のものか。大江さんが仰っていたように、現代のスノーは少なからず存在するだろう。局所化し、専門化を重ねる「二つの文化」の深刻な断絶に警鐘を鳴らす慧眼の一方で、客観的パースペクティヴを得ることの難しさもまた、この文章を通じて学ぶべきことであるように感じる。また、柴崎さんが述べた受験勉強の知識と大学において必要とされる知識の乖離についてであるが、私は興味を持てない科目を全て捨てるつもりで大学受験に臨んだので、受験勉強に割いた1年は現在の自分の礎を築くための、非常に有用な期間であったと感じている。故に、一方で高校の指導要領や受験で要請される解答法に対して少なからず疑念を抱いたのも事実だ。物議を醸した昨年のセンター試験であるが、解釈・感想を一元化し、出題者の意図を推し量ることに終始しなければならない国語の問題は、国語力等というものと関係があるといえるのだろうか。そして、名筆家と知られる小林秀雄の、本物の随筆を前に閉口せざるを得ないような読解力しか与えられない指導要領は果たして何のためのものなのだろうか。
大江倫子(仏文修士2年)
物理学者で小説家の著者による文理二つの文化の均衡ある協調とも読めた前半から一転して、後半では冷戦イデオロギーを盾にとった素朴な産業主義推進で終わってしまう1959年のテクストである。無批判な産業化肯定、一方的な論理展開、時代の限界、ナショナリズムの介入、環境主義の不在などが聴講者から指摘された。これまでに見てきたような技術に対する短絡的な反応や悲観主義に加えて、これもまたもう一つの極としての、技術との自由でない関係であり、技術の本質の伏蔵の様態である。現代でもなお根強いこうした産業主義的主張に対し、人文学は何を提起することができるのか。各自がその固有の用立てを自覚した上で、それを他者や事物との共生のうちに実現に努めること、これを熟考することである。そのような思索は行動に先立つ前奏のようなものにすぎないのではなく、それ自体決定的な行動なのである。そもそもそういう行動によって人間の世界との関係 が変化し始めるのである。

