不可視の禍との戦い――アルベール・カミュ『ペスト』(2012年5月16日)
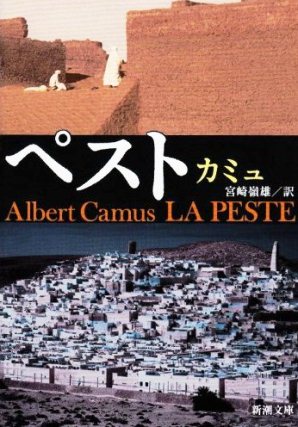
カミュの傑作『ペスト』(1947年)は、アルジェリアの要港オランを襲ったペスト禍の物語。オランが閉鎖され外界から隔離されるなか、医師リウーや新聞記者ランベール、司祭パヌルーらが目に見えないペストと闘う、破局的な寓意小説。この小説に描かれていることは、福島原発周辺が立ち入り禁止区域になるなかで、不可視の放射能と闘わざるをえない現状と重なり合う。リウーは言う、「ヒロイズムの問題ではないんです、ペストと戦う唯一の方法は誠実さなのです」、と。
発表者:小玉司(仏文博士2年)、山下竜生(仏文3年)/コメント:田中麻美(仏文4年)
ゲスト:高榮蘭(日本大学准教授)
引用は新潮文庫(1969年刊行)の宮崎嶺雄訳からおこない、引用頁数を丸括弧内に記す。

1.主要な登場人物
リウー:三〇歳半ばの医者。ペストの出来事の語り手(厳正な歴史家を装う記述者。犠牲者に与した善意の証言者)。病の妻を山間の診療所で滞在させる。保健隊の一員。
タルー:身分不明の若者。オランの町に着いてからの日々の出来事をノートにとる(些細な事象を記録し、物語のないものの物語を描く)。保健隊の発起人だが、オラン市の解放直前にペストで死亡。リウーと固い友情を結ぶ、その分身的存在。「ひとは神なくして聖者になれるか」(379)と自問しつつ生きている。リウーへの告白によれば、彼は判事の父の裁判を傍聴した際、死刑判決を下す父に失望し、被告に人間的連帯を感じて家出し放浪の旅に出た。
パヌルー:博学かつ戦闘的なイエズス会神父。ペストの到来をキリスト教的視点から説き、ペスト禍を神の愛ある罰と解釈。保健隊の一員。治療を拒否したまま、「疑わしき症例」により死亡。
ランベール:若い新聞記者。パリからたまたまアラブ人の生活状況の取材のためオランに来ていた。ペスト蔓延に伴う市門の閉鎖に憤り、恋人のいるパリに帰還しようと保健隊で活動しつつ画策。しかし、脱出の手筈が整ったとき、「ひとりで幸福になること」(307)を恥と考え、オランにとどまる決意をする。
グラン:市役所の臨時補助吏員。保健隊において幹事的役割を担う。「市臨時補助吏員という、つつましやかでしかも不可欠な職務を営むためにこの世に生まれてきたような」存在(66)。
コタール:犯罪者。非常事態下では逮捕の心配がなくなるため、ペスト禍を歓迎。「ほかの人々以上にわれわれが理解しようと試みる価値のある」人物(291)
オトン:予審判事。息子をペストで亡くす。
ペストによって変貌:パヌルー、オトン、ランベール、コタール
ペストによって変貌しない:リウー、タルー、グラン
2.『ペスト』の構成とあらすじ
1章 語り手によって通常のオランの描写
4~5月 血を吐きながら死んでいくネズミの出現から始まり、次に第一の犠牲者が
でる。しかし、市庁は何の対策や決定を為さないまま時間が過ぎる。5月になり、死亡率が増加し始め、市庁は遂に「ペストの流行」を宣言し、市を閉鎖する。
2章 5~7月 ペストが町に蔓延し始め、住民たちを襲い始める。市が隔離されることによって、彼らは追放生活や別離を身をもって体験することになる。そのような中、タルーの提案でペストに対する有志の住民による保健隊が結成される。しかし、ペストの勢いは夏の到来によりさらに増すことになる。
3章 8月 夏の暑さが高まるなか、ペストの流行が頂点を迎える。会話の場面はほとんどなく、ペストによって混乱していく孤立した街の情景が描かれていく。(埋葬・死体焼却炉・別離による人々の苦悩)
4章 9~12月 ペストは依然としてその猛威をふるい続ける。ペストと戦い続ける人々は疲労困憊するが、それでもできることをと、ひたむきに働き続ける。ペストはその症状を変化させ、腺ペストから肺ペストへと移行していく。死亡者は絶えることはないが、この頃になり血清のより回復する者が徐々にでてくる。統計もその事実を示すようになる。
5章 1~2月 予審判事のオトンやタルーにもペストが襲いかかる。死者は出るものの、しかし、勢いは少しずつ減少。疫病は収束の方向へと向かい、オラン市が開放される。
エピローグ:語り手がリウーであったことが明かされる。そこでリウーはペストに対する勝利が最終的なものではないことを述べる。
3.ペストが表象するもの
1、 現実的レベル
鼠、症状、病気の進行、隔離された市、隔離された同胞たちなどの客観的な描写。ペストのすべての医学的、臨床的、人間的、社会的な描写。
2、隠喩レベル
ペストは暗示的に、戦争、フランスのドイツ占領期間におけるレジスタンスを想起させる。(⇔作家カミュ自身がロラン・バルトへの手紙の中で、レジスタンスを意味するために書いたものではないと否定。Cf. Albert Camus, Œuvre complète II, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 2006, pp.1207-1208.)
3、 抽象的レベル
ペストは非人間的な災禍であり、我々を悲惨の中に突き落とす。絶対的な悪の象徴。
抽象との戦い 「ペストというやつは、抽象と同様、単調であった。」(132)
「抽象と戦うためには、多少抽象に似なければならない。」「一人一人の幸福とペストの中小との陰鬱な戦い」(133)
Cf. ロラン・バルトの批判 「連帯というモラル──熟慮された政治的内容の連帯性──は事物の悪とたたかうには十分でありえるが,人間の悪とたたかうには十分であろうか。「歴史」には非人間的な災厄ばかりではなく,戦争や圧政といった非常に人間的な悪もある。それらの人間的な悪は災厄以上ではないとしても,同じくらいに殺人的だ。それならば,医師であるだけで十分だろうか。自分の番として死刑執行人になることを怖れ,傷の元凶たる行為を攻撃しないで,傷を手当てするだけで満足するべきだろうか。攻撃してくる人間を前にして人間は何をなすべきだろうか。」
4.天災と人間
「彼らは人間中心主義者であった。つまり、天災などというものを信じなかったのである。天災というものは人間の尺度とは一致しない、したがって天災は非現実的なもの、やがて過ぎ去る悪夢だと考えられる。ところが、天災は必ずしも過ぎ去らないし、悪夢から悪夢へ、人間の方が過ぎ去っていくことになり、それも人間中心主義者たちがまず第一にということになるのは、彼らは自分で用心というものをしなかったからである。わが市民たちも人並以上に不心得だったわけではなく、謙虚な心構えを忘れていたというだけのことであって、自分たちにとっては、すべてはまだ可能だと考えていたわけであるが、それはつまり、天災は起こりえないとみなすことであった。」(56)
抽象的な数字 「歴史に残された約三〇回の大きなペストは、一億近い死亡者を出している。しかし、一億の死亡者とは、いったいなんだろう。戦争に行ってきた場合でも、一人の死者とは何であるかをすでに知っているかどうかあやしいくらいである。それに、死んだ人間というものは、その死んだところを見ない限り一向重みのないものであるとなれば、広く史上にばらまかれた一億の死体など、想像のなかでは一抹の煙にすぎない。」(57)
地震と病疫 「まったく、こいつが地震だったらね! がっと一揺れ来りゃ、もう話は済んじまう……。死んだ者と生き残った者を勘定して、それで勝負はついちまうんでさ。ところが、この病気の畜生のやり口ときたら、そいつにかかっていない者でも、胸のなかにそいつをかかえているんだからね。」(166)

5.ペストの公式発表
①県知事:「まあ、早いとこすますとしましょうや。ただし目立たないようにね。」(70)
②医師リシャール:「はっきり法律によって規定された重大な予防措置を適用しなければならなぬ。ペストであることを公に確認する必要がある。ところが、この点に関して確実性は必ずしも十分ではないし、したがって慎重考慮を要する。」(74)
③リウー:「問題は、法律によって規定される措置が重大かどうかということじゃない。それが、市民の半数が死滅させられることを防ぐために必要かどうかということです。」(74)
「しかし、私としては、それがペストという流行病であることを、皆さんに公に認めてくださることが必要なんです。」「問題の設定が間違っていますよ。これは語彙の問題じゃないんです。時間の問題です。」(75)
「つまり、われわれは、この病があたかもペストであるかのごとくふるまうという責任を負わねばならぬわけです。」「われわれはあたかも市民の半数が死滅させられる危険がないかのごとくふるまうべきではない。なぜなら、その場合には市民は実際そうなってしまうでしょうから。」(76)
→行政の優柔不断、責任の所在への問題意識
6.別離と追放(96-110)
「〔市門の閉鎖によって〕そんなつもりのまったくなかった人々が突如別離の状態に置かれた。」(96)
「だしぬけの、つなぎ目のない、将来の予想もつかぬ別離にわれわれはただうろたえさせられ、今なおきわめて近く、しかもすでにきわめて遠いその面影の思い出に抗するすべも知らぬ状態で、いまやその思い出がわれわれの日々を占領していた。事実上、われわれは二重の苦しみをしていた――まず第一にわれわれ自身の苦しみと、それから、息子、妻、恋人など、そこにいない者の身の上に想像される苦しみと」(101)
「市民一同は、別離の時間を計算するという、あるいは生じえたかもしれぬ習慣を、いち早く、公開の場所においてさえ、捨ててしまった。」(103)
「なんの役にも立たぬ記憶を抱いて生活するという、すべての囚人、すべての流刑者の深刻な苦しみ」(104)
「流刑といっても、大多数の場合、自宅への流刑」(105)
7.ペストに立ち向かうリウー
タルーはいった。「なぜあなた自身は、そんなに献身的にやるんですか」
〔…〕「さしあたり、大勢の病人があり、それをなおしてやらねばならないんです。そのあとで、彼らも反省するでしょうし、僕もそうするでしょう。しかし、最も急を要することは、彼らをなおしてやることです。僕は自分としてできるだけ彼らを守ってやるんです、ただそれだけです」(185-186)
「このペストがあなたにとって果してどういうものになるか」
「ええ、そうです」と、リウーはいった。「際限なく続く敗北です」(188)
〔リウー〕「今度のことは、ヒロイズムなどという問題じゃないんです。これは誠実さの問題です。こんな考え方はあるいは笑われるかもしれませんが、しかし、ペストと戦う唯一の方法は、誠実さということです」
「どういうことです、誠実さっていうのは?」と、急に真剣な顔つきになって、ランベールはいった。
「一般的にはどういうことか知りませんがね。しかし、僕の場合には、つまり自分の職務を果たすことだと心得ています。」(245)
「絶望に慣れることは絶望そのものよりもさらに悪い。」(268)

8.パヌルー神父の変化
①一回目の説教(134-) 五月末の土砂降りの日。信仰心に厚いわけではない多数の一般人が参加。
「忠告や友愛の手が皆さんを善に押しやる手段であった時期は、もう過ぎ去りました。〔…〕あらゆるもののうちに善と悪とを置き、怒りとあわれみと、ペストと救済とを起きたもうた神の慈悲が、ついに明らかに顕著されているのでございます。皆さんを苦しめているこの災禍そのものが、皆さんを高め、道を示してくれるのであります」(143) ペスト禍=神の愛ある罰
→オトン判事の子供の死亡に衝撃を受ける。無垢な子供の苦しみに納得ができない。
②二回目の説教(325) 十月のある大風の日。この種の催事は新奇さを失い、聴衆の列はまばら。信者は「ミサに出かけるよりも、好んで災厄除けのメダルや聖ロックのお守りを身につける」(326)だけ。
パヌルー神父の語り口の変化:「あなたがた」→「私たちは」
前回の説教は真実だが、「慈悲の心なく考え、かつ、言った」ことを反省。
「皆さん。その時期は来ました。すべてを信ずるか、さもなければすべてを否定するかであります。そして、私どものなかで、いったい誰が、すべてを否定することを、あえてなしうるでしょう?」(331)
→神への愛は困難な愛 →神への立ち向かい方が変化:恩寵への信を発見。能動的運命論。
9.リウーの無神論的挑戦
少年の死(315)≠「ある意味で抽象的な公憤」
パヌルー「まったく憤りたくなるようなことです。それはつまり、それがわれわれの尺度を超えたことだからです。しかし、おそらくわれわれは、自分たちに理解できないことを愛さねばならないのです。」(322)
リウー「子供たちが苛まれるようにつくられたこんな世界を愛することなどは、死んでも肯じえません。」
パヌルー:人類の救済
≠リウー:人類の健康「われわれはいっしょに働いているんです。冒涜や祈祷を越えてわれわれを結びつける何ものかのために。それだけが重要な点です。」
「天災のさなかで教えられること、すなわち、人間のなかには軽蔑すべきものよりも、賛美すべきものの方が多くある」(457)
リウーとパヌルーは無神論と有神論では反対だが、行動上の結論は一致
=カタストロフィ状況下において、神の無用を証明し、人間の連帯の根底的な力を肯定

西山雄二
カミュの『ペスト』の文学的卓越もさることながら、高榮蘭氏の鋭い指摘でより充実した回となった。文学作品を誠実な仕方で読解し探究する研究者――しかも異国から来た日本文学研究者の倫理的態度から多くを学んだ。カミュ作品における現地のアラブ人の不在、政治とメディアの言語に抗する文学言語、特異かつ普遍であろうとする文学作品の読解倫理など、本演習に不可欠な問いが提起された。『ペスト』は第二作目と思えぬほどの傑作で、それまでのカミュの分身のような登場人物が語りの多数性を際立たせる。アルジェリア原住民の悲惨を告発していた若き新聞記者カミュ=ランベールは「ひとりで幸福になることは恥」と宣言する。ナチス占領の不正義に抗するレジスタンスの闘士にして実存主義的な作家カミュ=医師タルーは無垢の子供が苦しむこの世界の不条理に立ち向かい、「永遠の敗北」を背負って反抗を止めぬ。解放後の粛清を目撃し、政治的殺人(死刑)を否定するカミュ=タルーは死刑判決を下す父を拒絶し、死に逝く者への人間的連帯を表明する。記録文学風の体裁だが、リウーとタルーの手帳からなる複数性も単線的な物語を断片化する装置として機能する。カタストロフィを前にして安易な語りは許されず、安定的な語りの立場が揺すぶられた以上、まずは語り口の問いや躊躇から始めなければならない――『ペスト』のような作品を範例としつつ、3.11以後、文学の力を召喚すること。
田中麻美(仏文4年)
時代も場所も越えて普遍性を持つ作品こそが読み継がれる名作であるならまさしくこの「ペスト」はそういった普遍性を持つ、まさに名作である。競技場が隔離場となり集団生活を営む様子は、さいたまスーパーアリーナが避難所になったことを生々しく想起させるし、「仕事は危険の度合いに応じて賃金を支払われていただけに、なおさらのことであった。」(261)などの記述は、福島の原発で作業に当たれば日給が10万出るなどの噂があったことを思い出した。これが浮遊するシニフィアンの力なのかと、西山先生の解説を聞いて感動した。人間の連帯とは、誠実とは何なのか。3.11のことを思うと、これらの意味を深く考えてしまう。しかし作中では、リウーも保健隊も大変な努力を尽くすが、この物語の終局はペストが勝手に勢いを弱め、平和が戻るという具合である。私たちは、ただ災禍に翻弄されることしかできない弱い存在なのかもしれない。そうであっても、連帯することや非常時でも誠実であることは最悪の状況下で、尊厳を失くすことなく生き残る為に必要なことであると思った。
柳沼伸幸(法学2年)
「死んだ人間というものは、その死んだところを見ない限り一向重みのないものであるとなれば、広く史上にばらまかれた一億の死体など、想像の中では一間の煙にすぎない」――3.11以後この文句を自分は肌で感じた。いや、感じている。3.11当時福島に居た自分ですらそうなのだ。もちろん、現代の技術で我々は画像や映像によって人間の死に迫ることができる。できるようになったと思っている。しかし、やはり死に近づいた気になっているだけなのだ。マスメディアが我々に提供する死は、それが現実を映したものであっても我々には具体的には感じられないように思う。結局は「どこかで起こっている誰かの死」として抽象的に感じてしまうのだ。むしろ具体的に見える情報が大量に与えられることによって死を抽象的に受け入れてしまうようになった。直接対峙していない現実は抽象的な物語と化してしまう。しかし、今回「ペスト」を3.11のメタファーと見て読解したが、物語の中のその具体的で凄惨な内容が具体的に描かれるほどに喩えられた現実の惨状に肉迫するように感じた。本来抽象的である物語の切実さが現実へと切実に迫るのだ。物語は下手な現実よりもよほど具体的で現実的である。これも「空白」や「媒体」の機能でしかないと指摘されるかもしれない。だが、自分はそれを承知の上でこれこそが文学の意義だと主張したい。
藤井淳史(社会学2年)
カミュの「ペスト」のなかでは天災に直面した人間の姿が如実に表現されていた。ここから、解釈のレベルでは今回の東日本大震災に結び付けられる部分も多々あったように思う。しかしながらご指摘にもあったように、これを現実のレベルで安易に結び付ける――現実を解釈に合わせる――ことはしてはならないことだろう。授業でも教わったように「ペスト」は浮遊するシニフィアンとして活用可能だが、適切に扱わなければステレオタイプを量産するただのボックスになってしまう可能性もある。「ペスト」と東日本大震災を結び付けて考える際に、確かに類似している部分はあるが、逆に違っている部分もたくさんあるはずである。そこをより掘り下げていくことが今回の東日本大震 災を正確に歴史に配置するうえで大切になってくるのではないだろうか。また小説とはもともとつまらない説という意味があったそうだが、メディアや行政等の発表では反映されない――数に還元されてしまう――もういない人々の声を残された人々へ伝えるツールとしての一面があることを知り、小節の新たな可能性を見つけることができた。
内田森太郎(哲学4年)
今回の講義について特に重要だと感じたのは、「ペスト」という作品に現実を過剰に投影させることでその作品のアイデンティティを損なってしまいかねない、という高先生の指摘だった。ペストという事件はメタファーとして読むことが通常の読解であるが、現実に抱えている大きな問題を念頭に作品と向き合うことが読解に与える影響は大きい。自分の読みたいものを求めて本を読んでしまうと、結局既に経験したものを本に見つけていくだけで、新たな発見が得られなくなってしまう。他者の思想に触れるに当たっては自分の今持っている情報を整理して、新たな視座を獲得することが重要であるだろう。では今この「ペスト」を読んで得られることはなんだろうか。私は特にリウーの思想に注目したい。圧倒的な不条理に直面した時に、それまでの自分が持っている価値観や道徳に従って(こだわって)行動することは確かに理性的であるし、合理的ではあるだろう。ただそうした功利主義的発想は緊急時においては役に立つものだが、現に打ちひしがれ、何かしらの変化を覚えた人間にとって、事件以前の秩序価値観を保ち続けようとすることは果たして意味のあることだろうか。非日常を体験し、日常をどう生きるかが重要なトピックとなった今現在に照らして考えると、むしろ感情を取り込み、未来を見据えた新しい秩序を意識した思想が必要であると思う。
聡倉富(社会学3年)
「ペスト」はまさに「浮遊するシニフィアン」「ゼロ記号」である、「我々が今経験している東日本大震災を、何でもかんでも『ペスト』に当てはめてはいけない。」、この二つのことが議論で最も印象に残った。そして、レジュメのブログ記事からの引用文、「カミュの『ペスト』には天災のすべてが載っている」も同様に印象的であった。この三つのことは我々に非常に重要なことを示唆してくれている。それは、学問による視座の獲得と、単なる定型文の作成とを取り違えてはいけないということである。この講義で我々は現前するカタストロフィを受け止めようと試みている。カタストロフィを目の当たりにしいまだその渦中にいる我々が、それを何とか受け止めようと参加したこの講義で、結局はゼロ記号に当てはめて型通りの解釈をしただけになってしまっては意味がない。この授業で手に入れた様々な解釈法、人類がどうカタルシスを受け止めてきたかを学び、新たに自分たちで解釈しなおしていかなければならない。この講義に参加する者として、襟を正された思いだ。
大江倫子(仏文修士1年)
小学生のころ父の書棚から抜き出して読みふけった本書への、私の独異な絆はどうなっているのか。第1章で知事に対し「市民の半数の死滅」を三度言明し、つねに眼前の事実に密着してそのラディカルな誠実さを実践するリウーは、小学生の憧れのロールモデルとして、また専門職の現場主義として今なお十分影響力をもつだろう。しかし第2章で語り手が告白するように、「世間に存在する悪はほとんどつねに無知に由来するもの」であるとすれば、その誠実さもまた「悪意と同じくらい多くの被害を与えることがあり得る」。これは、私たちは眼前の特定の被災者に専心することで、つねにその背後の無数の被災者を犠牲にしているという知でもある。ここで語り手はむしろ観念論者タルーを呼び求めているのだろうか。第3章ペストの猛威のさなかの絶望状態は、「無気力状態」であるとともに、「最も個人的なものの断念」として記述されているが、不条理のうちに生きる者について、卓抜な指摘である。私たちは不条理に遭遇するたびに、その断念を一歩進めているのだ。第4章リウーとタルーの友情の成立において、タルーはこの不条理の規定を試みている。「誰でもめいめい自分のうちにペストをもっている」「自然なものというのは病菌なのだ」。終章でタルーは喪われ、リウーは孤独のうちに残される。不条理がその終末を完遂するかのように。

