不幸の予言を信じて行動するために――ジャン=ピエール・デュピュイ『ツナミの形而上学』(2012年7月4日)
破局はなぜつねに「想定外」とみなされ、不幸の予言は聞く耳を持たれないのか。18世紀リスボン大地震からアウシュヴィッツ、ヒロシマ・ナガサキ、9・11、スマトラ沖地震という歴史的経験の考察を通して、「破局の未来」にどう向き合うかという問いを考察。
テクスト:ジャン=ピエール・デュピュイ『ツナミの形而上学』岩波書店
発表者:村上翔太郎(仏文2年)、久津間靖英(仏文修士2年)
『ツナミの小形而上学』、「始まりの時 未来を悼む」(3-18頁)担当:村上翔太郎

今日の危機(3-4頁)
人間中心の考え方によって、人間という種が消滅の危機に瀕している
システム化した(社会を全面的に破壊する)破局(カタストロフィ)の影
しかし、現在の人間たちが人類に対して多大な責任を負っているという考え方を信じ、人類は自分自身の救い手となる義務を負っていると信じることで、人類は破局へ向かう動きをいっそう早めてしまう可能性が高い
ギュンター・アンダースの寓話「ノアの不幸の予言」(4-7頁)
破局の予言者が陥る悲劇と、そこからの脱出方法を描いている
悲劇=不幸(破局)を予言しても人々は聞き入れないこと
信念の体系(破局は訪れず今までどおりが続くという見方)は揺るがない。 例:アウシュビッツ
予言によって知識がもたらされても、受け入れて不幸を回避する行動にいたるには不十分⇔予防原則(化学物質や遺伝子組換えなどの新技術などに対して、環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす仮説上の恐れがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも、規制措置を可能にする制度や考え方)を信じる人たちは、不幸についての知識を得れば人間は行動できると考える←しかし、知識がいくらあっても人は不幸を避けようとは動かない
では、脱出方法、すなわち聞き入れさせる方法とは?(7-10頁)
西欧哲学への批判:例 ロールズ『正義の理論』~世代間にまたがる正義には、正義の原理は適用されない
←異なる世代同士の間には相互関係はありえない
相対的に弱者たる先行世代が未来の世代を優先して保護しなければならないという矛盾
では、退行思想を抱けばいいのか?
←否。進歩か退行かという二者択一は無意味であり、複合的なアプローチが必要~
現代は最も胸躍る時代(進歩している)でも、最も恐るべき(退行している)時代でもある、と見なければならない
ロールズはどの世代も平等だとするが、道徳の観点からすると、世代は平等ではない:道徳的地位は未来の世代ほど高い(過去の世代がしてきたことの意義を知っているから)
未来の世代に責任があると考えても、哲学的な袋小路へと追い込まれる 未来世代の幸福に現在の世代が関心を寄せなくてはならない理由があるとは確信できないため
→現在の世代が守るべきは現在の世代自身である
現在の世代が未来の破局を招くとすれば、現在の世代の歩みまで(「遡及的に」)意味がなくなってしまう
西欧哲学以外に解決への手掛かりはあるのか?(10-14頁)
円環的な時間概念(アメリカ先住民の箴言「大地は子孫が貸してくれたもの」)
の有用性:直線的な時間概念の世界に揺さぶりをかけることができる
現在の世代の行いの意味は未来がどうであるかによって規定される、と考えることが出来る
アンダースの寓話に立ち返ってみる(14-16頁)
ノアが未来の洪水の死者を今悼むことで、時間を円環化している
しかし、人々は破局の予言を受けても信じようとはしない(破局が訪れなかった時、予言を聞き入れたからだとは考えない)
不幸の予言がはらむ逆説~予言の内容が不可避的に生じないと信頼されないが、内容が生じてしまうのでは、不幸を回避するという目的が果たせない。→破局が起きないようにするための意識と行動を呼び起こすことが肝要
一般的に、告げられた未来は、実際の未来とは一致せずともよいし、予測は実現しなくともよい(現実化せず、現実化しないままでいる可能性にすぎないため)
時間は枝分かれし、ツリーの形状を取る。
しかし、アンダースの寓話に示されている時間の見方は、円環状であり、過去と未来がお互いを決定し合う
→従って、予防というやり方は取れない(予防とは直線状の時間概念でしか成立しない)
必然性は、出来事が起きたという事実によって事後的に作り出される
破局の時代に適した用心の基礎となるべき形而上学は、破局の後に続く時間に自らを投影し、その破局の中に必然であると同時にありそうにない出来事を遡及的に見出すような形而上学
そしてその形而上学は、悲劇の人物像を基礎づける形而上学として、過去の文学においてたびたび出てきている
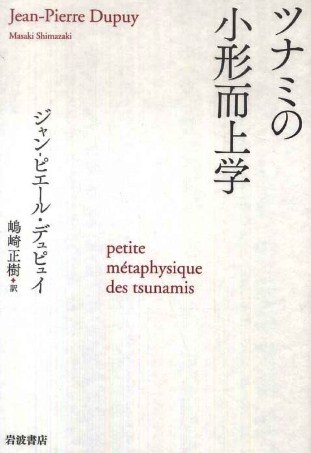
ジャン=ピエール・デュピュイ『ツナミの小形而上学』(61−125頁)担当:久津間靖英
悪を自然のもとに返す(61頁)
・悪の自然化
ルソーによる人義論 の限界「ルソーが始めた思想運動はつまるところ、それが人間に負わせた過剰なまでの責任の重さによって崩壊するしかなかった」(63頁)
現代の悪(破局)は人間がその責任を負うにはあまりにも大きい
悪が巨大となった今日では、悪の「理由(なぜ彼らはそうしたのか)」を道徳や倫理で説明することはできず、その「原因(どのようにして彼らはそうするにいたったのか)」しか、もはや理解することができない。
理由:人間の側(個人の自由意志のレベル)
原因:自然の側(個人の意志を超えたレベル)
→再び悪の自然化へ(「神義論の悪魔的分身」)「それは、私たちが被る出来事の一部、とりわけ私たちを打ちひしぐ不幸の責任を、再び自然に負わせることに帰着する」(64頁)ex. カント、マルクス
ニューヨーク(68頁)
・黙示録(啓示をもたらすもの)としての9.11→9.11によって、悪の一面が姿を現した
・ルソーの自己愛と自尊心
自己愛:個々人を自分だけで完結させるもの。「自分を観察する唯一の観客、自分に関心を寄せる世界で唯一の存在、自分自身の価値を判断する唯一の判断者としてみずからを眺める」(71頁)
自尊心:他者に向ける視線、嫉妬、今ある自分の殻を破りたいという欲望。「自尊心が生じるのは、他者が私の十分近くにいて、私とその者が視線を交差させることができ、互いに相手と自分自身との比較を始められるときである」(71頁)
→自己愛が自尊心へと変化したとき、人類に悪が誕生する ex. 犠牲のメカニズム
・対象から障害へ
ある対象をめぐる争いから、目の前の障害の排除や障害に対する憎悪へと向かう意識の変化
「この段階にいたると、彼ら[争う者たち]はすべてを吹き飛ばしてしまうことさえ厭わなくなる。自分自身や、まわりの世界もろとも」(75頁) =9.11のテロリストたち
→テロリストたちの憎しみの人間的な説明(彼らがテロを行った理由の説明)はできない
アウシュビッツ(79頁)
・『イェルサレムのアイヒマン』
アイヒマンの悪意ではなく、thoughtlessness 「短見、想像力の欠如」の記述
アーレントの意図:起きた事象の「説明」ではなく、そこから学ぶ「教訓」
「その過ちについては、犯罪にいたらしめる原因のメカニズムにではなく、その者が犯罪を行う上で抱えていた理由のうちに探る必要がある、と[アーレントは]いうのである」(82頁)
・「ここに、なぜという言葉はない」(アーレントの意図に対するデュピュイの意見)
「ところが[アーレントのいう]その理由はないも同然なのだ。なぜなら、被告の自由とその行為の結果との溝は、ゼロと無限大の違いにも等しいからだ」(83頁)
→なぜアイヒマンがそれを行ったのか(理由)を説明することはできない
ランズマン『ショアー』:供犠を意味する「ホロコースト」という言葉への拒絶
「私[ランズマン]がその名称を選んだのは、その意味するところが理解できなかったからだ」(86頁)
ヒロシマ(91頁)
アンダース:人の倫理、合理性を超えた悪として、アウシュビッツとヒロシマを関連づける
←原爆投下を必要悪と考える(=倫理や合理性によって原爆を説明する)人々の反感
ヒロシマやナガサキの合理性や倫理性を問うこと=原爆を目的のための手段として考えること
→原爆はあらゆる目的を凌駕する(その力が人間の力を超えている)ので、合理的や倫理的に問いをたてても答えを出すことはできない。
なぜ原爆が使われたのか?→原爆が存在したから
なぜ原爆を使うことの道徳的な恐怖は見過ごされたのか?→「なんらかの閾を超えてしまうと、私たちの行為に及ぶ力は、私たちの感じる力、想像する力を際限なく超え出てしまうのである」(96頁) ←アーレントのいう短見、想像力の欠如
未来の破局という問題
犠牲者の混同(107頁)
・三種類の犠牲者と秩序
自然災害の犠牲者‐自然の秩序/虐殺の犠牲者‐暴力の秩序/供物としての犠牲者‐聖なるものの秩序
「私たちは今や次のように推測することができる。ツナミという形象が、現代の道徳的一大破局に共通するリファレンスとして使われているのは、私たちが、そのきわめて宗教的な側面の考察を拒否しているからなのではないか、と」(114頁)
ex. 9.11テロ後「聖地」と称される跡地、ナチスの「ホロコースト」
・暴力の自己外在化
ユベール、モース:供儀者、犠牲、神の混同が供儀の本性そのものをなしている(cf. 「供儀の本性と機能に関する試論」 )
ジラール:聖なるものとは人間の暴力が人間自身の外に置かれたものをいう、供犠は暴力に暴力を捧げる行為(cf. 『暴力と聖なるもの』 )
→神を暴力に置き換える。「聖なるものへと物象化された暴力は、普通の暴力がその聖なるものに捧げる「捧げ物」を糧とする。暴力は象徴的・制度的な形式へとみずからを外在化することができる」(112頁)→暴力の自己外在化

未来を聖なるものにする(116頁)
・覚醒した破局論
catastrophisme éclairé「覚醒した破局論」
éclairer「~を照らす、~を明らかにする、~を啓蒙する」
覚醒した破局論とはネガティブな考え方ではなく、破局を明らかにされたもの、必ず訪れるものととらえ、それに向き合うポジティブな姿勢を意味する 。
「覚醒した破局論は一つの狡智である。それは暴力を一つの運命、つまり意図はないものの、私たちを殲滅することも可能であるような運命に変えることで、人類を自分たちに固有の暴力から分離しようとする。ここでの狡智とは、私たちに起きることの唯一の原因は自分自身なのだということは念頭に置きながらも、わたしたちがあたかもその犠牲者であるかのようにみなすことに尽きる」(116頁)
・「ツナミ」のモデル(自然的な悪)ではなくシステム的な悪
20世紀の道徳的破局や人類を待ち受ける大災禍→悪意やエゴイズムからではなく、近視眼やthoughtlessnessから生じる悪(≠道徳的悪、自然的悪)=システム的な悪
システム的な悪における自己超越の経験:システム的悪を生じさせたのは人類である。しかし、人はシステム的悪を前にしたとき、まるでその悪が自分を超越している運命であるかのように感じる。
ex. グローバル資本主義における実績を巡る「レース」
→覚醒した破局論は、現代の悪のシステム的な特徴を逆手に取る
破局の普遍的モデルとしてのツナミから手を切る必要性
・未来のもつ現実性(以下、「未来を悼む」を参照)
「人間の技術や科学がいずれ問題を解決してくれる」という考え方(=予防原則、人義論)
→未来を不確実なものとし、破局の脅威をとらえることができなくなってしまう(未来の非現実化)
・未来への感情と情動(再び出発点へ)
生まれていない未来の子供たちに同情することはできない
出発点:「だがしかし、感情も情動もわき上がらないままで、どうすれば未来に刻印されてしまっている破局に十全な現実の重みを与えることができるだろうか?」(122-123頁)→覚醒した破局論はこの疑問に対する一つの回答
コメント
久津間靖英
デュピュイの時間論や覚醒した破局論を聞いて、あまりにも抽象的で現実性を欠いた話だと感じる人もいるだろう。だが、著者は私たちからかけ離れた場所で話をしているわけでは決してない。彼の出発点は、私たちは未来の世代に対して同情することはできないというところにある。この意見に対して異論を持つ人もいるかもしれないが、少なくともこうした考え方がいくらかの現実性をおびていることは否定できないだろう。もし、数百年、あるいは数十万年先の子供たちのことを本当に真剣に考えることができているならば、原子力発電所はとっくになくなっている。高木市長の発言には狂気じみたものを感じるが、しかし彼と私たち(皆さんのような方たちを含めてしまうのは大変しのびないので、より控えめに言うならば「彼と私」)との間に大きな相違はない。
デュピュイはこうした人間の「弱さ」を評価づけることはしない。こうした「事実」を認めた上で、しかしこれから起こる破局について考えるためには未来に対する感情を生じさせなければならない、と彼は言う。「未来を聖なるものにする」というタイトル自体が彼の主張、あるいは希望をよく表している。そして一つの答えとして覚醒した破局論を挙げる。
ただ、正直に言うと、私にはデュピュイの覚醒した破局論がさほど力強いものであるようには思えない。「現実性がない」「感情論にすぎない」という反論は問題外だとしても、覚醒した破局論やアンダースの寓話にどれほど人を動かす力があるだろうか。いずれにせよ、今回の発表で私が何よりも恐れているのは、デュピュイの著作を暴力的にねじ曲げて皆さんにお伝えしてしまったのではないかということだ。もし、今回の発表でデュピュイの著作に興味を持ってくださった方がいるならば、是非とも実際に手にとってみていただきたい。
福田浩之
破局の進行が絶望的であるという立場に身をおくことで、破局の被害を最小限に抑えようとする『ツナミの形而上学』の発想は、カミュの『ペスト』における、流行病がとりあえずペストである「かのように」ふるまう、あのやり方とも似ているように感じた。さて、この文章でデュピュイがなそうとしていることは、すなわち、ギュンター・アンダースの語るノアに倣うことであるはずだが、不思議なことにデュピュイはその手の内を見事に明かしてしまっている。小咄のノアのやり方においては(こういう言い方が許されるなら)ハッタリを効かせることが重要であるはずにもかかわらず、だ。デュピュイは、「覚醒した破局論は処方箋ではない」と書く。しかし、まさに「覚醒した破局論は処方箋ではない」というこの強調によって、「覚醒した破局論」は(おそらく、すくなくとも、デュピュイ自身にとっては)「処方箋」になる。そのことは問題ない。どのみち、予言によって破局を回避するためには、予言者が語ることが嘘になることは必要条件なのだ。だから、破局を回避するためになされる的確な嘘――嘘とまではいかなくとも、逆説や多少の矛盾は、許されてしかるべきだろう。問題はその意図が、当の読者に伝わってしまうことにある。意地の悪い見方をすれば、予言が回避されることでペテン師とされることへの予防としてこの逸話を持ち出していると捉える事もできてしまうが、そうではないと信じたい。デュピュイが手の内を明かすことは、破局は回避できるかもしれないという認識を与えることで「覚醒した破局論」の真実味を削ぐ。一方で、回避不能な破局に対して、決まっているのならもはや何もしない、という怠惰を回避することにはつながる。メリットとデメリット、どちらが大きいだろうか。個人的にはあえてデメリットが大きいということにしておきたい。そのことで「覚醒した破局論」は適度な現実味を帯びなおすだろう。
野田大基
私は今回のゼミが終わった後、非常に落ち込んだ。それはデュピュイが何一つ解決策を示していなかったからだ。それはすなわち解決策が見つからないということを示している。デュピュイの言う「システム的な悪」とは現実すべてに当てはまる。その時々で人間が下してきたすべての決定が、後の破局の因子となる。それが善意であれ悪意であれ関係はない。逆説的に言うならば人間はどのような決定を下そうとも、破局からは逃れることはできない。そして覚醒した破局論とは、破局に対してのなんらの対策を含まず、破局から逃れられないことを認識することだけである。対策としての設計・プログラムは結局後の破局に収束するからだ。世界は複雑に絡み合い、もはや絶対的な善悪は存在しない。生きることそのものが矛盾を生み出していき、いつしか自縄自縛に陥った人間はどうすればよいのだろうか。デュピュイ自身が言うように、覚醒した破局論はいかなる希望も担ってはいなかった。
川野真樹子
覚醒した破局論は未来完了(決定事項)で考え、その破局をいかに回避するかが前提となったものである、という一節が重く感じられた。おそらく災害から身を守るのに、「絶対」や「完璧」というものはあり得ないのだろうが、それを忘れて「私だけは、何々だけは絶対に大丈夫」神話の虜になっていたのが震災前の状況だったように思う。今、津波が確実に来るものとして避難訓練を行った地区が連日のようにニュースに取り上げられているが、覚醒した破局論を知った上でこの訓練を見ると、まだ予防原則の段階を脱していないように思える。訓練をしているから大丈夫、ではなく、訓練していたけど、それでは対処できない災害が確定されている(だから次はこうしてみよう)、と少しずつ想定される災害の規模を大きくして訓練を行っていくことがよりよい破局の回避につながるのではないだろうか。もちろんこれでも本当の意味での覚醒した破局論になっているわけではないが… また、生まれていない未来の子供たちのことを考える、という主張は例えば、核廃棄物のような負の遺産をそれを作ったのではない(この言い方では語弊があるかもしれないが)子供たちに処理の責任を負わせていいのか、という主張と重なって来る部分があるようにも見える。この例から、今現在の快適さ、有用性だけを基準にして何かを為すのはあまりにも無責任なのだと感じた。自分が何か行動するとき、現在だけを基準にするのではなく、未来を含めた目線で客観的に見ることが必要だと今回の授業を通して考えた。
井上優
『ツナミの形而上学』は、今回の東日本大震災と大いに関連付けて読むことのできる文献だと思ったが、覚醒した破局論の考えについては自分の中でいまいちしっくりこないでいる。破局を必ず訪れるものとして捉え、それに積極的に向きあう必要があるということだったが、「想像力の欠如」によりアウシュビッツやヒロシマの原爆投下という悪を引き起こしてしまった人間に、未だ訪れることのない破局を想定するほどの想像力があるのかと疑問に感じる。また、ノアの箱舟の話にもあるように、人々は預言者の預言を信じない。誰かが危険の警鐘を鳴らしてくれてもそれを信じることができないのに、どうして主体的に未来の破局に向き合えるのだろうか。その際、何がモチベーションとなるのか。まだ生まれていない未来の子供たちへの同情が動機となりうるということも正直自分にとっては納得し難い。この先さらに大きな地震が起こる、富士山が噴火する、と言われても、実際それらを現実的に考えられず、そうした破局に対して何も備えていない自分がいるので、どうしたら覚醒した破局論が実践できるのかというのがとても興味深い。

