「世界の終わり」という観念――イマニュエル・カント「万物の終わり」(2012年5月9日)
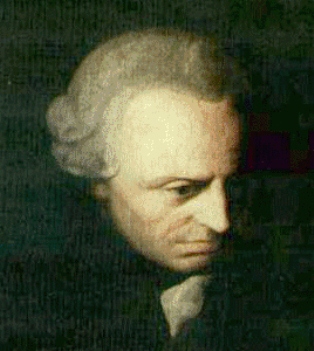
「なぜ人間はそもそも世界の終わりなるものを思い設けるのだろうか。世界の終わりを考えるのはよいとしても、なぜ人類の大部分は恐怖をもってこれを迎えようとするのか」とカントは問う。万物の終わりは自然界ではなく、人間の側の観念であるが、破局の終末論的思考をカントと共に考察する。
発表者:大江倫子(仏文修士1年)、内田森太郎(哲学4年)
引用は『啓蒙とは何か』(岩波文庫)からおこない、引用頁数を丸括弧内に記す。

万物の終りの推論(83-84)
臨終の人は「われ時間を離脱して永遠に入らん」という宗教的な言葉を口にする。
この「永遠」という語により、時間の有限性(終り)と人間の無限性が含意されている。このような事態は感性では把握できない。このような思想は難解であり、よって恐ろしいと同時に崇高である。
このような思想は普遍的に見出される。
「時間から永遠への移行を、理性が道徳的見地において自分自身のためにみずからなすところの移行に倣って追求していくと、われわれは時間的存在者としての、従ってまた可能的経験の対象としての万物の終りに達する。」
「しかしこの終りはそれと同時に、人間に規定された諸目的の道徳的秩序においては、時間的存在者がまさに超感性的存在者として、すなわち時間制約のかかわりのない存在者として存続する始まりである。このような超感性的存在者は、その特性としては道徳的規定以外のいかなる規定もあり得ないのである。」
末日の推論(85-86)
以上より、審判日としての末日が推論される。それは万物の終りであり、永遠の始まりである。それはすべての人間の行状が決算される最後の審判である。黙示録にはその自然的経過が記述されているが、万物の終りは理念であり、道徳的思弁のみに関わる。よって世界の道徳的経過も超感性的である。
「最後に生起するところの事件―すなわち末日ののちに来るべき事件の描写は、末日とその道徳的な結果とを具象的に示すものと見なされねばならない、しかしこのような結果は、いずれにせよ理論的には理解せられ得ないのである。」
二元論への疑問(86-87)
永遠については、一神教(すべての人に永遠の祝福が授けられる)と二元教(選ばれた人には祝福、他の者には刑罰)の体系がある。しかし永遠に罰せられる存在がもしあるとすれば、なぜその人間が創造されたかという疑問が生じる。
世界の終りの意味(.88-91)
一神教ではすべての人に祝福が授けられるが、実践的見地で自分を裁くにあたり有効でない。二元教の方が有利であるが、やはり客観的に妥当する理論的命題を作り出すには不十分である。自分の立派な行状から偶然的幸運による要素を差し引いて自惚れなく判断できる者はない。いずれの体系も人間理性の思弁的能力を超出している。これらの体系を来世の原理と考えることはできず、来世でも現世と同じ善と悪の原理が支配すると考えざるをえない。
「このように考えると、我々が現世の生活を終える際の道徳的状態と、それから生じるところの応報とは、来世の生活に入ってからもやはり不変であるかのように行動するのが賢明である」
「だがなぜ人間は、そもそも世界の終りなるものを思い設けるのだろうか。また世界の終りを考えるのはよいとしても、なぜ恐怖をもってこれを迎えようとするのだろうか」
⇒理性的存在者が究極目的を達成するために世界が存在する(人間の創造の意味の達成)、
人間は堕落状態にあるので、終滅させるべきである
このような前提から、人間は世界の終りを考えるのである。
他なる終末(93)
人間は生存の重荷を負うている。重荷と感じている。
その理由は、人類の進歩において、技術や欲望が道徳に先行したことである。これは道徳にも身体にも危険な状態である。しかし道徳は、いつかは欲望に追いつくであろう。よって永遠の祝福とともに万物の終りに至るとも十分期待しうる。しかし現実には恐ろしい終末の信仰が優勢のようである。
万物の終りの分類(94-95)
ここで論じているのは理念である。理念は超越的ではあるが、空虚ではない。それは万物の究極目的である道徳の原則を可能にするからである。これに従って万物の終りを考察すると3区分ができる:
① 自然的な終り⇒神の知恵による道徳的目的の秩序に従う、十分理解可能
② 神秘的(超自然的)終り⇒何一つ理解できない
③ 反自然的(誤れる)終り⇒人間が万物の究極目的を誤解
理性の目的論(96-98)
黙示録では万物の終りを感覚的対象として記述している。しかし世界の終りの後は時間が存在しない、したがって変化が存在しない可想的世界であり、感性的記述とは矛盾する。
他方で永遠という概念はたんに時間の欠如した状態が言われているにすぎない。このような状態では理性の使用もできない。
「理性は、時間において無限に進む変化を、究極目的の実現に向かう不断の進行とみなすが、しかしかかる進行においても、善に向かわんとする道徳的心意は常恆不変である、と考えるよりほかはない。するとこのような理念に則って理性を実践的に使用するための規則は―我々は、我々の格律を、我々の道徳的状態が善から更にいっそう善なるものへと限りなく進み行く変化にも拘らず、格律から言えば、時間の推移にはいささかも支配されるものではないかのように見なさねばならない、としか言い得ないのである。」
一切の変化の停止は、このような「まともな想像力」に挑戦するものである。自己の存在を時間においてのみ意識し得る存在者はとってこれは寂滅である。反省も時間においてのみ生じ得る。
神秘説(98-100)
人間はその道徳や自然状態の永遠の変化に満足できない
害悪もまた無限に進行するのではないか
⇒永遠の寂静を享受したい⇒神秘説へ
理性は妄想に耽る:老子思想、汎神論、スピノザ説
悟性の消滅、思惟の終り
反自然的終末(100-101)
最高の知恵、実践理性は神のみに属し、人間の知恵はこれに背反しないことである。人間はこれにみだりに近寄ってはならない、掴み取ったかのように振舞ってはならない。
全国民の宗教を純化し振興する企てもこうした勝手な信念のなすところである。
キリスト教と愛の精神(101-105)
公共体や国民の一部や国民全体が実践理性に聴従するようになるならば、推進するべきだが、その成果は摂理に委ねるべきである。
一方で、現在の計画を最上のものとする反論があるが、これによると万物の終りがすでに始まっているかのようだ。しかし今後もっと新しい計画が現れるだろう。
一世代を通じて良好だった事態は保存すべきである。
進取の気性の人も自戒する必要がある。
キリスト教は神聖な律法のほかに愛すべきものを備えている。
「愛は他者の意志を自己の格律のもとに摂取するものとして、人間の不完全性を補うに書くことのできない要件である。」
「キリスト教に全たき善を求めて、これになんらかの権威を付加するならば、たとえその意図が善意に充ち、またその目的が事実いかに善であるにせよ、キリスト教の愛すべき性格は消滅するのである。或る人に、何ごとかを為せと命ずるだけでなく、それを喜んで為せと命じるのは、矛盾だからである。」
キリスト教は愛のはたらきを促進して意図を実現する。命令者ではなく友として。不偏にして自由な考え方によって。
キリスト教と報い(106)
キリスト教は報いを約束するが、報奨による約定ではない。非利己的な行為には尊敬が伴われる。
キリスト教と反自然的終り(107)
キリスト教が愛すべき性格を失うことは、キリスト教はその本分を成就する運命に恵まれないのであり、万物の誤れる終りである。
終末論と永遠
1.終末論
終末の視点から歴史全体を一つの意味ある統一体として観じ、その意味に応えるべく現在と未来を生きる、個的であると同時に共同体的で人類史的な歴史的自覚を意味する。その実存的歴史的な自覚はユダヤ・キリスト教を源泉とし、中世からヒトラーまで西洋の歴史意識の底流に伏在する切迫的未来構想や、ルネサンスからヘーゲル、マルクスに至る統一的歴史展望として展開する。
現代思想と終末論:レヴィナスの他者論は責任を神に転嫁する自同者の終末論、この全体主義を挫折させる唯一の可能性としての「主観性としての神」(デリダ「暴力と形而上学」)
2.永遠
〈永続〉(いつまでも果てなく継続すること)と〈無時間〉(ある特権的事態が過ぎ去らず留まり続け、時間意識が消失すること)の概念がある。
① 通時間性:時間的経過や制約に依存しないこと。数学の命題など客観的普遍的真理。
② 超時間性:時間的位相から超越したあり方。時間性とまったく質の異なる他界。
③ 瞬間の永遠:時間のなかにありながら時間を越えた瞬間。神秘思想、プルースト。
現代思想と超時間性:主観性の起源としての時間(フッサール)、世界のなかの自己の存在了解の起源としての時間(ハイデガー)、自己性と他者性の共在としての時間(デリダ)
コメント
西山雄二
未読に値するカントの短論文を適切な発表によって十分に理解することができた。終末論(eschatology)はギリシア語のeschatos(終末)に由来するが、それはユダヤ=キリスト教において、終末を救済の目的とする救済史でもある。カントは見事な手つきで、時間と永遠をめぐる境界線を理性的に問いつつ、「末日」という厚みのある時間性(万物の終わりにして永遠の始まり)に着目する。また、終末を分類し、自然的/神秘的/反自然的という複数の終末=目的を分析する一節からは、私たちは終末論に対する「軽やかな遠近法」を身に付けることができるだろう。単線的な終末論ではなく、複数の視座からの終末を同時に想定することができることは人間の成熟した批判的能力であり、複数の未来から私たちの行動と規範を紡ぎ出す必要性を感じた。
柳沼伸幸(法学2年)
今回の講義は万物の終わりと終末思想についてであった。正直自分にはカントのテクストは難解で、理解できたかは疑問だ。それを踏まえたうえで言うならば、カントの終末思想は神を前提としているものであって神の存在を強く意識しない人々にとっては馴染まないということを強く思った。「終わり」というものを思考したことがないわけではない。しかし、人間が堕落状態にあるために終滅させるべきだと考えたことは一度もない。人間は生存の重荷を負うていると説かれておりこれを感じないことはないが、常に生きることを重荷だと思う者は恐らく生きることを選択しないだろう。だが、現代においてキリスト教的であれそうでないにせよ終末思想は様々なコンテンツで取り入れられ、一定の需要を保持している。終わりや死の持つ一種の神聖さやおどろおどろしさの他に対岸の火事的な面白さがこの需要を生んでいるのではないだろうか。また、この一種不謹慎な面白味は「所詮(自分の)世界は終わらない」という考えを助長させるものでもありそうだ。この「世界は終わらない」という思想が人々の現状への無関心を生むのだと自分は考える。
川野真樹子(表象4年)
今回の授業で、ふたつの終末論(合理的な終末論、キリスト教的な終末論)について知ることができたが、同時に、輪廻という考え方はどちらに位置するのかそれともどちらからも離れたところにあるのか、という疑問を持った。前世の業によって現世の立場、あるいは死後の立場が決定されるという考え方(だから今を良く生きようという考え方)はどちらかと言えば、合理的な終末論に近いように感じる。しかし、前世の業によって現在が決定されているならば、既に結末が到来しているというキリスト教的終末論とも似通っていると言えるのではないだろうか。ただし、この場合、キリスト教のように他者によって既に罪が清算されているわけではないため、キリスト教のように逆転した終末論までは行きついていないように思う。これらの二点から考えてみるに、輪廻思想は過去の終末(過去の他者)と未来の終末(未来の他者)とを意識し、その両者から現在の自分のmustを行動する、というまた新しい形の終末論になりうるのではないだろうか。
野田大基(法学3年)
今回のゼミを通して、カントの楽観的な思考と現実の原発問題の深刻さのミスマッチを感じました。カントの文献は難しかったため、完全に理解できているとは言えませんが、授業での説明などを聞く限りカントは人間に対して非常に楽観的な態度をとっているように思えます。特に93頁では「人類の道徳的素質は、(ホラティウスの「跛の罰」のように)跛をひきひきいつも欲望を追いかける、そして欲望が気ぜわしく走るにつれて、足をもつらせ、また躓きもするが、しかし(これは賢明な世界支配者のもとでは、十分に期待してよいことだが)いつかは欲望追いつくだろう」と明るい展望を述べています。カントと対照的な話として、藤子・F・不二雄の漫画の一場面を思い出しました。(必ず当たると評判だった占い師が突然占わなくなり、その理由を尋ねに行った記者に対して占い師が「孫に見てあげられる未来もない」と言う。)カントの時代ならば、いつか道徳が追いつくと期待していられたかもしれませんが、人が自らの手で世界を終わらせる力を持ってしまったこの時代に、そのような期待はできません。欲望によって、明日にでも世界が終わるかもしれないのに、いつまで待てというのでしょうか。

