ハイデガー『技術への問い』平凡社、7-60頁
(2013年5月22日) 発表者:大江倫子
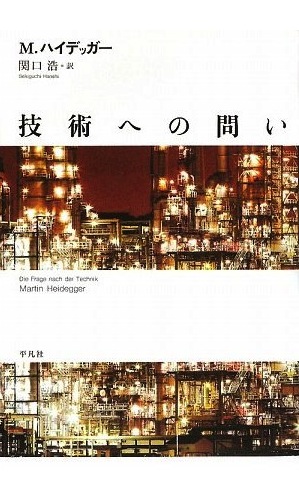
「われわれは技術について問う。問いは道をひらくことにたずさわる〔…〕われわれは技術について問い、そのことによって技術との自由な関係を準備したいと思う」。1953年の講演「技術への問い」でハイデガーは近代的な技術の本質を探りながら、哲学の最深部へと踏み入っていく。彼は技術時代の危機を主張しつつ、カタストロフィから脱却や救済を語らない。カタストロフィを引き起こさなければ近代技術は人間にとって安泰なのではなく、むしろ、あらゆるものが技術化される時代に生きる人間の不気味な命運を問い続けなければならない。

1.まえがき(p.7-8):「本質」について
この論考では「技術について問う」。道を開くこと、つまり思索の方法が問題であって、知識を得ることが問題なのではない。対象についての知識を得る学問とは異なって、対象との関係において真理が到来するのである。したがって「本質」「真理」などの言葉について、通常とは異なる意味で使っている。こうすることで技術との「自由な関係」を維持するのである。「真理」「自由」「本質」はここでは一体となっている。
通常の考えでは、「本質」とはその対象領域に共通する特性、すなわちその類である。ここでは「本質」をまったく異なる意味で使用する。それはその対象領域を「くまなく支配するdurchwaltet」ものである。
自分自身と技術の本質との自由な関係を経験することが重要である。通常の考えでは、技術とは人間が思うままに利用する無色透明な道具である。これは一見人間が自由であるように見えるが、実は人間が技術についての規定された概念に拘束された結果なのであり、自由に思考することが禁じられている。ここでは「本質」についてまったく別の仕方で思考する。
2.通俗的技術観から新たな技術の本質へ(p.8—19)
通俗的観念では、技術の本質とは、手段Mittelと行為Tunをしかるべく整えるEinrichtungであり、よって道具的規定、人間学的規定である。これは古代から現代技術まで正しい。しかし正しいだけでは「真理」ではない。ここで言う「真理」とは、本質、すなわちそれ自身の固有性を出来させることである。
道具性と密接に関係がある因果性からこのことを考えてみよう。古代の哲学では、四原因説(質料因、形相因、目的因、動力因)があるとされた。しかしこのこと自体を問いに付さなくてはならない。
古代ギリシャでは、この四原因は語源的にaition(責めを負う)= verschulden(自分の落ち度で引き起こす、しでかす)の相互的様態と解すことができる。捧げものの銀の皿の例では、材料、形態、目的、銀細工師が相互に責めを負っている。このうち銀細工師は動力因とはいえず、他の三者の本質が現れるように配慮するものであるはずである。このように四つの仕方が支配するwalten。「責めを負う」とは行為者の一方的過失でもなければ、一方的に作用する現象でもなく、相互関係の結果であることに着目するべきである。
この四つの仕方は、なにかを現出へともたらす。銀細工師が一方的に製作するのではなく、他の三者の固有性が顕われ出るように、解放し誘発するのである。このようにしていまだ現前していないものを現前へと到来させる、すなわちその本質にもたらすのである。これは「ポイエーシス」と呼ばれ、製作とともに詩作も意味する。自然もポイエーシスであり、それ自体において花が開くように実現される。この誘発は伏蔵性Verborgenheitから不伏蔵性へもたらすのであり、これによりそのものとしての固有性を出来させる。これは開蔵Entbergenという作用であり、アレテイアWarheitすなわち真理であり、表象の正しさである。

3.技術と開蔵、技術の真理(p.19—37)
技術の特徴である道具性はこの四つの誘発に属している。ポイエーシスは四つの誘発をくまなく支配している。よってあらゆる生産的製作の可能性は開蔵に基づく。技術は開蔵の一つの仕方である。技術の本質はこの開蔵としての真理に基づいている。よってテクネーはポイエーシスであり、詩的なものに通じる。テクネーとエピステーメも同等である。技術が本質を発揮するところに開蔵としての真理が生起する。
現代技術にも開蔵が当てはまる。現代技術の開蔵は挑発Herausfordernであり、自然からエネルギーを調達する。資源の採掘、耕作、原子力エネルギーに見るように、この挑発する調達は運び出し促進する。河川は水力発電や観光資源としても開発される。ここで開蔵Entbergenは挑発する調達であり、その進路を開蔵し、進路を制御し制御を確保する。挑発の不伏蔵性として顕われる固有なあり方を用象Bestandと名づける。非自立的機械としての対象ではない。
調達を遂行する人間は不伏蔵性を意のままにできるのではなく、それ自身すでに挑発されている。人間も人的資源として用象であり、用立てに参加している。
開蔵の生起を見出すには、その誘発の呼びかけを聞き取ることである。これに応じて人間の不伏蔵性が出来する。すなわち人間各々に固有の本質が現れる。挑発は人間を用象へと収集する。
このように人間を用立てに収集するもの、挑発し呼びかけるものを集立Gestellと名づける。自然の意味では「台架」であるが、プラトンによるエイドスの革新的用法(見えるものから見えないものへ、あらゆるものの本質への転位)と同じように、まったく新たな意味で用いる。集立は、用立てという仕方で用象として開蔵するよう人間を調達する、挑発する、立てることstellenを収集するものである。開蔵のあり方を意味し、現代技術の本質として支配するwaltet。
「立てることstellen」はHerstellen製作とDarstellen叙述に連関する。両者はポイエーシスとして現前者を不伏蔵のうちへ現われでさせるので、ともに真理である。技術の道具的規定も人間的規定も無効である。
技術時代に開蔵へ挑発される人間は、近代自然科学の成立として現れた。これは自然を計算可能な諸力の関係として追求するが、自然科学は現代技術の条件ではない。物理学は現代技術の本質の先駆、集立の先触れである。現代技術の本質は長期間伏蔵されたままである。本質を発揮するものWesendeは長期にわたり伏蔵されるが、その支配Waltenはすべてに先行している。近代自然科学から動力技術が実現されたのではあるが、実は現代技術が先行しているのである。
現代物理学における直観認識の断念も挑発されている。しかし計算による確定を断念できない。ハイゼンベルクの不確定性原理はこれを超え出る新たな因果性を予示している。
現代技術の本質としての集立

4.技術への問いへ、命運と自由、リスクと救い(p.37--60)
集立そのものという開蔵の生起の場所は、人間の行為の彼岸と人間の場所との間にある。人間は集立の本質のうちにすでに立つのであって、事後的に集立と関係をもつのではない。しかし人間はそれを自覚的に経験しているとはかぎらない。
現代技術の本質が人間に挑発する開蔵は、派遣として、命運Geschickとして生じる。これは収集する派遣であり、歴史的なものの生起である。表象への命運が史学としての歴史を可能にする。
集立は命運の派遣であり、ポイエーシスをもたらす。命運は宿命ではなく、隷属ではなく人間を自由にする。自由の本質は意志ではない。自由は開けを統御しverwaltet、真理の生起にかかわっている。開蔵には伏蔵が先行しており、それは自由にするものとしての秘密である。空け開けには真理を覆い隠すヴェールSchleierが現出し、命運によって開蔵に至る。このような命運は逃れることができない運命Schicksalとは異なる。集立を開蔵として経験することは、命運の自由な開けにあり、自らを技術の本質に開くことで自由の呼びかけに気づくことである。
命運によって人間は用立ての開蔵の追求の最前線を行くが、このことで不伏蔵との原初的関わりが閉ざされる。しかしこれにより開蔵への帰属が本質として経験される。開蔵の命運は必然的に危うさを含む。人間が見誤る危険、正当さの優位のうちで真なるものの退去の危険がある。開蔵の命運それ自体が危険なのである。集立における命運の危険として、用象の優位による対象の喪失から、自己の本質に出会えない人間が生じること、用立ての支配herrschtからポイエーシスの伏蔵に至り、あらゆるものの用象化に至ることである。集立は開蔵そのものを伏蔵し、不伏蔵性を伏蔵することにも至る。集立は真理の輝きScheinenと働きWaltenとを塞ぎ立てる。危険なのは技術ではなく、技術の本質=開蔵の命運である。集立の支配Herrschaftには本来的脅威がある。

ヘルダーリン「危険のあるところ、救うものもまた育つ」
救うこととは、本質の取り戻し、本質を本来の輝きにもたらすことと解する。危険を洞察し、救いを見出すために、ここでもう一度技術を問う。
「本質」の意味の再考しなくてはならない。通常の意味では共通の類であるが、開蔵は説明不可能な仕方で産出と挑発に分けられる作用である。現前する実体ではなく、関係としての作用だからである。集立は本質ではあるが類ではない。「本質Wesen」の他の意味を考えることが要請されている。Wesenは本質を発揮しつつ存続するwesenしかたとして、 Weserei村役場、währen存続の用法がある。他方でプラトンはイデアとして永続するものを本質と考えたが、本質はイデアではない。本質とは永続しない存続である。本来的存続とは、叶えられたものdas Gewährteであり、原初的に存続するのは叶えるものGewährendeである。
集立は命運であり、その挑発は叶えるものではない。しかし開蔵の命運は叶える、救うものであって、人間本質の最高度の尊厳に帰入させる。それは不伏蔵性と伏蔵性を見守ることにある。危険においてこそ叶えるものの人間への帰属性が輝き現れる。
この立ち現われを熟慮し追想しつつ見守るために、技術の本質を洞察することが必要である。技術を道具とみなすのではなく、道具的なものの本質を問い、叶えるものの固有性を出来させるのである。
技術の本質の両義性は真理の秘密を示している:
1 集立の荒れ狂う挑発 真理の本質への連関を危うくする
2 集立は叶えるものとして固有性を出来させる 人間を存続させる救うもの
用立ての止めがたさと救うものの控えめさは両者の近さの伏蔵を示している。技術の問いは相互関係への問いである。立ち止まって警戒し、ささやかさのうちで救うものの成長を保護することが救いに至るのである。開蔵を脅かす危険と救うものを熟慮し、原初的に叶えられた開蔵を待機する。
テクネーの語源には、真なるものを美しいものへ取り出すポイエーシスがあった。芸術がテクネーと呼ばれていた。唯一にして多様な開蔵えだり、真理の支配と保護に従順であった。職人芸・美的享受・文化創造ではない芸術、ポイエーシスとしての芸術は詩作である。
「ヘルダーリン:人間はこの大地に詩人的に住む」
詩人的なものがあらゆる芸術を存続させる。詩人的な開蔵と諸芸術が呼びかけあうことで芸術の可能性が叶えられるのではないか。
技術への省察と対決が生じる領域として芸術がある。
技術と芸術の本質を問う苦境は、その本質がそれ自身に属さないことにあり、その秘密が芸術にある。問うことは思索の敬虔さである。

西山雄二
ハイデガー存在論の思索の肌触りは推理小説の感覚に似ていて、いつもスリリングな読書体験になる。犯人が検挙されて登場人物一同がほっとしているときに、明敏な知性の探偵によって、別に真犯人が居るという真相が暴露される。私たちはすべてを見通しているつもりだが、その実相を何も見ていなかった。ハイデガーによれば、私たちが日常的に諸事象に触れる態度は一面的であり、そのせいで世界の実相を取り逃がしているのだ。彼の技術論、いや、「技術への答えなき問い」もまた、技術の本質を問うことで、技術の人間主義的・道具主義的な発想を超え出る。個々の技術の連関が「集立Gestell」と表現され、ある種の根源的な技術決定論が展開されるため、その壮大で抽象的な立論にはついていけない者もいるだろう。だが、科学技術が巨大化し資本化し私たちの生をすみずみまで規定している現代において、さらに別様に技術を思考し直そうとすれば、これほどの形而上学的な見通しと価値転換は多かれ少なかれ必要である。
志村響(心理学2年)
ハイデガー、技術、というトピックから、昨年度に私が発表を担当した『破局の等価性』におけるナンシーの言及を想起せずにはいられなかった。彼はハイデガーの「技術=存在の最後の歴運」という指摘を受けて、技術とは「生の様態であり、思考の様態であり、世界内に存在すること、世界を変容させることの様態」であると解釈、換言しているが、「技術とは人間そのものと異なるものではない」という価値観は、今もある種の重みをもって私の中に響いている。今回読んだ『技術への問い』もやはり難解で、内容は先見の明に富むものであったが、ここで焦点を当てたいのはそのタイ トル、およびその序文に見て取れるハイデガーの技術観だ。タイトルは『技術とは何か』でも『技術の本質』でもなく、『技術への問い』である。このことからまず、技術をただの“道具”とは捉えていないことがわかる。『ハサミへの問い』も『雨傘への問い』も不格好である。謎があるから“問う”のだ。また、ハイデガーは序文において、「われわれは技術について問い、そのことによって技術との自由な関係を準備したい」と述べているが、ここで人間≒技術という見地から半ば強引に読み替えると、「われわれは自身について問うことで自身との自由な関係を準備したい」となる。しかし、“自身との自由な関係”とはいったい何であろうか。技術の本質はそれを明らかにするものだろうか。堂々巡りにな ってしまいそうだが、これを問うことなしには技術はただ“危険”の様相ばかりを露呈し、われわれはそれを看過してしまうかもしれない。
浅利みなと(哲学2年)
哲学書の邦訳を読むといつものことではあるが、なぜこうも解釈が難しい日本語になってしまうのかと感じる。もちろん、自分の頭と努力と忍耐が足りていないのは重々承知なのだが…。しかしながら、今回、大江さんと西山先生の解説でなんとなくは理解することができて安心している。特に考えさせられた残った部分は、「人間は不伏蔵を意のままにできるのではなく、それ自身すでに挑発されている。」という論である。私は「人間自身が技術に使われている」というように解釈したのだが、至極もっともだと感じる。例えば、私たちは日ごろ楽だからといって、階段を使えばいいのにエスカレーターに乗ったり、必要もないアプリをスマートフォンでダウンロードしたりしている。これは『荘子』 で述べられていた「機心」と通ずるものがある。そして何より問題なのが、私たち自身が自らの「機心」や技術に使われていることに気付かないことだ。これがハイデガーの論じている技術の本質に内在する危険性のひとつであると感じる。果たして、文明はこれ以上進歩する必要があるのか。これ以上、機械化が進む必要はあるのか。考えていかねばならない。
飯澤愁(仏文修士1年)
難解な言説に包まれているが、関係する要素全てに原因が介在しており、起こり得ないカタストロフィに対して危機感を持つべきというハイデガーの主張そのものは明快だ。エーリッヒ・フロムやサルトルが言うように、自由であることは常に決断の重圧の下にあるということでもある。とかく人間は全体主義的な価値観に安易に逃走することで安寧を得ようとするが、逃れ得ない技術化の中で、せめて我々は見誤ることなく、そして安直な手段や思考停止に逃げることなく進む必要がある。また、ハイデガーは芸術を引き合いに出し、審美的であるよう要請する。審美眼というと観念的なものであるように思えるが、ハイデガーのいう救済とは人間そのものの存続という絶対的なリアリティに直接関わるものであり、すなわち、ここで言う美とは至極現実的なものと言えよう。ハイデガーは身体性に根ざした感覚と向き合うべしと、晦渋なこの文章を通じ音抜けの良い警鐘を鳴らしているように思えてならない。
大江倫子(仏文修士2年)
ハイデガーはその最初の著作『存在と時間』で、各自の固有の死に向けての投企に基礎づけられた人間の命運について、また単に道具として扱うことのできないあらゆる事物の固有の本質について論じた。これにより真理とは、人間や事物がある決まった「正しいあり方」に一致することではなく、その固有の本質が顕われることになる。この考え方を技術に適用するとどうなるのか。技術の本質とは、自然の資源と人的資源が固有な仕方で用立てられることで、その各々固有の本質が顕われることとされる。こうしたあり方は、技術が現在の形で現れるよりも前から隠されていたのであり、詩作にも通じる事柄である。この在り方はリスクと救いを共に含み、私たちはリスクを回避するようつねに配慮する必 要がある。これまでに見てきたような技術に対する短絡的な反応や悲観主義ではなく、各自がその固有の用立てを自覚した上で、それを他者や事物との共生のうちに実現に努めることに希望が見出されるのである。

