共同研究「哲学と大学」
共同研究「哲学と大学」
共同研究「哲学と大学」

2007-2008年、東京大学グローバルCOEの「共生のための国際哲学教育研究センター」のプログラムとして、共同研究「哲学と大学―近代の哲学的大学論の系譜と人文知の未来」がおこなわれました。以下、その概要と記録です。
哲学を通じて、大学において、現在、私たちは何を知りうるのか、何をなすべきか、何を希望することを許されているのか。
近代の大学の誕生は、哲学の学問的覇権の確立と不可分である。フンボルトのベルリン大学建設以来、哲学は学問の有機的統一性を保証し、大学の理念を支えるものとされてきた。大学における哲学の地位の後退は、それゆえ、20世紀を通じて明らかになる「哲学の死」と深く関係する。また、哲学の他分野(文学・芸術・社会・政治・人類学・精神分析)との混交によって、伝統的な人文学の枠組みは複雑な仕方で変容し続けている。
本共同研究の目的は、各哲学者の大学論を批判的に考察することで、哲学と大学の制度や理念との関係を問い直すことである。これは哲学と大学をめぐるある種の「没落の歴史」の考察となる。
カント、フンボルト、フィヒテ、シェライアーマッハー、シェリング、ヘーゲル、ニーチェ、ハイデガー、オルテガ、ヤスパース、デリダ……近代において、ほとんどの哲学者は大学教師である。彼らはその歴史的・社会的状況において、教師として大学制度のなかでどのように振舞ったのか。彼らはその大学論においていかなる哲学的主張を展開しているのか。そうした大学論は彼らの哲学の理論や実践においていかなる位置を占めるのか。哲学と大学をめぐる議論のなかから、各哲学者の教育法や教育論、学問論、教養論、人間論、人文学論といった主題も浮かび上がってくる。
本研究会はこれまで5回の研究会とシンポジウムおよびワークショップを実施し、当初の予定を終了した。その成果は来春、論集『哲学と大学』(未来社)において公表される。
主催:西山雄二(UTCP)、宮崎裕助(新潟大学)
これまでの活動(肩書きは当時のもの)
●第1回 2007年11月1日「ビル・レディングス『廃墟のなかの大学』の衝撃」
発表者:西山雄二(UTCP)
参考文献:ビル・レディングズ『廃墟のなかの大学』青木健・斎藤信平訳、法政大学出版局、2000年。
●第2回 2007年12月6日「カント『学部の争い』」
発表者:宮崎裕助
参考文献:「諸学部の争い」角忍他訳、『カント全集18』岩波書店、2002年。
「学部の争い」小倉志祥訳、『カント全集13』理想社、1988年。
 _
_
●第3回 2008年1月28日「フンボルトにおける大学と〈教養〉」
発表者:斉藤渉 (大阪大学大学院言語文化研究科准教授)
参考文献:
W. v. フンボルト『人間形成と言語』、C. メンツェ編、K. ルーメル、小笠原道雄、江島正子訳、以文社、 1989年。(「ベルリン高等学術施設の内的ならびに外的組織について」、 「ベルリン大学設置申請書」、「ケーニヒスベルク学校計画」、「リトアニア学校計画」などを収録。)
●2008年2月23日シンポジウム「哲学と大学―人文科学の未来」
・「ヘーゲルにおける大学と哲学」
発表者:大河内泰樹(埼玉大学他非常勤講師) コメント:岩崎稔(東京外国語大学)
・「哲学、教育、大学をめぐるジャック・デリダの理論と実践」
発表者:西山雄二(東京大学) コメント:鵜飼哲(一橋大学)
・「ヨーロッパの高等教育再編と人文科学への影響」
発表者:大場淳(広島大学) コメント:藤田尚志(学術振興会特別研究員)
・全体討議「日本の大学の現状と人文科学の未来」
岩崎稔、鵜飼哲、大場淳、小林康夫(UTCP)
 _
_
●第4回 2008年4月30日「条件付きの大学―フランスのエリート教育の光と影」
発表者:藤田尚志 (学術振興会特別研究員)
参考文献:
ジャック・デリダ『条件なき大学』西山雄二訳、月曜社、2008年。
マリー・ドュリュ=ベラ『フランスの学歴インフレと格差社会―能力主義という幻想』林昌宏訳 、明石書店、2007年。
●第5回 2008年7月3日
マックス・ウェーバーの学問論―大学のアメリカ化と知識人の「責任」
発表者:野口雅弘 (早稲田大学政治経済学術院・助教)
 _
_
●2008年9月19日
ワークショップ「大学の名において私たちは何を信じることを許されているのか」
・「ニーチェ的意味における哲学と大学」
竹内綱史(学振特別研究員) 司会:宮崎裕助(新潟大学)
・「研究空間スユ+ノモ」の挑戦@韓国・ソウル
西山雄二(東京大学)
・公開討議「大学の名において私たちは何を信じることを許されているのか――『現代思想2008年9月号 特集:大学の困難』(青土社)をめぐって」
発言:大河内泰樹(京都産業大学)、斉藤渉(大阪大学)、藤田尚志(学振特別研究員)、宮崎裕助(新潟大学) 司会・応答:西山雄二
第1回ビル・レディングズ『廃墟のなかの大学』
第1回ビル・レディングズ『廃墟のなかの大学』
2007年11月2日、東京大学グローバルCOEの「共生のための国際哲学教育研究センター」のプログラムとして、「哲学と大学―近代の哲学的大学論の系譜と人文知の未来」がスタートしました。第1回目(発表者:西山雄二)はビル・レディングズの『廃墟のなかの大学』(青木健・斎藤信平訳、法政大学出版局、2000年)を取り上げて、哲学と大学の歴史的関係を概観し、グローバル状況下における人文学の現状を考察しました。
→発表レジュメ「ビル・レディングズ『廃墟のなかの大学』の衝撃」(PDF)
34歳で夭逝したレディングズのこの遺著では、歴史の幅広い文脈のなかに哲学と大学の関係を位置づける野心的試みがなされています。大学の歴史と理念の相互性を浮き彫りにしつつ、近代の大学からグローバル時代の大学(「ポスト歴史的大学」)への移行が考察されます。彼は「文化」に力点を置き、近代の大学は近代国家のための「国民文化」形成という役割を担ってきたとします。ドイツでは哲学、英米では文学によって国民文化に確固たる歴史的アイデンティティが付与され、然るべき教養として学生たちに教授されてきたわけです。カルチュラル・スタディーズの隆盛は文化概念を決定的に変容させ、大学と国民文化の結びつきを多種多様な文脈へと開いていきました。

この著作で独創的な点は、グローバル時代の大学を突き動かす概念として「エクセレンス(卓越性)」を分析したことです。「エクセレンス」は外的対象も内実ももたない空疎な概念であり、それゆえに、大学に関するあらゆる事象の比較を可能とします。「要点は、エクセレンスが何かを誰も知らないということではなくて、エクセレンスが何なのかすべての人が自分なりの考えをもっているということである」。学生の成績、講義のサイズ、教員の質、財政状態、図書館の蔵書、卒業生の社会的声価から、駐車場の整然さまでがエクセレンスの名の下に評価されます。そして、大学の序列化やランキングを可能とし、さらには大学に対する学生の消費者主義を促進します。
討議の時間には、レディングズの視座が英米の大学からのものであることが指摘されました。グローバル時代において、大学はむしろ国民国家にある程度従属し、国力を増強するために国際競争を強いられます。グローバル化(≒アメリカ化)に対抗するために大学と国民国家的制度の結びつきは強化される傾向もあるでしょう。
自然を研究対象とする自然科学は諸事象の法則性を解明しようと普遍的なものへの志向性を有します。他方で、人為的構築物を研究対象とする社会科学は政治・経済・文化のグローバル化を受けて、より広い視座からの理論構築を強いられています。そこで、人文科学はどのように振舞うべきかが、現在問われてきます。人間の精神的活動を自己内省的に考察する人文科学では、自然の普遍性と社会のグローバル化の狭間で人間性を探求することが課題となってきます。それは、19世紀初頭、近代の入り口でフンボルトらが構想したように、国民文化の(再)形成とは異なる道となることでしょう。

ともかく、レディングズのこの著作は、グローバル時代における人文学の葛藤に正面から向き合った点で評価できます。ただ、前半の歴史的・社会的・哲学的分析の出来のよさと比べると、後半部で示される彼の展望は無理があるように思います。「第10章 教育の現場」で提示される、自律した諸主体を想定しない反モダニスト的な教育法、「第12章 不同意の共同体」で示される、同意を前提とせず、異質なものを受容する不同意の他律的地平は、ともに説得力のある結論にはなっていません。
ただ、大学で何を学ぶのか、大学にいって何になるのかといった、真理論や実践論、目的論の他に、彼が信をめぐる問いを提起している件が心に残りました。大学をめぐる深い信の問いを経ることなしに、現在の大学や人文学を根本的に考えることはできないように思うからです。
「教師と学生が直面している問題は、このように何を信じるべきかの問題ではなく、学術機関に対してどんな分析を加えれば、信念が価値あるものになるかという問題である。エクセレンスの観点からは、いったいどんな信念が価値評価の糧となりえないのだろうか」。
以下、討議内容を掲載しておきます。
1.「宛先Adressat」の問題
1)「私たち」の宛先
「哲学と大学」といった議論を始めるにあたっては、つねに議論の「場」がどのように形成されているのかに注意を払わねばならない。現在の状況において、「哲学と大学」などという「高尚な主題」を「東京大学」、しかも「グローバルCOEプログラム」において論じている私たちの立場や語り口自体を客観化しなければならない。言い換えれば、「ここにいない者」に注意を払わねばならない。
「ここにいない者」:
a)女性 (女性の参加は今回1名あったが、大学教員の男女比を考えると女性の視点はやはり重要)
b)「崖っぷち弱小大学」(杉山幸丸、中公新書ラクレ)の存在
「一流大学」と「弱小大学」の両極だけでなく、衰退する中間層の大学の状況も考慮に入れた方が良い。それは例えば、かつて「駅弁大学」と揶揄された地方の旧国立大学である。地方大学は地域の学術的・文化的中心地の重要な役割を担い、地元の優秀な人材を育て上げてきた。地方の行政官や教員など、地域に貢献する秀逸な人材育成の場として機能してきた。一流大学の旧帝国大学は別として、独立行政法人化以降、運営費交付金の削減の影響をもっとも被っているのが地方の旧国立大学。地方大学の衰退は大学状況のみならず、地域社会の盛衰という観点からも見過ごせない現象。
c)自然科学・理工系の存在 社会科学の存在
「大学とは何か」という問い自体が人文科学に固有の響きをもつのは何故か。自然科学はそもそも、大学という知の枠にとどまらない普遍性を相手にしているからか。
d)非西洋系の存在
「哲学と大学」という問題設定はきわめて西洋的。
2)レディングズの宛先
今回取り上げるレディングズの『廃墟のなかの大学』は、誰に向かって書かれているのか? 主として大学人に宛てられているようにみえるが、それだけでいいのか。
たしかに、性差などマイノリティの問題はカルチュラル・スタディーズの勃興の分析を通じて明瞭に意識されている。その一方で、「大学は従来、国民文化と強く結びついていたが、グローバリゼーション状況下でその結びつきが決定的に解消される」という図式が打ち出される。言い換えれば、本書においては「文化」と「国民文化」がほぼ同一視されてしまっているように思えるが、果たしてそれは妥当か(例えば、この図式は戦後日本にどれほど当てはまるのだろうか)。
こうした同一視は、日本のように大学の数がきわめて多い国において、以下のような点を分析する上で、見逃しえない影響を及ぼすだろう。
a)大学と文化の関係、教育と研究の関係
大学に「文化=教養」を求めるのか、ノウハウ=各種資格を求めるのか。
b)文科系と理科系の関係
c)カルスタの現状
2.『廃墟のなかの大学』の構成
批判的分析の部分(主に1~3章)、歴史的経緯の部分(主に4~9章)はおおむね的確。しかし、積極的提言の部分(主に10‐12章)にはかなり不満が残る。
批判的分析に関して「的確」というのは、現状を客観的に分析するに際して、「エクセレンス」概念がそのイデオロギー的な性格を暴露するところまで徹底的に議論を進めることによって、この「空疎な概念」に批判的な射程をもたせたから。「おおむね」というのは、その批判的射程が厳密に(とりわけ特殊日本的に)どこまで届きうるものなのか、未だ判然としないところも残るから。
もう少し時間があれば議論を深めたかったのは、むしろ後半部について、とりわけ「不同意の共同体」や「大学をめぐる信の問い」の真の射程について。
3.商業主義(commercialism)と消費者主義(consumerism)
エクセレンスを量的一元化志向と捉えるとしても、大学において追求されるエクセレンスは質においても量においても異なる。一方で、研究における学問的エクセレンスを追求する姿勢が文科省によって奨励・推進されるという事態がある。他方で、「即戦力」教育・資格取得を強調することで少しでも多くの学生を囲い込もうとする事態がある。両者はまったく同じ事態の裏表ではないように思われる。
だが、前者は国際競争における生き残りを賭けた闘いであり、後者は少子化を踏まえ生き残りを模索する闘いであると単純に定義できるだろうか。これについてはもう少し考えてみる必要がある。
エクセレンスの「本性の差異」に対して、あらゆる大学を貫く傾向、「差異の本性」として指摘できるのは、学生や学費を払う親を「消費者」として位置づける消費者主義の蔓延ではないだろうか。周知のように、オープン・キャンパスなどの試みはすべて、学生獲得競争の一端にほかならない。留年する学生が大学側から「賛助会員」と暗に呼称されることもあるらしい。
第2回「カント『学部の争い』」
第2回「カント『学部の争い』」
2007年12月9日、公開共同研究「哲学と大学」第2回は、UTCP共同研究員・宮崎裕助によるカントの『学部の争い』に関する発表だった。

『学部の争い』(1798年)は、『人間学』と並んで、カントが生前に公表した最後の著作である。初版の諸論文は検閲に遭って発禁処分となったため、序言には検閲を行ったフリードリッヒ・ヴィルヘルム二世への弁明が綴られている。大学論は第1部「哲学部と神学部との争い」で展開されており、この部分は日本語訳にしてわずか20頁ほどだが実に豊かな問題を提起している。
カントの時代、大学は三つの上級学部(神学部、法学部、医学部)と下級学部(哲学部)とから構成されている。上級学部の教説は国民に強力な影響力をもつ。神学部は各人の永遠の幸せを、法学部は社会の各成員の市民的な幸せを、医学部は肉体的な幸せ(長寿と健康)を対象とする。上級学部は政府から委託されて、文書にもとづく規約(聖書、国法、医療法規)を整備することで公衆の生活に直接的な影響を及ぼす。政府は上級学部の教説を認可し統御することで、国家権力を行使するのである。
他方、下級学部(哲学部)は国家の利害関心からは独立しており、その教説は国民の理性のみに委ねられる。哲学部は国家権力の後ろ盾がないが、しかし、すべての教説を判定する理性の自由を保証されている。哲学部は国家権力に対して反権力を対置するのではなく、一種の非権力、つまり権力とは異質の理性を対置することによって、この権力の限界画定を内側から試みるのだ(デリダ)。哲学部は大学の一学部として制度的に限定されると同時に、批判的理性を行使する無条件な権利をもつという点で学問の全領域を覆う。それゆえ、哲学部をめぐるアポリアは、ひとつの有限な場所と遍在的な非場所(シェリング)という二重性をもつ哲学部をどのように大学制度のうちに定着したらよいのか、という問いになるだろう。
上級学部と下級学部の争いは合法的なものであって、戦争ではない。上級学部が右派として政府の規約を弁護するならば、下級学部(哲学部)は反対党派(左派)として厳密な吟味検討をおこない、異論を唱える。理性という裁判官が真理を公に呈示するために判決を下すかぎりにおいて、この争いは国家権力に対しても有益なのである。その場合、まるで梃子の作用が働くように、真理への忠実さという点で哲学部は右派となり、上級学部は左派となるだろう。こうした大学の建築術的な図式において重要なことは、各勢力の争いの両極を分かつ支点において大学全体の方向を転換するような「梃子(モクロス)」(デリダ)の作用が維持されること、そうすることで、真理をめぐる複数の政治的戦略が可能性として残されることであるだろう。

討議の時間では、カントの大学論を現在の視点から読む上での注意事項が挙げられた。まず、カントのいう哲学部と哲学を分けて考える必要性だ。カントの時代の哲学部から文学部や理学部、経済学部などが派生してくるわけで、それは狭義の哲学部ではない。また、この大学論はカントの政治的な振る舞いが込められたテクストであり、その文脈を十分に考慮しなければならない。
大学の各学部の上級/下級という区分は、現在で言うと専門と基礎教養に対応するものだろうが、カントの区分は実によく練り上げられている。神学は来世、法学と医学は現世を対象とし、さらに法学と医学は社会的次元と身体的次元に関係する。上級学部は人間の生活に関わるほとんどすべての領域を包括するのであり、これを統御する国家は優れた「統治性」(フーコー)を発揮することができる。これに対して、下級学部(哲学部)には理性の自由が許可されるとカントは幾度も書いているのだが、意外にも、真理に関する記述は手薄である。つまり、カントは真理を実定的なものとして提示するのではなく、むしろ真理の可能性の条件を提示し、理性の自由な判断はいかにして可能かを論及するのだ。例えば、真理とは虚偽を発見し、これを排除する手続きであって、そのためには公開性の原則が保持されなければならない、というように。
「学者の形象」に関しても議論となった。カントは『啓蒙とは何か』において「als Gelehrter(学者として)」という表現を何度か使用して、理性の公的使用を説明した。日常生活において聖職者や士官として社会的役割をはたす人々が、「Gelehrter」として理性を世界市民的な視点から行使しうるとされる。この場合、「Gelehrter」は敢えて「知識人」と解した方がよい、という意見が出た。カントは大学教育を受けた者を原像として「Gelehrter」を使用し、これを「自分の見解を書くことを通じて表現できる者」という意味合いで使っているのではないか。こうした「学者の形象」を踏まえて、それでは、誰もが「自分の見解を書くことを通じて表現できる」この高度情報化社会において、「在野の学者」とはいったい誰のことを指すのか、という問いも発せられた。
前回に引き続き関西から参加してくれた斉藤渉氏(大阪大学)は、カントの時代の大学制度に関して詳細なコメントを加えてくれた。次回(1月28日)は、フンボルト研究者である斉藤氏による発表である。あのフンボルトの大学理念がいよいよ登場するわけだ。
第3回「フンボルトにおける大学と〈教養〉」
第3回「フンボルトにおける大学と〈教養〉」
2008年1月28日、公開共同研究 「哲学と大学」の第 3 回、「フンボルトにおける大学と〈教養〉」が実施され、斉藤渉(大阪大学言語文化研究科准教授)が発表をおこなった。
周知のように、フンボルトは、ナポレオン軍に大敗後の荒廃状態のなか、プロイセンの精神的な権威の復興のために、内務省の宗教・公教育局局長としてベルリン大学の創設に尽力した重要人物である。局長フンボルトの主要な職務は、宗教・公教育局制度の整備、学校・教育計画の策定、財政管理の健全化(教員や聖職者の給与の安定化)であった。だが実際は、聖職者の教育行政への圧力や地方分権的行政機構の不統一から教育改革は暗礁に乗り上げ、フンボルトは一局長のもちえた権限に限界を感じて、1年半あまりの在職期間の後、1810年春に辞職願を出している。1810年9月29日にベルリン大学が創設された時、彼はすでにウィーン大使に着任している。それゆえ、彼の経歴や歴史的・社会的背景を加味した上で、ベルリン大学創設者=フンボルトという規定のイメージを捉えなおす必要がある。

本発表では主に、フンボルトにおけるBildung概念が論じられた。これは動詞bilden(形成する・形づくる)およびその再帰形sich bilden(自らを形成する・形づくる)の名詞形であり、「教育」「陶冶」「教養」「形成(人間形成・人格形成・国民形成)」などの訳語が可能である。この語はさらに、教育(Erziehung)、文化(Kultur)、啓蒙(Aufklärung)などとも関連しており、当時の社会的・歴史的・思想的文脈を解明するうえで重要な言葉である。
フンボルトがその学校計画のなかで目指した教育は、一般的人間教育(allgemeine Menschenbildung)である。社会に役立つ応用技能の習得を目途とする職業教育ではなく、一般的人間教育は「人間自身を強め、純化し、整えること」を目的とする。それは「どのような人間にも必要な能力を育成する」という点で「一般的」である。また、一般的人間教育において重視されるのは、「素材」ではなく「形式」である。つまり、個々の学習の内容ではなく、さまざまな素材に共通する基盤となるものの習得、すなわち、「形式的陶冶(formale Bildung)」が尊重されるのだ。これは、実生活の要求に即した有用な人材の育成を目指し、古典語教育重視を批判した、啓蒙主義の教育学とは相反する考え方であった。例えば、「形式的陶冶」の論理によれば、古典語学習は、特定の職業に限定された効用ではなく、思考や判断の能力を養うという一般的目的のために有効かつ必要とされるのである(教育における「素材」と「形式」の関係――もちろん、両者を明確に区別することなどできない――は、今日の外国語学習を考えるときに興味深い議論である。「素材」として「役に立つから」外国語を学ぶのか、それとも、「形式」として「言語能力一般の向上のために」外国語を学ぶのか)。
フンボルトの大学論としては、「ベルリンに設置される高等教育施設の内的および外的組織について」がもっとも有名である。これは未完の草稿(アカデミー版で10ページ)であり、かつ、 成立時期が未詳(推定も1809年12月から1810年夏までの幅あり)であるという点で慎重な解釈を要求するテクストである。さらに、フンボルトはベルリン大学の構想にあたって、J. B. エアハルト、J. J. エンゲル、フィヒテ、シュライアーマッハー、シュテフェンスなどの既存の大学論を読んでいたと考えられるので、フンボルト独自の着想がどこにあるのかを見定めることは困難であるだろう。
斉藤はまず、大学の「孤独と自由」という論点を取り上げた。「[高等教育]施設が目的を達成できるのは、一つ一つの施設が学問(Wissenschaft)の純粋な理念と対峙する場合だけであるから、孤独と自由(Einsamkeit und Freiheit)こそがその領域内で指導的な原理となる」という有名な箇所である。この場合、「純粋」とは、社会や国家(大学の外部)による要求や介入を捨象したという意味であり、それゆえ、大学は自己の活動に責任をもち(=孤独)、他からの干渉を受けない(=自由)とされる。ただし、フンボルトはいたずらに大学にとっての国家無用論を唱えたのではなく、最終的には「実践」の言説を強調しているのであり、ここには、学問の純粋さの社会的実践という屈折した思考が描かれていると言える。
(「孤独」は客観的な概念ではなく、あくまでも反省的な概念である。つまり、孤独とは「独りでいること」ではなく、「独りでいると感じること」であり、例えば、ひとは「都会の雑踏のなかでも孤独でありうる」。大学を「孤独」と規定する場合には、それゆえ、その内省的な質が問われることになるだろう。意図的に社会から距離をとることのできる「孤高」なのか、それとも、社会から排除された「孤立」なのか。大学は社会とは異質な論理をもつ場であるべき〔=孤独〕だ、という場合、その反省的な質は時代と社会の各文脈において異なる。)
次に、フンボルトが提起したとされる、いわゆる「研究と教育の統一」である(実は彼自身はこの表現を使用していない)。「教師と生徒の関係もこれまでとはまったく異なったものになる。教師は生徒のために存在するのではなく、両者は等しく学問のために存在する」。大学での学問研究は教師を不用にし、学生はもはや学習者ではなくなる。「教育」が伝達可能な完成した知識の形態を前提とするとすれば、「学問」(研究と教育の統一)はつねに未完成な創造的探究であり、教育の対象とはなりえない。これは狭義の大学理念に収まるものではなく、「啓蒙」の課題としての「自ら考える」ことの実践という広義の文脈をもっている。
最後に、斉藤は、大学運営に関するフンボルトの実務的側面を強調した。魅力的な大学運営は諸外国からの留学生を引き寄せるため、ベルリン市への経済効果が見込まれること。また、ベルリン大学の創設によって、政府に対する国内の知的尊敬を高めうるだけでなく、他のヨーロッパ諸国に対する国家主義的な対外文化政策としても有効であること。「深く徹底した精神は、学問と技芸においてドイツ民族が他の民族に勝っている点ですが、それは大学によってのみ維持されうるものです」言うフンボルトには、すでに「ドイツ的大学の自己主張」の問いが見え隠れしている。

質疑の時間にはさまざまな論点に話が及んだ。ここでは、フンボルト・モデルに関する論争を引き起こしたパレチェクの仮設にだけ触れておこう。
(パレチェクの立論に関しては、潮木守一氏の論考「フンボルト理念とは神話だったのか―パレチェク仮説との対話」、広島大学高等教育研究開発センター編『大学論集』第38集、2007年3月)が有益である。
シルヴィア・パレチェクは、論考「19世紀ドイツの大学で『フンボルト・モデル』は広まっていたか?」(2001年)において、近代的大学の理念を提示したとされるフンボルトの影響を否定した。まず第一に、「フンボルト・モデル」「ベルリン・モデル」と呼ばれるものは19世紀を通じて知られておらず、1910年以降に流通し始めたものである。つまり、ベルリン大学100周年記念行事を通じて、大学の「フンボルト・モデル」は発見され、神話化されたのであり、それは、当時の自然科学の隆盛に対抗するための精神科学の復興の試みでもあった。また、「研究と教育の統一」という大学モデルが19世紀に浸透していたかどうかはきわめて疑わしく、実際は依然として職業教育が大学の主たる役割であった。
斉藤によれば、まず、パレチェクは主に19世紀の百科事典や法律教科書を調べて、フンボルトの名前が引かれていないことを論拠に「フンボルト・モデル」の影響力を否定する。フンボルトの大学理念には、たしかに事後的な伝統の発明という作為性がつきまとうものの、しかし、彼女の議論にはいくつもの留保をつけなければならない。例えば、パレチェクはベルリン大学関係の資料などは参照しておらず、こうした関係資料を踏まえてより精度の高い説明を導き出すべきではないだろうか。次に、フンボルトは独創的な思想家ではなく、むしろ、さまざまな思想の網の目のなかで自らの言説を紡ぎ出した人物である。それゆえ、「フンボルト理念」をフンボルト個人に即して実体化し批判するのではなく、むしろ、当時のもろもろの大学論の伝統と影響関係から出発して、「フンボルト・モデル」「ベルリン・モデル」を読み解く必要があるのではないだろうか。

フンボルトが準備したベルリン大学は敗戦後の荒廃状況のなかで、国家の精神的権威の復興のために誕生した。
「国家が不幸にもこれまでとまったく違う状況に置かれた場合、何らかの方法でふたたび諸国の注意を自らに向けさせ、何らかの点で抜きん出る努力をすることが必要だと思われる。啓蒙と学問の振興によってプロイセンはいつも尊敬を勝ちとってきたが、この尊敬を増し、外国の賛同を取りつけ、政治的にもまったく無害な方法でドイツにおける精神的権威を獲得することは容易であろう。こうした権威は、さまざまな点できわめて重要になりうるものである。」
過度の経済的競争を強いるグローバル化経済によって、国家が「これまでとまったく違う状況に置かれた」現在、大学は諸個人の「精神的権威の復興」に寄与する場になりえているだろうか。すでに政治・経済の論理に幾重にも包囲されている以上、大学は「政治的にまったく無害な方法で」学問探究を進展させることはできない。フンボルト・モデルが発明された伝統だったとしても、彼が提起した問いの数々――大学の主権性、研究と教育の統一ないしは対立、大学組織と経済・社会との関係、学問の宛先としての権威の所在――は、とりわけ学問が困難な時代において、何度でも私たちに回帰する。
シンポジウム「哲学と大学―人文科学の未来」
シンポジウム「哲学と大学―人文科学の未来」
2008年2月23日、駒場キャンパスでUTCPシンポジウム「哲学と大学―人文科学の未来」が開催された(司会:宮崎裕助・西山雄二)。
本シンポジウムは、UTCPの公開共同研究「哲学と大学」の一環として開催されるものである。公開共同研究「哲学と大学」の目的は、各哲学者の大学論を批判的に考察することで、哲学と大学の制度や理念との関係を問い直すことである。「哲学と大学」の問いは日本では大学紛争の1960年代末にとくに議論され、実際に『理想』誌(1969年1月号)、『実存主義』誌(1969年4月号)などで特集が組まれている。現在、グローバルな市場原理主義によって効率性や収益性の論理が社会そして大学を席巻しているが、そうした状況において哲学や人文学の意義を再び問うてみたい、というのが本研究会の趣旨である。
1. 教養・体系・国家:ヘーゲルにおける「大学」と「哲学」
発表者:大河内泰樹(埼玉大学他非常勤講師) コメント:岩崎稔(東京外国語大学)

ヘーゲルの大学論・教育論の文献はギムナジウム校長・ベルリン大学学長としての式辞、ハイデルベルクおよびベルリン大学での教授就任演説など数少ない。だが、ヘーゲルがエンチュクロぺディー(体系)を志向したことから彼の成果すべてが教育論だったとも言えるのではないか。なぜなら、エンチュクロぺディーはそもそも円環の中にある教養(enkyklios paideia)を指し、円環運動に即して包括的知が獲得される過程であるからだ。ヘーゲルにとって、哲学教育はギムナジウムの「エンチュクロペディー」においても大学での「哲学」においても「予備学」に過ぎないとされる。しかし、哲学自体がまさに予備学であるにすぎず、予備学の向こうには何も存在しない。この意味で、ヘーゲルの教養は理想的な人間のモデルへと人間を形作ることではなく、自己否定の反復が哲学による教養の目的となる。
ヘーゲルによれば、「真理の認識はその目的を外部にもたない以上、有用ではなく」、「哲学との交通は生活の日曜日(der Sonntag des Lebens)とみなされうる」。コジェーヴが強調して有名になったこの「人生の日曜日」を、大河内は宗教から哲学への移行、『創世記』の日曜日の世俗化として解釈する。ヘーゲルは世俗化された日曜日の場所をプロイセン国家によって保証された大学とみなしていた。大学での教養や哲学の教育によって獲得されるのは、何らかの拠り所となるような有用な常識や健全な人間悟性ではない。ヘーゲルにとっての大学とは否定性が作用する安息のない日曜日の無用性そのものなのである。
岩崎稔氏はまず、国立大学の独立行政法人化反対運動への彼自身のコミットメントは、ヘーゲル哲学の研究とはどこかで重なっていたと幾分控え目な声調で告白する。「人生の日曜日」については、ヘーゲルはそもそもキリスト教的表現を世俗化する達人であり、ここにも労働と休日の関係が有用-無用の対概念でもって上手く表わされている。通常、日曜日とは労働の後で人間が自分の力を再び獲得する時間である。『創世記』にならえば、世界創造の後で神が振り返って自らの創造物を見るという認識の時間である。ヘーゲルにならえば、その役割を継承するのが哲学であり、世界史の展開を事後的に思考することが哲学を日曜日たらしめるのである。最後に岩崎氏は、教養を否定性とともに規定するヘーゲルの考え方は実に魅力的であり、今後もヘーゲル思想とともに大学や教養について批判的な考察を続けたいと力強く言葉を締めくくった。
2. 哲学、教育、大学をめぐるジャック・デリダの理論と実践
発表者:西山雄二(東京大学) コメント:鵜飼哲(一橋大学)

ジャック・デリダはフランスでは伝統的な大学制度の門外漢だったものの、哲学と教育、哲学と大学の関係を実践と理論の両面で真摯に問い続けた。発表では、哲学、教育、大学をめぐるデリダの実践と理論を概観した後、哲学と大学という主題をめぐってデリダがカントをいかに読み解いたのかが論じられた。
デリダは晩年の大学論『条件なき大学』において、大学の無条件性として〈すべてを公的に言う権利〉を提唱する。当然ながら、すべてを公的に言うことなど事実としては不可能であり、これは事実と権利の間での交渉を要求する。〈すべてを公的に言う権利〉はカントの公表性に類似しているように見えるが、しかし、それはいまだ知られざる真理を十全に開示すること(情報公開による説明責任)ではなく、むしろ、秘密や嘘、偽証といった類をも含む虚構と紙一重の権利である点でカントの公表性以上のものであるだろう。また、カントが「理性が公的に語る権利」を哲学部に求め、この権利を大学の建築術的構図の要としたのに対し、デリダは〈すべてを公的に言う権利〉を大学の主権を保存する特権(学問的自由)ではなく、大学を創造的な変形へと導く力だとする。大学における真理論と大学の制度論の結節点に働きかけるこの権利は、たしかに、大学の主権を強化することのない弱さや脆さと隣り合わせの原理である。しかし、これはきわめて両義的で微妙な点だが、〈すべてを言う権利〉は政治的、法的、経済的な力が大学を我有化しようとする場合、これらに創造的に抵抗する力としてかろうじて残余するともされる。
鵜飼哲氏はデリダの卓越した読み手として、『条件なき大学』をめぐって補足的な、だが、本質を見事に浮かび上がらせるコメントを加えた。『条件なき大学』は大学教師をめぐる職業論、労働論でもある。デリダはprofessionの語源「公的に語ること」にさかのぼり、教師(professeur)の職務をある種の信仰告白(profession de foi)として規定する。フランス語professionのドイツ語はBerufであるが、ウェーバーの分析からもわかるように、職業論は宗教と世俗に深く関わる。また、19世紀から20世紀にかけて、近代の大学モデルはドイツ(とくにベルリン大学)からアメリカへと移行したが、これはプロテスタント圏で大学モデルが形成されてきたことを意味する。デリダはこの文脈を十分に意識し、宗教と世俗の問いを絡めつつ、職業の観点から大学論を執筆しているのではないか。
また、〈すべてを公的に言う権利〉だが、明示してはいないものの、デリダはこの表現をブランショから引いている。ブランショはサドのエクリチュールを参照しつつ、「数ある自由のなかでも第一のものはすべてを言う自由である」とする。つまり、〈すべてを公的に言う〉という公表性をめぐって、カント、サド、ブランショ、デリダが複雑に絡み合い、啓蒙と脱構築、理性と狂気、文学と政治の問いが錯綜しているのである。
3. ヨーロッパの高等教育再編と人文科学への影響
発表者:大場淳(広島大学) コメント:藤田尚志(学術振興会特別研究員)

大場氏はまず、欧州における高等教育再編の流れを概観した。欧州では1999年以来、2年ごとに高等教育担当大臣の会合が開かれ、欧州高等教育圏の枠組みが議論されてきた(ボローニャ・プロセス)。EUの国際競争力を高める戦略の一環として、高等教育や研究のネットワークづくりが進められている。この過程でとくに重視されているのが、共通の学位制度の構築と高等教育の質保証である。後者については、研究教育の市場化とともに、提供される「商品」や「サービス」の質の確保が制度化されてきた。伝統的な大学の自治の論理ではなく、評価制度、情報公開、利用者(学生)の参加といった要素が大学には不可欠となる(日本では学生の参加が著しく遅れている)。さらに、大学評価を学生(利用者)がおこなう場合、例えばスコットランドのように学生自身が事前に研修を受けて、意識と学識を高めるというやり方は斬新だった。
ボローニャ・プロセスに法的拘束力はないため、各国の対応には温度差がある。逆に言えば、欧州規模での画一的な教育再編が進行しているのではなく、各国制度の多様性や質保証(市場化)の多様性が保持されているのである。そして、重要なことは、規制緩和(市場化)か大学の保護かという二者択一ではなく、各国政府が責任をもって高等教育を統制していくことである。
人文科学への影響であるが、フランスでは人文科学の学生や教員の数は近年さほど変化していない。ただ、その内部では多様な変化が生じており、美術史、社会学、心理学が90年代末に拡大し、英語以外の語学は衰退傾向にある。また、職業専門化が奨励され、職業学士が創設されると優秀な学生はそちらに流れていったという。
最後に大場氏は基礎研究を市場化から守ることの必要性を主張した。そのためには、例えば日本でも、大学人は自らの社会的な説明責任を果たしつつ、各国立大学や国大協、さらには文科省などあらゆる関係者と積極的に交渉をし、立体的な議論を展開させることが重要だとした。これはこの日もっとも印象に残った重要な主張のひとつだった。

藤田尚志氏は絶妙な語り口でコメントし、ユニークな視点から哲学と大学の問いを提示して聴衆を魅了した。哲学や思想に携わる者は自分がどのような場所で思考しているのかを問う必要がある。例えば、日本ではドゥルーズ、デリダ、フーコーと並置されるが、彼らがいかなる学術機関に所属し、哲学の教育研究制度にいかに関係したのかはそれぞれ異なっており、思想研究者はそうした基本的な差異に敏感になるべきだろう。また、ヘーゲルは日曜日だけでなく、『信と知』の末尾で聖金曜日にも言及している。日曜日が無用性の安息日だとすれば、金曜日はキリストの復活した日である。平日と日曜日、有用と無用のあいだの対立(例えば市場原理VS大学)ではなく、両者の異質な仕方での交渉を誘発することが大学や哲学の使命ではないだろうか。
4. 全体討議「日本の大学の現状と人文科学の未来」
参加者:岩崎稔、鵜飼哲、大場淳、小林康夫 司会:西山雄二

まずは、大学と新自由主義の関係をつねに問い続けてきた岩崎氏が、国立大学法人化以降の現状を力を込めて報告した。2004年に法人化が実施されて以来、ボディブローのようにその影響が旧来の大学に響いている。高知大学の学長選挙疑惑問題など、その影響が顕著となったのが2007年度だった。大学の慣習法が変質し、学長が独裁的にやろうと思えば何でもできる体制が「トップ・ダウン方式」の美名のもとに整いつつある。
次に、鵜飼氏はフランス語教師の立場から大学の第二外国語の現状について語った。英語優勢の状況下でたしかに仏独語のステータスは下がっている。だが、中国語への関心は高まり、その履修者が増加したために、第二外国語全体の意義は保持されている。今後はEUの動向を見据えながら、仏独語の中心的ヘゲモニーを弱めつつ、イタリア語・スペイン語を含めて外国語を拡充する必要がある。国際的教養を維持するために、大学では第二外国語必修を維持することが望ましいと述べた。

大場氏によれば、学長のトップ・ダウン方式と言っても、アメリカのように、大学教員と学長のあいだで双方向的な意志表示の回路が確立していることが望ましい。日本でも大学運営への学生の参加の可能性を含めて、文科省、学長、教員など関係者のあいだで意識が共有され、互いの意見をフィードバックさせる仕組みが必要である。
最後に、小林氏は人文科学の危機に言及した。ここ20-30年ほどのあいだに人類が経験している文化的変容はおそらくかつてないほど大規模なものである。つまり、人間の知が、そして知を生産する大学が「一般化された競争」のなかに完全にさらされてしまったのだ。この競争はたんに学術研究の優劣だけでなく、軍事技術に象徴される国力の競争にも通じる熾烈なものである。だから、この危機の時代に人文学にできることは、人権や民主主義といった人文主義的な概念の守護者であり続けることではないだろうか。大学という枠を越えて思考しつつ、こうした概念が地上から消えないようにすることではないだろうか――小林氏は熱い口調で語った。

その他にも興味深い議論が交わされた。
人文学と新自由主義は実は内在性という点で似た者同士かもしれない。両者とも「外部はもはやない、この舞台で競争に専念せよ、もっと早く走れ」と駆り立てられ、外部の存在に気がつきにくい。内在性の論理に惑溺することなく、いかにして外部を見出すのかが課題となるだろう。
今年は68年40周年だが、あの時代から私たちの現代までに何が変化したのか、その射程を確認する必要がある。それは研究教育の大衆化、国際化、情報化、ジェンダー性といった課題である。新たな変革を着想する前に、この前の変化を見定めることが重要だ。
領域横断的な研究は重要である。例えば、先頃来日していたドミニク・レステル氏はもともと動物行動学の専門家だった。後に哲学研究へと進路変更して彼は驚いた。動物行動学が従来の哲学的な人間観・動物観の枠組みにいかに深く規定されているのかが透けて見えたからだ。境界を踏み越える彼の視座から、動物行動学と哲学の双方が脱構築されるわけだ。領域を横断することで既成の枠組みが変容する好例である。
シンポジウム全体を通じて、大学、哲学、人文科学という問いが現代の社会状況において実に多種多様な問題を内包していることがわかった。藤田氏の卓抜なコメントを借用すると、このシンポジウムが開催されたのは土曜日である。金曜日と日曜日のあいだ、復活と安息のあいだの時間である。一方で、私たちはもはや旧来の大学への回帰や人文科学の十全な復活を夢見ることはできない。また他方で、市場原理的な競争のなかで、大学や人文科学の新たな形を模索する私たちにとって、十全に休息することなどとても叶いそうにない。だからこそ、引き続き共に問い続けることにしたい――哲学や人文科学、大学を通じて、いまなお、私たちは何を希望することを許されているのか、と。伝統の復活と競争後の安息のあいだで振動する、あの両義的な「土曜日の時間性」に踏みとどまりながら。
(シンポジウムには50余名の参加があり、大阪や山口からはるばるお越しいただいた方もいました。足を運んでいただいたすべての参加者に感謝します。)
第4回 「条件付きの大学―フランスのエリート教育の光と影」
第4回 「条件付きの大学―フランスのエリート教育の光と影」
2008年4月30日、公開共同研究「哲学と大学」第4回が実施され、藤田尚志さん(日本学術振興会特別研究員)が発表「条件付きの大学―フランスにおけるエリート教育の光と影」をおこなった。

藤田さんの発表の大半はジャック・デリダ『条件なき大学』(西山雄二訳、月曜社)の細緻な批判的読解に充てられた。彼の主張は主に次の三点に要約される。
1)「無条件性」(政治)に関して――『条件なき大学』の中心にある「無条件性」という概念は、「正義」や「贈与」などと同様、きわめて後期デリダ的であり、脱構築不可能な逆説的観念ではないか。そしてその逆説性を誇張法によって強調するだけにとどまり、本来であれば直ちに行われるべき「無条件性」の精緻な分析や、《無条件性を条件づけるもの》の具体的な分析が無限に延期されているのではないか。例えば、「無条件性」に関して、デリダは「かのように」の論理に基づいて大半の議論を組み立てているが、しかし、脱構築を出来事の思想として論じる末尾において、〈おそらく〉の思考を引き合いに出している。「かのように」の論理と〈おそらく〉の思考の関係はいかなるものなのか。
2)職業/労働(経済)について――デリダは、資本の論理とはまったく無縁なものとして人文学の純粋性を想定し、それらを大学全般に押し広げようとしているようにみえる。しかし、デリダ自身言うように「大学が真理を事とし職業とする」のであれば、資本の論理ではないとしても、何らかの〈エコノミー〉が人文学においてすらも作動していると考えるべきではないか。
3)パックス・アメリカーナ(文化)について――デリダはカントの「かのように」をアメリカ的人文学研究が継承発展させたことをもって、ドイツの近代大学から現代アメリカの大学へのヘゲモニーの移行を彼なりの仕方で語る権利を確保しようとしているように見える。現代アメリカの大学をモデルとして世界中の大学について語るのであれば、はたしてそれを「資本主義の《精神》」と完全に切り離されたものとして語ることは可能だろうか。
私(西山)は訳者としていくつかのコメントをした。短い講演録『条件なき大学』はたしかに理解しにくい論点を含むテクストである。大学を擁護するために結局何をすればよいのか、という問いに対する具体的な回答は提示されず、理想論が語られているだけだという印象を受けるかもしれない。ただ、大学の無条件性と条件付け、大学の無条件性と主権性、人文学の純潔性と資本の論理をデリダは区別しているのだろうか。無条件性を分割不可能な主権のあらゆるファンタスムから分離することはきわめて困難であり、それゆえ、無条件性は主権との識別しえない地点でかろうじて生じるのではないだろうか。信仰告白の形でデリダが言い表わそうとしているのは、識別が困難な無条件性と主権性との関係ではないだろうか。

また、藤田さんは発表後半、フランスのエリート教育について、大学とグランゼコールを比較しながら分析した。選抜方式や財政面で著しい差別化が図られている両者だが、近年ではグランゼコールの特権性に対する批判も高まっている。例えば、国立土木学校の元学長ピエール・ヴェルツは、『グランゼコールを救わねばならないのか。選抜の文化から刷新の文化へ』(2007年)において、グランゼコールのフランス的閉鎖性を指摘し、ハーヴァードやイェール、オックスブリッジなど海外の一流理工系大学と比べて研究教育制度の規模が中途半端だとしている。
藤田さんは「エリート教育には賛成、ミクロエリート主義には反対」というヴェルツの主張を強調しつつ、「日本でエリート教育は可能か」と問う。藤田さんによれば、例えば、世界基準の哲学・思想研究のためには、1)哲学史・思想史に関する知識(技術力)、2)問題を直観する力ないし感性(身体能力)、3)確かな語学力が必要であり、そのための教育制度を日本でも整備する必要がある。
私見では、ミクロエリート主義は、例えば、社会的に負けたくないという心理に後押しされて、有名校に入学・進学することで将来の安定を目指そうとする私的な出世主義と同義であるだろう。これに対して、エリート教育は、社会の安定と繁栄を実現するべく、公共的な視点から行動し思考することができる人材の育成のことを指すのだろう。藤田さんが指摘するように、「エリート教育」という響きが敬遠され、知性に対するシニシズムが浸透する日本社会でこの問いを考える意義は大きいと感じられた。
第5回 「マックス・ウェーバーの学問論」
第5回 「マックス・ウェーバーの学問論」
2008年7月3日、公開共同研究「哲学と大学」第5回が実施され、野口雅弘 (早稲田大学政治経済学術院・助教)が発表「マックス・ウェーバーの学問論――大学のアメリカ化と知識人の「責任」」をおこなった。『職業としての学問』(1917/19年)が集中的に読解され、そのアクチュアルな解釈が披露された。

『職業としての学問』において、ウェーバーは二つの流れと対決している。一つ目は、第一次世界大戦後の政治の横溢状況のなかで、大学の講堂に「指導者」を求め、「生き方」を聞きに来る若者たち。二つ目は、アメリカ的な技術的手段としての学問である。
学問は世界観を教授するのか、それとも、生活上の技術を提供するのか――1910年代、大学モデルの趨勢はドイツ型モデルからアメリカ型モデルに決定的に移行した。膨大な研究予算によって工業化や専門化が促進されるアメリカ型の大学が優位となり、生き方の基準となる原則の研究教育を掲げてきた大学先進国ドイツが凋落し始めたのである。
なるほど、ウェーバーはこの講演のなかで、学問は「生き方」を教示するものではなく、研究の専門化に随従しなければならない、と若者たちに厳しく説く。彼はアメリカ的な実証主義の視座からドイツの学問観の後進性を批判しているようにみえる。だがしかし、野口氏によれば、ウェーバーはアメリカ―ドイツ双方の理念から距離を取りつつ、その両義的な立場から学問の意義や学術への態度を規定しようとする。

ただ、ウェーバーの戦略は安易な相対主義に帰着するものではなく、むしろ諸々の価値対立のなかでの態度決定の責任と切り離せない。彼は、「もし君たちがこれこれの立場をとるべく決心すれば、君たちはその特定の神にのみ仕え、他の神には侮辱を与えることになる」と言う。つまり、自分が態度決定をおこなうことで、何らかの犠牲がつねに生じていることを自覚させ、対立関係やジレンマに敏感であるように促すことが学問の「責任」なのである。専門に没頭することによって、より広範な視野で、他の価値の犠牲に対する感性を洗練させること――これこそが「学問としての学問がなしうる最後の功績」であり、また「学問の限界」なのである。
その他にも、不安定な身分だが自由な「私講師」と常勤職だが自由のない「助手」という研究者の類型、もっとも厳しいウェーバー批判者レオ・シュトラウスの評価、価値対立の表面化が見えにくい冷戦以後の脱政治化状況、といった興味深い主題が議論された。
ウェーバーは学問にできることとして、①技術に関する知識の教授伝達、②思考の方法、そのための用具と訓練の提供、③明晰さと責任という教師の義務、を挙げている。野口氏は「この規定はあまりにもシンプルだったので、若い頃に初めて読んだときにはかなり拍子抜けした」と告白する。これに対して、未來社社主・西谷能英氏は応答する、「ウェーバーは学問の単純な限定を提示しつつ、だがしかし、その枠内では徹底的に学問を追求しなければならないとする。つまり、学問の限界に触れ続けなければならないのだ。学問におけるこうした徹底性の追求に読者は胸を打たれるのではないか」、と。
『職業としての学問』はかくして、学問の素朴な自己限定と学術活動の過度の情熱が共存する稀有なテクストであり、「学問にいったい何ができるか」という問いの前で逡巡する多くの読者をこれからも魅了し続けるだろう。『職業としての学問』の結論にいささか拍子抜けした野口氏がドイツおよび日本で研究書を刊行し、気鋭のマックス・ウェーバー研究者として活躍していることがその何よりの証左だ。
ワークショップ「大学の名において私たちは何を信じることを許されているのか」
ワークショップ「大学の名において私たちは何を信じることを許されているのか」
2008年9月19日、公開共同研究「哲学と大学」のワークショップ「大学の名において私たちは何を信じることを許されているのか」が50数名の参加者を得て開催された。

まず冒頭に竹内綱史氏(日本学術振興会)による発表「ニーチェ的意味における哲学と大学」が行われた。「学者は決して哲学者になれない」と言い放ったニーチェは、ショーペンハウアー同様、大学嫌いとして有名である。よく知られたストーリーはこうだ。古典文献学で早くから頭角を現したニーチェは、1869年に25歳で教授職を得、28歳で野心的な大作『悲劇の誕生』を発表するが、斯界の大家ヴィラモーヴィッツの徹底的な批判を受けて学界から抹殺され、以後病もあって35歳で大学を退職、在野の思想家として孤独な執筆活動に沈潜する…。ニーチェの個人史を繙けば、彼の「大学嫌い」は容易に理解される。事は一見単純明快に見える。
だが、ニーチェにとって大学とはその程度のものだったのか。大学とは単なる仕事の場、すなわち経済基盤にすぎず、凡庸な学者たちが徒党を組んで俊英を抹殺し自己保身を図る場、つまり知的権力闘争の場にすぎなかったのか。少なくとも二つの点でこのような通俗的理解を修正する必要がある、と竹内氏は言う。第一に、ドイツ帝国成立(1871年)の翌年早々、ニーチェは「われわれの教養施設の将来について」と題して連続講演を行なっていた。当時、伝統的身分でも財産でもなく「教養」をアイデンティティの核とする支配的な社会階層、いわゆる「教養市民層」による教養の我有化は、一方で大学の実利主義化、他方で専門化という名の虚学化(とニーチェの眼に映るもの)を進行させていた。ニーチェの講演は、この状況に対する徹底的な批判であり、大学およびギムナジウムが「そこからその施設が生まれてきた理想的精神へと可能な限り近づく」ことを願って企図されたものであった。「生活の必要のための施設」とは区別された「教養のための施設」は、教養の純化による精神的貴族制の達成を目指すという条件さえ満たせば、若きニーチェにとってむしろその将来に希望を託せるものですらあったのである。
第二に、『教育者としてのショーペンハウアー』である。「教養施設の将来」の二年後(1874年)に『反時代的考察』の第三篇として刊行されたこの著作は、もはや教養施設の復活を語ろうとはしない。講壇哲学(大学の哲学)への呵責なき批判が大勢を占め、学者は絶対に哲学者にはなれない、それゆえ哲学は大学を離れるべきだという主張が繰り返されるに至る。だが、ニーチェは「大学」は捨て去っても、「教育」を手放してはいない。「教育者としての」ショーペンハウアーが重要なのである。言いかえれば、誠実さを核とするニーチェ哲学の自己反省と批判精神は、決して〈求道〉―生に意味をもたらす真理の追求―だけにとどまらず、〈啓蒙〉―真理を求めることを求めること―を呼び求める。
時間の関係もあり竹内氏が暗示するにとどめたこの第二点は、デリダの言葉によってその真の射程が白日の下に晒されるように思われる。「条件なき大学は、こんにち、大学と呼ばれているものの囲いのなかに必ず位置づけられるわけでも、もっぱらそこに位置づけられるわけでもありません。条件なき大学は、当の無条件性が告げられうる至るところで生じ=場をもち、自らの場を求めるのです」(デリダ)。〈求道〉と〈啓蒙〉が交わる地点において生じる「あの新しい義務」について、ニーチェはまさに次のように述べていた。「あの新しい義務は一人の孤独者の義務ではなく、むしろひとはこれらの義務をもって一つの有力な共同体に属し、そしてこの共同体は外面的な形式と法則によってではないけれども、一つの根本思想によって確かに締めくくられていることである。この思想とは〈文化〉の根本思想である」(『教育者としてのショーペンハウアー』)。ニーチェはある「条件なき大学」を最晩年に至るまで追い求めていたと考えるのは穿ちすぎであろうか?
*なお、竹内氏の関連論文「大学というパラドクス : 《教養施設》に関する若きニーチェの思索をめぐって」がネット上に公表されているので参照されたい。(以上文責:藤田尚志)

続いて、西山雄二(UTCP)は、韓国・ソウルの現地取材として「研究空間スユ+ノモ」について報告をおこなった。「スユ+ノモ」は博士号を取得したものの就職先がない「高学歴ワーキングプア」たちが創設した、大衆に開かれた研究教育のための、類まれな自律的な生活共同体である。詳細は2008年8月4日付のUTCPブログを参照されたい。質疑の時間には、「スユ+ノモのような若手研究者の実践は日本でも可能なのか」「こうした共同体が軌道に乗るまではやはりカリスマ的なリーダーが大きな役割を果たしたのではないか」「スユ+ノモと従来の大学との関係はどのようなものか」といった質問が相次いだ。

(左から、大河内、宮崎、斉藤、藤田、西山)
そして、共同討議では、『現代思想2008年9月号 特集:大学の困難』(青土社)をめぐって議論が交わされた。
大河内泰樹(京都産業大学)は、日本の研究教育制度がモデルとしてのアメリカよりも非合理的で貧弱な現状を取り上げて、グローバル化は概してその先発国よりも後発国においてこそ歪な構造をもたらすと指摘した。また、ドイツ留学中に通った大学の哲学科の図書室のことを引き合いに出して、アーカイヴの充実とそのアクセス可能性の重要さについて力説した。その図書室は年代順に各哲学者の一次・二次文献が並んでおり、部屋で時間を過ごせば網羅的な哲学史を身体的に経験することができるという。
宮崎裕助(新潟大学)は、今回の特集号が、大学の歴史的条件をなす学問探究の自由や無条件性のうちに、アソシエーションのための新たな突破口を見出そうとしている点を高く評価したうえで、「理念なき大学」以後の大学への信として、デリダの『条件なき大学』を取り上げた。ただし、デリダが大学(とりわけ人文学)に認める無条件性は大学の主権を強化するものではなく、むしろ弱さや無力さと深く関係することが強調された。
斉藤渉(大阪大学)は、大学の存在意義たる「教養」が、根本的には、「実利や市場に解消できないもの」といった「~でないもの」という否定的な形でしか説明されえず、積極的な規定をもたないことを指摘した。また、マスメディアが大学の現状を伝えないことで、国民と研究教育現場とが乖離していることが問題だとした。
藤田尚志(学振特別研究員)はまず、大学論を語るときに誰に宛てて語るのか、という宛先の重要性を示唆した。彼は、スロー・サイエンスが活きる大学も市場原理を必要としているというジレンマにおいて、「今ここ」の重要性を主張すると同時に、「反時代的」であらねばならないという両面作戦の必要を説いた。

その後、今回の『現代思想』誌の執筆者にコメントをいただいた。岡山茂氏(早稲田大学)は、大学が確固たる制度であるのかは自明ではなく、つねに不可能なものに曝されて変容し続けるのが大学ではないかと指摘した。また、新自由主義的な趨勢のなかで大学が淘汰されるなかで、いかにして大衆のための高等教育を残せるのかが重要な課題になるとした。
永田淳氏(早稲田大学生協「大学の夜」主催者)によれば、大学には数々の困難がつきまとうものの、彼のような書店員が公的に発言できるのもまた大学の特性である。フーコーが「啓蒙とは何か」で示したように、問いに的確に答えようとするのではなく、自分の立場でアクチャルな態度を模索することを大切にしたいと語った。
青土社『現代思想』編集部の栗原氏によれば、今号で指摘されている大学の困難はすでに国立大学法人化の頃から予想されていた問題であり、「今さらか……」という徒労感を感じさせるものであった。だが、本誌全体が大学の希望を模索し、希望を語ろうという声調に包まれたことは予想外だった。とりわけ、大学院生のポテンシャルには目を見張るものがあり、院生の存在が今後の大学を左右するものであることが明示された。
大場淳氏(広島大学)は、研究教育をめぐる日本とアメリカの新自由主義の落差について重要な報告をした。アメリカでは1990年代に業績主義や評価主義が研究教育活動に浸透したものの、目に見える成果をあげることができず、その反省から近年では地道な基盤研究を見直し、重視する傾向が生まれているという。周回遅れで業績主義を促進している日本の研究教育の将来にとってきわめて示唆的な事実である。

最後に西山が二つのコメントを加えた。まず、大学関係者が制度論に関心を寄せることの重要性である。大学の制度論に傾倒する前に自分の専門研究に専心するべきだという向きもあるだろう。だが、大学の環境が激変する現在、関係者はその制度的現状にいくら注意しても注意しすぎることはない。
また、現在、とりわけ高学歴ワーキングプアの研究生活を鑑みるならば、学問の無償性(gratuité)とは何だろうか。どれほどの見返りがあるのか分からぬまま、院生が20-30代の時間と労力を学問探究にこれほど費やすことは、とりもなおさず、学問をめぐる圧倒的な事実であるだろう。フランス語gratuitéの語源はgré(好ましい)であるが、学問の無償性にはある種の肯定的な情動が付随する。しかし同時に、gratuitéは「根拠不明」「気まぐれさ」など、不確定さの危険をも含意する。見返りや収益性といった論理とは異質な学問の無償性は、「信じられないけれども信じる」という約束と危険をともなうのである。過度の競争のなかで院生が卑小なルサンチマンとともに同じ院生といがみ合うことなく、学問の無償性に触れつつ、互いに尊重し合う関係をいかにして保てるのかが、院生の潜在的な共同性を高めるために必要ではないだろうか。
論集『哲学と大学』刊行
論集『哲学と大学』刊行
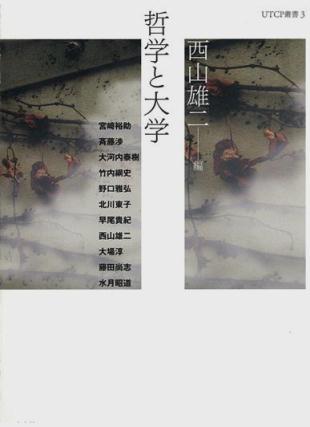
短期教育プログラム「哲学と大学」はこれまで5回の研究会とシンポジウムおよびワークショップを実施し、当初の予定を終了しました。その成果が『UTCP叢書3 哲学と大学』(未來社、2009年)として刊行されます。巻末には、「哲学と大学」に関連するコメント付きの詳細な参考文献リストを付しました。
本論集は、近代の哲学的大学論を総覧する第一部と、人文学の制度的矛盾を考察する第二部からなります。大学における哲学教育を考えるうえでも、哲学者の大学論の系譜を辿る教科書としても最適です。またさらには、大学におけるさまざまな問い――学問の有用性と無用性、基礎と応用、人文科学と自然科学、教師と学生、哲学と哲学研究、といった諸関係を考えるための材料を提起する書でもあります。
いま、大学は〈可能〉なのか――大学存立の危機が叫ばれる今日的状況をまえに、気鋭の論者が人文科学の未来を探る。哲学・思想史に屹立する先哲の大学論を読みとき、現代の高等教育における歴史的・制度的矛盾をあぶりだす多元的論集。(帯紹介文より)
「大学において私たちは何を希望することを許されているのか――研究教育活動を信じることが許されるために、大学の名に値するいかなる場が、いかなる条件において、いかなる責任において残されるのだろうか。たとえ没落の歴史であるにせよ、「哲学と大学」をめぐって紡ぎ出された言葉を辿り直すことで、こうした信の力の所在を確かめることが本論集の目途である。」(「はじめに」より)
西山雄二編『UTCP叢書3 哲学と大学』(未來社、2009年、全290頁、2400円)
はじめに――大学において私たちは何を希望することを許されているのか
第1部
第1章 秘密への権利としての哲学と大学――カント『諸学部の争い』における大学論 宮﨑裕助
第2章 フンボルトにおける大学と教養 斉藤 渉
第3章 世俗化された日曜日の場所――ヘーゲルにおける「哲学」と「大学」 大河内泰樹
第4章 求道と啓蒙――ニーチェにおける哲学と大学 竹内綱史
第5章 比較と責任――マックス・ウェーバーの学問論 野口雅弘
第6章 ハイデガーの大学論 北川東子
第7章 「ユダヤ人国家」の普遍性を追求したヘブライ大学の哲学者たち 早尾貴紀
第8章 ジャック・デリダにおける哲学と大学 西山雄二
第2部
第9章 欧州高等教育再編と人文科学への影響 大場 淳
第10章 条件付きの大学――フランスにおける哲学と大学 藤田尚志
第11章 高学歴ワーキングプア――人文系大学院の未来 水月昭道
編者あとがき
「哲学と大学」に関する参考文献
対談「哲学と大学―大学において私たちは何を希望することを許されているのか」
対談「哲学と大学―大学において私たちは何を希望することを許されているのか」
2009年4月16日、ジュンク堂書店新宿店にて、『UTCP叢書3 哲学と大学』(未來社)の刊行記念トークイベント「哲学と大学―大学において私たちは何を希望することを許されているのか」が実施され、熊野純彦(東京大学)と西山雄二(UTCP)が登壇した。

まず、編者・西山の方から、個人的な大学の経験と『哲学と大学』の趣旨説明がおこなわれた。大学の経験は各人多様であり、とりわけここ10年間の高等教育改革のなかで、各々の大学経験は著しく異なることだろう。西山は自身の経験を辿りつつ、独立行政法人化への布石として、1998年に一橋大学において学長選挙での学生の拒否権が廃止されたことを「大学の危機」として、また、フランス留学中に2004年に目の当たりにした、管理ポストの集団辞職を賭けて研究者たちの「研究を救おう!」運動が政府に異議申し立てをしたことを「大学の抵抗」として回想した。そして、現在、UTCPの活動を通じて、学部や学科を横断する国際的な研究教育体制の創出に従事していることを「大学の創造」と形容した。

論集『哲学と大学』はUTCPの共同研究の成果である。ここで問題となるのは、近代における哲学と大学の関係である。少なくともカント以降、哲学は大学の諸学問の宇宙を統括する理性の批判的活動の拠点とみなされてきた。しかし同時に、哲学は大学の一部門でしかない。つまり、大学のなかで他律的に限定される哲学が、しかし、大学の全体を自律的に統括するという二重の規定性が問われるのである。哲学者たちが大学論を執筆してきたのは、哲学による真理探究が大学という制度に妥当であるのかどうかを確かめるためである。本論集が描き出しているのは、理性の自律的かつ他律的な制度化を構想しつつ、大学に期待し、あるいは失望してきた哲学者のドラマである。

これに対して、熊野は、大学のなかで管理運営の役目を負わされるなかで、大学や人文学、哲学の今日的使命とは何かと「現実的に」自問しているけれども、しかし、今日は「若干の夢を含んだ形で」西山に応答したい、と対話の口火を切った。この『哲学と大学』はその主題設定からにして、肯定的な意味で、実に「浮世離れした」論集である。大学の現実的な危機を思考するためには、いま不在であるかもしれない理念を多様な仕方で語る必要があるのだ。
現在の大学は「工学部的なもの」が制覇しているのではないだろうか。しかし、人文学もまた、理念を語るだけでなく、人文学の現実的な有用性をいじましくも公言し続けなければならない。現実的な後退戦を放棄することなく、これを貫かなければならない。なぜなら、そうしなければ、後続する若い世代の研究者が根絶やしになるだろうからだ。その際、注意しなければならないのは、有用性の価値を軽んじることなく、哲学的な思考に基づいて有用/無用の二分法を批判的に問い直すことである。つまり、有用/無用を単純な二分法で語ることを留保しつつ、両者の錯綜した継ぎ目を繊細な表現で語ることが必要なのだ。
また、この論集は「哲学と大学」を対象としているが、各々の論考はさらに国家との関係をも問うている。つまり、国家のなかに大学があることの意味、そして同時に、国家の枠組みに収斂しえない大学の存在意義を問うているのだ。

歴史的に反復される大学の危機
西山:「今日の大学がかつてない危機に曝されている」というけれども、実は、歴史的にみて、大学はつねに危機的な状況を経験してきた。中世の大学が確立する過程の苦難、17世紀における大学とアカデミーの対立、18世紀における啓蒙主義者による大学への非難、ナポレオン戦争によるプロイセンの多数の大学の閉鎖、ナチス・ドイツによる大学の道義的破壊、1960年代の大学教育のマスプロ化など、大学はつねに危機に曝されてきたのだった。それゆえ、重要なことは、こうした歴史的危機を考慮しつつ、今日の大学の危機がいかなるものかを分析することである。
大学において人文学および哲学とは何か
西山:人文学は独特の速度をもっている。基本的に人文学はひたすらテクストを読み、思考するという愚直な営みである。しかも、テクストは様々な言語表現から成っている。それゆえ、人文学とは、異なる言語表現に即して、読解し思考することで、他者を受け入れようとする倫理的な訓練なのである。哲学がもつ独特の速度がこうした営みを可能としているのである。
熊野:哲学は大学の諸学問には収まりきらない、人文学一般には吸収できない何かを抱えているのではないか。情報や知識を伝達するだけではなく、何か過剰なものを生み出す営みではないだろうか。

大学と旅
西山:研究教育の機会を得るために、なぜ大学という場所が必要なのだろうか。そもそも、12世紀に教師の同業組合から生まれた大学(universitasは「組合・結社」の意味)は専用の建物を所有せず、教会や修道院のなかで授業がおこなわれた。また、少なくとも15世紀になるまで、教師と学徒の群れそのものが引っ越しを厭わなかった。大学はキャンパスという閉域のなかで動かない「象牙の塔」ではなく、逆に固有の場所とは結びつかず、つねに移動する運動体だった。ヨーロッパのさまざまな知性が集合し流動し、大学はつねに旅の途上にあった。それゆえ、大学のなかで個々人が真理探究の旅に出ること、さらに言えば、大学そのものが旅に出ているという雰囲気が必要である。とくに行先のない放浪ではなく、保守するべき場所をもちつつ学問的探求を通じて旅路についていることが。

大学において私たちは何を希望することを許されているのか
熊野:「あなたの研究は何の役に立つのか」と聞かれて、おそらく、ほとんどの人文学研究者はこう答えるだろう――「えっ! そんなこと、考えたこともありませんでした!」、と。例えば、『源氏物語』の研究者は自らの研究の価値を信じているだろうし、『旧約聖書』の研究者は『旧約聖書』が人類史上の最重要のテクストであることを疑わないだろう。そして、そうした信を抱いているからこそ、他者の研究に対して敬意をもつことができるのだ。逆に言うと、有用性の過剰な論理によって蔑ろにされるのはこうした他者への敬意である。かくして、大学においては、有用/無用の尺度を越えて、研究教育に没頭する他者への無条件的な敬意を洗練させることが許されているのだ。しかも、実社会において不利になるにもかかわらず、若い世代の人文学研究者が後を絶たず、ゼロにはならないこともまた大学の希望である。

西山:今回の論集に水月昭道さんに高学歴ワーキングプアの論考を寄せていただいたことは大きな収穫でした。実は、私も、博士論文を書き終えた後で、大学のなかで何の身分もなくなり、たんなるフリーターになる恐れがありました。自分でも驚いたのですが、その時、大学や大学関係者を激しく憎悪しました。長年授業料を払い、博士論文に労力を注ぎ、その結果が社会のなかにフリーターとして放り出されるということなのか、と絶望し激怒してしまったのです。そしてそのとき、逆説的にも、自分がいかに研究教育を愛しているのか、大切にしてきたのかを悟りました。いわば、研究教育をめぐって、愛情と憎悪の空虚な境界線の上に立たされたのです。
しかしながら、しばし考えて、「人文系研究者でよかった」という深い実感に到達しました。人文学とは、それぞれの個的実存が世界と衝突することで生み出された生の過剰さ=作品を研究する学問分野です。だとすれば、自分が置かれたこの境遇を、人文学研究者として、直接ではないにしろ、間接的な仕方で探究することを許されていることになります。それは、人文学研究者であることのきわめて慎ましやかな幸福でしょう。これは、カントが言う哲学部の「慎ましさ」、デリダが言う大学に認められるべき「無条件性の弱さ」にも通じる何かであるような気がします。虚無のなかで、大学における希望として残されたのは、こうした独特の幸福を信じることでした。
メフィストフェレス「沈みなさい。登りなさいとも言えますがねえ。
どちらでも同じことなんですから。」――ゲーテ『ファウスト』

(今回のイベントを企画・準備していただいた、ジュンク堂書店の阪根正行氏、未來社の高橋裕貴氏には深く感謝いたします。)
公開ワークショップ「哲学と大学」
公開ワークショップ「哲学と大学」(2010.12.26)
2010年12月26日、一橋大学にて「哲学と大学」公開ワークショップが開催され、15名ほどが集まった。(主催:科研費基盤研究(B)「啓蒙期以後のドイツ・フランスから現代アメリカに至る、哲学・教育・大学の総合的研究」)
まず、西山雄二(首都大学東京)の発表「フランスの哲学と制度」において、20世紀のフランスの哲学の制度化とそれをはみ出す運動との関係が概説された。高校や大学で哲学が制度化され、専門化されると同時に、在野での哲学的活動(民衆大学、ポンティニーの十日、コレージュ・フィロゾフィック、雑誌の公刊など)が活発となる。これは、哲学の閉鎖性と開放性といった哲学そのものの二律背反性(デリダ)に端を発するものではないだろうか。

次に、宮崎裕助(新潟大学)氏は、「英米語圏における「人文学」的思考の現在」と題して報告した。サイードは晩年の『人文学と民主主義的批評』において、文献学への回帰を強調しつつ、あらゆる階級と背景の人々に開かれたデモクラシー的解放を謳った。ただ、サイードの人文学論は狭義の人間主義に裏打ちされており、言語の根本的にアナーキーな性格への配慮は見られない。人間の規範的な諸価値を問い直す、ポストヒューマニティーズとしての人文学を構想することが課題と可能性として残されている。

最後に、藤本夕衣(京都大学)氏は、博士論文にもとづいて、発表「アメリカの大学における教養教育論争 ―「文化戦争」にみる政治哲学の問い」をおこなった。ポスト・モダン時代の大学を論じる糸口をつかむために、藤本氏は、リチャード・ローティとアラン・ブルームの古典論を参照する。
ローティは解釈学的立場から形而上学的な哲学の無効化(それゆえ、形而上学的理念が保証する近代的大学の無効化)を示唆し、文化左翼と分析哲学への批判を通じてポスト・モダン的大学の病理を描く。ローティにとって、偉大な作品は読者のインスピレーションを回復させる点で重要であり、古典を読む場としての大学は社会からの一時的な避難所である。

他方で、西洋中心主義的な保守主義者とされるブルームもまた、大学の二つの解体を意識する。啓蒙主義的理念にもとづくドイツの大学を経て、出口のないニヒリズムが蔓延するアメリカの大学において必要なのは、古典の著者の声に徹底的に聴き従う読者の態度である。古典の読解を通じて、読者は自らの不完全さを自覚し、知へのさらなる欲望(エロス)を抱く。大学は社会との緊張関係を保ったまま、古典を読むことのできる場所である。
藤本さんはさらに、両者の師であるレオ・シュトラウスを参照し、歴史主義と古典の意義という視座から古典論を分析した。古典論と政治哲学(近代民主主義の問いと規定)との接点を浮かび上がらせ、さらにこの関係をポスト・モダンの大学論へのひとつの解として示す手ほどきは的確で、とても興味深い発表だった。
公開ワークショップ「哲学と大学II」
公開ワークショップ「哲学と大学II」(2011.12.03)
2011年12月3日、一橋大学にて、ワークショップ「哲学と大学II」が開催され、3名の発表がおこなわれた(主催:科学研究費補助金「啓蒙期以降のドイツ・フランスから現代アメリカに至る、哲学・教育・大学の総合的研究」、一橋大学国内交流セミナー補助事業)。


まず、大河内泰樹(一橋大学)氏は「ポリツァイとコルポラツィオンの間で <大学>という制度をめぐる統治の問題」において、ヘーゲルとフーコーの統治論と連関させつつ、アドルノの人文学論へとスリリングに議論をつないだ。ヘーゲルが『法哲学』で分析するコルポラツィオンは市民社会における職業活動にもとづく団体であり、他方、ポリツァイは行政や内政一般をも包括する概念である。それゆえ、ヨーロッパ中世の職能団体として誕生し、近代において国家的制度として継承されてきた大学はまさにポリツァイとコルポラツィオンが絡み合う位相であるだろう。ヘーゲルの時代に統治は国民の安寧と自己涵養Bildungに配慮していたが、新自由主義的統治が進行する現在、経済体制における有用な人材の養成が重視される。こうした現在の新自由主義的な統治に対して、大学はいかなる方途を示すことができるのか。大河内は、フーコーの「自己への配慮」(自己超克としての啓蒙実践)と、アドルノの「理性と批判の底荷(バラスト)」としての人文学の意義を示唆的に強調した。

斉藤涉(大阪大学)氏は、「〈大学論〉は何を考えればよいのか――タルコット・パーソンズ『アメリカの大学』を手がかりに」 において、パーソンズの社会体系論からその大学論を読み解いた。パーソンズは四機能図式によって社会体系のあらゆる構造を説明する。それは、L(潜在パターンの維持)、I(内的安定性を確保するための統合)、G(望ましい状態の実現を目指す目標達成)、A(変化する諸条件への適応)からなる図式である。大学ならば、L(大学院教育)、I(知識人による社会状況への実践的貢献)、G(一般教育による学部生育成)、A(専門職に向けた専門家訓練)と区別される。社会システムが十全に機能しうるための要件は、逆に、それが機能不全を起こす条件ともなるのであり、この図岸によって大学の構成要素とその(不)成立要件が明確に示される。

阿部ふく子(東北大学)氏は、「〈自ら考えること〉と〈教養形成〉をつなぐ哲学教育――ドイツにおける哲学教授法(Philosophiedidaktik)の展開から」 において、1999年に設立された「哲学。倫理学教授法フォーラム」の取り組みを具体的に紹介しつつ、哲学教育をめぐる論点を具体的に浮き彫りにした。哲学者や哲学史などの既存の知識を蓄えることのみならず、主体的に思考する能力もまた哲学には重要であるために、「哲学」と「哲学教授法」の関係は繊細かつ複雑である。哲学教授法研究者Johannes Rohbeckは、「哲学」と「哲学教授法」を区別し、両者の出会い(「教授法的変換」)を通じて、学ぶ主体に開かれた哲学の公教的特質を重視する。①哲学の知識を伝達する演繹的な「模倣教授法」があり、②学生と教師による対話重視型の帰納的な授業がある。Rohbeckはさらに仮説推論的な「教授法的変換」を構想する。例えば、アリストテレスの一節を学生に提示すると同時に、哲学的な思考方法と能力の道具立ても示される。それは、反省能力のための構造主義、観察能力のための現象学、批判のための弁証法、創造性のための脱構築といった読解モデルである。学生はテクストの解釈の客観的妥当性を追求するのではなく、多元的な読解方法を用いて自らの思考をさまざまに試す。確固たる「哲学die Philosophie」が伝達され習得されるというよりも、「哲学的な何かetwas philosophisches」と「学ぶ主体」とが媒介的に交わることが目指されるのである。

