巡回上映の記録 2010年9月 韓国
2010/09/16 誰かの共感を得ること、そこから生まれるただ一度の出来事
2010/09/16 「誰かの共感を得ること、そこから生まれるただ一度の出来事」(『文芸中央』誌)
金美晶さんによるインタヴュー「誰かの共感を得ること、そこから生まれるただ一度の出来事――2010年の大学、人文学、そして……」が韓国の文芸誌『文芸中央』に掲載されました。金美晶さんは留学していた昨年度、東京大学での拙自主ゼミに足を運んでくれて、映画「哲学への権利」も二度観ていただきました。韓国でもまた、大学制度内でも在野でも、人文学を問い直す時期に来ているようです。日本と韓国の人文学の状況に即して私の仕事を振り返っていただき、たいへん刺激的な対話をもてたことを感謝しています。韓国上映がとても楽しみになってきました。 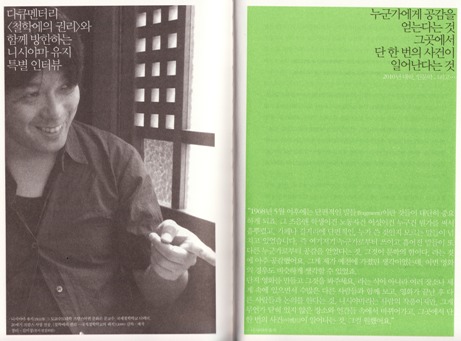
金美晶さんの印象的な言葉を引いておきます。
「映画『哲学への権利』に対する自分の所感ですが、レトリックが強すぎるかもしれませんが、これは人文学の一種の「没落」や「終焉」以後を模索する方法論のひとつだと思いました。没落や終焉への予感は、韓国でもありふれています。私が大学に入学する1990年代半ば頃から、いつも「危機」が叫ばれてきたのです。文学も哲学も批評も「危機だ、危機だ」といった、「危機一辺倒」の雰囲気でした。
ところが、2000年代になると、「危機」という表現は「終焉」や「終末」という言葉にとって代わった感があります。極端な例で言えば、2004年に柄谷行人がある文章で、韓国文学を指して「(近代)文学の終焉」を宣言し、それによって韓国文壇において「終焉」をめぐって大きな波紋がありました。
私のこうした経験もあって、西山さんの試みは、近代的な価値の危機を、さらにはその終焉以後を思考しなければならなかった韓国の状況と重なったのです。西山さんは「哲学」や「大学」に力点を置いて、映画で表現されました。私の場合は、どうしても文学に身を置いてしまいます。」 
「映画では、国際哲学コレージュのアソシエーションという運営方式がたいへん興味深いです。おそらく、西山さんも高い関心を寄せているのでしょう。
アソシエーションとは「自発的な人々の集い」です。西山さんも御存じの通り、韓国にも大学制度の外にいくつかの私的研究所があります。政府からの援助とは無縁で、自発的な運営が可能だという点が、コレージュとはまったく異なる韓国的特質かもしれません。これは「私と君」「私とわれわれ」という関係、すなわちコミュニティ感覚の違いから生まれるものでしょうか。私の考えですが、大学制度外の研究空間は「研究」コミュニティであり、そして、80年代の学生運動を受け継ぐ「運動」コミュニティでもあるのです。
私は大学院時代に、大学制度の外の研究空間に関心をもって行ったり来たりしたことがあります。「引きこもりのような自分だけの空間」ではなく、「一緒に集まって、何かをおこなう、つくり出す、変化に期待する」点が良かったのです。その運営方式は、成員の経済力に合わせて会費を集めたり、、社会的・経済的に余裕のある方から後援金をもらったりという方式でした。これは、市場や国家を他の仕方で横領する好例ではないでしょうか。」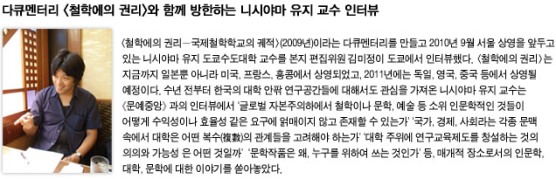
2010/09/27 韓国・研究空間スユ+ノモN(李珍景、鄭晶熏、宮崎裕助)
2010/09/27 韓国・研究空間スユ+ノモN(李珍景、鄭晶熏、宮崎裕助)
2010年9月27日、研究空間スユ+ノモNにて、李珍景(イ・ジンギョン Yi-Jinkyung)、鄭晶熏(ジョン・ジョンフンJeong Jeong Hoon)、宮崎裕助(新潟大学)とともに上映・討論会がおこなわれた。学校教師が引率してきた中学生(?)の団体、日本から駆け付けた学生たちも含めて45名ほどが参加した(韓国の中学生たちは辛抱強く映画を観て、夜遅くまでの討論にも残ってくれて感動的だった)。
スユ+ノモは1997年、若手研究者たちが創設した、大衆に開かれた研究教育のための自律的な生活共同体である。それは理論探究がなされる研究所であり、数々の教育活動が実施される施設であり、研究員の共同生活が重視されるコミューンである。講義室(兼ヨガ室および卓球室)、セミナー室、カフェ、厨房+食堂、勉強部屋などを備えたスユ+ノモが目指すのは学問と生活の適切な調和である。スユ+ノモは2009年に分割され、現在は各々の特色に即して四つのスユ+ノモの拠点施設がソウル市内に点在している。今回の会場はそのひとつ、「スユ+ノモN」である。






宮﨑裕助氏は、国際哲学コレージュの最も重要な意義を制度の無条件性にみる。大学はグローバルに進行する市場原理主義の荒波のなかで、競争原理の渦中に投げ込まれている。ならば、既存の大学制度に必ずしも依存することなく、かつ、たんに無関係ではないしかたで介入しつつ、哲学や人文学の名のもとに、思考の無条件な権利を確保することができるのか。
李珍景氏は、映画には教師の一方的な発言しかないが、教室風景や学生の姿とともに、コレージュがいかなる難点に突き当たったのか、具体的な成功と失敗を描き出した方がよかった、と述べた。彼は韓国の歴史的背景にも触れ、金大中および盧武鉉政権時代に政府から支援を受けた団体が、新自由主義的な李明博政権になって支援金を絶たれて苦労した、という事実を挙げた。韓国では制度が政府に対する独立性を維持することが困難で、デリダが示唆する「制度に抵抗する制度」はどの程度可能だろうかと問うた。
(李珍景、宮崎裕助)
李珍景氏は、スユ+ノモの実践を、制度の内と外を横断し、資本主義や国家には回収されえない外部を創案する愚直で素朴な試みと規定。それは、人文学の学びがもたらす制度からの離脱の誘惑によって、新しい生の方式、コミューン的な生の空間を創出する試みである。彼は、制度から溢れ出てしまう学びに対する欲望の匂い、そうした外部に対する欲望の匂いを感じるがゆえに、国際哲学コレージュに惹かれるとした。本作のエンドロールにも着目し、上映場所と人名が長々と列挙されるが、これは大学制度を超えた運動の証しだと指摘した。
鄭晶熏氏にとって人文学の核心のひとつは物事を問い続ける権利である。その意味で、人文学は到達するべき目的地とは異なる道そのものではないか。状況と条件の変化にしたがって、問いを変化させ、必要な暫定的な解決策を模索する過程的思考こそが人文学である。彼は、日本人がフランスの哲学学校を撮影し、フランス語の映画作品として仕上げているが、この映画は誰に見せるためにつくられたものなのか、と問うた。また、鄭晶熏氏は、人文学を自らの生の主人になる方法を実践的に学ぶことと規定した上で、コレージュにおいて学生たちは何を得るのだろうか、と疑問を投げかけた。
(左からオ・ハナ、鄭晶熏)
スユ+ノモ研究員のオ・ハナ氏によれば、映画には建物の風景が映されていないが、例えば、教室の掃除は誰がどんな風にしているのか、朝、玄関の鍵は誰が開けているのか、といったことが気になる。スユ+ノモではメンバーが当番制で建物を管理し、食事をつくり、掃除をおこない、会計をおこなっているが、そんな知的共同体ならではの意外な問いだった。
東京大学の学生・近藤伸郎さんは、コレージュとスユ+ノモが経済という点でまったく異なると指摘。スユ+ノモが資本主義の外部を目指すとはいかなる可能性をもつのか、と問うた。さらに、宮崎氏は、在野の知的運動と大学制度圏という二極化が韓国では鮮明であることはよく分かったが、制度(国家や資本)から逃れようとする試みは自己満足的な処方箋にしかならず、逆に制度を補完することになりはしないか、と指摘。これに対して鄭晶熏氏は、制度に包摂されるかどうかという問いは制度の側の問いであって、スユ+ノモ側では気にならないと応答。ただ、新自由主義下で人文学の危機が叫ばれるが、それ以前の時代に果たして人文学はどれほど実り豊かだったのか、内省する必要があると鋭いコメントを加えた。
コレージュでは学位ではなく計画書だけで誰もがディレクターに応募できる。オ・ハナ氏によれば、スユノモでは教えたいという「意志」によって誰もが講師になることができる。講座を担当するなかで他の人々から厳しい助言を受けながら、教える仕方を洗練させていくという。選抜や意志など、〈教える権利〉の基準とは何か、という論点は興味深かった。
知的共同体の管理運営の現実、教える―学ぶ権利の民主的要素、国家と資本が深く関与する大学制度の外部への希求など、スユノモならではの充実した討論をおこなうことができた。
2010/09/28 韓国・延世大学(金杭、金洪中、羅鍾奭、藤田尚志)
2010/09/28 韓国・延世大学(金杭、金洪中、羅鍾奭、藤田尚志)
2010年9月28日、延世大学にて、金洪中(キム・ホンジュンKim Hong Jung,ソウル国立大学)、羅鍾奭(ナ・ジョンソクNa Jonseok,延世大学)、藤田尚志(九州産業大学)とともに、金杭(キム・ハンKim Hang,高麗大学)の司会で上映・討論会がおこなわれた(主催:延世大学韓国学術研究院。70名ほどの参加)。
今回の主催団体・延世大学韓国学術研究院に触れておこう。韓国学術研究院は韓国政府が主導する18の人文学系高等研究院の重点的支援「韓国人文学(Humanities Korea: HK)」事業のひとつである(年間支援総額200億ウォン(約24億円)、支援期間10年)。韓国では1999年、「BK21(頭脳韓国21世紀事業)」の第1期7か年計画(1999-2005年)が開始され、年間2500億ウォン=約250億円(韓国学術史上、最大規模の研究助成額)が投入され、69プロジェクトが選定された。しかし、BK21は理・工・医系に偏っており、人文社会系が1割程度の採択率にとどまったことへの批判が高まった。そこで、第2期(2006年-)では別枠で新たに「韓国人文学(HK)」事業が打ち出された。HK事業では、若手専任研究員を雇用する人件費を保証すると同時に、10年後の事業終了時には大学の自己努力で彼ら若手を大学の正規教員に組み込むことを条件とする点が特徴である。韓国学術研究院は人文学の危機の克服を目指し、新たに「社会人文学」の地平を構想している。(ちなみに、日本の科学研究費補助金の場合、人文社会系の予算の割合は20%弱。日本でHK事業に相当するものはCOEプログラム〔2001年-〕であろうが、人文系は拠点数12、予算10億円程度と規模は約半分である。)
(左から羅鍾奭、金洪中)
金洪中氏は、西山と同時期にパリのEHESSに留学をしており、同じ教室でデリダの講義を受けていたという同時代性から語り始めた。映画については、コレージュの教室風景がなく、表札一枚という物質的現実しか映っていない点を指摘。さらに、西山がブランショ研究者であることを考慮して、推測的な仕方で批評を進めた。ブランショはヘーゲル的な弁証法に対して実在物の不在に力点を置く。だとすれば、西山の映画もまた、現実の不在の現前、物質の非実現化との終わりなき対話なのではないか。
藤田尚志氏は、本作の印象を、1)表現手法の旅、2)表現内容・表現主体の旅、3)上映運動という旅という三点から語った。1)思想研究者が文章ではなく映像作品を試みることで、奥行きのある表現手法となっている。2)日本人の研究者がフランス人と対等に対話をし、問題点を引き出している。3)本作は上映運動の形で旅を続けているが、それは作者・西山をも後押しする哲学の根源的な力ではないだろうか。
(中央・藤田尚志)
ヘーゲル研究者の羅鍾奭氏はコレージュの試みに共感すると同時に、自分なりの哲学擁護を発見することができた、と告白。デリダはヘーゲルの敵だと思っていたが、本作を観て、複雑な仕方でデリダはヘーゲルの同伴者であることが分かったとした。哲学を何かから擁護するとはどういうことだろうか。哲学をその外部から守るというよりも、自分自身で思考する、共同で思考することこそが哲学擁護の本質ではないだろうか。
羅鍾奭氏はさらに、ポストモダン思想はロゴス中心主義を推し進める余りに隘路に陥っている、と批判。無条件性や歓待といったデリダ特有の曖昧さや危険性を回避するために、主体の形成の問題は必然的である。学問の運動性に固執してはならず、制度の組織化と結束力、規律、そして倫理的主体といった主題を忘れてはならないとした。
(右端・金杭)
金杭氏の見事な司会によって、フロアとの質疑応答は上手く展開された。「自由なブルジョワ、自由なプロレタリアが人文学の学びの場を発展させてきたとすれば、デリダがいう哲学とは誰のためのものなのか。」「〈哲学への権利〉というからには、国家や資本によって奪われている権利なのか。奪い返すべき権利なのか。」「国家の補助金を受けならが自律性を維持するなかには、おそらく熾烈な戦いがあったはずではないか。」さらには、市民団体の方からは、「潤沢な国家補助を受けているHK事業は市民との対話を尊重しているのだろうか」という言葉も飛んできた。神戸大学の院生・人見勝紀さんは、「日本と韓国はともに儒教を知的基盤とし、近代化以降は西欧化にさらされたのだが、こうした歴史性を今日の討論会はどう体現しているのか」と問うた。
韓国学術研究院の院長・白永瑞(ペク・ヨンソ)氏は、本作を観て、韓国の歴史学者のドキュメンタリー映画を製作したくなったと告白。制度の問いに関する映像作品化という発想はこれまでの大学人にはなかった。今回をきっかけに、映像も含めて学問の制度の歴史を検討する学術イベントを積極的に開催するとした。そして、大学制度とも純粋な学問とも異なる「運動」とはいったい何か、と疑問を投げかけた。
藤田氏は、運動としての学問、制度としての学問は対立関係とされてきたが、20世紀の後半以降、とりわけ「脱構築」思想を通じて、両者の相補的な関係が浮き彫りになってきたのではないか、と応答。つまり、運動にも制度的傾向があり、制度は運動の契機を孕むのだ。また、藤田氏によれば、「誰の権利か?」という問いそのものが再考されなければならない。規定の主体から問い始めるのではなく、主体の場や根拠を問い直すことが重要であり、これが「哲学への権利」に込められた含意であると作者・西山の意図を明確にした。
2010/09/28 旅への誘い ― 映画『哲学への権利』、韓国での巡回上映を終えて
2010/09/28 旅への誘い ― 映画『哲学への権利』、韓国での巡回上映を終えて
現に自分が今いる場所とは異なる他の場所に行きさえすれば、万事がつねにうまくいくだろう、と思われる。この居場所を変えるという問題は、私が自分の魂と絶えず議論を交わすという問題のひとつだ。―ボードレール「この世界の外へなら何処へでも」
2010年9月27-28日の韓国での映画上映と討論会は濃密な2日間で、質疑応答を含めて実に実りある成果をあげることができた。東京大学UTCP以来、韓国への出張は4度目になるが、韓国の友人たちのおかげで毎回、豊かな学術交流に成功している。心より感謝する次第である。
これまで私は独りで映画上映を続けてきた。だが今回の旅は科研費「啓蒙期以後のドイツ・フランスから現代アメリカに至る、哲学・教育・大学の総合的研究」によって実施され、宮崎裕助氏、藤田尚志氏が同行した。同輩の若手研究者でチームを組み、寝食をともにしながらの海外出張は、各々の思考を共鳴させる意味でも良い経験だった。来年以降もドイツ、イギリスと海外上映が続くが、この科研費チームの共同によって学術交流を成功させていきたい。

さらに特筆すべきは、今回の上映に合わせて、学生や一般市民ら10名ほどが韓国に旅立った点である。彼らは映画上映を通じて知り合った人々だが、韓国が近隣であることもあり、多数の日本人同行者が上映会に参加した。それは移動ゼミのようでもあり、懇親会でも日本と韓国の人々のあいだで濃密な交流がおこなわれた。発表者だけでなく、聴衆も含めて国際的な交流が、規定の学術プログラムとしてではなく、自発的な形で達成されたたぐい稀な好例だろう。
そして、今回、映画を上映させていただいた場所がそもそも魅力的な場所だった。一方で、大学制度の外に在野の知的共同体を創設したスユ+ノモ。他方で、国家の潤沢な支援を受ける、大学制度圏の重要拠点であるHK事業の延世大学韓国学術研究院。在野と大学、運動と制度、国家や資本の外部と内部といった両極の場所で、本作をめぐって議論がなされた意義は大きい。両者は韓国において、人文学の新たな枠組みを模索する最前線だからだ。本作がこうした先鋭的な場所で議論されることで、不思議な知的化学反応が引き起こされ、あまりにも刺激的な体験だった。

今回の韓国上映を機に、映画『哲学への権利』の旅は新たな段階に入った。韓国のホテルでは、イギリスとブルガリアの友人から上映依頼のメールが届いた。新たな風景を前にして、多くの同伴者と共に、さらなる旅への誘いを予感せずにはいられない。
さすらいの旅の想いを乗せて、お前の望みに尽くすために、
船は来る、遠くこの世の極みから ―ボードレール「旅への誘い」

