2010年度
離任・着任
2010年3月末をもって、東京大学グローバルCOE「共生のための国際哲学教育研究センター(UTCP)」での特任講師の仕事を終えました。UTCPでは小林康夫・拠点リーダーのもとで数多くのことを学びました。UTCPという日本におけるもっとも活気ある先鋭的な人文学の研究拠点を離れることは、実はとても心残りなことでもあります。
4月1日、首都大学東京・都市教養学部(フランス文化圏コース)の准教授に任命されました。新天地での研究教育活動に心と力を尽くします。
首都大学東京の前身、東京都立大学の仏文専攻は、20世紀フランス思想の研究教育活動において大きな役割を果たしてきました。デリダ『グラマトロジーについて』やドゥルーズ『ニーチェと哲学』の訳業で知られる足立和浩氏やクリステヴァ研究の西川直子氏、レヴィナス研究の合田正人氏、反ユダヤ主義研究の菅野賢治氏らが教鞭をとられていました。またここは、バタイユ研究の西谷修氏、レヴィナス研究の内田樹氏、ブランショ研究の谷口博史氏らを輩出した研究科でもあります。数年前に都知事によるカイカクの騒乱があってから、仏文科の教員・学生数は激減し(教員数12人→3人)、20世紀フランスを担当する教員は不在となっていました。伝統ある貴重なポストゆえに責任感は重いと言わざるをえませんが、自分なりに心と力を尽くします。
(前期)ジャック・デリダ入門(水曜5限・フランス語圏文化論A)
ジャック・デリダは脱構築の思想家として知られているが、彼の仕事は哲学のみならず、文学、政治、言語、倫理、教育、芸術、精神分析など多岐にわたるものだった。デリダの思想がいかなる意義をもつのかは、20世紀の思想の風景を眺望するための重要な問いであり続けるだろう。本講義では、まず脱構築をめぐる入門的な解説から出発して、言語や文学、倫理、教育、政治といった今日的な主題をテクストに即して具体的に検討する。毎週、異なるテクストをとりあげて、参加者による発表形式で演習が進められる。
5/26 南唯利(東京外国語大)『たった一つの、私のものではない言葉』、IおよびVIII、岩波書店、1-11および113-132頁。
6/2 奥山浩通『パピエマシン(下)』、「歓待の原則」、ちくま学芸文庫、153-162頁。
【参考文献】『歓待について』、産業図書。
6/9 平山雄太(首都大)『声と現象』、「序論」、ちくま学芸文庫、7-35頁。
6/16 八木悠允(首都大)『留まれ、アテネ』、みすず書房、1-12および86-98頁。
【参考文献】ロラン・バルト『明るい部屋』、みすず書房。
6/23 大江倫子『アポリア』、「II 到来を待-期する」の前半部分、人文書院、91-124頁。
6/30 公開セミナー「『条件なき大学』(月曜社)」
大宮理紗子、守屋亮一(早稲田大学生)、伊藤拓也
7/7 櫻田和秀(首都大)『友愛のポリティックス』、みすず書房。
7/14 島田健司(首都大)『他の岬』、みすず書房。
初学期の演習を終えて
首都大学東京にて開催されている2010年度前期水曜5限の演習「フランス語圏文化論――ジャック・デリダ入門」が終了した。首都大に赴任して最初の演習だったが、参加者の方々の熱意と努力によって大変満足のいく成果を得ることができた。
冒頭で入門的講義を数回おこなった後、『たった一つの、私のものではない言葉』、『歓待について』、『声と現象』、『留まれ、アテネ』、『アポリア』、『条件なき大学』、『友愛のポリティックス』、『他の岬』と学生発表をもうけた。各著作をすべて通読するのは大変だろうから、重要個所30-40頁程度を毎週指定し、参加者にさほど負担をかけないようにした。一冊の著作をじっくり精読する醍醐味は失われたかもしれないが、しかし、毎週異なるテクストをテンポ良く読んでいくスリリングさを味わうことができた。
学部生相手にデリダの演習など成立するのだろうか。デリダのテクストには独特の難しさがある。デリダは基本的に誰かの思想やテクストに即して脱構築を実践するため(寄生虫的身振り)、彼自身の哲学体系を抽出することは難しい(デリダ哲学の現前不可能性)。それゆえ、演習でもデリダが扱っているテクストや哲学史などに遡って理解を深めておく必要が生じる。哲学の歴史的背景も同時に理解しておかなければならず、学部生には骨の折れる演習だったことだろう。
参加者は学内生と学外参加者が半々で、つねに計12名ほどだった。学外から学生や社会人が(わざわざ南大沢まで)足を運んでくれるのは大変嬉しいことだが、学内生とのバランスが当初から気がかりだった。意識の高い学外参加者によって演習の水準が極端に引き上げられないかどうか。学外者は休まずに定期的に参加してくれるかどうか。結果的に、双方のバランスは上手くいき、演習全体に活気が出た。とりわけ、公開イベント「『条件なき大学』を読む」の際にはさらにいろいろな学外参加者が集い、刺激的な会となった。
授業の最後にアンケート・シートを書いてもらい、感想を徴集することがある。しかし、個人的にこのやり方には不満だ。学生のさまざまな感想はきわめて興味深く、内容豊かであるのに、回収した感想が学生には還元されないからである。また、理解したばかりの内容に対して授業の最後の数分で感想を求めることには少し無理がある。そこで演習では感想を後日ツイッターで数回つぶやくか、メールで送ってもらうことにした。すべての感想は集約して、次週印刷して参加者に配布したが、こうした意見の循環はとても重要である。
就任してまだ4カ月だが、大変充実した演習を実施することができた。参加された方には感謝と敬意を表したい。今後もこのデリダ・ゼミは継続していきたいと考えている。(2010/7/22)
(後期)サルトル『文学とは何か』を読む(火曜2限・フランス語圏文学演習)
 _
_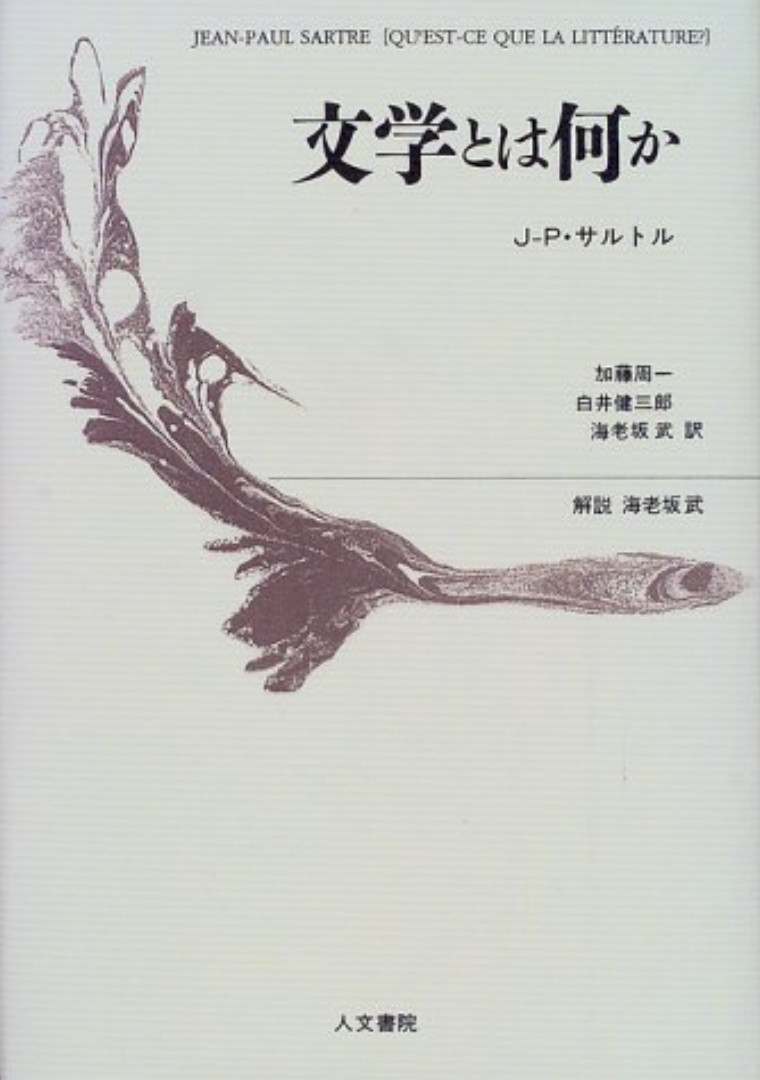
ジャン=ポール・サルトルが著わした20世紀の代表的文学論『文学とは何か』(1948年)を通読しつつ、今日の「文学=書くという公的表現行為一般」の可能性を探る。「文学」の概括的な理解にとどまらず、作家論、読者論、表象文化論、文体論、ジャンル論、記号論、意味論といった文学をめぐる各論、そしてサルトルの実存主義哲学とその思想的背景にも踏み込んで知識を深める。考察の指針となるのは、まさにサルトルが『文学とは何か』の各章の表題として掲げた明快な問いである―「書くとはどういうことか?」、「なぜ書くのか?」、「誰のために書くのか?」
【使用テクスト】ジャン=ポール・サルトル『文学とは何か』改訳新装版1998年。
10/5 ガイダンス 10/12 サルトルとは誰か?
1)「書くとはどういうことか?」 10/19(15-26頁 上別府) 10/26(26-40頁 西山)
2)「なぜ書くのか?」 11/9(48-60頁 植松) 11/16(60-73頁 近藤)
11/30 中間まとめ
3)「誰のために書くのか?」12/7(75-92頁 小澤)
12/14(92-111頁 川野) 12/21(111-139頁 一戸)1/11(139-152頁 坂元)
1/18 サルトルの知識人論を参照予定 1/25 まとめ
(後期)デリダのバタイユ=ヘーゲル論通読(水曜5限・フランス語圏文化論B)

『エクリチュールと差異』に収録されたジョルジュ・バタイユ論「限定的エコノミーから一般的エコノミーへ 留保なきヘーゲル主義」を通読することで、デリダの脱構築思想のエッセンスを紹介する。デリダは、止揚、否定性、至高性、労働といった概念や、「主人と奴隷の弁証法」や「絶対知」といったヘーゲルの問題系を議論の俎上に載せる。デリダとヘーゲルとの関係、つまり、脱構築と弁証法の関係、差延と止揚の関係を考える上での重要テクスト。
【使用テクスト】ジャック・デリダ「限定的エコノミーから一般的エコノミーへ 留保なきヘーゲル主義」、『エクリチュールと差異(下)』(法政大学出版局、1983年)
10/6 ガイダンス
10/13 ヘーゲルとは誰か? 発表:平山雄太
10/20 バタイユとは誰か? 発表:八木悠允
10/27「限定的エコノミーから一般的エコノミーへ」(157-162頁 櫻田)
11/10(162-169頁 川野)
11/17 映画「哲学への権利」上映・討論会
11/24「主人と奴隷の弁証法」について 発表:木本
12/1(170-180頁 横手)
12/8(180-195頁 奥山)
12/15 公開セミナー「笑い」とは何か?
12/22(195-202頁 大江)
1/12(202-208頁 平山)
1/19 予備 1/26 まとめ
公開セミナー「ジャック・デリダ『条件なき大学』を読む」(2010/6/30)

2010年6月30日ゼミ拡大版「ジャック・デリダ『条件なき大学』(月曜社)を読む」 が首都大学東京で開催された。大宮理紗子(首都大学生)さんが発表して、守屋亮一(早稲田大学生)、伊藤拓也(東京都立大学生)さんがコメントを寄せた。大学情報研究会との共催で、30名ほどが参加した。首都大学東京に着任してから最初のイベント開催であり、しかも、首都大学東京という改革の深刻な歴史をもつ大学において大学論イベントを実施するという点で重要な会となった。

大宮さんは『条件なき大学』の的確な概説をしつつ、大学とはいかなる場なのか、いかなる場でないかと問うた。また、自分なりの視座から、情報化社会における大学の意義、大学における無条件と無制約の違いについて問題提起をした。
守屋さんは、大学には雑多性が必要だが、勉強する学生が減少するという悪い方向にあるのではないかと問うた。それは大学が就職相談所と化しており、高校と大学の接続が上手くいっていないからではないか。大学、とりわけ人文学の意義は、たとえ独りでテクストを読んでいたとしても、ある種の社会的な交わりが生起する点にあるとした。伊藤さんは、首都大学東京の改革の過去に触れて、自分の信じるところを公言しない教員の沈黙によって改革が後押しされたのではないか、と問うた。

質疑応答の時間で、ICUのMさんは、伊藤さんが教員を断罪する立場はいかなるものか、と問うた。また、大学においては、デリダが指摘するような信仰告白に収斂することなく、具体的なプロジェクトを制度的に提起してこそ、信仰告白が出来事であるかのような瞬間が訪れるのではないかとした。東京大学のKさんは、アーレントの『人間の条件』とデリダの『条件なき大学』を的確に比較して、労働/仕事/活動という三幅対に即して、多数性が保持される言論の場はいかにして開かれるのかと問うた。和光大学のSさんは大学をいかなる場と空間として構想すればよいのかとした。首都大学のMさんは、各人がある種の寂しさを感じながら勉強するだけという現状において、その寂しさから出発する共同性をつくっていくことが重要だとした。首都大学のYさんは、なぜ大学が存在しなければならないのか、と本質的な問いを発した。首都大学のFさんは、大学が雑多な場でありにくいのは、入学する際に各人が明確なアイデンティティをもって入学するからではないかとした。

充実した発表とコメントによって、議論の可能性が豊かに開かれた。ただ欲を言えば、たくさんの質疑を受けたにもかかわらず、登壇者はほとんど応答できなかった。発表するだけならたんなる自己主張に終わってしまう。登壇者はフロアの質問に対して応答を返す義務があるのではないか。
大学内外からのさまざまな方の参加によって、教室は独特の雰囲気に包まれた。こうした学術イベントがいかなる形で実施されうるのか――それはその大学における出会いの潜在的可能性を端的に指し示す。首都大学東京は人々の出会いを誘発するいかなる雑多な場でありうるのか。今日はそうした学問の「出来事性」の肌触りを実感することができた。参加された方々に感謝する次第である。
公開セミナー「笑いとは何か?」(2010/12/15)

2010年12月15日、首都大学東京(南大沢)にて、ゼミ公開拡大版「笑いとは何か?」が開催された。通常のゼミメンバ―に加えて、社会人や都内の複数の大学生ら20名ほどが集まった。

まず、大宮理紗子(心理学専攻)さんが、発表「大きな笑いへの小さな考察」において、笑いに対して多角的かつ的確な考察を加えた。動物は現実と密着して生きる動物とは異なり、人間だけが世界を対象化して笑う。笑顔は人類共通のコミュニケーション手段である。しかし、笑顔は少しの変化でグロテスクな表情に映り、恐怖や怒りを表わすことがあり、実は非常に微妙な身体表現である。
笑いはその原因とともに分類され、①「快の笑い」(生後一カ月の乳児が授乳後満足して出る人間の基本的な笑いから成長とともに発展した笑い)、②「社交上の笑い」(人間関係を円滑に行うための技術としての笑い)、③「緊張緩和の笑い」などに大別される。 これら三区分はさらに細別され、「本能や期待の充足による笑い」(おなかいっぱい! 課題をやり終えた!)、「優越の笑い」「不調和の笑い」「価値逆転・低下の笑い」(飼い猫に無視される…)、さらには、「協調の笑い」(あいさつ笑い、つられ笑い)、「防御の笑い」「攻撃の笑い」(ブラックジョーク)、「価値無化の笑い」(笑ってごまかす)などが考えられる。これらの分類は単一的ではなく、通常は複数の要素によって笑いは生じるだろう。
「笑い」は、一人の世界の中では生み出されえず、つねに他者を必要とする。そして、誰か、何かとの関わりの中(それは恐怖体験かもしれないし、快楽を得るような体験かもしれない)でより大きなものへと構築されうる、というのが大宮さんの結論。

次に、西山雄二が発表「真理、笑い、神」をおこなった。大宮さんが笑いを「世界のなか他者」との関係として規定したのに対し、西山は笑いを「世界の他者」を創造する行為として説明した。
多種多様な笑いに関する考察はまさに人間論そのもので、人間に単一の答えがないように笑いにも単一の答えはない。ただ、ホッブズ、スタンダール、ボードレール、柳田国男などの笑い論にみられるのは、嘲笑や優越による笑いの規定である。これは人間の人間や動物に対する笑いであり、人間主義的解釈の域を出ない。言葉遊びやナンセンスなどの言語表現から生じる笑いをどう考えればよいのだろうか。
動物とは異なり人間だけが笑う、そして人間だけが宗教をもつ。だとすれば、笑いと超越的な存在(神など)との関係はいかなるものだろうか。例えば、キリスト教において笑いはつねに問題含みで、大笑いや高笑いといった動物的な仕草は愚者の振る舞いとして忌避されていた。キリスト教の価値転換を図るニーチェはそれゆえ、反キリストとして笑いの預言者ツァラトゥストラを登場させる。ツァラトゥストラはパロディによってキリスト教を破壊し、さらに笑いと舞踏によって人間の創造を試みるのだ。

最後に参照されたのは深沢七郎「風流夢譚」。天皇家の断首を描くこの小説は右翼の反感を買い、発売元の中央公論社社長・嶋中宅への暴行事件に発展する(右翼少年によって家政婦が刺殺、夫人が重傷)。この小説に対して天皇家の生々しい処刑が問題とされるが、むしろ短歌のパロディこそが重要ではないだろうか。天皇が伝統的に保護してきた短歌を揶揄し、主人公はその中身の空虚さを指弾する。これは天皇の根源のパロディであり、滑稽な模倣はオリジナルな世界を二重化し、その正統性を揺るがす。世界の他者を生み出すことこそが、宗教的ファナティズムに拮抗する文学的フィクションの自由と権利である。
そして、坂巻美穂(仏文学専攻)さんがコメントを加え、モリエールの文脈に即して論点が展開された。とりわけ、貴族と平民を共に笑わせるための技法やモリエールによる自作の自己パロディの事例が興味深かった。その後の充実した質疑応答も含めて、笑いの絶えない実に豊かな年末の会だった。
彦江智弘講演会「子どもたちにとって文学とは何か?」

2011年2月14日、首都大学東京にて彦江智弘(横浜国立大学)氏の講演会「子どもたちにとって文学とは何か?」が開催された。(司会・応答:西山雄二、主催:首都大仏文教室)

彦江氏はまず、啓蒙的な仕方で文学研究の基本的な心構えを述べた。テクストを読む際に初発のアイデアで観念的な図式を先につくることに甘んじてはいけない。テクストの物質性に接近することで、最初の観念的着想は破壊されなければならない。いろいろな角度から考察した結果、浮かび上がってくるものを自分なりに描き出すことが、文学の経験や研究にとって肝要である。
講演では、「サルトルによる文学のコンセプト自体において〈子ども〉という主題を問うことははたして可能か」、という問いかけがなされた。そして魅力的な仕方で、子供がほとんど登場しないサルトル『嘔吐』が参照され、同時代のベンヤミンとのありえたであろう対話が試みられた。
ベンヤミンは「物語作者」(1936年)において、近代社会における物語の失墜を語る。口から口へと伝承され共有される経験である「物語」は効力をなくし、その代わりに、各人が孤独に生きる文学形式として「小説」が前景化する。『嘔吐』(1938年)でアニーが戦争に負けた王様の様子や臨終を迎える父に対して落胆するのは、こうした物語の失墜を示しているのではないか。

ルイ・マランによれば、17世紀に口承の童話が書き言葉として記録されることで、権威や権力を帯び、人々を服従させ始めた。口は声を発すると同時に食物を摂取する器官でもあるが、そうした換喩的イメージとともに、『嘔吐』では口承性の権力への転化が何度か示される。「経験のプロ」であるロジェ医師は「子供たちに経験を消化させる」ことで過去を手際よく保存する。美術館でパロタン教授が講釈をたれる際に弟子たちは「むさぼるように耳を傾ける」。安直なヒューマニズムの物語にロカンタンは「嘔吐」を感じるのだった。
ロカンタンの冒険は世界旅行(行動)、ロルボン公爵の伝記作成(歴史)と続き、そして、「起こり得ないような物語、ひとつの冒険」を見い出すために「他の種類の本」を書く決意に至る。文学へと向かう彼の振る舞いをどう解釈するべきだろうか。彦江氏は、水溜りの脇におちている紙切れの文字、ポスターの文字「purâtre」に触れようとするロカンタンに着目する。彼はそのとき、言語がその安定性を失い、物質性を剥き出しにする瞬間に遭遇している。それは、「言語活動をもたない状態=幼年期」(インファンティア)への遡行であり、ロカンタンはもう一度生まれ直すためのさらなる冒険=文学に魅惑されているのだ。(文責:西山雄二)

(講演が終わって外に出ると、バレンタイン・デーの大雪)
