2011年度
(前期)レヴィナス『倫理と無限』を読む(水曜5限・フランス語圏文化論A)

現象学や存在論に依拠しつつ、西洋哲学が見落としてきた他者の倫理学を根本的な仕方で探究したユダヤ人思想家エマニュエル・レヴィナス。レヴィナスは、知の体系や論理的秩序によって倫理を基礎づけ、倫理の学を洗練させるのではなく、西洋のモノローグ的な思考に抗して倫理の根源を問い続けた。難解にみえるレヴィナス思想だが、ラジオ対談『倫理と無限』は平易な語り口で彼の経歴や著作、重要概念が簡潔に解説されており、入門的テクストとして定評がある。『倫理と無限』(西山雄二訳、ちくま学芸文庫、2010年)を通読することでレヴィナス思想の今日的意義を考える。
4/13 ガイダンス
4/20「レヴィナスとは誰か?」発表:平山雄太
4/27 第一章 西山
5/11 「世界」(岩波書店)2011年5月号「東日本大震災・原発災害 特別編集」を読む
5/18 第二章 新田 5/25 第三章 川野
6/1 発表「オルフェウスについて」久津間靖英
6/8 第四章 横田 6/15 第五章 小玉
6/22 第六章 仙石+第七章 大木
6/29 第八章 水上+第九章 井上 7/6 第十章 山下
7/13 公開セミナー「レヴィナス『倫理と無限』を読む」 馬場智一(東京外国語大学非常勤講師)
7/20 まとめ
【演習を終えて】
レヴィナス『倫理と無限』の通読演習が終了した。自分の訳書だし、入門書なので容易いだろうと思っていたが、やはりレヴィナスは手強かった。「ある」「光」「糧」「エロス」「顔」「秘密」「責任」など、何気ない言葉をその哲学の核心に据えているけれども、あるいはそのためにこそ、構築された彼の知的世界は奥深い。現象学の手法に即して、「私」がいかに数多くの他なるものと関わり、貫かれ、その力と言葉を加えられて生きているのかが、根本的な仕方で解き解されていくのだ。
今回は後半、受講生の方にレヴィナス・アレルギーが発症してきたことに満足した。「無限者の栄光の証し」など、宗教的な表現が登場し、「結局、レヴィナスの倫理学は宗教思想に裏打ちされているものでしかない」という拒絶感が湧き上がる。ただ、それはレヴィナスを理解し始めた証拠。私自身最初はそう思った。倫理を学として構築するのではなく、実存するこの私を起点として倫理の意味を考えると、なぜこうした宗教的な構造を帯びてしまうのか。超越的な他者との関わりが問題となってくるのか。このアレルギーはさらに思考を駆動させる。そして、その原因であるレヴィナスの思考がいかに力強くてラディカルなものであるかを思い知らされる。
東日本大震災があった。震災、津波、原発という三重のカタストロフィがあり、現在進行中だ。とりわけ、五千もの行方不明者に日本列島が見つめられているとふとした瞬間に思い、異例の事態だと痛感する。にもかかわらず、ナショナルな目線で被災地復興が叫ばれ(「頑張れ日本」)、原発再開の無遠慮な言葉も聞こえ、さらに異常な事態だなと怖れおののく。進行中のカタストロフィの最中でとり組んだ、今回の演習は実に濃密だった。毎回丁寧に準備していただいた発表者と参加者の皆さんのおかげで、「倫理と無限」がより重要な主題となった。避難した子供がうつろな調子でつぶやく、「早くお家に帰りたい」――その小さな言葉にいまはまだ十分に応答できない、だから、これからももっともっと勉強したい。
(前期)「岩波新書を読む」(月曜5限・基礎ゼミナール)
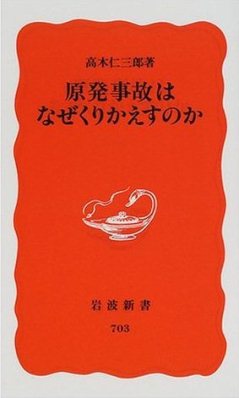
基礎ゼミナールは全学の一年生向けの必修演習です。今年度は下記の予定で、毎週、岩波新書の発表を継続していきます。
健全な市民的教養の育成のために創刊された岩波新書は、新書の代表格としてその確かな内容に定評があります。その対象ジャンルは文系理系を問わず、学問的なものからジャーナリスティックなものまで多岐に及び、第一線の学者や作家が筆をとっています。本ゼミナールでは、各人が自分の関心に即して、岩波新書を一冊とり上げて、発表します。さまざまな主題に触れることで知見を広げ、議論を通じて主体的に思考する能力を養うことで、大学生活への第一歩を固めます。
〈日程〉ジャンル、発表テクスト、発表者を記載
4/18 授業の進め方の説明
4/25 【経済】橘木俊詔『格差社会』(西山)
5/9 【教育】斉藤孝『教育力』(桝井)/【言語】鈴木孝夫『日本語と外国語』(吉田)/
5/16 【社会】香山リカ『「悩み」の正体』『若者の法則』(平野×林)
5/23 【法】岡本薫『著作権の考え方』(金城)/【現代世界】酒井啓子『イラクは食べる』(福田)
5/30 【現代世界】藤原帰一『デモクラシーの帝国』(落合)/【芸術】烏賀陽弘道『Jポップとは何か』(橋本)
6/6 【社会】内田隆三『ベースボールの夢』(松下)/【社会】大澤真幸『不可能性の時代』(明田川)
6/13 【自然科学】高木仁三郎『原発事故はなぜくりかえすのか』(堀)
6/20 【社会】佐々木芳隆『海を渡る自衛隊』(伊藤)/湯浅誠『反貧困』(倉科)
6/27 【哲学】大庭健『善と悪』(佐藤彰)/【哲学】木田元『ハイデガーの思想』(松本)
7/4 【情報】西垣通『ウェブ社会をどう生きるか』(今井)/【自然科学】竹内啓『偶然とは何か』(佐藤)
7/11 【宗教】大貫隆『聖書の読み方』(森下)/【経済】神野直彦「分かち合いの経済学」(杉山)
7/18 祝日 7/25 まとめ
(前・後期)ジャック・デリダ『獣と主権者』を読む(水4限・大学院演習)
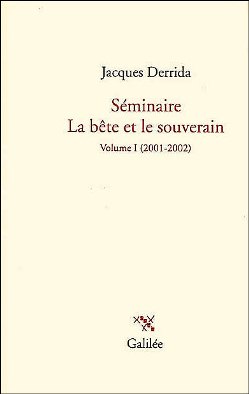 _
_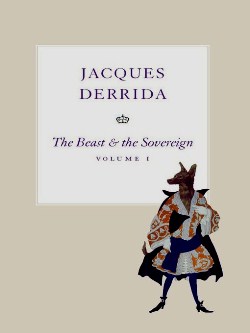
本演習では、2008年11月に刊行が開始されたデリダのセミネール・シリーズ(約14000頁、全43巻)の第1巻目『獣と主権者』をフランス語原書と英訳を用いて精読する。本書では、主権の概念とその諸形象の政治的かつ存在-神学的な歴史が、人間の固有性に対する動物の規定性という概括的な問いと交差されつつ探究される。動物の問いは、まず、動物的な生はいかにしてさまざまな領域(狩猟、家畜化、飼育、動物園、動物実験など)で扱われるのか、という生き物に関する政治的思考、生物学的なものや動物学的なものをめぐる政治性の問いとして分析される。またさらに、「人間が政治的動物である」という伝統的な定式にしたがうならば、獣を政治的主権性へと従属させる政治的な過程はいかにして組織されるのだろうか。また、獣と主権者は法や権利の空間に対して外在的かつ例外的な場を占めるがゆえに、法の起源と根源となりえるのだが、だとすると、両者の類比関係はいかなる過剰さを指し示しているのだろうか。本演習では、獣と主権者の古典的な対立を脱構築的に読み替えることで、政治的な主権の伝統的な規定を問い直すデリダ晩年のセミネールを読み進める。
〈使用テクスト〉
Jacques Derrida, Séminaire La bête et le souverain Volume I (2001-2002), Galilée, 2008.
(英訳)The Beast and the Sovereign, Volume I, University Of Chicago Press, 2009.
集中講義 「サルトル『文学とは何か?』を読む」
8月8日(月)-12日(金)2,3,4時限 名古屋市立大学
(11日は『哲学への権利』上映・討論会に振替)
ジャン=ポール・サルトルが著わした20世紀の代表的文学論『文学とは何か』(1948年)を通読しつつ、今日の「文学=書くという公的表現行為一般」の可能性を探る。「文学」の概括的な理解にとどまらず、作家論、読者論、表象文化論、文体論、ジャンル論、記号論、意味論といった文学をめぐる各論、そしてサルトルの実存主義哲学とその思想的背景にも踏み込んで知識を深める。考察の指針となるのは、まさにサルトルが『文学とは何か』の各章の表題として掲げた明快な問いである―「書くとはどういうことか?」、「なぜ書くのか?」、「誰のために書くのか?」
【集中講義を終えて】
今回ははじめての集中講義だったので、どうなることかと心配だった。15時間の講義を1日3コマずつ5日間で実施する長丁場。いわば真夏の合宿状態だが、参加者の方々がへばって飽きないように、視覚的資料を多用し、議論の時間をもうけて講義の流れにメリハリをつけた。終了後のレポート課題は「帳尻合わせ」の無難な作文になりがちなので、毎日のコメント・シートのみを成績評価の基準とした。全員参加のワークショップ的な雰囲気を重視し、比較的テンポよく、気持ちよく話すことができた。名古屋市立大学には哲学やフランス文学の専攻がない。そんな状況でのサルトル『文学とは何か』の講義なので、適切な説明の仕方、レジュメの効果的な使用、ぜひ伝えたいキーワードの強調など、サルトルを知らない学生にも何かが印象に残るように配慮した。学生の学力の高さと熱心さに助けられた。名古屋市大では社会人編入の方が多く、留学生の方も含めて、多様性のある教室は魅力的だった。5日間はあっという間で、せっかく学生たちと仲良くなったのに、もう、さよなら。「またぜひ講義をしてほしい」と何人もに声をかけていただいたのは嬉しかった。
(後期)都市教養科目「フランス文学」(火曜2限)

10/4 導入 10/11 表象とその限界
10/18 マルセル・プルーストの批評―作家の「別の自我」
10/25 シュルレアリスムの思想―無意識の芸術的創造性
11/8 受容理論―読者の自由の方へ、そして、その彼方へ
11/15 受容理論(続)―生の記述
11/29 ジャン=ポール・サルトル―実存主義の射程
12/6 アルベール・カミュ―不条理の方へ
12/13 ジョルジュ・バタイユ―死と共同性
12/20 「私」から始まる革命―68年5月革命から脱原発デモまで 12/27 復習
1/10 愛と死:見ることの禁止―オルフェウスの眼差し 1/17 全体討論
【講義を終えて】
都市教養プログラム「フランス文学」は昨年は受講生23名だったので、小教室が確保されていた。初回時に教室に行くと、廊下一杯に学生がいて教室にたどり着けない。他の講義だと思っていたところ、自分の講義への参加者だと知って驚愕。大至急、階段大教室に移動して講義が始まった。500名にも人数が膨れ上がった理由は、試験・レポートを課していないことと同じ時間帯に人気科目がないことだった。理系の学生も多数参加していたので、趣向を変えて、大人数でも参加意識をもてるような試みを仕掛けた。
「表象と作品」「実存と共同性」をそれぞれ全4回のシリーズとして、中期的な時間の流れを入れた。また、68年5月革命の回は、脱原発デモという時事的主題と連関させて、参加学生の政治的な意識を直接問うてみた。講義開始前に、その日の講義内容に「間接的に」関連する作品を前座として放映したことは刺激的だった。講義そのものを参加者との共同によってワーク・イン・プログレス的に創作し続けたと言える。
また、「大学の講義とは何か」というメタ的問いを学生に対して適宜投げかけた。私語の禁止、著しい遅刻の禁止、コメント・シートの意義、着席場所による学習効果、大教室の非人間的な空間性など、大学制度への自覚をうながした。最終回は、そうした実践の一環として教務職員6名に出席してもらい、学生らとの全体討論の会とした。学生の熱心な参加のおかげで、これまでになく成功した名残惜しい講義となった。
(後期)ジャック・デリダ『死を与える』(水曜5限・フランス語圏文化論B)
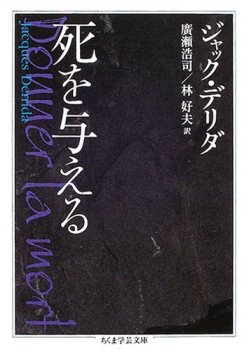
ジャック・デリダは宗教論『死を与える』(1990年)において、責任、秘密、贈与、犠牲、死、赦し、父子関係といった主題を相互に連関させながら論じている。参照されるのは『旧約聖書』における謎めいた供犠のエピソードだ。神はアブラハムに対して最愛の一人息子イサクを犠牲に捧げよと命じる。モリヤ山で息子の死を神に与える瞬間、アブラハムの手は押しとどめられる。死を与える瞬間に到来したこの出来事は、アブラハムのいかなる責任を物語るのだろうか。『死を与える』を通読しながら、デリダ哲学を理解しつつ、責任、秘密、贈与、犠牲、死、赦しといった概念群への理解を深める。
〈使用テクスト〉ジャック・デリダ『死を与える』ちくま学芸文庫、2004年。
10/5 ガイダンス 10/12 第一章(10-47頁)西山
10/19 第一章(48-74)八木 10/26 第二章(75-94)仙石
11/9 第二章(94-111)金谷
11/16 キルケゴール『おそれとおののき』(著作集第五巻)久津間
11/30 第三章(112-140)水上・大貫 12/7 第三章(140-168)川野
12/14 マルセル・モース『贈与論』(ちくま学芸文庫)を読む 島田・小林
12/21 第四章(169-191)大江 12/28 第四章(191-215)井上
1/11 第四章(215-236)小玉 1/18 モース『供犠論』山下・聡倉
1/25 伊藤 幹治『贈答の日本文化』平山・田中・小島
【演習を終えて】
今年度もデリダの演習が読了した。こんな難解な文章を非哲学系の学生20名で読めるのかと不安だったが、受講生は根気強く付き合ってくれた。毎回のレジュメも濃密で、コメント文章も秀逸。無神論でも有神論でもない神の二重化において責任の問いを立てることの微妙さは伝わったと思う。デリダ読解とは別に、贈与や犠牲、責任に関して理解を深める回も適宜設けた。
公開セミナー「レヴィナス『倫理と無限』を読む」(馬場智一)
2011年7月13日、首都大学東京にて公開セミナー「レヴィナス『倫理と無限』を読む」が開催された。

馬場智一(東京外大)氏に基調講演をしていただき、西山が司会・応答を務めた。今学期、西山の演習では『倫理と無限』を精読しており、その最後を飾るセミナーだった。大震災や原発事故のカタストロフィの最中で「倫理と無限」の主題にとり組むことになり、受講した学生の豊かな発表と議論とともに今期の演習は実に濃密だった。演習講義の最終回であるがゆえに応用的で、一般公開セミナーであるがゆえに入門的――そもそも、「哲学への入門」とは何か――である会にしようと準備した。当日は他大学の学生や一般の方々など45名ほどが詰めかけた(主催:首都大学東京都市教養学部フランス語圏文化論)。

馬場氏は、レヴィナスの略歴、ハイデガーの概略を説明した後で、両者の存在論の差異を際立たせつつ、レヴィナス哲学の骨子を丁寧に説明した。ハイデガーは現存在(人間)と世界の関係から問い始めるのに対して、レヴィナスは世界のなかに実存者が成立する地平から問う。ハイデガーにとって「不安」とは有限な人間が死(無)へと臨む先駆的決意を抱くときに感じられる情動であるが、レヴィナスにとっては人間がどうしても自分の身体を生きざるをえないという自己脱出の不可能性(無になることがなくつねに何かが〈ある〉)を示す。
レヴィナスは、他者がその他者性によって訴求することを〈顔〉と名付ける(〈顔〉は強い表現なので、熊野純彦氏が言うように、「けはい」と解釈した方がよいかもしれない)。〈顔〉はその脆弱さでもって「汝殺すなかれ」と根本的な仕方で訴える。ただし、レヴィナス哲学は、「~しなければならない」「~してはならない」という規範倫理学ではない。〈顔〉との対面は、その他者を殺害できる可能性をも示すがゆえに両義的である。「殺すことができる」と思った瞬間にその当人は、逆説的にも、「倫理的な」問いのなかにいるのだ。

〈顔〉についてはさまざまな議論が展開された。他人の顔を見ながら殺害がおこなわれる事例は数多い。その際に殺害者が見ている「顔」とは何だろうか。〈顔〉との対面が起こらないならば、それは殺人ではなく、たんなる物理的な破壊に等しいのだろう。レヴィナスにとって、植物や動物に対しては〈顔〉の対面がない以上、倫理的な関係はないのだろう。収容所で非人間的なドイツ兵に反応しなかった犬ボビーは唯一例外的だ。また、現われない〈顔〉の対面をいかにして私の内面は把握するのだろうか。逆説的にも、私にとっての秘密を介してしか〈顔〉と関係することはできないのではないか。

最後に馬場氏は、印象的な仕方で、東日本大震災においてレヴィナスの倫理はどういう意味をもつのかについて語った。
「他者からの呼びかけと言えば、フランス語でappel(呼びかけ)は「電話をかけること」をも意味する。私たちが被災地の親族や友人に電話をかけるのは、自分のなかに他者からの呼びかけをすでに受けとってしまっているから。現地に入って支援活動に従事する者も誰かにこうしろと言われてやっているわけではなく、呼びかけを受けとってしまったがゆえに行動してしまっている。そして、被災地に知人がいなくても、現地にボランティアにいかなくても、遠く離れた地でいかに無関係にみえようとも、日本や世界の各地で多くの人が被災地のことを気にかけている。レヴィナスの倫理は「~すべきである」という規範を前提とはしない。他者からの訴求力に反応するとはどういうことなのか、と倫理を思考する。呼びかけに反応するかしないかという主体的な選択の余地はなく、私たちは呼びかけを受けとってしまっているということ――ここに〈顔〉の呼びかけの最たる重要性がある。」

