(演習科目の一部を紹介しています)
2016年度
前期・演習「愛」

愛を知らない人間はひとりもいない。明らかに愛は誰もが経験する人間共通の感情的な現象である。しかし同時に、逆説的なことに、愛の体験は各々の言語のように絶対的に特殊なものであって、他人と同じ経験を共有することがほとんど不可能なようにもみえる。個々人が別々の仕方で経験する愛に対して、いかなる普遍的な規定を与えることができるのだろうか。愛は各々の文化において、穏和な人間関係として(友愛、仁愛、博愛…)、私的な愛情(恋愛、片恋、悲恋、同性愛…)として、家族的な関係(家族愛、兄弟愛、母性愛、父性愛…)として、社会的制度(婚約、結婚、離婚…)として、共同体の紐帯(愛国心、愛郷、愛校、愛社…)として多様な形で現われる。本講のテーマは、「愛」のさまざまな問題系を主に人文社会学の知見を通じて考察することである。
4/27【思想】プラトン『饗宴』
一堂に会した人々がワインの杯を重ねつつ次々にエロス(愛)讃美の演説を試みる。最後に立ったソクラテスが、エロスは肉体の美から精神の美、さらには美そのものへの渇望すなわちフィロソフィア(知恵の愛)にまで高まると説く。人間はもともと背中合わせの一体(アンドロギュノス)だったが、神によって二体に切り離され、その片割れを互いに探し求める、という愛の神話は有名。一篇の戯曲を思わせるプラトン対話篇中の白眉。
5/11【文学】スタンダール『恋愛論』第1-7章、第34-36章
19世紀フランスの作家スタンダールによる著名な随筆集。恋の猟人であった著者が、苦しい恋愛のさなかで書いた作品。自らの豊富な体験にもとづいて、すべての恋愛を「情熱的恋愛」「趣味的恋愛」「肉体的恋愛」「虚栄恋愛」の四種類に分類。恋の発生、男女における発生の違い、結晶作用、雷の一撃、羞恥心、嫉妬、闘争などのあらゆる様相をさまざまな興味ある挿話を加えて描きだし、各国、各時代の恋愛について語る。
5/18 浅見克彦『愛する人を所有するということ』第3、6、7章
そもそも人を愛するとはどういうことだろうか。どうして愛は他者を所有しようとしてしまうのか。自我は所有の求めをどう実現しようとするのか。愛する者は自我と愛と所有のトライアングルのなかで、苦悩と哀しみを身にまとう。愛をめぐる心の動きを桜井亜美や山田詠美などの小説やAYUの歌のなかに、あるいはR・バルト、J=P・サルトル、D・ヒュームなどの哲学思想のなかに探り、私たちの存在そのものの核心へと肉薄する。愛する者たちのありふれた感覚と思いによりそいながら紡ぐ、深い探求と刺激的な挑発に富んだ思索。
5/25【社会学】ゲオルグ・ジンメル「コケットリー」(『ジンメル著作集 7文化の哲学』所収)
コケットリー(coquetterie)はフランス語のcoq(オンドリ)に由来し、女性特有のなまめかしさ、色っぽさを意味する社交の一要素。女性のコケットリーの本質とは、自分を与えることを仄めかす一方で、拒むことも仄めかすことで男性を惹き付け、男性に自分を所有も非所有もさせない絶妙なところで自分の魅力を最大限にする点にある。「コケットリーとは、イエスとノーを同時に言うことである。」コケットリーを通して形成される関係は男女に限定されず、あらゆる社会的関係の原型となる「愛の遊戯的形式」である。
6/1【思想】九鬼周造『いきの構造』第1-3章
日本民族に独自の美意識をあらわす語「いき(粋)」とは何か。江戸時代より広がり、いまや日本国民共通の美意識と考えられている「いき」。哲学者・九鬼周造によれば、「いき」は世界でも日本だけにみられる感覚であるという。「運命によって“諦め”を得た“媚態”が“意気地”の自由に生きるのが“いき”である」。「いき」とは「垢抜して(諦)、張のある(意気地)、色っぽさ(媚態)」。なかでも、「媚態」は一元的の自己が自己に対して異性を措定し、自己と異性との間に可能的関係を構成する二元的態度とされる。
6/15 映画討論会「ロミオとジュリエット」
6/22【人類学】ジョルジュ・バタイユ『エロティシズム』
エロティシズムの本質や意味は何か。人間の性と動物の性のあり方はどう違うのか。美の本質はどこにあるのか。労働の発生と組織化、欲望の無制限な発露に対する禁止の体系の成立、そして死をめぐる禁忌…。エロティシズムの衝動は、それらを侵犯して、至高の生へ行き着く。人間が自己の存続を欲している限り、禁止はなくならない。しかしまた人間は、生命の過剰を抑え難く内に抱えてもいる。禁止と侵犯の終りなき相克にバタイユは人間の本質を見ていった。内的体験と普遍経済論の長い思考の渦から生まれ、1957年に刊行された本書によって、エロティシズムは最初にして決定的な光を当てられた。
6/29【キリスト教】アガペーについて
ギリシア語「アガペー」は、エロス(性愛)やフィリア(愛情、友愛)とは異なり、キリスト教において神の人間に対する「無限で無償の慈悲深い愛」を表すようになる。その現代語チャリティー(英: charity、羅: caritas)は実際、「慈善の愛」を含意する。神は無限の愛によって有限なる人間を愛している以上、神が人間を愛することで、神は何かの利益をえるわけではない。カトリック神学でアガペーは信仰や希望と並ぶ基本的な徳の一つであるが、新約聖書のアガペーは、神の愛、キリストの愛、キリスト信者同士の愛のすべてについて用いられる。
7/6【精神分析】自己愛 フロイト「ナルシシズム入門」
ナルシシズムとは、自己を愛し、自己を性的な対象とみなす状態をいう。転じて「自己陶酔」「うぬぼれ」といった意味で使われることもある。その語源は、ギリシャ神話に登場する美少年ナルキッソスが水面に映る自らの姿に恋をしたというエピソードである。フロイトは『ナルシシズム入門』において、ナルシシズムを自我発生の問題として取り上げた。自体愛と対象愛の中間に位置する発達段階において、自体愛に特別な心的作用が加わり、ナルシシズムに発達すると考えられた。
7/13【思想】アリストテレス『ニコマコス倫理学』 第8-9章
恋人や配偶者でもなく、親族でもなく、知人や顔見知りでもない、友とは誰だろうか。友の数はどれくらいがふさわしいのか、そして、真の親友とは何人だろうか。アリストテレスの『ニコマコス倫理学』(第8巻)によれば、友愛は人間の人間に対する親愛の情で、相互応酬的な好意であり、また互いに自己の好意を他者に知られている状態をいう。彼はさらに好意の原因が快楽、有用性、善のいずれであるかによって3種の友愛を区別し、善のゆえに求められる友愛こそが、真に永続する究極的な友愛であるとする。
7/20【人類学】ロバート・ブレイン『友人たち/恋人たち』
後期・演習「愛」
10/5 初回ガイダンス
10/12 【宗教】キリスト教的結婚
関根清三『現代キリスト教倫理〈2〉性と結婚』日本基督教団出版局、1999年
序論、第一章
「性と結婚」の問題を「キリスト教倫理」の視点から考え、多様化する「性と愛」および「結婚」に対する価値観の変化に焦点をあてて、伝統的キリスト教倫理を超えた、新しい倫理の可能性を問うていく。
10/26 連続国際セミナー「文学と愛」①
ジゼル・ベルクマンGisèle Berkman(フランス・国際哲学コレージュ、ディレクター)
コメント:西山雄二、藤原真実
11/9 【社会】加藤秀一『恋愛結婚は何をもたらしたのか』ちくま新書。
序章、第1-3章
夫婦別姓論議や少子化、不倫、熟年離婚など「結婚=家族」という主題が、ここ十数年メディアを賑わしてきた。だが、こうした話題の前提として、「一夫一婦制」自体が論議されることがなかったのはなぜか。そもそも明治期に唱導された一夫一婦制は、単なる精神論や道徳談義ではなく、「総体日本人」の、改良という国家戦略と共存していた。本書では、一夫一婦制と恋愛結婚をめぐる言説が、優生学という危険な部分と表裏一体であったことを検証し、恋愛・結婚・家族という制度の「近代性」の複雑さを明らかにする。
11/16 連続国際セミナー「文学と愛」②
「愛の悪霊 The Demon of Love」
ダリン・テネフDarin Tenev(ブルガリア・ソフィア大学、准教授)
趣旨:プラトンの『饗宴』でソクラテスが語ったダイモン(daimon)とジャック・カゾット(Jacques Cazotte) の『悪魔の恋 Le Diable amoureux』に出てくる悪魔などをめぐる議論。
コメント:山本潤(ドイツ文学)
11/23【社会】ロランス・ド・ペルサン『パックス―─新しいパートナーシップの形』緑風出版、2004年
欧米では、結婚を選ばない異性カップルや結婚を認められない同性カップルが増えて、多様なパートナーシップの形が定着してきている。しかし、その共同生活の中で、さまざまな問題も起きている。住居、財産、税制などでの不利や障害、別離後の財産分割、死亡による相続での不利や差別の問題などなど。こうした問題を解決するために、連帯民事契約=パックスとして法制化したフランスの事例に学び、新しいパートナーシップの形を考える。
11/30 連続国際セミナー「文学と愛」③
「愛の地政学 ──『蝶々夫人』の変身」
デンニッツァ・ガブラコヴァDennitza Gabrakova(中国・香港城市大学、助理教授)
コメント:大杉重男(日本文学)、荒木典子(中国文学)
趣旨:「蝶々婦人」を島田雅彦氏の小説などに触れながら、人種・ジェンダーなどの観点から分析。
12/7【歴史文化】佐伯順子『「愛」と「性」の文化史』角川選書、2008年
私たちが現在使っている「愛」や「性」という言葉の概念は昔から同じような意味で使われていたものではない。現代の日本人が「愛」や「性」に抱くイメージは、どのような軌跡をたどり形成されてきたのだろうか。その変容を文学や絵画などに描かれたさまざまな表現に焦点をあてて考察。時代や男女の違いによって異なる多様な恋愛観、結婚観、性愛観の文化史的意味を探る。
12/14【民俗学】小沢俊夫『昔話のコスモロジー──ひとと動物との婚姻譚』講談社学術文庫、第2−3章
日本を始め世界各地の昔話に数多く見られる人間と動物との婚姻譚。パートナーとなる動物はどこから来るのか。日本の夫は去ってゆく妻をなぜ追いかけようとしないのか―昔話の研究家として知られる著者が、「つる女房」や「天人女房」「ばら」など各国の異類婚姻譚を詳細に比較考察して昔話の本質を追究。他の民族とは異なる昔話をはぐくんできた私たち日本人特有の文化や民族性を解きあかした好著。
12/21連続国際セミナー「文学と愛」④
「『愛せ、さもなくば去れ』? マグレブ系フランス人による文学からの回答」
下境真由美(フランス・オルレアン大学、准教授)
趣旨:フランスで生まれて育ったアラブ系移民第二世代(ブール)のブール文学作品から、周縁化された移民たちのフランスへの愛憎を考察。
1/11【映画】「ヒロシマ・モナムール」(1959年)
『二十四時間の情事』(原題:Hiroshima mon amour)は、アラン・レネ監督、マルグリット・デュラス脚本による日本・フランス合作映画。被爆地広島県広島市を舞台に、第二次世界大戦により心に傷をもつ男女が織りなすドラマを描いた作品で、アラン・レネ監督の第1回長編劇映画作品である。日本での邦題は当初『ヒロシマ、わが愛』とされていたが、公開時に『二十四時間の情事』へ変更された。
1/18【社会】風間孝・河口和也『同性愛と異性愛』岩波新書、2010年
日本は同性愛者に寛容というのは本当だろうか。なぜ「見えない」存在なのか。エイズ・パニックや「青年の家」利用拒絶事件、ある殺人事件などを題材にしながら、異性愛社会に染み付いたホモフォビア(同性愛嫌悪)の諸相を描き出す。また、同性愛者が肯定的に生きるための取り組みも紹介。同性愛者から見た日本社会論。
1/25【社会】ジャン・ガブリエル・マンシニ『売春の社会学』白水社クセジュ、2000年
売春は人類最古の職業の一つとされる。売春という職業が成り立つためには、貨幣経済の浸透と、家父長制や嫁取り婚が成立している必要があり、たとえば、ヨーロッパで売春が始まったのは古代ギリシア以来だという。売春とは、婦女が、金銭を対価として、自由意志で、拘束されること無く、常習的・反復的・かつ不断に性的交渉を行うことである。そして、この行為以外に生活の手段をいっさいもたず、性的交渉の対象は求められればいかなる相手だろうと選択しあるいは拒絶することはなく、喜びでなく、ただ金銭の獲得を本来の目的とする行為である。洋の東西を問わず、必要悪と考えられてきた売春の歴史的意味を考察する。
後期・演習「テロリズムの精神と歴史」

2015年、フランスでは衝撃的なテロ事件が二度起こった。1月7日、パリ11区にある風刺週刊紙「シャルリー・エブド」本社を複数の武装犯が襲撃し、編集長や風刺漫画の担当者ら12人を殺害した。その後、フランス国内外で、「Je suis Charlie(私はシャルリー)」という合言葉とともに、報道と表現の自由をめぐるデモや議論が起こった。11月13日、パリとその郊外で銃撃戦と爆発が同時多発的に発生し、 130人以上が死亡した。オランド大統領はこのテロ事件を主導したイスラム国への戦争を宣言し、その拠点であるシリア空爆を強化させた。二つの象徴的なテロ事件は、「西洋」対「イスラーム」、「表現の自由」対「宗教」といった対立図式では単純化できず、イスラム嫌悪や移民の社会的排除など、その社会的・歴史的な暴力の構造は根深い。本講のテーマは、フランスのテロ事件をきっかけとして、テロリズムの精神と歴史を批判的に考察することである。
使用文献
ゲイロー、D. セナ『テロリズム――歴史・類型・対策法』
エマニュエル・トッド 『シャルリとは誰か?』
ジャン・ボードリヤール「テロリズムの精神」
ユルゲン・ハーバーマス+ジャック・デリダ『テロルの時代と哲学の使命』
京谷秀夫『風流夢譚事件』
カミュ『正義の人々』
加藤朗『テロ──現代暴力論』
『ふらんす特別編集 シャルリ・エブド事件を考える』
『ふらんす特別編集 パリ同時テロ事件を考える』
『現代思想 2015年3月臨時増刊号 総特集=シャルリ・エブド襲撃/イスラム国人質事件の衝撃』
『現代思想2016年1月臨時増刊号 総特集=パリ同時多発テロ』
2015年度
前期・演習「死」

あらゆる生き物はかならず死を迎える。逆に言えば、いつ到来するかわからない、ほかの誰とも交換できない死によって、つねに生は限定されている。生物学的に言えば、生命活動が停止した状態が死であるが、私たち人間にとって、死の意味はそれだけにとどまらない。死の定義は地域、文化、時代によって異なり、死を想像し解釈することは人間の文化の中核を占めている。一方で死は恐怖と不安をともなう、容易には受け入れがたい悲劇的な出来事だが、他方で、死は新たな旅立ちや再生、救済や解放として肯定的にも表象されてきた。宗教的発想によれば、肉体が滅びた後も魂が生き延びる死後の世界がある。文学・芸術の表現において、登場人物の死や死の風景などは不可欠な要素である。有限な存在が死をいかに自覚するか、死にはいかなる意味があるのかという問いからは哲学的な思索が始まるだろう。
授業計画・内容
演習では死に関する思想、表象、倫理、科学、宗教について順次、テクストの抜粋を読んでいく。その上で、殺害や自殺といった人間的問い、安楽死や尊厳死といった「死ぬ権利」、死刑という社会制度、大災害・大事故による大量死の衝撃、近親者の死別の悲嘆、生物学的な死の分析、死と共同性の相関関係、といった主題群が取り上げられる。
4/8 初回ガイダンス
4/15 全体討論
4/22 フロイト「快感原則の彼岸」
人間の心は「性欲動(リビドー)」に突き動かされており、「快感原則」と「現実原則」のバランスの上で自らを保持しようとする。現実原則は、快を目がける快感原則に歯止めを掛け、満足を延期し、不快に耐えることを強いる。だが災害神経症(≒トラウマ)のように、快をもたらす可能性のない過去の経験が呼び起こされ、あえて不安を形作ることで刺激を克服することもある(「反復強迫」)。その原形は子供の頃の「いないいない、ばー」だろう。快感原則よりも根源的なこの反復強迫とは? 快感原則は「生の欲動(エロス)」ではなく、「死の欲動(タナトス)」のもとにあるのではないだろうか。「あらゆる生命の目標は死であり、無生命が生命あるものより先に存在していたのだ。」
5/6 内堀基光・山下晋司『死の人類学』(講談社学術文庫)1-3および6章
死や死者に対するとき、人間は居心地の悪さを感じるが、超越的なものとの関係をさまざまに想像し始める。死は透けて見える真理ではなく、不透明な宿命である。この不透明さを想像する点に人間文化の発端があり、つまり、人間文化と死は切り離せない。人類学は個別の文化事象に即して、死によって人間以前から人間的状態へと移行する様子を見定める。ボルネオ島のイバン族の文化を例にして、生者との別離、喪失の儀礼、死霊の世界、再生産としての死について考察する。
5/13 フィリップ・アリエス『死と歴史』(みすず書房)1-90頁
ヨーロッパの中世から現代まで、死の迎え方、葬礼、遺言、死後のイメージ、追慕などの起源や変遷が考察される。〈死〉は五つの類型に整理される。まず、静かな諦観とともに共同体の一員として死んで行く「飼いならされた死」。ついで12世紀に始まる、現世へ執着し自分個人が不幸にも死ぬと感じる「己れの死」。ついで、常に死を身近なものと考えるルネサンス期から18世紀にかけての「遠くて近い死」。19世紀は家族や恋人の死が強い感情を喚び起こすロマン主義的な「汝の死」の世紀である。そして現代において、医療技術と衛生観念の進歩のもとで死は隠蔽され、瀕死者はもはや死の主体ではない(「倒立した死」)。
5/20 カミュ『シジフォスの神話』「不条理な論証」
「真に重大な哲学上の問題はひとつしかない。自殺ということだ。人生が生きるに値するか否かを判断する、これが哲学の根本問題に答えることである。」人生に意義がないという判断はひとに死を命じるのだろうか。自殺は不条理の解決になりうるのか。不条理を認識し前提としつつ、カミュはこの不条理の極限まで論証を試みる。
6/3 映画「おくりびと」
遺体を棺に納める納棺師となった男が、多くの別れと対峙する、本木雅弘主演の人間ドラマ。一見地味だが、人生の最期に必要な職業を通して、家族や夫婦愛のすばらしさを描く。授業では、現代社会における死のタブー、宗教による儀礼的コミュニケーション、生死による絆の回復、故郷の意味などをとりあげる。
6/10 「ゾンビ」という形象
当初、ホラー映画は吸血鬼ドラキュラ、フランケンシュタイン、狼男を御三家とする怪物ものが主流だった。1968年、ジョージ・A・ロメロ『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』によって、ホラー映画の変革が起こる。生きた屍体=ゾンビである。ロメロはブードゥー教のゾンビに着想を得て、吸血鬼の特徴を混ぜ込み、現在風のゾンビの形象(動きが遅い、理性がない、感染する、腐っていく)をつくりあげた。ゾンビとは生と死が宙づりになった優れた形象で、実は、現代社会を生きる私たち自身の不気味な鏡像でもある。20世紀末からTVゲームやコミックを通じて、ゾンビの刷新的リバイバルが起こり、現在膨大な作品がつくられている。
6/17 柳田國男『先祖の話』(角川ソフィア文庫)
柳田國男は本書を昭和20年4-5月に執筆した。3月10日の東京大空襲によって一夜で10万人が亡くなり、大日本帝国の敗戦が濃厚だった戦争末期。膨大な数の死者(日本人310万人、そのうち軍属は230万人)を無縁仏にすることなく、いかにして先祖として祀るのか。死者を迎え入れる「家」も焼き払われ、焦土と化した日本で、誰がどこで死者を先祖として迎え入れるのか。靖国神社や護国神社へ英霊として祀ること(近代国家による死者の管理)で十分なのか、「家」が先祖を祀る伝統との齟齬はないのか。国家、社会、家族、個による先祖の祀り方を民俗学研究の知見から論じる。
6/24 モーリス・パンゲ『自死の日本史』(講談社学術文庫)
日本精神の光輝と陰影を描き出し、日本人の「運命への愛」を讃えるフランス最高の知性が透徹した眼差しで、日本二千年の歴史伝統に迫る。意志的に選び取られた死=自死。記紀と『万葉集』にある古代人の殉死に始まるこの風土の自死史。道真の怨霊、切腹の誕生、仏教と自死の関係を問う。『葉隠』『忠臣蔵』に表出する武士道精神と近松、西鶴が描く心中とは何か? そして近代日本が辿った運命を、芥川、太宰、三島らの作品に探る。自殺大国の謎を西欧知性が論理と慈愛で描く「画期的日本文化論」。
7/1 ジャック・アタリ『カリバニズムの秩序』(みすず書房)1-87頁
カニバリスム(食人、食人俗、人肉嗜食)は、未開社会の人喰いを指す言葉で、カリブ海のカリブ族の風習に由来している。悪と病いと死を祓い、治癒を願う儀礼であり、コロンブスがヨーロッパ世界に伝えたといわれ、野蛮の同義語とされてきた。しかしながら、キリスト教世界にみるパンとブドー酒による聖餐は、同じカニバリスムの隠喩といえるのではないか。「イエス言ひ給ふ『まことに誠に汝らに告ぐ、人の子の肉を食はず、その血を飲まずば、汝らに生命なし。わが肉をくらひ、我が血をのむ者は、永遠の生命をもつ、われ終の日にこれを甦へらすべし』(ヨハネ伝6:53-54)。かつては死者=他者を喰い、生を回復したという人類。そして現代の臓器パンク、試験管ベイビー、プロテーズ(補綴)など、いずれもカニバリスムの進化の極点ではないか。ここでは生と死とは、身体の消費過程とされてしまった。隠喩はもはや隠喩ではない。ロボット的生か、人間的死か? 新たな野蛮と新たなカニパリスムの告知であろう。
7/8 国際セミナー「動物たちは死ぬのだろうか。動物、死、私たち(Les animaux meurent-ils ? L'animal, la mort et nous)」パトリック・ロレッドPatrick Llored講師(フランス、リヨン大学)
7/15 復活の思想──イエス・キリストの事例
7/22 まとめ
後期・演習「死」
10/7 初回ガイダンス
10/14 講師フランス出張のため休講
10/21【演劇】ソフォクレス『アンティゴネー』
古代ギリシアの三大悲劇詩人ソポクレスの『アンティゴネー』は、『オイディプス』とならんでギリシア悲劇を代表するのみならず、ヨーロッパ演劇史・思想史上きわめて重要な位置を占める作品。この戯曲では、男と女、老年と青年、法と正義、公と個人、国家と家族、生者と死者といった根源的な価値基準をめぐって、アンティゴネーとクレオン(テーバイの王)という二人の主要人物がそれぞれの主張・世界観を担って対決する。祖国に攻め寄せて倒れた兄の埋葬を、叔父王の命に背き独り行うアンティゴネー。(クレオン)「敵というものは、死んだあとでも友とはならないのだ」/(アンティゴネー)「私は憎しみを共にするのではなく、愛を共にするよう生まれついているのです」。王女アンティゴネーは亡国の叛逆者か、気高き愛の具現者か。悲劇の終幕は人間の運命と葛藤の彼岸を目指す。
10/28 連続国際セミナー「死と文学」① (フランス語、通訳有)
「演劇における死――死骸と幽霊」
講演者=ブリジット・プロスト Brigitte Prost(レンヌ第2大学)
コメント=高橋博美(レンヌ第2大学)、榎本恵子(首都大非常勤)
11/11 連続国際セミナー「死と文学」② (英語・日本語)
「魯迅の散文詩「死後」について」
講演者=デンニッツァ・ガブラコヴァ Dennitza Gabrakova(香港城市大学)
コメント=大杉重男(日本文学)、荒木典子(中国文学)
11/25 【生物学】柳澤桂子『われわれはなぜ死ぬのか―死の生命科学』(ちくま文庫)
私たちは、生れ、成長したあと、老いて死んでゆくものだと思っている。けれどDNAは受精の瞬間から、死に向けて時を刻み始めている。産声を上げる10ヶ月も前から、私たちは死に始めているのだ。生命が36億年の時をへて築きあげたこの巧妙な死の機構とはどのようなものなのだろうか。私たちの生命にとって老化と死は、逃れられない運命なのだろうか。なぜ生物には死がプログラムされるようになったのだろうか。これまでだれも語ることのなかった死の進化をたどり、われわれはなぜ死ぬのかを考える。クローン羊、脳死法案など死と生命の倫理が問われる現在、生命科学者柳澤桂子が死の本質に迫る画期的な書。
12/2 【社会学】澤井敦『死と死別の社会学』
死が医療などの専門職に管理され、日常生活から隠蔽・排除される「死のタブー化」が進行している。他方で、それに対立する考え方も台頭した。他者の死や死別を共有する伝統的な共同性を回顧する志向、そして「自分らしい死」という理念=死の自己決定を重視する志向である。一見すると相容れない死をめぐるこれらの志向は、しかし相補的な図式を形成してある種の死の共同性を生起させている。そのとき、共同性=規範として選択された「良き死」が同化と排除の構造を駆動することを、本書は、ウェーバーやデュルケム、パーソンズ、エリアス、ギデンズ、バウマンなどの社会理論から明らかにする。現代社会における死と死別の意味を再考し、死のコード化によって他者を否定しない生の関係性のありようを模索する。
12/9 【美術】ジュリア・クリステヴァ『斬首の光景』(みすず書房)
ブルガリアの思想家クリステヴァがルーブル美術館の全面的な協力のもと、あらゆるイメージの根源に、「斬首」のヴィジョン(首の光景=決定的な場面)を探求した待望の美術・哲学論。クリステヴァは、デッサン(素描)という行為に、自らの母親の記憶から人類の黎明期につながる人間の普遍的な営みを見出す。それは、あらゆる宗教現象の起源となり、切断された頭部のイメージに結晶する。太古の人類における頭蓋骨崇拝から、古代神話のゴルゴン、そして聖ヨハネの首とキリストの顔が変成したビサンチンのイコンへ。さらには「残酷」そのものとして屹立する近代のギロチン、現代のアヴァンギャルド芸術に至るまで、恐怖と魅惑に満ちた120点の図版とともに、精神分析学、文化人類学、ギリシア正教を中心とした宗教学、さらにはフェミニズムに由来する膨大な知識を駆使して「斬首」のヴィジョンが分析される。
12/16 連続国際セミナー「死と文学」③ (英語・日本語)
「あなたは私の死だった」(ツェラン『糸の太陽たち』)─文学における死について
講演者=ダリン・テネフ Darin Tenev(ブルガリア・ソフィア大学)
コメント=山本潤(ドイツ文学)、南谷奉良(一橋大学)
1/6 【社会】川村邦光『弔いの文化史 日本人の鎮魂の形』(中公新書)
日本人は天災や戦争によって非業の死を遂げた者をどのように弔ってきたのか。『古事記』『日本書紀』を起点に仏教説話集『日本霊異記』の世界に分け入り、念仏結社を作った源信、女人救済を説いた蓮如らによる弔いの作法を歴史的に辿る。さらに死者の霊を呼び寄せる巫女の口寄せ、ムカサリ絵馬や花嫁・花婿人形の奉納など現在も続く風習を紹介し、遺影のあり方をも考察。古代から東日本大震災後まで連なる鎮魂の形を探る。
1/13 【歴史】藤原彰『餓死(うえじに)した英霊たち』(青木書店)
アジア太平洋戦争において、日本人の戦没者数は310万人、その中で、軍人軍属の戦没数は230万人とされている。この戦争で特徴的なことは、日本軍の戦没者の6割以上の140万人前後が戦闘行動による戦死ではなく、餓死もしくは飢餓による病死だったことだ。食糧補給を無視した無謀な戦争拡大で、飢餓地獄の中で野垂れ死にした実態──ガダルカナル島の戦いは、戦没者118,700人のうち9割が餓死、及び栄養失調・薬品不足のためのマラリアによる病死。 ポートモレスビー攻略戦とニューギニアの第18軍の戦没者127,600人のうち、9割以上、インパール作戦では78%以上が餓死。中部太平洋の孤島で置き去りにされた半数の125,000人が餓死・病死。戦場で最も多い50万人の戦没者を出したフィリピン戦では8割以上の40万人が餓死。中国戦線では455,700人の半数が栄養失調に起因するマラリア、赤痢、脚気による病死。本書は、無理で無茶苦茶な作戦を計画して実行したり、はじめから補給を無視して栄養失調が起こるのに任せた日本軍の責任と特質を明らかにする。
1/20 【社会】高橋哲哉『靖国問題』(ちくま新書)
21世紀の今も、なお「問題」であり続ける「靖国」。「A級戦犯合祀」「政教分離」「首相参拝」などの諸点については、いまも多くの意見が対立し、その議論は、多くの激しい「思い」を引き起こす。だが、その「思い」に共感するだけでは、あるいは「政治的決着」を図るだけでは、なんの解決にもならないだろう。ベストセラーになった本書は、靖国を具体的な歴史の場に置き直しながら、それが「国家」の装置としてどのような機能と役割を担ってきたのかを明らかにし、犀利な哲学的論理で解決の地平を示している。
1/27 まとめ
後期・演習 ジャック・デリダ『嘘の歴史 序説』読解
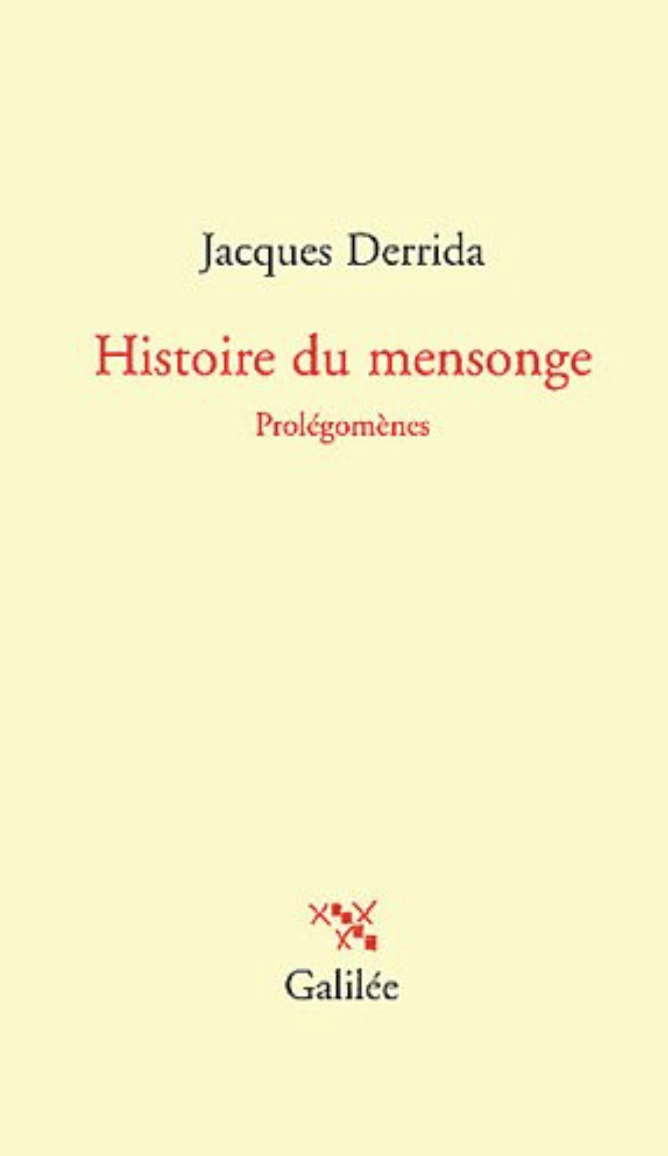 _
_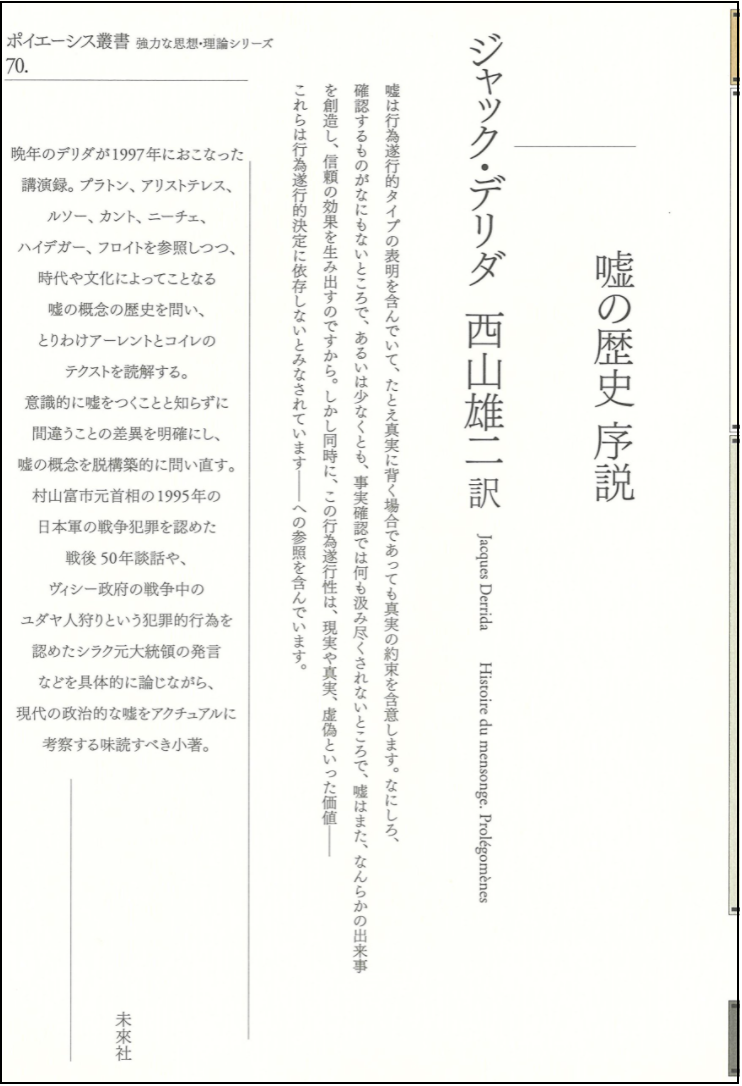
デリダが2003年に他界してから10年、本演習では1994-95年に執筆された『嘘の歴史 序説』を精読することで脱構築思想の理解を深めます。「嘘をつくこと」は、内心で他人をだまそうと思って、意図的に間違った言葉を発することです。たとえ間違ったことでも自分の発言が真実だと信じているならば、その言葉は嘘にはならず、たんなる誤謬とされます。「嘘つきは泥棒の始まり」と言われるように、嘘は大きな悪事に通じる最小限の悪であり、やましい行為です。しかし、「嘘も方言」と言われるように、すべてを本音で話していたら、嘘なしには人間関係や社会は成り立ちません。嘘は悪の発端として忌避されると同時に、必要悪として嘘は社会中に偏在します。本演習では、デリダのテクストに即して、嘘の原理、嘘の歴史、嘘の文化、現代の政治的嘘の特質などを考えます。
第1 回 ガイダンス
第2-4 回 デリダ『嘘の歴史 序説』精読
第5回 カント「人間愛から嘘をつく権利と称されるものについて」
第6-8回 デリダ『嘘の歴史 序説』精読
第9回 アレクサンドル・コイレ「嘘に関する考察」
第10-12回 デリダ『嘘の歴史 序説』精読
第13回 ハンナ・アーレント「政治に於ける嘘」
第14-15回 まとめ

