□ 2009年度研究成果
1. PC鋼より線を用いた梁曲げ破壊型PRC十字形骨組の耐震性能評価に関する研究
北山和宏・矢島龍人・畑山摩琴
現在建築物の耐震設計では,個々の部材および建物全体の地震時挙動の制御を可能とする性能評価型設計法への移行が進みつつある。性能評価型設計法を確立するためには,部材の復元力特性やそれに付随した損傷状況を把握する必要があるが,プレストレスト・コンクリート(PC)部材においては,断面の鉄筋とPC鋼材の配筋量,およびそれらの付着性状によって耐震性能が変化し,その組み合わせが多岐にわたるため,性能評価型設計法を確立するための十分な資料は得られていない。
そこで本研究では,梁断面の主筋とPC鋼材の組み合わせを変数とした梁曲げ破壊型のPC十字形部分骨組試験体4体に対して静的載荷実験を行い,それらの耐震性能(復元力特性,梁主筋の付着性状,塑性ヒンジ領域,残留変形,ひび割れ幅,梁部材の各種限界状態,等価粘性減衰定数など)について調査した。PC鋼材として直径12.7mmの7本より線あるいは直径15.2mmの7本より線を用いた。コンクリートの圧縮強度は69MPaであった。得られた結論を以下に示す。
(1)梁主筋として付着の良いD13を使用した試験体3体は紡錘形の復元力特性を示し,梁のコンクリートの圧壊と梁主筋の座屈・破断が生じた。梁主筋として付着の悪いD19を使用し,プレストレス率が0.45の試験体はRC造に類似した復元力特性を示し,柱梁接合部パネル内の梁主筋の付着劣化によって履歴ループのピンチ化と梁コンクリートの圧壊を生じた。
(2)全試験体で梁部材角の増加とともに梁危険断面から0.5D(D:梁全せい)の領域内の曲げひび割れ幅が増加し,その区間の梁主筋が塑性化した。
(3)梁付け根のコンクリート圧壊領域はプレストレス率が大きくなるほど拡大し,押切載荷時でプレストレス率が最大の0.79である試験体は,プレストレス率が最小の0.45である試験体の1.8倍であり,圧壊長さは全試験体で0.18D〜0.33Dであった。
(4)梁部材角3%(梁の最大耐力程度)時の梁のたわみに占める梁危険断面から0.5Dまでの領域の回転変形の割合は全試験体とも80〜90%であった。
(5)梁の残留変形と残留ひび割れ幅はプレストレス率に影響し,プレストレス率が大きくなるほど残留変形が小さくなり,載荷ピーク時に対する除荷時の曲げひび割れ幅の比は,プレストレス率が0.45ではRC造と同様の0.5程度であったが,プレストレス率が0.79ではその比は0.14であった。
(6)各種限界状態時の梁部材角は,使用限界は0.25〜0.50%,修復限界1は0.93〜1.66%,修復限界2は1.35〜2.26%,安全限界は2.94〜4.32%であった。
(7)梁部材の等価粘性減衰定数はPC鋼材量が増加するほど低下する傾向にあった。
2. スリーブ継手で柱接合したプレキャストPRC骨組の耐震性能評価に関する研究
北山和宏・矢島龍人・見波 進・島 宏之
実際に建築される物件を想定して、プレキャスト梁を通し配置し、上下の柱部材を柱主筋のスリーブ継手で接合して一体にしたときの、プレストレスト鉄筋コンクリート(PRC)骨組の力学特性および耐震性能を正負交番載荷実験によって調査した。この工法では、地震時に曲げモーメントが最大となる柱面で部材を接合しなくてよい上に、梁主筋を柱梁接合部内に通して配筋できるためにエネルギー吸収性能の改善を図れるという利点がある。
実験では、実設計に沿って梁曲げ降伏が先行する試験体を検討対象とするとともに、このような構法によって組み立てられた外柱梁接合部パネルのせん断強度を調査するため、接合部パネルのせん断破壊が先行する試験体も計画した。試験体数は、平面十字形部分架構およびト形部分架構あわせて5体として、一体打ちおよびプレキャスト工法の耐震性能を比較検討した。本研究によって得られた結論を以下に示す。
(1) プレキャスト工法と一体打ちの骨組の復元力特性および破壊性状に差異はなく,最大耐力時の層間変形に占めるプレキャスト柱の目地部のずれ変形の割合は1.5%以下であった。
(2) プレキャスト工法による外柱梁接合部パネルのせん断終局強度は、鉄筋コンクリート柱梁接合部パネルのせん断終局強度評価式を準用して安全側に評価できた。
(3)外柱梁接合部パネル内での柱主筋の付着強度は、シース管内に配筋したプレキャストの場合のほうが一体打ちの場合よりも大きかった。これに対して内柱梁接合部パネル内での柱主筋の付着強度には、プレキャストと一体打ちとで顕著な差は見られなかった。これについて今後、詳細な検討が必要である。
3. PRC柱梁十字形部分架構内の梁部材のエネルギー吸収性能の定量評価
北山和宏・田島祐之
プレストレスト・コンクリート(PC)骨組あるいはプレストレスト鉄筋コンクリート(PRC)骨組の耐震性能を精度よく評価するためには、地震時のエネルギーを主に消費する梁部材のエネルギー吸収性能を定量的に評価することが必須である。通常の柱梁骨組においては、PC鋼材や梁主筋は中柱を通して配筋される。そのため地震時に繰り返し載荷を受けると、柱梁接合部パネル内での付着劣化によってPC鋼材や梁主筋が抜け出し、それに起因して生じるエネルギー吸収能力の低下を無視できなくなる。そこでここでは梁部材単体ではなく、柱梁十字形部分架構内の梁部材を検討の対象とした。
部材のエネルギー吸収性能を定量的に評価するには,コンクリートや鋼材の応力―ひずみ関係の履歴ループの面積を積分する原理的な方法や、部材の復元力履歴特性をモデル化することによって履歴ループの面積を算出する方法等がある。しかし本研究では、柱梁十字形部分架構内の梁部材のエネルギー吸収性能は、柱梁接合部パネル内を通し配筋される梁主筋およびPC鋼材の付着性状によって変化することに着目した。具体的には、これらの両者および梁の終局曲げ耐力に対するPC鋼材の寄与率(プレストレス率)を変数として、等価粘性減衰定数を定量評価する手法を提案した。このような等価粘性減衰定数の評価式を作成する過程で、柱梁接合部パネル内を通し配筋されるPC鋼材の付着性状の良否を判断する指標を提案し、実験結果を詳細に検討することによってその妥当性を確認した。ただし本研究では、柱梁接合部パネル内での付着劣化が、PC鋼材とグラウトとのあいだで生じる場合のみを対象としたことに注意を要する。
4. PC鋼より線に貼付したひずみゲージの養生方法に関する実験検討
北山和宏・嶋田洋介
当研究室でのPC構造を対象とした既往の実験では多くの場合、PC鋼より線の表面に貼付したひずみゲージの出力が載荷試験前に信頼できなくなった。PC鋼より線へのプレストレス導入時やアンボンドの場合では信頼できる出力を得られたことから、シース管内へのグラウトの注入によって引き起こされる何らかの理由によって、ひずみゲージの出力の信頼性が損なわれると考えられた。
そこで本研究ではPRC梁形試験体を製作してPC鋼より線にプレストレスを導入し、その後にグラウトを注入した状態で、PC鋼より線に貼付したひずみゲージの養生試験を行い、養生方法・性能を検討し、今後の実験へのフィードバックを目的とした。実験ではプレストレス導入と同時にひずみの計測を開始し、グラウトの注入を経た約40日間、数時間ごとに箔ひずみゲージ(検長1mm)の出力を記録した。
計6種の養生方法を検討した結果、ひずみゲージを貼付した素線一本に対してコーティング剤等による養生を二層行った上から、自己融着テープと接着剤を含浸させたガーゼとをそれぞれ一層ずつPC鋼より線全体に巻きつけた養生方法が最もゲージ生存率が高く、良好な結果を示した。ゲージ出力値の信頼性はグラウトの水分によって損なわれることが多かった。
5. 純曲げを受けるPRC梁部材の各種限界状態に関する実験研究
北山和宏・嶋田洋介
純曲げを受けるPRC梁部材の各種限界状態について実験によって検討した研究は少ない。そこで本研究では梁せい450mm、梁幅300mmの梁形試験体2体に二点曲げ載荷する実験を行い、PC鋼より線の付着性状,純曲げを受けるPRC梁部材のひび割れ幅、各種限界状態を決定する物理的要因などを検討した。
実験変数はPC鋼より線の径(φ12.7とφ17.8)であり、中央の純曲げ区間は900mm、両側のせん断区間はそれぞれ1000mmとした。コンクリート圧縮強度は42.3MPa、グラウト圧縮強度は51.8MPaであった。実験は漸増片振り載荷とし、載荷ピークおよび除荷時の時期は、主筋降伏、PC鋼材の弾性限界および降伏、圧縮縁コンクリートの圧縮強度到達、などした。実験によって得られた主要な成果を以下に記す。
(1) プレストレスレベルを2倍に増やした梁部材の残留ひび割れ幅は,もとの梁部材の半分程度と小さかった。
(2) プレストレス率が0.75である梁部材の純曲げ区間におけるひずみ適合係数は、0.6〜0.7の一定値を示したのちに断面曲率の増加とともに低下し、PC鋼材降伏時には0.35になった。
(3) 両梁部材の各種限界状態は、使用限界が“主筋の僅かな降伏”あるいは“PC鋼材弾性限界”で決定され、修復限界のほとんどは残留変形角(1/400あるいは1/200)で決まった。この傾向は、既往のPRC柱梁十字形部分架構内の梁部材の結果と同様であった。
6. 既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート耐震壁の新設開口補強に関する実験的研究
北山和宏・和田芳宏・黒倉 花・見波 進・高木次郎・小泉雅生・門脇耕三
既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート(WPC)構造建物の耐震壁に開口を設けた場合を想定し、8体の直交壁およびスラブ付き立体試験体(実建物の1/2スケール)を作製して静的載荷実験を行い、耐震壁の耐力や破壊性状等に対する開口の影響および補強効果を検討した。実験変数は、耐震壁の開口の有無、開口周囲の補強方法(RC補強あるいはS補強)および連層耐震壁を想定したときの反曲点位置である。プレキャスト(PCa)壁板のコンクリート圧縮強度は50〜67MPaであった。
WPC建物では、水平接合部(セッティング・ベース)によってPCa壁板を上下に接合して一体化を図る。そこでこの水平接合部を撤去することは避けて、PCa壁板の左右の水平接合部のあいだに開口を設けることにした。このときの耐震補強方法として次の二通りを考え、試験体を作製した。
1) 新設開口脇のPCa壁板に上下階壁との接合部を設け,転倒モーメントに対する耐力を向上させる。
2) 新設開口上部に補強梁を新設し,開口によって左右に分割された壁板の回転変形に対する曲げ戻し効果を確保する。
これら両方の補強を施すことを基本とし,鉄筋コンクリート(RC)または鉄骨(S)を主体とした耐震補強を行うことで,開口壁の耐震要素としての機能を向上させた。
実験によって得られた結論を、反曲点の位置ごとに分割して以下に示す。
(1) 反曲点位置が高い場合(すなわち対象壁頭部の曲げモーメントが大きく、純曲げに近い状態)
試験体の耐力低下の主要因は、開口および補強の有無に関わらず水平接合部(セッティング・ベース)の損傷であった。
PCa壁板に開口を設置すると、最大耐力は無開口の場合と同等でありながら、変形性能は無開口の場合の4倍程度に増大し、靭性能が大きく改善された。しかし初期剛性は無開口の場合の3割程度に低下するとともに、履歴形状はエネルギー吸収性能の劣るピンチ化を呈した。地震動を受けるWPC建物内の連層耐震壁の外力分布は刻々と変化し、今回の実験のように固定化されたものではないことを勘案すると、既存のPCa壁板に開口を設けた際に未補強のまま使用を継続することには慎重であるべきと判断する。
開口周りにRC補強またはS補強を施すことによって、最大耐力は1.5倍または1.2倍,初期剛性は3.6倍または1.9倍、それぞれ増大した。このことから開口両脇に対する補強の効果を確認できた。しかし,鉄骨補強では補強接続筋を定着した上下階のPCa壁板のひび割れによる損傷によって最大耐力が決定された。またRC補強では、下階の壁頭部に増設した梁(開口脇のRC柱形の主筋を定着するためのもの)の直下のPCa壁板のひび割れ開口によって最大耐力に到達した。以上から、縦方向の補強部材の上下階への定着方法には改善の余地がある。
(2) 反曲点位置が低い場合(すなわち対象壁頭部の曲げモーメントが小さく、片持ちに近い状態)
無補強試験体は水平接合部の損傷により、補強試験体はプレキャスト壁板のせん断破壊により、それぞれ耐力が低下した。開口周りにRC補強またはS補強を施すことによって、最大耐力は2.1倍または1.6倍,初期剛性は4.7倍または2.5倍、それぞれ増大した。このことから両手法による耐震補強効果が確認されたが、補強によって耐力が増大したことからPCa壁板は最終的にはせん断破壊し、壁板の損傷が顕著となった。これに対しては修復性確保の観点から、今後の検討が必要である。
7. 兵庫県南部地震で生き残ったRC中層建物の被害と耐震性能に関する研究
北山和宏・白井 遼・青木 茂
検討対象としたF医院は神戸市灘区に現存し、2008年に青木茂建築工房によってリファインされた建物である。地震直後に日本建築学会によって実施された調査報告によれば、F医院は無被害と判定された。しかし、周辺の鉄筋コンクリート(RC)建物には大破あるいは中破のものが多くみられた。リファイン時に仕上げを撤去した際、施工不良および地震による損傷が多数みられ、その際に行われた三次診断では1〜4階がY(梁間)方向で基準値Iso(=0.6)を満足せず、耐震性能は十分とはいえないことが判明した。本研究では、この建物の調査・分析を行い地震による実被害の詳細を把握し、大地震を生き抜いた原因を検討した。
F医院は1972年竣工のRC建物で兵庫県南部地震の際に震度7を経験した。東西(X方向)4スパン、南北(Y方向)2スパンからなる5階建ての中層部分と、東西2スパン、南北2スパンからなる2階建ての低層部分がL字形に配された構成であり、両者は構造的に一体である。なお、低層部分はY方向に耐震壁のないピロティである。架構形式はX・Y方向ともに耐震壁付フレーム構造である。耐震壁はX方向には多く設置されているがY方向は少ない。下階壁抜け柱は1階のA通り3柱,1・2階のE通り2・3柱である。当該敷地は第2種地盤で直接基礎であった。主要な柱の断面寸法は600×600mmであり、柱のせん断補強筋の間隔は構造図と現地調査から1・2階:150mm(せん断補強筋比pw=0.14%),3-5階:200mm(pw=0.11%)であった。
兵庫県南部地震による柱の損傷は中層部分1階に多く、損傷度?に分類した柱にはせん断ひび割れ・コアコンクリート欠損がみられた。下階壁抜け柱(A-3,E-2及びE-3柱)の損傷度はいずれも?であり、下階壁抜けの悪影響が表れた。また、耐震壁の他に構面外のRC壁(構面外壁)にもせん断ひび割れが見られた。低層部分では鉛直部材の損傷はみられなかったが、中層部分と低層部分の境界梁にはせん断ひび割れを生じたものが複数あった。地震動によるひび割れが多数見られたものの、RC柱の軸縮みや鉄筋の座屈・破断といった甚大な損傷は見られなかった。耐震性能残存率Rによる被災度区分は小破に近い中破であった。
この建物の耐震性能を検討するために、耐震二次診断を実施した。施工不良を無視した二次診断に加えて、ジャンカを考慮した場合、構面外壁を考慮した場合および両者を同時に考慮した場合もあわせて実施した。なお、コンクリートブロック壁は診断では無視した。ジャンカによる影響はX方向1,4階、Y方向3,4階で見られ、Is値は最大で0.06低下した。構面外壁の影響はY方向で顕著であり、2〜4階でIs値が0.1以上増加した。リファイン時に行われた三次診断および施工不良を無視した二次診断ではY方向の耐震性能が劣ると判定された。しかしジャンカおよび構面外壁を同時に考慮すると、Y方向では1階以外は0.6以上のIs値を有していた。構面外壁が地震力に有効に抵抗したことによってF医院は兵庫県南部地震に生き残れたと考える。ただしY方向1階のIs値は0.48と小さく、今後さらに検討が必要である。
8. わが国の耐震構造の発展に対するジョサイア・コンドルの技術的貢献に関する研究
北山和宏・宮木香那
ジョサイア・コンドルは、明治維新後の日本に学問としての建築学を教授するために日本政府に雇われて来日し、工部大学校造家学科の唯一の教授として日本の建築界を産み出し、育てた恩人である。コンドルは地震のない英国から来たが、地震国である日本においては耐震構造が必要であることを度々指摘した。
そこで本研究では、日本の耐震構造の発展にコンドルが果たした技術的貢献について、文献および図面を調査することによって検討した。ここではコンドルが煉瓦造建物を鉄材で補強する方法を考え、実践したという事実に着目した。
小野木重勝による既往の研究にはコンドルの書簡(明治15[1882]年)が紹介されており、皇居造営計画における正殿建物の煉瓦壁体に水平および鉛直の鉄材を挿入して補強するという手法、およびそのときの煉瓦目地(石灰モルタル)の水平強度および水平鉄材(錬鉄)の引張り強度が具体的に記されている。これをもとにコンドルが暗黙のうちに想定した水平震度(k=Q/W)を幾つかの仮定のもとで求めたところ、1.1となった。すなわち、重力加速度と同等以上の水平加速度が地震時に建物に作用しても壊れないくらいの強度を想定していたことになる。
ただしコンドルは、建物の保有水平耐力を考えていた訳ではなさそうである。上述の書簡によると、建物内の諸々の部位がその質量に依存して様々な周期で振動する(このことはニュートンのf=maという力学法則から容易に想像できよう)ことから、壁体の連層開口の上下の部材(短スパン梁に相当)のように左右の重量物に挟まれた部位には大きな引張り力が作用するので、この部分に水平鉄材を挿入して補強すればよいと考えた。すなわち、純粋な引張り補強である。
現代においては水平力を受ける煉瓦やRCの壁部材がせん断破壊する、という現象は周知であるが、19世紀のコンドルはそのような現象は知らなかったであろう。地震のない英国では基本的には軸力に対して建物を設計すればよいので、日本において地震対策を考えたときにも軸力だけに対処すればよい、と考えたと思われる。その証拠にコンドルは、煉瓦壁体に挿入した鉛直鉄材は鉛直地震動による引張り力のみを受ける、と述べた。水平力にともなって生じる曲げモーメント(転倒モーメント)に起因する軸力については触れていないのである。
当時は地震動によって建物がどのように振動するのか誰も知らなかったし、鉄組補強煉瓦造の力学挙動についても未解明であったから、コンドルがこのように考えたのも無理からぬものがある。しかしコンドルは同じ書簡で、煉瓦壁体内の鉛直および水平鉄材がフレームを形成して各煉瓦ブロックを拘束するのに役立つ、とも述べており、煉瓦と鉄材とが協同して外力に抵抗する効果を想定していたとも思われる。
コンドルの時代には建物の構造力学が未成熟であり、地震動の特性についても未知であったために、地震動に対して安全な建物を構築するための耐震構造を科学的に考えるには時期尚早であった。結局、煉瓦造を鉄材で補強するという一点において、その後の我が国における鉄筋コンクリート構造の導入を準備するのに役立ったと判断できよう。
9. 鉄筋コンクリート骨組内の梁部材に対する耐震性能評価手法の高度化研究
北山和宏・王 磊
「鉄筋コンクリート造建物の耐震性能評価指針(案)・同解説」(日本建築学会、2004年)には、鉄筋コンクリート造(RC)骨組内の梁部材の耐震性能を評価する実用的手法が提案されており、当研究室での既往の研究によって、主筋降伏までの変形性能(使用限界に相当)は比較的精度よく評価可能であることが明らかになっている。しかしそれ以降の修復限界や安全限界に対応する変形性能の評価手法の妥当性についてはほとんど検証されていない。
そこで本研究では梁降伏型骨組を対象に、柱梁接合部パネルからの梁主筋の抜け出しによる変形および梁部材内の梁主筋の付着劣化に起因する変形に注目して、これらを実験によって詳細に測定することによって、梁部材の修復限界時および安全限界時の変形性能を検討する。2009年度はそのための平面十字形柱梁部分骨組試験体3体を作製した。今後、実験を行う予定である。
|

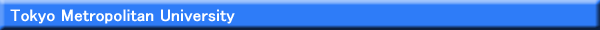
 トップページ > 研究について > 2009年度研究成果
トップページ > 研究について > 2009年度研究成果
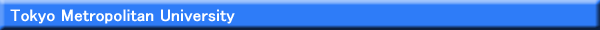
 トップページ > 研究について > 2009年度研究成果
トップページ > 研究について > 2009年度研究成果