Reports
国際哲学コレージュ30周年イベント(2013年6月)
西山雄二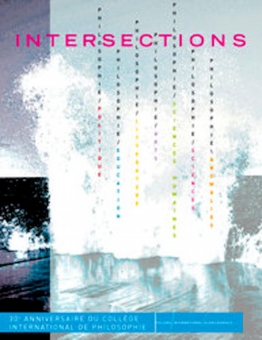
1983年10月、ミッテラン政権の文化政策の目玉として、フランソワ・シャトレ、ジャン=ピエール・ファイユ、ジャック・デリダ、ドミニク・ルクールの主導で国際哲学コレージュが開設された。コレージュは創設されたのは、閉鎖的で権威的な大学組織とも異なり、大衆化されたマスメディア風哲学とも異なる、開放的で創造的だが学究的で専門的な研究教育の場をつくるためだった。コレージュは「哲学」という名称を掲げつつも、文学や政治、経済、自然科学、芸術、精神分析との領域交差(intersection)を誘発する場である。また、いわゆる大学教員以外、高校教員や分析家などにもセミネールを担当する権利――哲学への権利――を付与する、フランスでは例外的な制度である。
本2013年に30周年を迎えた国際哲学コレージュは、6月最初の2週間に記念イベントを組んだ。イベントは哲学の国際的な交流や混交を議論するシンポジウム「思想の移動」に始まり、総括的討論会「領域交差」をメインにして、パルメニデスの詩を多言語で翻訳し朗読するイベントで幕を閉じる。単独の講演会としては、エティエンヌ・バリバール「1983年――共同体の問い」、ジャック・ランシエール「芸術と政治」、ブルーノ・ラトゥールの書評会、カトリーヌ・マラブー「超越論的なものを放棄しうるのか」が予定されている。デリダ関係としては、脱構築と大衆文化の関係を問う「脱構築の大衆性」、デリダの自伝著者ブノワ・ピーターズとの討論会が組まれている。
10年前の2003年、私はパリに留学しており、コレージュの20周年の開会イベントを聞きにいった。デリダとナンシーの対話でコレージュのあり方を振り返る内容で、デリダがカント「啓蒙とは何か」を引き合いに出したのが印象的だった。同日の午後、諸外国の研究者の招待講演がおこなわれ、日本からは小林康夫氏が講演「アナクロニズム」をおこなった。後で聞いた話では、この招待講演は彼の生涯の中でももっとも力を入れて、緊張して準備した原稿だと言う。光栄なことに、今回は映画「哲学への権利」の上映と討論会で30周年イベントに参加させてもらった。
(映画「哲学への権利」討論会)
「脱構築の大衆性」では、「到来するもの」と表現された脱構築がポップカルチャーや、大衆性・民衆性といかに関係するのかが議論された。デリダの脱構築は直接的に大衆文化を対象とはしなかったが、「脱構築」の表現や思想はすでに十分大衆的であり、悪しき世俗化にいかにさらされないようにするのか、配慮する必要がある。脱構築は明確な体系や方法論をもたないので、「大衆的秘教主義」とでも言える現象を誘発する。現前性に依拠しない脱構築の戦略はある種の秘密を宿した大衆性をともない、さらには、脱構築の「ファン」とは誰か、「ファン」とは何か、という問いも提起される。
(中央はA-G.デュットマン)
デリダは『哲学への権利について』において、「大衆性」に関する論考を収めている。カントは『人倫の形而上学』で、たしかに哲学は「大衆性(一般民衆へ伝達されるために十分なだけ感覚的であること)を備えていなければならない」が、「ただし、理性そのものの批判の体系、およびこの批判の規定によってしか証明されえないいっさいのもの」、すなわち、「超感性的でありながらもなお理性に帰属するもの」との区別は必要だと主張する。デリダによれば、「脱構築的な数多くの手法は長いあいだ、まさにこの区別をそれ自体において、その効果の極端な多様性において追跡してきたのであり、この区別は代補的な複雑さにほかならない」。脱構築の責任の厳密さと公共空間やメディア空間の新たな秩序を両立させるためにはそうした区別を考慮する必要がある。
作家ブノワ・ピーターズ(写真中央)は詳細な伝記『デリダ』と同時に、日記風エッセイ『デリダとの三年』(Trois ans avec Derrida)を刊行した。自伝の方は七カ国語での翻訳が進められているが、『デリダとの三年』に翻訳依頼はなく、むしろ軽視されている。『デリダとの三年』では伝記執筆に向けた日記風の文章が日付順に配され、取材や執筆過程の様子を記した文章やデリダの伝記執筆の意味を問うメタ的な文章が並ぶ。今回は、デリダの伝記へのこの代補的エクリチュールを考察する珍しい機会だった。
デリダの没後にその伝記を執筆する試みは、デリダが問い続けた「起源」と「代補」の構造を必然的に孕む。通常、伝記を準備するためには、刊行されたテクスト群を参照すると同時に、数多くの関係者の証言を聞く。デリダの痕跡をたどるうちに、デリダのひとつの伝記を真面目な仕方で書くことはできるのだろうかと、ピーターズは自問したという。
演劇作品「ポワンチュールの真理」。ゴッホの「靴」をめぐるハイデガーとデリダの解釈を戯曲化。デリダの同名のコロンビア大講義やハイデガーの再現が盛り込まれる引用の織物。生前のデリダに許可を得ており、この30周年での初公演となった。

『絵画における真理』のもとになった、デリダ講義を再現。話し方がそっくりで、誇張された語りには会場からは笑いも起こる。
国際哲学コレージュ30周年記念のランシエール講演。彼は86−92年までコレージュのディレクターを担当。床に座るほど満員の会場で、『感性的なもののパルタージュ』を軸に美学と政治の関係に関して、いつものように何かが憑依したように語る。
カトリーヌ・マラブーの講演「超越論的なものを放棄しうるのか」は、気鋭の哲学者クオンタン・メイヤスーの「思弁的実在論」の批判的考察。カント以来の超越論的なものの思考枠組みを放棄しつつ、思考の脱自己固有化や根本的な他性化をラディカルに試みるメイヤスーに讃辞を惜しまないマラブー。ただ、哲学の数学化にも似た手続きには違和感が残り、「思弁的実在論」は思考に何かが到来する契機を完全に欠落させてしまう「何でもあり」の思想になる恐れはないか、と批判。
コレージュは今年、ディレクターの半数25名が改編され、初の中国人ディレクターとして姜丹丹(Dandan Jiang)氏が選出された。風景の哲学を専門とする姜氏と話し合い、アジア方面でのフランス思想の展開を図ることで合意した。学術研究において中国の躍進は著しく、今後、(その質というよりも、数や量、存在感という点で低迷に向かうおそれがある)日本のフランス研究は、中国のフランス研究と連携しなければならない時代になるのではないか。
10年前の20周年のイベントと比べると、たしかに国際哲学コレージュの活気は失われている。あの頃はデリダが生きていて、重要な催事には足を運び、最前列で聞いていたが、その存在感は大きかった。30周年のイベントではデリダへのノスタルジー的な雰囲気も感じられた。ある日の質疑応答で、「コレージュの創設者のひとりであるジャン=ピエール・ファイユは今春、創設に関する論争的な小著『デリダへの手紙』を出版したけれど、今回の記念イベントに呼ばないのか」という質問があった。「30周年イベントは1年以上前から準備しているため、ファイユの新著でイベントを組むことはできなかった」とコレージュの担当者は応答したが、会場の興奮は収まらなかった。40周年になると、デリダとは直接の面識のないディレクターがますます多くなるだろう。たしかに国際哲学コレージュはデリダの制度的実践の産物だが、ただ今後、彼へのノスタルジーからいかに自由になるかが課題であることは明らかだった。これは私自身に対する自己確認でもある。

