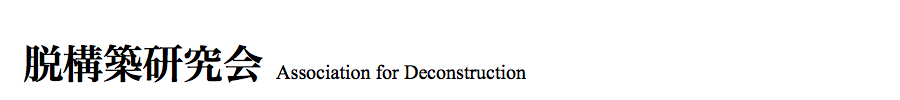Review

守中高明『ジャック・デリダと精神分析 耳・秘密・灰そして主権著』岩波書店
評者:佐藤 嘉幸(筑波大学准教授。哲学・思想史専攻)
ジャック・デリダの思想は精神分析といかなる関係を取り結んでいるのか――この問いをめぐって、これまで複数の著者によって様々な議論がなされてきた。しかし、守中高明『ジャック・デリダと精神分析』はこの問いに新たな角度から回答を与えている。これまでの議論は、デリダによるラカン的精神分析の批判という論点に議論が集中していた。例えば、「真実の配達人」におけるラカン理論の批判――すなわち、欠如に基づいて組織化されるラカン的主体概念の批判であり、その「ファロス中心主義」批判である。むろん、守中も本書でこれらの点を丁寧に論じている。しかし、その仕方は従来とはいささか異なるものだ。彼は、デリダによるラカン批判からデリダ独自の精神分析的思考が導かれると考え、それを「デリダ的精神分析」あるいは「脱構築と(しての)精神分析」と呼ぶのである(しかし同時に、それが単に精神分析理論ではなく、デリダ独自の哲学であることも強調しておかなければならない)。
それでは、「デリダ的精神分析」とは何か。最も簡潔に述べるなら、それは散種的思考の謂いに他ならない。ラカン理論とは、特権的シニフィアン(超越論的シニフィアン)である欠如のシニフィアンを中心として構造化された欲望と、そのような欲望によって組織化された主体、すなわち欠如の主体に関する理論である。それに対してデリダは、欠如のシニフィアンも特権的シニフィアンも存在せず、諸々の情動はただ散種と差延の運動に従って絶えざる移行と相互干渉を繰り返すに過ぎないと考える。そこから、欠如の超越論的シニフィアンによって構造化された象徴界あるいは同一性の主体は解体され、散種的運動を原理とする多数多様性の主体が形成されるだろう。守中は、そのようなデリダの散種的思考を幾つかの異なった名前で呼んでいる。すなわち、ラカン的な同一性の主体に還元されることを絶対的に拒み続ける「秘密」、ヘーゲル=ラカン的弁証法の同一化の運動には決して還元されない非現前的「痕跡」としての「灰」、そして国家的/国民的同一性に依拠した主権的支配の構造を壊乱し、解体する「歓待」……。
ここで興味深いのは、守中がこのような散種的思考をアクチュアルな政治情況へと差し向け、それへの抵抗の手段として用いている点である。例えば彼は、デリダ的な「秘密」概念を、フーコーが『知への意志』で明らかにしたような、人々に常に内心の告白を強制する司牧権力への抵抗の一形態として位置付ける。そして、それを「思想及び良心の自由」(日本国憲法第一九条)以上のものと定義することで、思想信条のレヴェルで国家的/国民的同一性を押し付けようとする現在の政治(例えば国旗国歌問題を参照せよ)に対する抵抗の手段となすのである。また彼は、九・一一以後のアメリカ、さらにはEU諸国による「対テロ戦争」が中東から大量の難民を生み出し続けている情況を参照し、難民に対する主権的管理の強化、「対テロ」を名目としたセキュリティ管理の強化、そしてこの情況を最大限に利用した極右勢力の台頭に対して、デリダ的な「無条件の歓待」――「待ち望まれても招待されてもいない誰に対しても前もって開かれており、絶対的に異質な訪問者として、同定不可能で予測不可能な到来者として、つまりはまったき他者として到来する誰に対しても前もって開かれている」ような歓待――の思想を突きつける。そして、「強者の理性」の側にある「寛容」は主権的管理の別名である、というデリダの言葉を引用しながら、無条件の歓待が散種的思考に従って国家的/国民的同一性の構造を解体するという「来るべき民主主義」を構想するのである。このように「デリダ的精神分析」がアクチュアルな政治情況へと差し向けられるとき、本書は「デリダ的精神分析とは何か」という問いを超えて、現代に生きる私たちにとって不可欠な政治的思考へと変貌するのである。