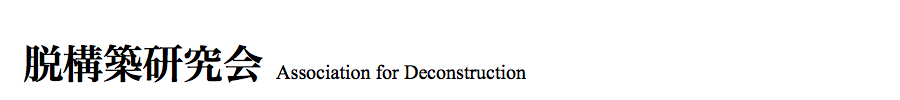Review

マーティン・ヘグルンド『ラディカル無神論 デリダと生の時間』、法政大学出版局
評者:立花 史(早稲田大学非常勤講師)
ヘグルンドは、すでに邦訳のある三本の論文から、ポスト現代思想の旗手メイヤスーをデリダ哲学の見地から批判した論客として認知されているかもしれない。本書は、彼のデリダ論の全貌であり、巻末には、雑誌掲載されたメイヤスー論が特別に収められている。論争する思想家ヘグルンドの姿は本書でも健在だ。論敵の立場をしっかりと見定めて、相手の問題点を理詰めでていねいに論駁し、明快な論理で周囲を説得しようとする姿勢がうかがえる。その意味で『ラディカル無神論』という本書の題名も示唆的である。
今日、デリダには倫理的な哲学者のイメージがつきまとっている。「脱構築は正義である」という定式を打ち出した『法の力』以降、倫理・法・政治を問い直す論考をいくつも発表してきたことを考えれば無理もない。デリダの思想にひそむ論理を丹念にたどってきた研究者たち自身でさえ、その論調を、留保の括弧とともに“政治的”あるいは“倫理的”な転回と称する場面がしばしば見られ、さらには、ある種の宗教哲学としてデリダを受容する傾向が、英語圏やフランス語圏にかぎらず、おそらくは日本にさえ存在する。宗教倫理のごとき規範を語り、理念的な民主制を謳う――まさにそうしたデリダ像に、本書は徹底して異議申し立てをおこない、デリダ像の刷新に挑んでいる。
ただし急いで付け加えておかねばならないが、「ラディカル無神論」は、宗教一般を全否定するものではない。それ以前に、本書で論じられるデリダは、批判者としての相貌からはある意味でもっとも遠い。むしろそこには、シンプルな思想的洞察から、思いがけない論理的もしくは主題的な帰結を無数に導き出す哲学者が、ジェフリー・ベニントンのような堅実な研究者が辛抱強く指摘してきたデリダがいる。そして本書の醍醐味は、ヘグルンドが、ときにはデリダ自身の不徹底に苦言をもらしながら、「彼の議論を発展させ、彼の議論を補強し、そのさまざまな含意を追跡」(二三頁)している点にある。濃密かつ大胆なその議論は、英語圏のデリダ通たちに大きな反響をもたらした。
本書の構成を見ておこう。序文で、ジャン=リュック・マリオンらの“否定神学的”なデリダ理解の難点を示したのを皮切りに、その論理と概念を明確化すべく、デリダをさまざまな哲学者と対比している。第一章では、時間の無条件性に立脚した脱構築の論理をめぐって、カント(とりわけその「理念」概念)が、第二章では、時間の綜合をめぐって、フッサール(とザハヴィ、ベルネット、バーンバウムのデリダ批判)が、第三章では、原―暴力と倫理の関係をめぐって、主にレヴィナスが、第四章では、ラディカル無神論をめぐって、アウグスティヌスが、第五章では、デモクラシーや覇権の概念をめぐって、エルネスト・ラクラウ(と彼が依拠したラカンの欲望理論)が参照されている。
デリダの哲学は、アリストテレスが『自然学』で論じた時間の問いを共有する。「今」という契機は、つねに同じ今でありながら、その継起のなかで次々と別の今に入れ替わってゆく。現在は〈もはやない〉と〈いまだない〉につねにすでに引き裂かれている。そうした運動を示す時間なるものを、現前性という同一性の側からではなく、デリダは(ハイデガーを経由しつつ)差延の側から捉えなおす。時間とは痕跡の綜合であり、おのおのの今は痕跡であって、現前を終えて次の今が現前するのではなく、その変質がそもそもの初めから生起していて、存在し始めるやいなや過ぎ去る。そうした痕跡は、未来のために残された過去の痕跡であるかぎりにおいて、本質的にその抹消可能性や破壊可能性にさらされている。
同じ事態を、デリダは「時間の間隔化」としても論じている。時間の空間化と空間の時間化をもたらす世界の「超―超越論的な条件」は、何ものも、それ自体として現前させることはなく、すべてを原理的に分割する。かくしてヘグルンドは、物事を、存在の充溢ではなく、時間のもたらす差延の観点から、つまり痕跡、間隔化、分割、有限性、自己免疫性の側から捉える哲学を、理路整然と組み立てなおしている。現象学者たちのデリダ批判への反論はその一環だが、それ以上に重要なのは、彼の議論がデリダの諸概念にもたらす帰結である。
ヘグルンドは、デリダが用いる正義、歓待、デモクラシーといった鍵概念を、デリダの思想を織り込んだ形で再定式化してゆく。これらの概念は、時間の分割を踏まえたものである以上、「好機と脅威」という両極端の出来事の到来に開かれたものであり、それゆえに実定的な規定をもたないばかりか、倫理的価値を有しておらず、対立する概念にも開かれている。本書でヘグルンドは、デリダの「べき」や「ねばならない」が、倫理的要請ではなく、事態の必然性を示していることを力説し、むしろ特定の価値を帯びた諸概念を、「それら自身に抗するものとして」語り直したところにデリダの脱構築を認めている。
出来事への開かれの論理に沿って、ヘグルンドは、デリダの「生の無条件的肯定」という論点にも着目する。そこで重要となるのが「生き延び」の概念であり、本書の貢献の別側面は、この概念の分析にあると言ってよい。人間の生は、過去に失われたものと未来に失われるだろうものの狭間にあり、生もまた、存在の充溢ではなく、そもそもの初めから死を刻印されている。そうした生を生きる他者を愛し求めるとき、われわれは、死すべき者としてその他者を欲望している。「デリダにとってメシア的希望は時間的な生き延びへの希望であり、信は有限なものへの信であり、神への欲望は、他のすべての欲望と同様に、死すべきものへの欲望なのだ」(二三〇頁)。
「ラディカル無神論」という概念は、デリダ由来ではあるが、デリダの哲学を、時間による分割の外部を一切認めない透徹した論理によって、世界の事実性から、人間の欲望、文学・宗教・政治までを再考したものとして描き出すヘグルンドの立場を示したものである。この立場が、カプートやクリッチリーらの宗教哲学的なデリダ理解に対する強い疑念を含んでいることは明らかだが、同時にメイヤスーへの根本的な批判の軸線ともなっている。二人の争点は、時間が有する絶対的な破壊可能性に対する両者のアプローチの相違や、神や宗教の捉え方の違いのうちに端的に見てとることができるだろう。
ところで本書は、デリダを始め、いわゆる“大陸哲学”を中心に扱ってはいるものの、かならずしもそれに尽きるわけではない。ヘグルンドが何度か援用しているヘンリー・ステーテンは、『ウィトゲンシュタインとデリダ』で、「推移的本質」(邦訳一九〇頁)を手がかりに、後期ヴィトゲンシュタインとダーウィンの接点を探りながらデリダを論じていた。その影響か、ヘグルンドもまた、生物の進化や放射能の半減期を事例に、痕跡の概念を解き明かしている。ただし、宗教哲学な解釈への批判には一理あるとしても、デリダの思想から倫理的な含意を大幅に脱色した本書の立論全体が、デリディアンたちから満場一致で迎えられたわけではなく、デレク・アトリッジとの論争の核心部分も、いまだ決着がついているとは言いがたい。
それでも本書は、デリダ哲学の数ある未来の一つを垣間見せてくれたのではなかろうか。オール・オア・ナッシングの二項対立的な概念、矛盾律、通信モデルに拘束された思考の外側で、シャノンの情報理論を越えて、物理情報・生命情報・社会情報を再統合する新たな情報概念に立脚した世界記述の可能性を。かつて、リチャード・ビアーズワースが、デリダ哲学の二つの将来的ヴィジョンとして、宗教哲学的な方向とメディア論的・技術哲学的な方向を挙げていた。その後者の先で、ヘグルンドの語る「時間の原―物質性」が“情報のマテリアリズム”へと展開し、ラディカルな情報哲学が到来する可能性は、しかし、いまだ来たるべきものにとどまっている。