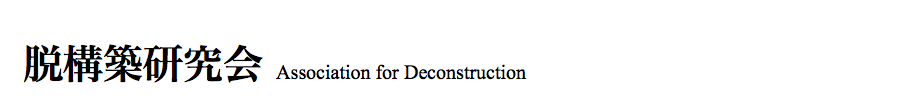Review

カトリーヌ・マラブー『新たなる傷つきし者――フロイトから神経学へ 現代の心的外傷を考える』平野徹訳、河出書房新社、2016年
評者=西山雄二(首都大学東京・フランス思想)
本書は、哲学者カトリーヌ・マラブーが可塑性という概念を軸として精神分析と神経学の建設的な対話を試み、脳と思考の新たな唯物論を示した見事な著作である。博士論文をもとにした『ヘーゲルの未来』においてマラブーは、絶対知の自己円環運動たるヘーゲル哲学には未来がないという定式を覆し、ヘーゲル哲学に新しい何かが到来する諸契機を探り当てた。本書も、精緻なフロイト読解から精神分析と神経学の限界を見定め、その彼岸へと新たな地平を垣間見させるという痛快な論述に満ちている。なお、専門用語が多用されるものの、日本語訳は実に平明で、読みやすい訳書に仕上がっている。
マラブーは祖母が患ったアルツハイマー病を目の当たりにして本書を構想した。精神分析では、傷の前後での自己の心的連続性を前提とするため、アルツハイマー病は退行と解され、自己同一性は不変である。だがマラブーによれば、脳損傷を受けて同一性が破壊される場合、別の同一性が創造される。彼女はこれを、昔日の悪魔憑きや狂人、精神分析の神経症者とは異なる、現代の「新たなる傷つきし者」と呼ぶ。フィアネス・ケージの有名な症例などを参照しつつ、本書で目指されているのは、脳損傷の事例だけでなく、戦争やテロ、性的虐待などの現代の暴力にも関わる心的外傷の一般理論である。
「可塑性」はマラブーがヘーゲル哲学を再解釈するなかで見出した概念で、形を受け取り、形を与える能力を指す。また、可塑性にはあらゆる形を破砕し無化するという否定的な作用もある。つまり可塑性は形の創造と破壊という両極的な概念であり、外傷による主体の同一性の根本的変容を解釈する上で有効な考え方となる。
フロイトは『快原則の彼岸』で生の欲動と死の欲動、構築と崩壊の力を認めているが、あくまでも前者の方が優位に置かれ、適切な弾性的均衡として解釈される。精神病理学における復元性は、衝撃を被った個人や社会がいかに修復され再構成されるかを説明してくれるが、予定調和的な柔軟性に帰着してしまう。マラブーは精神分析と神経学が把握し損ねている否定的可塑性を追及し、快原則の彼岸の実在を概念化する。神経学が解き明かす脳の真の可能性が教えてくれるのは、傷を受けた自己変貌に破壊者と創造者が共存しているという破壊的可塑性である。自己抹殺的な変容の後で、別の同一性とともに生き延びるという創造的出来事が起こりうるのだ。
マラブーが切り開いた地平から繰り出される批判の鋭さには随所で圧倒されるが、結尾ではジャック・デリダの『精神分析のとまどい』が参照されている。彼女は、残虐性という喫緊の課題に対する精神分析の応答というデリダの主張に賛同しつつも、彼が神経学との対話を敬遠して、精神分析だけにその未来を期待する態度を論難する。フロイトは失敗したが、死の欲動に固有な形象や構造を形づくることが重要であり、マラブーは、精神分析と神経学の中間で破壊的可塑性の概念を洗練させる。彼女は偶発事故の主体という新たな概念を提示し、脳と無意識をともに考察する新たな精神哲学を力強く指し示すのである。性事象と脳事象の体制の根底に破壊的可塑性の実在を認めることは悲観的な態度にもみえる。しかし、それは安直な救済の展望を退けて、過去を空無化された「新たな傷つきし者たち」に応答しうる新たな臨床の可能性に通じているのである。
私事で恐縮だが、私が十歳のとき、父が脳内出血で倒れ、言語活動を失い、半身が麻痺してしまった。突然幼児のようになった父を見て、私は驚愕した。その後十年間、三度の手術を経て徐々に状態は悪くなり、最後は植物状態で彼は静かに呼吸を止めた。マラブーの斬新な主張に感銘を受けたいま、偶発事故によって根本的に変容した主体と過ごしたあの体験を、私は別な仕方で解釈することができる。
(読書人2016年9/23号)