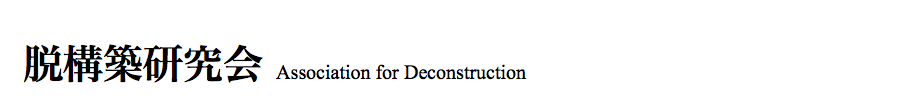Review

バーバラ・ジョンソン『批評的差異──読むことの現代的修辞に関する試論集』土田知則訳(法政大学出版局、2016年)書評
宮﨑裕助
脱構築が文芸批評の一大潮流として力を揮っていたのはいつのことだったのか。台風の目たるフランスの哲学者ジャック・デリダ、北アメリカでイェール学派を率いた批評家ポール・ド・マン、この二人の仕事を除けば、脱構築批評の価値はいまでは訝しく思う者もいるかもしれない。所詮は流行の名にすぎず、残るはデリダとド・マンという特異な個人の仕事のみ、と。
このたび翻訳されたバーバラ・ジョンソンの『批評的差異』、原書刊行は八一年、三十五年も前である。一九四七年生まれのジョンソンは二〇〇九年に他界している。本書は一般的には、脱構築批評の退潮とともに、もはやほとんど顧みられることがなくなってしまったように思われる。
しかしいま、土田氏の流暢な日本語訳によって読み返してみるならば、本書が、一般に流布している英語圏の脱構築批評のイメージ──デリダやド・マンの劣化コピー版──とはほど遠い、きわめて高いテクストの質を備えていることがわかる。これはたんなる二番煎じなどではない。そうではなく、彼らの洞察を最良の部分で継承しつつ換骨奪胎し、独自の仕方でテクスト読解を実践してみせた見事な範例である。本書は、紛れもなく脱構築批評の最高の成果のひとつであり、デリダやド・マンとは別に、ジョンソンのような存在(他にもド・マンの教え子であった「イェールの娘たち」、ショシャナ・フェルマン、シンシア・チェイス、キャシー・カルースが挙げられよう)を通じて、脱構築がいまなお再検討すべき歴史的な名であることに気づかされるのである。
本書が取り組んでいる対象は、一九世紀から二〇世紀前半の古典的かつ多彩なテクストであり、ざっと著者名を挙げておけば、ジョンソンの専門であるマラルメとボードレール、加えてバルザック、ロラン・バルト、メルヴィル、ポー、ラカン、デリダ等々である。
慧眼な読者ならすぐに看て取るように、彼らは、一般には詩や小説の書き手として知られる者であっても批評的作品を残している者であり、逆もまた成り立つ。つまり哲学者や思想家と知られる者であっても限りなく文学と呼ばれる書き物に近い作品を多数残している書き手たちである。
したがってまずもって問題になっているのは、文学/批評というジャンル間の差異である。本書のタイトル「批評的差異[クリティカル・ディフェランス]」は、そうしたジャンル分けを攪乱するテクストの現実を指し示している。すなわち当の「差異」は、さまざまな二項対立(男/女、セクシュアリティ/テクスチュアリティ、散文/韻文、オリジナル/反復、詩/理論、科学/文学、犯人/被害者/裁判官等々)を通して標定されながら、まさしく「決定的な違い」──本書のタイトルの口語的な意味──としてはそこから逸脱してゆくことが追跡されるのである。結果、本書が示唆するのは、そもそも私たちが読むとはどういうことなのか、あるいは読むことに否応なく媒介された私たちの生とはいかなるものなのか、ということにほかならない。
本書の企図の困難さにもかかわらず、その論述は明晰さと尖鋭さという点で水際立っている。ここにはデリダのような冗長さもド・マンのような難解さもない。哲学者や思想家の書き物としてではなく、しかし彼らの達成した理論的水準は決して落とすことなく、あくまで一人の読み手として、個々のテクストの精読に定位して果敢に議論を展開していることの意義は強調してもしすぎることがない。
ジョンソン自身は本書以後、古典の読解よりも、フェミニズム批評やポストコロニアリズム研究の流行に応じるかたちで、より「現実的で」「倫理・政治的な」(コン)テクストへ向かっていた。そのために正典[キャノン]を主対象とする本書の企てが時代遅れのように扱われることがある。
しかし本書をいま読み直してわかるのは、後年デリダによって展開されるいくつかのアプローチや主題──言語行為論の援用や、真実と嘘、法と判断といった問題系──がすでに本書に出ているということである。後年のジョンソンは言うまでもなく、ある側面のデリダやそれに触発された数多くの現代の批評も、本書が切り開いていた射程に負っていると言えよう。
前言を翻すようだが、本書の先駆的な達成は──あらゆる古典がそうであるように──みずからの師たちの影響下にあることで、結果的には彼らの名から切り離して扱うことのできる、それ自体独立した価値を獲得するに至っている。かくして本書は、私たちの時代からこそあらためて見出されるべき現代的テクストであり続けるのである。
初出:『週刊読書人』2016年11月4日、第3163号