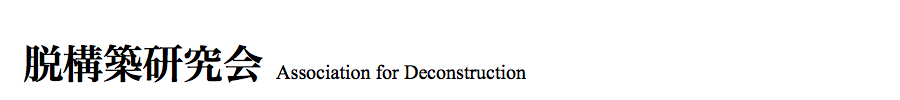Review

コスタス・ドゥージナス編『来たるべきデリダ』藤本一勇監訳、澤里岳史・茂野玲訳(明石書店、2007年)
目次
デリダの追悼文 C・ドゥージナス
1 最小限差異
ジャック・デリダへのオマージュ A・バディウ
差延への回帰の請願(マイナーな「自分の家のために」をともなって) S・ジジェク
2 単独的普遍性
民主主義は何かを意味するのか J・ランシエール
〈普遍的なもの〉の構築と脱構築――ジャック・デリダの感覚的確信 E・バリバール
マッド・デリダ――思考と狂気の事実そのものから J-L・ナンシー
3 他なるもの
ジャック・デリダへの謝辞に向けたノート G・C・スピヴァク
デリダ――未来の贈り物 D・コーネル
レイト・デリダ J・ヒリス・ミラー
監訳者あとがき デリダの幽霊奇譚
松葉祥一
二〇〇五年五・六月、ロンドン大学で行われた、デリダ追悼の連続講演の記録である。本書を特筆すべきものにしているのは、執筆者の顔ぶれである。ナンシー、スピヴァク、ミラーらデリダに「近かった」人々だけでなく、バディウ、ランシエール、バリバールら、むしろデリダとは「遠かった」人々──三人ともパリ高等師範学校でデリダの教えを受けたという意味ではけっして遠くなかったのだが──が、デリダをどのように論じ、評価するか。この期待は裏切られない。彼らは、おざなりな讃辞や弔意を示すのではなく、それぞれの思想の中心点からデリダとの距離を測っている。
かつてデリダを厳しく批判したアラン・バディウは、デリダとの対立点だけでなく近接点をも明らかにしている。対立点は、デリダが哲学の第一の役割を、思考の限界を画定する脱構築に置いたのに対して、バディウの方はドゥルーズ同様、積極的に概念を構築することに置いている点だという。もちろんこの評価に対して、脱構築は肯定だと主張し続けたデリダの側から反論することもできるが、デリダをカントの批判哲学の系譜に位置づけている点は検討に値するだろう。他方、近接点は、自らの哲学を支配的な政治イデオロギーの対岸に定位した点、そして非実在的なものを無とみなさない形而上学的視点であるという。したがってバディウは、政治と形而上学という自らの二つの主要な作業場において、デリダの重要性を認めたことになる。
ジャック・ランシエールもまた、デモクラシーという自らの思考の基点から、デリダとの近さと距たりを計測している。確かにデリダは、現行の統治形態としての自由民主主義と、他者への無限の開けという超越論的地平とを対置し、後者を「来るべきデモクラシー」だとしている。デモクラシーとは、前者から後者に向かうための民衆(デモス)の政治的実践にほかならないと考えるランシエールにとって、このようなデリダのデモクラシー論は政治的実践を等閑視していることになる。しかし他方でデリダが、この開かれたデモクラシーを「他者の無限の尊重」あるいはメシアへの無限の期待という倫理的形式として捉えなかった点、さらにはデモクラシーを国民国家の枠を超えたものとして定義した点では評価されるだろう。デリダが呼びかけるこの「新たなインターナショナル」の内実を形成していくのは、もはやわれわれの役割なのである。
またエティエンヌ・バリバールは、デリダの脱構築が、普遍的なものと特殊なものの対立を解体する試みであると評価する。そしてデリダが、バンヴェニストの人称性についての分析を批判的に検討することによって、「わたし」という人称が特殊性と同時に普遍性を表すというヘーゲルの議論の脱構築的性格を示すに至ったことを、それぞれのテクストに即して実証している。脱構築が普遍的なものの解体であると同時に構築であるというデリダに対するこの評価は、例えばプロレタリアート概念の個別的普遍性について考察してきたバリバールにとっては、非常に大きな意味をもつことがわかる。
もちろん興味深いのはこの三人のテクストだけではない。デリダ・フーコー論争の再検討を通して、デリダにおける狂気の概念の重要性を論証するジャン=リュック・ナンシーや、デリダのフェミニズムへの貢献とその限界を問い直すガヤトリ・スピヴァク、最晩年の講義においてデリダがいかにロビンソン・クルーソーについて物語ったかを明らかにするヒリス・ミラーらのテクストは、スラヴォイ・ジジェクやドゥルシラ・コーネル、さらには監訳者解題によって示される新たなデリダ読解とあいまって、デリダ読解の可能性の豊かな地平を示している。それゆえ、『さらば(アデユー)、デリダ』という原題を、『来るべきデリダ』と訳すことには十分な理由がある。
初出=『読書人』、2687号、2007年5月11日
宮﨑 裕助
デリダが死んで二年半が経った。直後の「追悼騒ぎ」が一通り去って以来、日本では断続的に翻訳が出るにとどまっているが、海外では現在、英語圏を中心として追悼論集や雑誌の特集号が続々と刊行されつつある。そこで発されているのは、死に際した一時的な哀悼の言葉を超えて、デリダが生き思考した時代とは何だったのか、そうして残された思考の遺産と何なのか、私たちはそれをどのように継承し、まさにそこからどのような未来が開かれているのか、といった正面からの問いかけと応答にほかならない。
本書はまさにそのような試みの中心を占めるべき一連の応答からなる論集である。ちょうど二年前にロンドンで行われた連続講演の内容を収めた本書の寄稿者は、バディウ、ジジェク、ランシエール、バリバール、ナンシー、スピヴァク、コーネル、ヒリス・ミラーという豪華な布陣であり、現代思想の第一線で活躍する論客として日本でも彼らの名は知られていよう。本書の特色は、狭義のデリダ研究の論集とは異なり、必ずしもデリダと立場が近いわけではない著名な論者(とくにバディウ、ランシエール、ジジェク)が各々に独自の視点からデリダについての自説を披瀝する貴重な機会をもたらしているという点にある。それだけに本書は、たんなるデリダ論集にはとどまらない射程、すなわちデリダへの応答を機縁としながら、私たちの時代が要請する「思考のアクチュアリティ」そのものを浮かび上らせるような射程をもつのだと言えるだろう。
とはいえ、本書の議論は各者各様、きわめて多岐にわたっている。ここでは全体を通覧することはせず、とくに注目すべき論点を拾い出して整理しておきたい。私の理解では、ジジェクとランシエール、バリバールとナンシーの論文はカップリングさせて読むことができる。
ジジェクによれば、90年代以降のデリダは、ポスト世俗的なメシア主義へと転回した。すなわち後期デリダは、「歴史の終わり」を説く(コジェーヴ゠フクヤマ的な)ヘーゲル主義に反対して、来たるべき「メシア的な正義の約束」を、いわば準カント的な統整的理念として強調することにより、純粋な〈他者〉への応答責任を果たすという倫理的主張に傾斜していくのである。これに対してジジェクは、よりラディカルなヘーゲル主義者として、《あらゆる他者性に先行する》徹底して内在的な「矛盾」、ヘーゲルの用語で「具体的普遍性」と言われるいっそう根本的な「敵対性」を、万人の遍在的な闘争の場として強調する。ジジェクの考えでは、これは初期のデリダが「差延」と呼んで思考しようとしていたものだ。それゆえジジェクは、初期デリダへと立ち返ることで「差延」に秘められた未聞の唯物論的な潜勢力を解き放つよう提案するのである。
ランシエールもまた、デリダのいう「来たるべき民主主義」が、メシア的約束のもとに主張される「他者への無限の開け」という構造をもつ点をめぐってデリダに異議を申し立てている。デリダの注意深い読者ならば、ジジェクやランシエールのこうした「誤解」に対し、デリダのテクストに即して逐一反論を呈したい思いに駆られるだろう。しかしそれでも認めざるをえないのは、後期のデリダが自身の思考を一種の否定的なメシアニズムの構造において語ったがために、こうした誤解がいかに避けがたい可能性として含まれるに至ったかという事実である。誤解の可能性が十分予測しえたにもかかわらず、なぜデリダは「メシア」と言ったのか。後期デリダの「メシアニズムなきメシア的なもの」の問題は、いまだデリダの読者が直面せざるをえない躓きの石であり続けている。
興味深いことに、バリバールとナンシーは、デリダのよき理解者として、そうした問題に答えるためのヒントを与えているようにみえる。バリバールは、模範的な論証の手つきで、ヘーゲル『精神現象学』の感覚的確信の議論を、バンヴェニストの言表理論へと架橋しつつ、自己意識がつねにすでに孕んでいた遂行的矛盾の構造のもとに読み替え、そこからデリダの「新たな感覚的確信」を指摘する。これは、ジジェクの主張に反して、デリダの思考に一貫して通底する「具体的普遍性」の所在を探る議論になっている。また、ジジェクのヘーゲル主義よりもいっそうラディカルにヘーゲル的読解──あまりにヘーゲル的であるためにもはやほとんどヘーゲル的でない読解──をデリダの思考のうちに達成しているのは、ナンシーだろう。ナンシーは、デカルト解釈をめぐるフーコーとデリダの論争を想起しつつ、デリダがいかに自己意識としての理性(デカルト的コギト)のなかに理性そのものの狂気を読み取ってきたのか、と同時に、それをいかにデリダが自身のテクストのうちに実行してきたのか、といった議論を驚くべき思弁的強度において練り上げている。そしてこの「理性の狂気」が、自己愛の底を踏み破るような「愛の狂気」としていかにデリダの思考を突き動かしてきたのかをナンシーは明らかにするのである。
最後に特筆すべきは、バディウによるデリダへのオマージュだ。デリダが逝ったいま、一種の精神的庇護をもたらしていた「哲学的60年代」の世代は皆この世を去ってしまった。そう述べるバディウは、もはや「私こそ老いた人間である」と吐露しながら、かつては敵対関係にあった上の世代の哲学者全員に留保なしの敬意を表明する。そこから、デリダの「大いなる思索的な優しさ」「思考の女性的な繊細さ」を「触れること」のモチーフに即してたどってみせるバディウのオマージュは、戦後フランス思想の「電光のように閃いた」時代の貴重な証言となっており、本書の最も感動的な部分をなしている。
本書はけっして回顧や総括の書ではない。バディウの言葉を借りれば、デリダという名をもちえた哲学的創造の瞬間は「いまだ我々の先にある」。それは「混乱に満ちた我々の時代において進むべき道を照らす光」なのであり、かくして本書『来たるべきデリダ』は、その題にふさわしく、私たちの未来にむけてまさにこの「光」を増幅する反射鏡のような役割を果たすのである。
なお、本書は英語の原著に先駆けて日本語で出版された。加えて本書には、日本語版独自の題名や章立て、豊富で丁寧な訳註等、読者の理解を助けるさまざまな工夫が凝らされている。本書を企画した編集者・訳者諸氏の慧眼と見事な連携を付記しておきたい。
初出:「コスタス・ドゥージナス編『来たるべきデリダ』藤本一勇監訳(明石書店、2007年)書評」『図書新聞』2007年6月30日、2827号。