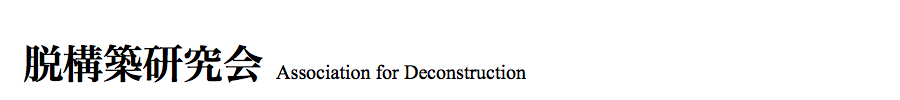Review

亀井 大輔『デリダ 歴史の思考』法政大学出版局
評者:宮﨑 裕助(新潟大学准教授)
20世紀後半を生きた哲学者ジャック・デリダにとって「歴史」が大きなテーマであり続けたことはこれまでもそれなりに知られていた。デリダといえば、脱構築という鍵語を最初に思い浮かべる人も少なくないだろう。しかし、なにをどこからどこまで脱構築するのか、そもそも脱構築すべきなのか、脱構築してどうするのか、といった一見当然にもみえる疑問に対して、脱構築の論理や方法をいくら知ってみたところで、脱構築の形式自体がその答えを教えてくれるわけではない。脱構築が介入するのは個々の具体的文脈、コンテクストであり、そこに関与する者に歴史への応答責任の感覚がなければ、脱構築はまったく効果を発揮しようもないのである。
本書は、まさにそうした歴史の思考が立ち上がってくる問題圏を、デリダ自身の著作を追跡しつつ、とりわけ六〇年代の著作を中心として描いてみせたものである。主題そのものは決して目新しくはないにもかかわらず、本書の企てが明確に際立ったものとなっているのは、まずもって現代のデリダ研究の要求に応えようとしている点にある。
とりわけ一九九〇年に三百頁に近い修士論文が公刊されて以来のデリダのフッサール論をめぐる先行研究、また二〇〇八年から始まったデリダの講義録の刊行、とくに二〇一三年に出たハイデガー講義、さらに研究者向けに整備された草稿アーカイヴ、それらを駆使した伝記等の文献学的研究など、ここ十年ほどで生じた研究状況の大きな変化がある程度踏まえられている。
なにより本書の利点は、ともすると遺稿著作や先行研究の山に押し潰されがちな現代のデリダ研究としては例外的なまでに明快であり、一貫して読みやすいという点である。これは、デリダ自身のテクストへの異様なこだわりと、その日本語訳がしばしば増幅する、デリダの読みにくさを知っている者からすれば、いくら強調してもし足りない長所である。
デリダの最初の公刊著作は、一九六二年のフッサール『幾何学の起源』翻訳とそれに付した長大な論考であった。本書がもっとも丁寧に論じているのはこのフッサール論である。デリダが明らかにしている論点のひとつは、フッサールの議論の核心には歴史主義批判があるということ、それがひとつの超越論的歴史性の探究となっているということである。
本書がデリダの「歴史の思考」の出発点を見いだすのは、フッサールのこの超越論的歴史性の概念である。さらに六四/六五年のハイデガー講義では、デリダが『存在と時間』の読解を「時間性と歴史性」の章から企てていることが重要である。つまり、初期デリダの思考は、フッサールとハイデガーから歴史主義批判のモティーフを継承したのであり、そこから、歴史の可能性の条件として超越論的な歴史性を問うこと、さらにはその不可能性の条件として「超‐超越論的歴史性」の名のもとに歴史の臨界点を探ろうとすること、このことが、本書全体を導くデリダの「歴史の思考」の枠組みをもたらすのである。
こうした歴史主義批判が、脱構築のひとつの雛型を与えている。しかし問題は、脱構築がたんに否定的で破壊的な企てでないとしたら、いかにして積極的な意味をもちうるのかということである。要するに、脱構築はいかに歴史に応答すべく当の歴史を書くにいたるのだろうか。
本書が触れているように、デリダとフーコーの有名な論争もおそらく最終的にはその点にかかわっている。フーコーはデリダにこう問い質すだろう。君は私の数百頁の歴史書の三頁を占めるにすぎないデカルト解釈を批判しているようだが、君自身はどんな歴史を書くつもりなのか、と。
そのような問いかけを念頭に本書を読めば、デリダの「歴史の思考」が、既存の歴史観に抗して試みられた恐るべき格闘の軌跡であったことが見えてくるにちがいない。本書が提起している重要な論点のひとつは、レヴィナスへの応答を通じてデリダが目的論と終末論とを明確に区別し、メシアニズムなきメシア的終末論ともいうべき歴史像を構想しているという点である。
そうした試みを本書がデリダに即してどこまで追究できたと言えるのかは評価の分かれる点だろう。しかし本書は、デリダにとって「歴史の思考」がもつ重要性を解明するには十分である。真正面からデリダの思考の核心に切り込んだ研究書の登場を歓迎したい。