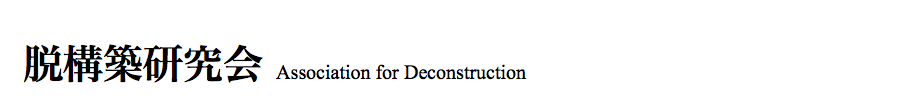Review
 _
_
ジャン=リュック・ナンシー+ジャン=クリストフ・バイイ『共出現』大西雅一郎+松下彩子訳、松籟社、2002年
ジャン=リュック・ナンシー+フィリップ・ラクー=ラバルト『ナチ神話』守中高明訳、松籟社、2002年
松葉祥一
コミュニズムの「崩壊」と湾岸戦争によって印づけられる一九九一年に出版されたこの二冊の共著で、ナンシーが問うのは共同体の問題である。このテーマは、『無為の共同体』(1986)〔以文社、二〇〇一年〕以来、『共同-体』(1992)〔松籟社、一九九六年〕や『複数的単独存在』(1996)を経て、『対向的共同体』(2001)(『共出現』の訳者後書きが、同書の要点を整理してくれている)に至るまで、一貫してナンシーの問題圏の中心にあった。しかし、ナンシーが目指すのは、けっして共同体の「復権」ではない。
(『共出現』、『ナチ神話』とも、かつて『批評空間』に訳出されたテクストが主体になっているが、大幅に手が加えられている。とくに『共出現』には、ナンシーの希望で「民主主義の様々な意味」、「ユートピアの場に/代わりに」、「すべては政治的なのか」の三論文が加えられている。二〇〇〇年前後に書かれたこの三つのテクストは、最近のナンシーの民主主義論-存在論-キリスト教の脱構築を理解する上で重要な位置を占める)。
神話的同一化
なぜなら共同体は、それが目的となるとき排除の閉域と化すからである。この過程を明らかにしたのが『ナチ神話』である。
『ナチ神話』のテーマは、いかにしてナチ神話が形成されたかを理解すること、そしてなぜ全体主義のドイツ的形象が人種主義であったのかを理解することである。そこで問題になるのが「神話的同一化」の過程である。すなわち、歴史的・地政学的状況のなかで自己同一性の欠如に苦しんでいたドイツ的思考が、古代神話モデルをフランスから奪い取るだけでなく、「発明」さえすることによって固有性を確立しようとした。そしてこの象徴的同一化を国家規模で、しかも政治的に実現したのがナチズムにほかならない。また、ローゼンベルクの『二〇世紀の神話』やヒットラーの『わが闘争』の分析を通じて明らかにされるのは、こうした神話的同一化が政治的なものにおける何らかの形象──ヴォーダンやアーリア神話における太陽神──に結びついていることである。そして、こうした神話的同一化と形象化作用が結びつくとき、形象をもたないものを排除する人種主義が可能となる。
しかし、本書でナチ神話が審問に付されるのは、歴史の問題としてではない。それが問題になるのは、現在、「東京からワシントン、テヘランからモスクワにいたるあらゆる種類の原理主義やナショナリズムや純粋主義」、極右勢力の勃興、歴史修正主義の復活などがたどりつつある神話的同一化の過程を明らかにするためである。これらが、新たな神話、あるいは神話的意識の必要性、古い神話の再活性化に訴えていることは容易に見て取れる。そしてナンシーは、こうした動きの中に共同体の形象化を見る。すなわち、こうした時代の空気のなかには、「何か共同体の存在ないし運命の表象のようなもの、形象化、それどころか血肉化のようなものへの密かな要求あるいは期待」が存在しており、さらには「この共同体という名そのものが、それだけで、すでにそような欲望を目覚めさせるように思われる」と指摘するのである。
主体と共同体
そして、このような共同体概念は主体概念と相補的関係にある。ナンシーは、「ナチ・イデオロギーがその真の保証人を見出すのは、近代哲学ないし完成された<主体>の形而上学において」であり、「主体というイデオロギーこそがファシズム」であると述べると同時に、「共同体とは、実際のところ、想像上の同一の個人ないし主体の肥大化であった」と述べている。
この相補的関係は、近代を「共同体解体」の過程と見る視点に起源をもつ。ルソーに一つの淵源をもつこの観点によれば、近代の共同体の解体は、二つの帰結を生んだ。一方は、主権をもつ自由な市民が誕生したことであり、他方は共同体への郷愁が生まれたことである。そして、第一の帰結を重視する立場は、主体概念と結びついて自由主義へと発展し、第二の帰結を重視する立場は共同体主義へと引き継がれることになる。そして、近代はこの二つの立場の相克の歴史、したがって相補的な歴史だったとされるのである。
ナンシーによれば、このように近代を「共同体解体」の過程であるとする視点は、共同体をとらえ損なっているだけでなく、主体と共同体を切り離して、いずれをより根源的とするかとする点で誤っている。すなわち、ナンシーは、アリストテレスの「ポリス的動物」という定義に象徴される共同体が主体に先立つとする立場も、社会契約説に代表される主体が共同体に先立つとする立場も、同時に否定するのである。両者とも、主体と共同体を切り離す点で変わりがない。その上で、共同体を分解することによって主体を導き出すか、主体を融合したり弁証法的に綜合したりすることによって共同体を導き出すかという点で異なるだけである。(ナンシーにおける主体と共同体については拙論参照。「存在論としてのコミュニズム──J-L・ナンシーの共同体論」、『現代思想』、一九九八年一〇月)。
したがってナンシーは、あらゆる共同体-主体主義、したがってあらゆるルソー主義を拒絶する。それは目的としての共同体の拒否であると同時に、近代は共同体の抑圧から主体を解放する過程であり、共同体主義の残滓であるコミュニズムを克服することによって、主体の自由がすべてに優先するリベラリズムが決定的に勝利を収めることになったという物語の拒否でもある。
共出現=出頭
しかしそれにもかかわらず、ナンシーが「おそらく、私たちは共同体なるものそれ自体を喪失したわけではない」と述べるのは、何よりも「絶対的な不正義という硬質な破片が残る」からである。「餓死寸前の身体、拷問を受けた身体、砕かれた意志、虚ろな眼差し、戦争による死体の山、蹂躙され踏みにじられた生活状況、そして郊外での孤独、出稼ぎ労働者の当て所のない状態、また若者や老人の不安、狡猾に剥奪される存在、殺人、愚劣な文句のなぐり書き、これらは現に存在する」。そして、排他的共同体に支えられたリベラリズムがこうした不正義を生み出すとき、ナンシーは「様々な特異なるものの複数性と共同的実存に正義を与え返すこと」が何よりも必要だと主張するのである。
ではナンシーの考える共同体はどのようなものか。それは、「共-に-あること」そのものである。それをナンシーは、共出現=出頭(コンパリユシオン)と呼ぶ。この語は、「世界という法廷の前に出頭する」ことと同時に、われわれが共出現すること、つまり共に世界に到来する=誕生することを意味する。それは、他と区別される複数の実体的存在が同時に産出されるということではない。むしろ、根源的に共同でないような存在はない以上、世界へ到来=誕生することと「共-に-あること」は等しいのである。
そしてナンシーは、このような共同体の可能性を、分割=共有(パルタージユ)と呼ぶ働きのうちに求める。それは、存在者を分割すると同時に、それらの「共-に-あること」、あるいは世界への出頭-共出現を可能にする根源的な差異化の働きである。したがって問題は、新たに共同体を創設したり、ましてや復興したりすることではけっしてない。なぜなら、それは、「われわれの一切の企てや意志や企図のはるか手前に」あるからである。問題は、共同体の亡霊と主体の形而上学をともに拒否しつつ、絶えず来るべき「共同体」の可能性を探ることである。
こうした共同体の問題は、ナンシーが言うようにキリスト教と結びついた西欧固有の問題であることも確かだ。しかし、一方で教育現場での日の丸・君が代の強制が公然とまた陰湿な形で浸透し(岐阜県を始め各地の教員採用試験で、例えば「国歌を歌わない児童に対してあなたはどのように対処しますか」という質問が行われているという)、建国神話から始まる歴史教科書が愛媛県立中学校で採用された現在、共同体とその「形象」への同一化は現実の問題である。また他方で、狭義のグローバリゼーションという名のネオ・リベラリズムの強制によって戦争と貧困化が加速しつつある現在、ナンシーの示す共同体の可能性を思考することはわれわれにとっての義務でもある。ただ、こうした共同体が考えにくいことも確かだ。なぜならそれは、直観による充足をあらかじめ欠いているからである。しかし、ここでもまた「思考不可能なるものこそが思考されねばならない」のであり、「不可能なるものこそがその法=権利を要請している」のである。
初出=『図書新聞』、2002年8月