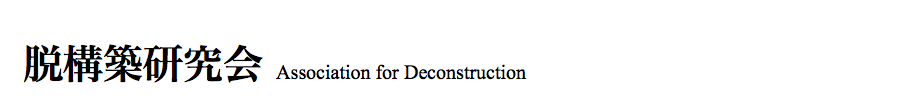Review

ジャン=リュック・ナンシー『世界の創造 あるいは世界化』(大西雅一郎・松下彩子・吉田はるみ訳、現代企画室、2003年)
西山雄二
〈目次〉
都にそして世界に
創造について
脱自然化としての創造―形而上学的テクノロジ
補遺(「生命政治」という用語についてのノート;無カラノ至高(Ex nihilo summum)至高性について コスモスこそ王)
本書は哲学者ジャン=リュック・ナンシーが初めてグローバル化の現状を踏まえながら世界概念を論究した著作である。九九―二〇〇一年に執筆された彼のアクチャルな政治論考が、三人の訳者の的確な翻訳によっていち早く私たちの元に届けられたことに感謝したい。
ナンシーのいう「世界化(モンディアリザシオン)」は、ここ数年来新自由主義的な技術革新や経済発展とともに加速するグローバル化だけに限定されない。それは、より広義な意味で、ギリシアにおける哲学の誕生が刻印され、ユダヤ―キリスト的一神教を基にし、資本主義を起動・発展させた西洋の拡大過程そのもの、西洋の世界化のことである。資本主義の運動に関して言えば、その経済体制は剰余価値の過剰を自らの根拠としながら、投資・搾取・再投資の無限循環を繰り返し、資本蓄積を増大させ続けている。ヘーゲル的に「悪無限」と呼称しうるこの運動、自らを根拠づけ、自らの前に目的を設定し続ける自己再生産のプロセスに彼はグローバル化の実相をみる。
こうした技術的・経済的な含意の強い「世界化」を別様に思考するために、ナンシーは見たところ一神教の負荷を帯びた「世界の創造」を論究する。この場合、「世界」とは、神や真理といった超越的および外在的価値を欠いた、徹底して内在的な「この世界」のことである。世界全体を俯瞰する神は消え去り、存在神論の神は単一の世界像を表象することを止めた。いかなる所与ももたない有限なる存在者からなる「この世界」、すなわち「理由=根拠もなく、目的=終焉もないひとつの事実」であるような「この世界」が残された、というのが彼の見立てである。だとすれば、創造とは超越的な神の手による世界創造のことではなく、この世界が製作者・設計者も、あらゆる所与による根拠づけももたないためにその都度、無から創造され続けるという「われわれ実存者」の絶対的な事実性を意味する。「世界はある何かとして成長する無から創造される」。有限な実存者が根拠なき根拠たる無というものに触れることによって新たな世界の創造が開示される。ナンシーは世界を成長させ、創造するこの「現動化する無限」に資本主義とは異なる世界像を見い出すのである(この「無というもの」を考慮する点で「世界化」概念はネグリ+ハートの「帝国」と袂を分かつ)。
有限な実存者が自らの限界へと露呈され、隣接したその無限=無という何かを互いに分かち合う存在様態――これはナンシーがかねてから「分割=共有(パルタージュ)と呼んでいるものだが、本書における彼の理論的変節は、この思考実践がキリスト教的一神教の文脈へと批判的に接合され、さらにグローバル化の運動へと接続されている点にある。ちなみにナンシーは、本書が執筆されたのと同じ時期に、あるインタヴューで「共同的なものの存在論は直接的には政治的ではない」と自己批判している。そして実際、彼は近年、政治的なものの問いへの別の行論として美術やキリスト教の問題系に本格的に取り組んできた。本書でも、ナンシーは「分割=共有」概念をもとにして、いかにして「共同性=共同体(コミュノテ)は創造されるのか、いかにして共同性に正義が送り返されるのか、といったより多層的な問題設定をおこない、「共同体」と「政治的なもの」および「世界」についての理論的広がりを模索しているようにみえる。
「無からの創造」の分析はさらに、「至高性=主権」の問い直しと通底する。「その上に何ももたない者」である至高性とは絶対的な頂点、上昇の運動そのものである。上方と下方という区別さえ問題とならないこの「いと高き者」は、その高さに眩暈さえ感じながら、自分で自分をつねに根拠づけるしかないような自己関係である。だが、自己以外の何ものにも依存しない以上、バタイユが言うように「至高性とは無である」。至高性とは自己の自己に対する関係の間隙に介入するこの無のことであり、それゆえ、至高性は至高者に自己固有化されることなく、そこから逃れ去るのである。ナンシーは至高性の位相に取って代わるものを「民衆」という表現で仄めかして確答を留保しているが、現実的に、グローバル化の進展がアメリカという至高性の無際限なそれと合致する現在、至高性の(無)根拠を問い直すことは私たちにとって焦眉の問いである。
圧倒的な規模と速度で生生発展するグローバル化に一個人が抵抗することは難しい。だからこそ、この「共同体」の哲学者の著作のなかに、「もうひとつの世界を求める人々(アルテルモンディアリスト)」の実効的な連帯の可能性を見い出したいという思いに駆られもする。しかし、本書では、現下の世界状況に対抗する即効的な方途が縷説されているわけではなく、むしろ徹底して哲学的な調子で原理的な考察が進められる。かつて「主体の後に誰が来るのか?」と問題提起したことのあるナンシーである、その著作から現実的な抵抗「主体」を措定する契機を読み取とうとすることは筋違いであるし、彼のいう「分割=共有」は現実的なあらゆる主体の手前に位置するような存在様態である。だがそうであればこそ、彼の「分割=共有」概念を参照軸としつつ、グローバル化のなかで来るべき共同性を実践的に思考する務めは、まさしく私たちに課せられているのである。(『図書新聞』2004年2月21日号)