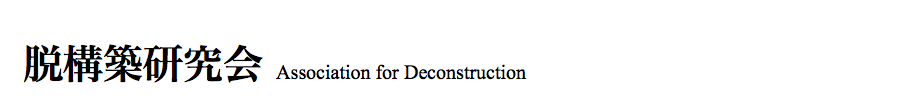Review

ジャン=リュック・ナンシー『限りある思考』(合田正人訳、法政大学出版局、2011年)
西山雄二
〈目次〉
終わる思考
外 記
犠牲にしえないもの
実存の決断
崇高な捧げ物
物々の心臓
粉々の愛/輝く愛
省略的意味
笑い、現前
魂と身体のうちに真理を所有すること
神の進行性麻痺
一九九〇年に刊行された本書は、八九年の歴史的な節目の後で、歴史や世界、国民、主体といった近代的な「意味」が根本的に衰弱し漂流し始めたという時代経験のなかで執筆された。こうした西洋的な意味が破綻するとともに、その思考もまた終焉を迎え、新たな配置を求めている。意味そのものが終わりうるという有限性を引き受ける思考を。完成や成就といった一切の目的論的で終局的な意味とは縁を切った、有限性の思考を。
ナンシーは思考の終末論的ニヒリズムに陥っているわけではない。逆に、そもそも有限な存在者(実存)が限界(誕生と死)へと自己を曝け出し、無限に触れる地点に即して、思考が継続させるのだ。例えば、バタイユの「供犠」をめぐって、有限な自己の否定によって無限な真理が固有化される限界が検討され、ハイデガーの「決断」をめぐって、有限な実存が自らを思考の開けとなす限界が検討される。確立され基礎づけられた意味の全体性を前提としないで、意味のそのつどの到来へと実存が己を曝け出すために、いかに「新たな超越論的感性論」を構想すればいいのか。ナンシーの筆致は、喪失や欠如へのノスタルジアを感じさせない前進性に満ちている。
ナンシーの見方は、「大きな物語が終わり、個々の実存の小さな物語が散在するだけだ」というポストモダン風の定式とは異なる。私たちは意味の限界の屈折に際しているのであり、「大きな物語」から最終的に解き放たれたわけではない。個々の実存による有限な思考は、十全な意味づけを欠いているがゆえに、歴史の出来事によってそのつど不意を突かれる過程にとどまるのだ。
ナンシーは大胆にも、「意味」「実存」「技術」「供犠」「決断」「愛」「崇高」といった、哲学的伝統の負荷を負った諸概念に楔を打ち込む。その堅固さゆえか、「意味とは自己への連関の開け=始まりである」「真の実存は犠牲にしえない」「思考は物々の心臓にある。ところがこの心臓は動かない」などと文章は断定的で硬質だ。この果敢さはナンシー哲学のスタイルの魅力で、かつて朋友デリダが「蠅取り紙に敢えて突進する蠅のような行為で、自分には真似できない」と当人に語ったほどだ。ただ同時に、バタイユ、ハイデガー、デリダのテクストが集中的に読解され、縦横無尽にさまざまな引用が散りばめられるナンシーの文章は精緻さと柔軟さも兼ね備えている。
ナンシー哲学の特質は、哲学的概念の岩盤の適切な地点を探り当て、異質な次元のあいだで亀裂を生じさせる点にある。もはや言語が通用しない亀裂を指し示す文章表現(エクリチュール)は、バタイユとランボーが主に参照されながら、「外記(excrit)」と表現される。
例えば、「愛」は欠如による欲望の成就でもなく、二者の情感的合一でもなく、経済と非経済の単純な対立を挫くとされる。愛は贈与と所有の対立を終わらせ、その裂け目とともに愛する者を構成し、その自己への回帰をもたらす。愛する者同士のあいだで愛は粉々に輝き、この分有によってこそ二者は惹かれ合う。
また、「意味」はフランス語sens(意味=感官)の二重性に即して再検討される。意味とは概念と指示対象が混じり合った絶対的な自己把持である。石の観念が外的現実の石と関係を結ぶときに意味が作用するように。他方で、意味には「感性的」な特質があり、意味を感覚する、感覚することを理解する、といった自己感情をともなう。知性的なものと感性的なものの解消されない区別において、「意味」が位置づけ直される。
une pensée finieは書名では「限りある思考」、本文中では「有限な思考」「終わる思考」と適宜訳し分けられているが、その必然性はさほど感じられなかった。本書には訳註は付されていないが、ナンシー独特の表現の訳し方や日本語訳書の該当箇所については、最低限の訳註を入れた方が読者には有益だっただろう。(『週刊読書人』2011年3月25日号・2882号)