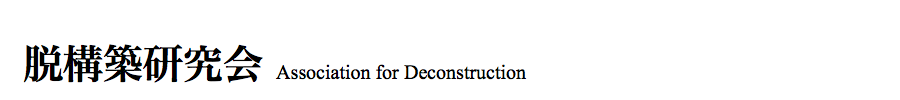Review

主権の問い、暴力の問い
(ジャック・デリダ&エリザベート・ルディネスコ『来たるべき世界のために』藤本一勇・金澤忠信訳、岩波書店、2003年)
守中高明
ジャック・デリダの最新対談集『来たるべき世界のために』が刊行される(藤本一勇・金澤忠信訳、岩波書店)。大著『ジャック・ラカン伝』(藤野邦夫訳、河出書房新社)によって名高い女性精神分析家-歴史家エリザベート・ルディネスコを相手に、理論的問題のみならず、現在進行形の社会-文化-政治的諸問題(「ポリティカル・コレクトネス」、「混乱する家族」の像、「人間性/動物性」の問い、「ショアー」とイスラエル問題、「死刑廃止論」等々)を縦横に論じるこの本は、その意図された平明さと、にもかかわらず損われないその厳密さによって、読む者を引き込むだろう。
この国におけるデリダの受容は、この二十年ほどのあいだに、大きく変化し深まりを見せた。西洋形而上学の伝統を支えている諸概念の階層秩序的二項対立を再-刻印し、その対立を可能にしている地盤そのものを転位させ、掘り崩すこと――『声と現象』(一九六七年)や『グラマトロジーについて』(同)以来のデリダの戦略をそのように要約することはたしかに間違いとは言えないし、事実、七〇年代後半から八〇年代初めにかけて、とりわけアメリカ合州国において、そして日本においても、デリダの思考はそのように形式化されることで浸透し、定着したとも言える。だが、その場合、哲学のテクストを問題化すると同時に文学のテクストをも相手取るデリダは、形式化可能な一つの戦略を複数のジャンルにおいて実行し、いわばどのテクスト-コンテクストにおいても、その歴史的意味を問わず、破壊的ではあるが価値中立的な効果を残すだけの読解者だと見なされてもいただろう。
むろん、このような見方は検討に耐えない。そもそも概念の作業とメタファーの作業という二項対立こそ、デリダが切り開く「エクリチュール」ないし「原-エクリチュール」の場面において、まっさきに失効するのであり、そのことは、たとえば『散種』(一九七二年)におけるプラトン論とソレルス論を同時に読む視線にとってすでに明らかなことであった。にもかかわらず、八〇年代初めの時点においては、デリダの試みはなお、哲学と文学との境界線を曖昧にしつつ行なわれる、精緻で大胆だが結局のところ美学的なテクスト実践として理解されかねなかった。『弔鐘』(一九七四年)から『郵便葉書』(一九八〇年)に至るデリダのテクストは、ヘーゲルやフロイトおよびラカンの思考とのかつてない強度と緊張をともなった対決であり、その形而上学(の残滓)の転覆の企てであったわけだが、そこに書き込まれた自伝的要素とその全般化された「パフォーマティヴ」な形式のゆえに、それらをその政治的効果と含意において読む視線は、ごく限られていたのである。
この構図に顕著な変化がもたらされたのは、八〇年代半ば以降である。「ハイデガー論争」の直前に発表された『精神について』(一九八七年)を一つの明確な分水嶺として、デリダの思考は、みずからの位置する歴史的文脈をいっそう積極的に意識化し、直接的に問題化するようになる。「倫理的-政治的転回」と呼ばれもするこの変化は、デリダの像を、「テクストの戯れ」の思想家から、アクチュアルな倫理的-政治的諸問題に介入する最も深い「アンガージュマン」の思想家に転換させた。そしてこの傾斜は、八九年/九一年の世界史の激動以後、『他の岬』(一九九一年)、『マルクスの亡霊たち』(一九九三年)、『法の力』(一九九四年)、『友愛のポリティクス』(同)などを通して、加速度的に強まっていくことになるが、しかし、繰り返せば、それが何であれテクストの政治的含意についてデリダが無自覚であったことはかつて一度もなく、そのことは、たとえば『余白――哲学の/について』(一九七二年)所収の「人間の目的=終末」を読むだけで確認できるだろう。一九六八年五月十二日の日付を持ち、同年十月にニューヨークで発表されたこの講演を、デリダは、「どんな哲学的コロキウムも必然的に政治的意味作用を持つ」と宣言することから始めており、その冒頭部分は、哲学的言説の本質主義的幻想を批判しつつ、哲学の「ナショナリティ」による非-同一性を、そして「国際的な哲学コロキウムの可能性を民主主義の形式に結びつけているもの」を「指摘」する言葉からなっている(そこではヴェトナム和平交渉と、マーティン・ルーサー・キングの暗殺が必然的に呼び起こされている)。デリダにとって、一つの哲学的言説とは、どこでもよい場所から誰でもよい相手にむけて発せられる抽象的なものではいささかもないのである。
だがそれでは、この度の対談の中枢はどこか。デリダはどのような場所を作り、誰に宛てて語りかけようとしているのか。
国家主権を制限すること――おそらく、他者の名において、「私」の名のもとには決して同定されない存在によって。デリダの今日の思考の中心には、おそらくこの賭札があり、さまざまな問題系はその周囲を旋回しているだろう。
第一に、「歓待」の思考を練りあげてきたデリダがいる。「グローバル化」と呼ばれる世界の一元化の運動の影で、かつてない規模で移民が、「不法滞在者」が問題としてあぶり出され、排外主義的思考がそれぞれの国民国家において顕在化してくるとき、この事態への抵抗はいかにしてなされるべきか。『歓待について』(一九九七年)をはじめとするいくつものテクストにおいて、デリダは、「異邦人の問い」に取り組むことの緊急性を語っている。だが、デリダの言う「歓待」とは、すでに確立した主権が「異邦人」を迎え入れる権能のことではない。そうではなく、この「歓待」が前提とするのは、反対に、あらゆる自己性に先立つ他者の侵入についての知、すなわち、私がつねにすでに他者に対して開かれており、したがって自己を閉ざすこともこの「最初の開かれへの反動」であるという認識である。それは、たんなる寛容とは異なる。「真正な歓待が開かれる」のは、自己の能力によるのではなく、むしろ「わが家という場の解体」から発してなのである。「到来者にはウィ(oui)と言おうではありませんか、あらゆる限定以前に、あらゆる先取り以前に、あらゆる同定以前に」――ここには、カントの『永遠平和のために』の「第三確定条項」(「世界市民法は、普遍的歓待を促す諸条件によって制限されるべきである」)を再定位しつつ、さらに無条件な歓待へと国家主権を開こうとする思考の賭けがある。
ついで――だが目的論的順序の外で――、「死刑廃止」に哲学的根拠を与えようとするデリダがいる。今日、「死刑廃止」は世界的な流れであり、この制度の存置国は確実に減りつつあるとはいえ、日本を含む多くの国がいまだに、国家主権によるこの「合法的な殺人」手段を手放そうとしていない。そして、死刑廃止論もまた、その決定的な論拠を、いくつかのテクノロジーによって空転させられているかのようにも見える。その典型が、死刑の「残酷性」であるだろう。死刑は、その「残酷性」のために、たとえばアメリカ合州国においても一九七二年には憲法違反とされ、廃止にむかうかに思われた。しかし、合州国は一九七七年に死刑を復活させる。麻酔による安楽死という「技術革新」によって、その「残酷性」が解消されたからというわけだ。しかし、このような論点こそは、「人道的な処刑」という擬似論理とともに、デリダによる脱構築の対象となるだろう。あるいは、罪と罰とのあいだの不可能な等価性についてはどうか。死刑制度を支えている思考の一つは、「タリオの刑法」以来の、罪の「計算可能性」の思考であり、負債の価値評定の、したがって罪と罰との共約可能性への幻想である。だが、罪の償いは、はたしてそのようなエコノミーにおいて果たされるものか。すでにデリダは、「赦し」の問題系において、「無条件の、非エコノミー的な、交換を超えた、贖罪や和解の地平さえ越えた赦しへの参照を維持する必要性」を説いていた(「世紀と赦し」)。「和解のセラピー」には属さないというこの「純粋で無条件」な「赦し」を語るとき、デリダはなにも「精神的潔癖主義」の名においてそうしているわけではない。「どんな「意味」も、どんな「合目的性」も、どんな理解可能性さえ、持ってはならない」という、この「狂気」に似た「赦し」を語るとき、デリダが指し示しているのは、ここでもまた主権の外部である――「その名にふさわしい赦しの「純粋性」として私が思考しようとしているもの、それは権力なき、無条件だが主権なき赦しだということになるでしょう」。
だとすれば、デリダによる死刑廃止論はどうなるのか。その細部はこれから聞き取らねばならないにしても、それが、「死刑」の本質は違法に対する罰にではなく、「新たな法の確定」と「法」の「強化」にあると断言した、ベンヤミン的な意味における「暴力批判論」の今日的展開でもあることは間違いない。
……私は歓待の場所を開く、無条件で、今-ここに。私は死刑を廃止する、絶対的に、あらゆる主権を超えて――おそらくこれが、デリダが現在立っている地点である。困難な場所だ。しかし、その場所からの語りかけを聞くとき、すなわち、困難なその宛先の位置を選び取るとき、私たちの一人ひとりが、来たるべき民主主義の確かな声を分かち持つことになるだろう。
初出=『図書』第645号(岩波書店、2003年1月)