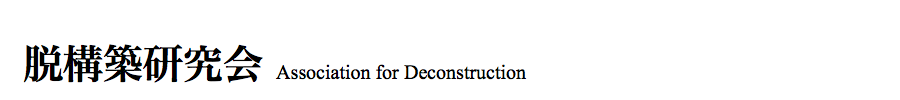Review

ジャック・デリダ『アデュー──エマニュエル・レヴィナスへ』藤本一勇訳、岩波書店、2004年
松葉祥一
本書は、一九九五年一二月、デリダがパンタン墓地で読み上げたレヴィナスへの弔辞と、翌年一二月に開かれたレヴィナス・シンポジウムでの開会講演「迎え入れの言葉」からなる。
書名にアデューという言葉が選ばれたのは、もちろんレヴィナスへの告別の辞としてである。「ずいぶん長いあいだ、かくも長いあいだ、私はエマニュエル・レヴィナスにアデューと言わねばならないのではないかと恐れていました」という一節で始まる本書は、友の死に捧げられた数多くのデリダのテクスト(『その度毎に唯一の、世界の終わり』、ガリレイ社、二〇〇一年参照)のなかでも、最も哀惜の念に満ちたものの一つだろう。
しかし、このタイトルが選ばれたのは、むしろデリダがこの概念をレヴィナス哲学の可能性の中心だと見なしているからである。アデューは、永遠の別れを意味するだけでなく、出会いの挨拶でもあり、したがってすべてに先立つ他者の受け入れを意味する。さらにそれは、まったく見知らぬ他者ですら「神(デユー)の許にある」ことを意味する。それゆえレヴィナスにおけるアデューとは、私と絶対的他者との関係を創設する倫理的出来事なのである。
デリダは、この絶対的他者の「迎え入れ」、「歓待」の倫理を、レヴィナスのテクストにそって明らかにしていく。しかし、レヴィナス思想の称揚に終始するわけではない。むしろその両義性を明らかにすることによって、思想的遺産の相続という責任を果たそうとするのである。すなわち、歓待がつねに主人と客にという二つの側面をもつものでありながら、つねに他者のイニシアティヴが先行することの意味。歓待概念の女性性とレヴィナスの男性中心主義の両義性。レヴィナスの後期思想における第三者あるいは正義の問題。
そしてデリダの記述は、歓待概念の内在的分析を超えて、「政治的な」問題に移行する。それは移民の問題であり、またとくに本書の焦点である平和の問題である。
平和とは戦争のない状態なのか。少なくとも『永遠平和のために』のカントはそうだと考えた。それゆえ平和を実現するためには、政治によって戦争を中断することが必要になる。すなわち、「自然状態としての戦争状態」を断ち切って永遠平和を実現するためには、世界市民法や普遍的歓待などの制度化が必要だということになる。
それに対してレヴィナスは、平和とは、「政治的な思考をはみ出す概念」だと考える。彼にとって平和とは、政治的次元に先行する倫理的次元における他者との関係である。それは、「我を殺すな」と命じる他者を「受け入れる」ことによって成立する倫理的関係である。したがってそれは、たんに戦争のない状態ではなく、政治によって設立される「平和」やさらには戦争の基盤でさえある。それゆえ、戦争を前提にしてその不在を平和だと定義すれば、政治の介入なしに平和を実現することは不可能だということになるが、このように平和を他者との倫理的関係だと定義する場合、平和を実現するためには、むしろ政治を断ち切って、倫理的次元に立ち返ることが問題になるであろう。
ただここでもデリダは留保をつける。倫理的次元に依拠すれば、自らを範例とすることによって絶対化する普遍主義に陥る危険がある。例えばレヴィナスが、シオニズムはナショナリズムを越えた倫理的立場だと主張するとき、デリダはそれに与しない。
われわれが、レヴィナスのそしてデリダの遺産を相続するために必要なことは、この歓待の倫理と倫理的平和の可能性を考え抜くことであろう。とりわけ「正しい戦争」が復権し、「戦争ができる普通の国家」の実現が目前に迫っている現在、何よりもまず必要なことは、この政治次元から「殺すな」という倫理的次元への「倫理的転回」なのである。
初出=『週刊読書人』、2577号、2005年3月4日)