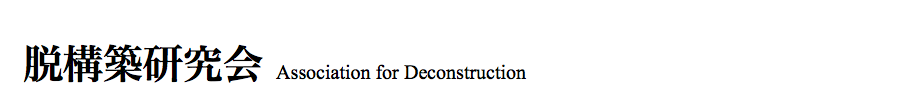Review

ジャック・デリダ『アポリア──死す──「真理の緒限界」を[で/相]待-期する』、港道隆訳、人文書院、2000年
松葉祥一
本書は、一九九二年夏、フランスのスリジー・ラ・サールで開かれた国際コロック「諸境界の通過──デリダの仕事をめぐって」における、講演の訳である。この豊かなテクストを暴力的に単純化することが許されるとすれば、テクスト全体を貫く三本の線、あるいはむしろ絡みあった「三つ編」を指摘することができるだろう。第一の線は、コロックのテーマでもある境界、限界、国境をめぐる問いである。デリダによれば、境界は三つのタイプに分けることができる。第一に、領土、国民、国家、言語、文化などをへだてる境界。第二に、哲学、自然科学、神学といった言説の分野をへだてる境界。第三に、概念や事項をへだてる境界である。それに応じて、本書では、例えば、第一に歓待、マラーノ、翻訳不可能性といったテーマ、第二にハイデガーの現存在分析とフィリップ・アリエスらの文化人類学のあいだの境界、第三に「滅ぶ」、「死亡する」、「死ぬ」といった概念の境界が問われることになる。
そしてこの線が、第二のアポリアについての問いに結びつけられる。というのもアポリアとは、まさに境界を前にして通過することができない状況にほかならないからである。これについても三つのタイプが指摘される。まず、境界が明確でないために通過できない場合。第二に、対立がなかったり境界に穴が多すぎたりするために境界が存在せず、通過できない場合。第三に、中間つまり道そのものがなく、前進も後退も不可能な場合である。
そして最後に、この二本の線が、死をめぐる問いに重ね合わされる。なぜなら、私が「私の死」について語ることは可能か、誰がこの最後の境界をまたぎ越し、それを証言しうるのかといった問いこそ、アポリア中のアポリアにほかならないからである。デリダは、『存在と時間』の一節の「翻訳」として提案する《s'attendre (à)》という語、その多義性によって、死のアポリアの重層性を示している。すなわち、死がつねに「切迫したもの」であること、現存在が死を「自ら待-期」しなければならないこと、さらに生がつねに短かすぎるものであるがゆえに「自他がおたがいに待-期」しなければならないこと、しかしこれらが「不可能性の可能性」を宣告されたアポリアそのものだということ、である。なぜなら、現存在が自らの死を「実存する」こと、他者が私の死という待ち合わせ場所に到着することは不可能だからである。言いかえれば、「現存在のまったき存在不可能性の可能性」としての死とは、通過の形式をもちえないアポリアなのである。
では、われわれは、この死のアポリアを前にしてどのようにふるまうべきか。ハイデガーがいう「こちら側でなされるものとしての存在論的な死の解釈」が、例えば文化人類学におけるような、彼岸的に行われる存在的思弁に先立っているというのは確かである。しかし、この存在論的分析も、それを保証する「死それ自体」が不可能である以上、その可能性は内部から崩壊している。われわれは、定義上このアポリアに決着をつけることはできないのである。したがってわれわれは、このアポリアを乗り越えたり逃れたりしようとすることなく、アポリアがわれわれの決定を嘲笑する、まさにその瞬間に、別の仕方で決定しなければならないであろう(『触れること〔触覚〕──ジャン=リュック・ナンシーのために』、ガリレイ社、2000年参照)。
このように本書は、今やデリダの著作の通奏低音となっている死後の生〔生き延びること〕や喪の作業、亡霊といった一連のテーマ、その中心にある死の問題を正面から扱っている点で、また歓待や法、正義といったますます重要性を増しつつある諸テーマを「境界」という鍵概念によって総括して論じている点で、さらに、注目されることは少ないが「真理の諸限界」としてのアポリアという初期から最近のテクストまで一貫して引き継がれているテーマを主題にしている点で、きわめて重要なテクストである。
初出=『週刊読書人』、2348号、2000年8月11日