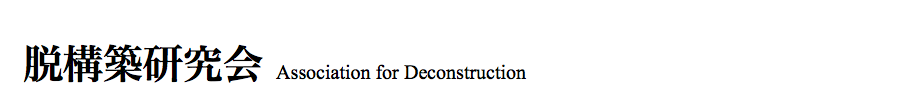Review

ジャック・デリダ『有限責任会社』高橋哲哉・増田一夫・宮崎裕助訳、法政大学出版局、2003年
松葉祥一
本書は、デリダ・サール論争の全記録である。本書に収められているのは、第一にデリダがオースティンの言語行為論を批判した「署名 出来事 コンテクスト」(1972)。第二に、サールがオースティンを擁護した「差異再び──デリダへの反論」の要約(1976)。第三に、デリダがサールの反論のほとんど全文を引用しながら徹底的な批判を加えた「有限責任会社abc…」(1977)。そして最後に、本書の英語版の編者からの質問に答えるかたちで論争をまとめたデリダの「討議の倫理にむけて」(1990)である。一部は『現代思想』誌などに訳出されたことがあるが、「討議の倫理にむけて」は初訳。
オースティンとサールの主張のかなめは、例えば劇のなかでの約束は、実生活(リアル・ライフ)での約束に依存する二次的なものだということである。なぜなら、まず前者は、実生活における誰かの言葉の「引用」だからである。また、劇は何度でも反復して上演=表象することができるが、「現実のコンテクスト」における発話は一回限りのものであり、反復することができないからである。こうして彼らは、演技という「異常」で「ふまじめな」言語行為が、実生活における「正常」で「まじめな」言語行為に依存している以上、当然後者から考察を始めるべきだと主張するのである。
それに対してデリダは、俳優の言語行為を特徴づけているこうした「引用可能性」や「反復可能性」は、けっしてフィクションの場合だけではないと言う。例えば、実生活で約束することができるのは、約束という言語行為の反復可能な形式があって、それを反復することができる限りにおいてである。つまり、一般に引用されたり反復されたりする可能性がなければ、「正常な」発言もありえない。「まじめ」だとされる言説も、「ふまじめ」な言説を特徴づけている引用可能性や反復可能性をもたなければ成立しないのである。こうして、デリダは、オースティンやサールが「異常な言語使用」を排除する身ぶりに、伝統的哲学におけるロゴス中心主義の典型を見出し、その「目的論的かつ倫理的な決定」の仕方を批判するのである。
この論争は、米国やヨーロッパだけでなく、日本でも多くの反響を呼んだ。それは、この論争が、「瑣末な」言語哲学上の議論にとどまらず、法的、政治的、倫理的に広い射程をもっているからである。そうした反響の一つが、デリダ自身によるガダマーとの論争(1981)である〔『テクストと解釈』轡田・三島他訳、産業図書、一九九〇年〕。そこでは、「まじめさ」に代わってガダマーの「善意志」が批判される。もし対話において、聞く側が、語る側の意図をつねに善意志をもって受け取らなければならないとすれば、そこではあらかじめ排除の暴力が行使されることになる。つまりデリダは、ガダマーの善意志がある倫理的公準を前提にしていると批判し、善意志を最終的な審級とする形而上学だと批判するのである。これは、無批判にコミュニケーションを前提とするあらゆる政治哲学にあてはまる。
本書の重要性はそれにとどまらない。「有限責任会社abc…」という最も緊張感に満ちた言語行為の実践例として、またデリダの九〇年以後の「政治的」展開の出発点の一つとして、そして何よりも今まさに行われようとしている「正常さ」や「正義」を名目にした国家テロリズムに抗して、どのような言説を構築できるかを考えるための手がかりとして、本書は重要性を持ち続けている。
初出=『週刊読書人』、2479号2003年3月21日