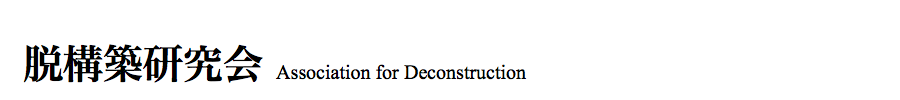Review

ジャック・デリダ『滞留』湯浅博雄・郷原佳以・坂本浩也・西山達也・安原伸一朗訳、未來社、2000年。
守中高明
出来事を証言するとはどのようなことか。それも、事が「私の死の瞬間」に関わっているとき、すなわち、歴史上の或る特定の日付と時間をもち、ただ一人「私」のみに起きた出来事を、その絶対的単独性において他者に伝えようとするとき、そこには何が必然的に含み込まれ、そこではどんな自然な信憑が解体されることになるか――本書においてデリダがブランショを読み解きつつ向き合っているのは、このような問いである。
ブランショの物語〔レシ〕『私の死の瞬間』(一九九四年)は、文字通り特異な経験の報告である。第二次大戦末期、「一人の青年」が敗走中のナチによって銃殺されかかる。「最後の命令を待つばかり」の銃口の列。しかし、不意に、間近で起きた別の戦闘による混乱のため、銃はかろうじて発射されない。そのとき「彼」は「尋常ならざる軽さの感情」に貫かれる。この「言い表しようがない」感情は「生からの解放」か、それとも「開かれる無限」を意味しているのか――「幸福でもなく不幸でもなく、恐れの不在でもなく、そしてもしかしたらすでに彼方への一歩」――「これ以後つねに待機中の私の死の瞬間」。
この物語が現実の経験を伝えるものであることは、デリダが(これまで一度もその種の手続きに訴えたことはないと付言しつつ)引用するブランショからの私信が証言している。だが、まさしく、ここで問題になるのは、証言という言語行為のはらむ何重ものアポリアである。第一に、「瞬間という審級」のアポリアがある。一般に証言とは、「分割に抵抗する瞬間性」に属していたかつての私の特異な出来事を、同じく分割不可能な〈今-ここ〉の瞬間において、現前性の場において告げる行為だと考えられている。「証言には瞬間がなければならない」のである。ところが、証言のこの可能性の条件たる「瞬間」を、証言はつねに破壊する。証言が行なわれるとき、そこには「たとえば文章のような時間的連鎖」が必要であり、またその連鎖が「それ自身の反復」を、すなわち「技術的」な「再生産可能性」を約束していなければならず、したがって、「瞬間」は「瞬間それ自体の外に引き出され」、まさに証言の瞬間に分割され破壊されるほかないのである。
第二に、代替不可能な特異性であるこの「瞬間」が、同時に代替可能な普遍的範例でなければならないというアポリアがある。私は唯一かつ代替不可能な者として証言する。私は私の経験を語る唯一の人間である。しかし、実のところ、私のこの証言が真実であり得るのはただ、「誰でもよい不特定のひと」が「私の代わりに、その瞬間に、同じもの」を経験していたかも知れないかぎりにおいてであり、その「不特定のひと」が「範例的に、普遍的に、私の証言の真実を反復」し得るかぎりにおいてなのである。私の証言が「無限に秘密であると同時に無限に公的なもの」であるということ、その反復可能性と引用可能性、「一回における一回以上」「一つの瞬間における一つの瞬間以上」という構造的可能性……。
この構造は、ただちに証言と虚構の境界線の非決定性、「虚構と証言のあいだの厄介な共犯関係」へと人を差し向ける。とりわけ、「死」の経験に関わるとき、この問題化は不可避である。現存在が不可能になる可能性として最も自己に固有のものでありながら、そのようなものとして経験に与えられることは決してない私の「死」は、それを証言しようとするとき、「つねにすでに過ぎ去ってしまったことの切迫」(ブランショ『災厄のエクリチュール』)という時間錯誤の形式を必要とするだろう。これは単なる幻想〔ファンタスム〕、あるいは文学的修辞だろうか。いや、まさしく、ナチの銃口の前で「青年」が知ったのは、そのようなものとしての「死なき死」、「経験されざる経験」としての出来事の情動にほかなるまい。そこでの「死」は「潜在的であると同時に現実的であり、潜在的なものとして現実的なもの」である。ここで「死」は、「潜在的に到来」しているのだが、「その潜在性はもはや顕在的な実際性に対置させられるような潜在性」ではない。そしてこの出来事の場所こそは、「偽証と文学的虚構が、なお真実において証言することができる」可能性の場所そのものなのである。
「現実的なものと幻想的なものの区別の彼方」にあるこの経験、その「亡霊の法」を受け容れること――それこそが、書くことの経験、文学のパッション(情熱=受苦)である。ブランショとは、このパッションをほとんど唯一の存在感情として書き続けた作家-批評家であり、そしてこの感情を肯定し、ときにみずからのエクリチュールにおいて独自の仕方でそれを徹底化するかぎりにおいて、デリダもまた「作家」であることは言うまでもない。そのことは、たとえば『弔鐘』(一九七四年)が、『郵便葉書』(一九八〇年)が、そして『火 灰』〔『今は亡き灰』〕(一九八七年)が証し立てているだろう。
ところで、この訳書の刊行直後に、ブランショをめぐるデリダのこの分析が、「済州島四・三事件」を生き延びた「在日」朝鮮人詩人・金時鐘の経験にも妥当するであろうことをかつて本紙の座談会で指摘してから、この文章の筆者は、一年あまり執筆を遅延させ続けた。そこには、個人的経験に起因する強い「抵抗」が存在していたことをここで「証言」するべきだろうか。その間に筆者は、偶々、当の詩人を囲む鼎談の機会に恵まれた。そこでも二人の作家-詩人の経験の世界的共時性を、そして第二次大戦中の植民地の言語経験については、ほかならぬデリダ自身と詩人との重なり合いを確信することができたが、この問題については稿を改めることができればと思う。
初出:『週刊読書人』2002年3月8日・第2427号