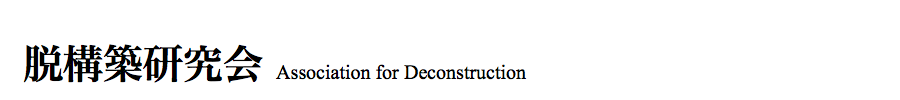Review

ジャック・デリダ『テレビのエコーグラフィー──デリダ<哲学>を語る』原宏之訳、NTT出版、2005年
廣瀬浩司
『テレビのエコーグラフィー』は一挙に私たちを現代のテレビをはじめとするメディア世界へと連れ去る。だがここに現代のメディアにたいする斬新な分析を期待する読者は、がっかりしてしまうかもしれない。対話者スティグレールのいささか挑発的な発言を前にしても、デリダはすこぶる慎重であり、状況論としては、彼の分析はときに常識的にすら見える。だが『グラマトロジーについて』から一貫して、デリダ思想の中心は、エクリチュールを含む「遠隔通信技術」の「間隔化」によっていかに「自然的なもの」「現前性」が汚染・侵蝕されていることを示すこと、したがって「自然」と「技術」の対立そのものを問題視することにあるのだから、メディアそのもののエレガントな分析や、社会学的な「メディア論」を期待するのがそもそもの間違いなのである。
彼の思考は終始一貫している。それは私たちの「現在」がいかにそれじたいで分裂しており、この分裂そのものが、「テクノロジー一般」による「反復」と「人工的代補」の可能性、そして「死の可能性」をはらんでいることを示すことである。アクチュアリティは作られている。というよりは、「反復可能性」のひとつの「効果」なのである。だが問題はアクチュアリティの「構築性」を糾弾することであるよりも、いかにそれが人工的なものであれ、前述の「不可能なもの」(特異な他者の到来)にたいして開かれていることを示すことにあるのだ。すべてはシミュラークルなのだと開き直る「新観念論」に抗して、アクチュアリティを通してそのつど起きていることを問うこと、そしてそれが起きる「場」そのものの変容を<いまここ>において問うことこそが必要なのであり、差延の思考は緊急性の思考でもあるとデリダは言う。
技術的なものと自然的なものとの必然的な混淆と汚染、そしてこの混淆のただなかにおいて到来する特異なもの──デリダはかならずしも明示的には語っていないが、こうした思考は新たな技術論やメディア学に向かうよりはむしろ、両者の混淆がもたらす「リズム」の変容の分析へと開かれていると思われる。「リズム」とは初期のデリダの「間隔化」を時間論的に展開し直したものであろう。文字社会からデジタル社会への変容を語るとするならば、それはまずこの「リズム」のある種の自己加速化として分析されるべきであり、それがどのように国家と市民社会と家族(およびそれらの場の記憶と約束)を侵蝕し直しているかを検討することなのである。
翻訳については、positionを一貫して「定立」と訳すなど、やや生硬であり、また誤訳も散見されたのが気になった。
(『週刊読書人』第2619号、2006年1月6日)