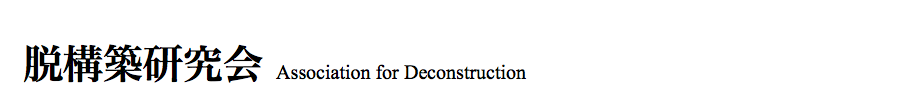Review

ジャック・デリダ『名を救う──否定神学をめぐる複数の声』西山雄二訳、未來社、2005年
祈りと無神論──ジャック・デリダ『名を救う』
鵜飼哲
ジャック・デリダが残した仕事はどれも「テクスト」であることをみずからことさら強調する。どんな著者の作品も作品であること自体によって著者の生前からその死を予示せずにいないとしても、デリダが署名した作品群のようにみずからことさら「テクスト」であることを強調する場合、著者の死もおのずと特異な作用を及ぼすように思われる。もちろん彼はそのためにあらゆることをしたのだ。しかし、みずからの死後の、来るべきテクストの生成を、彼はどこまで計算していたのだろう。あるいはむしろ、どこで計算を「放下」したのだろう。どのように。いま私は、このようなことを考えることなくして彼が残した仕事に触れることができない。そのようにして彼に思いを向けること、馳せることなくして彼について書くことができない。ある祈りの経験にみずからを開くことなくして……。
「テクスト」はそれが置かれた位置、選ばれた視野によってさまざまな姿を見せる。『名を救う』という訳題でその日本語版が出版されたSauf le nomも同様である。この「テクスト」は、ひとつの表題を与えられ、ひとつの「作品」として出版された。だから、貴重な翻訳の労働のおかげで、いま私たちは、ひとつの日本語版を手にしている。これほど当たり前のことはない。しかし、この「作品」は、同じ時期に、同じ出版社──「ガリレー社」──から、同じ装幀で出版された他の二冊の本、『パッション』および『コーラ』とともに、一見明らかな三部作を構成している。このポジションは、日本語版では、同じ出版社──「未来社」──がこの三部作の版権を取得し、同じ時期ではなかったが同じ装幀で出版したため、さいわい忠実に「翻訳」されることになった(他言語版は管見に触れたかぎりかならずしもそうなっていない)。だから、この「テクスト」は、他の二つの姉妹作の間に置かれるとき、ひとりでは見せない顔を見せる。
主題上の補完性が明白なこの三作は、しかし、執筆時期はかならずしも近接していない。それは『コーラ』が、一九八五—一九八六年度のセミネールの草稿をもとにしていることからすでに明らかだ。それに対して本書は、「ニースーベルリン、一九九一年八月」と末尾に記されているように、本が出版された一九九三年に比較的近い時期に書かれた。この二つの日付の間に起きた出来事、世界的な、そして/または私的な出来事の痕跡を、本書は──そのうえに、そのなかに、そのまわりに──さまざまにとどめている。その点でこの小品は、執筆時期によって近接する他の作品群、一方における『マルクスの幽霊たち』や『友愛のポリティックス』など政治的主題に捧げられた大著に、他方における『盲者の記憶』や『割礼告白』など自伝的色彩の濃い著作にそれぞれ密接な絆で結ばれていて、この星座のなかではまた別の光で輝きだす。
第三に、日本語版がオリジナルな副題(「否定神学をめぐる複数の声」)で明示したように、本書はデリダが「否定神学」を主題的に論じた作品のひとつである。翻訳者の一人西山雄二が記しているように、デリダの「否定神学」との取り組みは、講演「いかにして語らないか──否認=脱否定」(『プシシェ、他者の発明』所収、日本語未訳)によってすでに決定的な一歩を印していた。一九八六年、エルサレムで行われたこの長大で委曲を尽くした講演で、本書で論じられることになる否定神学をめぐるトポスはほぼ出揃っていると言っていい。しかし、さきにも触れたように、まさにこの二つの「否定神学」論をはさむ時期に起きた出来事の数々は、本書におけるデリダの思考の歩みに、限りない瞑想に誘ういくつもの痕跡を残した。ここでは私は、本書がそこに──どこに?──位置するいくつもの、より広いテクストの編目のなかで、このもうひとつの「否定神学」論との絆を特権的に扱うことにする。それを通じて「ガリレー=未来社三部作」や同時期の他の著作との関連を間接的に視野におさめつつ、本書がとどめる出来事の痕跡のいくらかを、〈読む〉ことを試みたい。
デリダの思考に対する「否定神学的」という形容は、とても早くから、さまざまな含みをもって用いられてきた。すでに一九六八年、講演「差延」ののちの討論で、質問者の一人がこの指摘を行っている。当時その問いに否定的に応答しつつ、同時にデリダはこの場面の異様な性格に注意を払っていた。というのも、「否定神学的」という形容に否定的に応答するとき、人は何をしていることになるのだろう。差延の思考は肯定神学的でも否定神学的でもないと応答したとたん、そこには「否定神学」に少なくとも類似した身振りが随伴せざるをえないのではないか。「否定神学」をめぐるデリダの本格的な応答は、したがって、一つは「いかにして語らないか」に、もう一つは本書に読まれる、次のような相補的な二つの前提的注意を踏まえて行われることになる。
「かつて誰が、それとして、この名のもとに、単数形で、定冠詞付きの否定神学の企図を、それをわがものと明確に主張しつつ、それを他の事柄の下におくことなく、従属させることなく、少なくともそれを複数化することなく、引き受けたことがあっただろうか? 定冠詞付きの否定神学というこの表題を主題としては、否認する以外のことができるだろうか?」(『プシシェ』、原著五三六頁、脚注1)
「私はどんなテクストも否定神学にまったく汚染されていないとは信じない。たとえそれが、一見したところ、神学一般といかなる関係ももたない、もとうとしない、もたないと信じているテクストであってもである。」(本書七五頁)
前者の注意がよりどころとするのは、哲学史、宗教史で一般に「否定神学」とみなされている文書、この表現がはっきり見えるディオニシオス・アレオパギテスの『神秘神学』においてさえ、この表現はつねに複数形であり、肯定神学とけっして単純に対立させられてはいないという事実である。そうである以上、ある〈もの〉、例えば脱構築が「否定神学」的か否かという問いは、「否定神学とは何か?」という前提的な、とはいえ容易ならざる問いが無視ないし閑却されるなら、およそいかなる意味も持ちえない。
後者の注意はこの認識を、逆の側から再確認する。トマス・アクイナスはディオニシオスを高く評価していたし、カントにおける理論理性に認識不可能な物自体の仮設はもとより、ライプニッツやヘーゲルも、ジヨルダノ・ブルーノ、ニコラウス・クザーヌス、マイスター・エックハルト等を経由する「否定神学」的思考の流れを継承している。このように、〈否定神学的なもの〉とその「他者」ないし「外部」を一義的に切断する境界はけっして自明ではなく、見る角度を変えさえすればヨーロッパ思想史上のどんな思想、どんなテクストにも、「否定神学」の影を認めることは困難ではない。
問題とされる事態の基本的性格を以上のように把握しつつ、デリダは「否定神学的」という形容に含まれうる非難の含意を分析していく。二つの「否定神学」論を横断して展開されるこの分析はおよそ三点に整理される。彼によれば、「否定神学的」という非難には、①単に否定するだけで何も肯定せず結局何も言ったことにならない ②否定的ではあれ結局神学であり宗教的規定性をまぬかれない ③あれこれの名辞を否定するのは容易であり「否定神学的」テクストの生産は機械的にできる、という三重の含意が認められる。
これらの非難に対し、デリダは次の点を想起あるいは強調することで応答する。非難の①と②は、一見相反するように見えるが、実際には思想史についての同じ皮相的認識から派生したものである。ラテン語キリスト教世界において、否定神学的とみなされた思想表現は、しばしば異端の、さらには無神論の嫌疑をかけられてきた。この危険視は何に由来するのか。そもそも無神論とは何か。これらの問いが掘り起こされ、現代の思想的課題と突き合わされなくてはならない。他方、③のタイプの非難に対しては、ある祈りの次元が、「否定神学」の「言語表現」を、機械的言表生産から構造的に区別する事情が強調される。祈りと無神論、こうしてデリダの「否定神学」論は、この二つの極の間で展開されることになる。
祈りはアリストテレスが、「否定神学」が現れるはるか以前に、奇妙にも「否定神学的」な言語表現で述べたように、「真でも偽でもない」(『命題論』)。それは本質的に述語付与の秩序に属さず、その点で「否定の道」の神学とあらかじめ親近な関係にあったと言える。しかし、祈りの本質はまた他者への呼びかけの経験でもある。そして、キリスト教、とりわけヨハネ神学によれば、その呼びかけの宛先である神なる他者こそが一切の言葉の起源である以上(「はじめに言葉=ロゴスがあった」)、この経験は、根源的にどんな言語表現にも先立つ。このような他者への呼びかけappelは、つねにすでに呼ばれてしまっている者の呼び応えrappelであり、応答réponseである。一切の言葉以前の、言葉の起源である他者への、緊迫した、この関係なき関係が、例えば『神秘神学』の言説を、機械的言説の弛緩から区別するのである。
しかし、それ固有の契機においては言語以前的である祈りも、その言葉がひとたび書かれるやいなや引用の構造にとらわれる。宗教の、そして教育の可能性は、そのようにして開かれる。「ディオニシオスのエクリチュール」は、『神秘神学』の冒頭から、無言の「祈りそのもの」と、「祈りの引用」と、そして「弟子への語りかけ」の間の「間隔化」のうちに身を持している。神への呼びかけ、すなわち神からの呼びかけへの応答、その引用、弟子への呼びかけが、「同じテクスト」を「織りなして」いる。講演「いかにして語らないか」は、ディオニシオス・アレオパギテスとマイスター・エックハルトのいくつかの著作、「否定神学」の古典的かつ規範的とみなされるテクストを扱いつつ、この特異な言語表現のありようを教育の問いに連接していく。
それに対し、対話体の本書は、「否定神学」の伝統のいわば周縁に位置するドイツ十七世紀の詩人アンゲルス・シレジウスのテクストの読解を通して、<否定神学的なもの>を、教育以上に、友愛および愛の経験に接近させる。本書の冒頭で、アウグスティヌスの『告白』から『神秘神学』における祈りと同型の構造が取り出され、そこにキリスト教的な愛の実践と、西洋における自伝autobiographie、文字通りには「自己の=生の=痕跡/エクリチュール」一般の可能性が同時に見さだめられていることは重要である。「いかにして語らないか」では、少なくとも表面上はまず論じられていた「祈り」は、ここでは、より明白なある自伝的コンテクストのうちで実践されているのである。
sansとsauf、フランス語のこの二つの否定の前置詞の差異は、後者のうちに、前者には少なくとも表面上は認められない<救済>の含意、この二つの前置詞と同じくsaの二文字を含むsalutの含意があることである。言い換えれば、<否定の道>と祈りの不可分な関係が、saufの方によりあらわに認められるということである。一九八六年、エルサレムのデリダは、「私の誕生が私に与えて然るべきだったもっとも近いもの」、すなわち「ユダヤ」と「アラブ」については「私はいまだかつて語りえたためしがない」と述べながら、この講演を、事後的に、「他者──ギリシャ人、キリスト教徒──の否定神学」を語ることによる「自伝」の試みとして読み直す可能性を示唆していた。それから五年、パレスチナ第一次民衆蜂起(インティファーダ)、ソ連邦崩壊、そして湾岸戦争と、政治的世界はいくつもの出来事の激震に見舞われた。そしてジャック(ジャッキー)・デリダは、母ジョルジェットの長い臨終に連れ添いつつ、いくつもの「自伝的」テクストを書き継いだ。
本書の対話は、二つの声のうちの一方が、他方の母が病床にある地中海岸の実家に招かれ、そこへアンゲルス・シレジウスの『ケルビムのごとき旅人』抄を携えて訪れるという設定で始まる。「自伝」的言葉は終止他者の声に担われ、対話の最後の言葉も〈客〉の側に委ねられる。〈客〉が前半の議論をリードし〈主〉が問う立場で展開するが、やがて〈主〉の口からひとつの命題が提出される。「ギリシャ-ラテン系統の固有言語で「否定神学」と呼ばれるもの、それはひとつの言語表現である」というこの命題をめぐり、二つの声の立場はいわば対等になり、それとともに両者の観点の相対的な差異がいくらかはっきりと現れる。〈主〉の命題は「否定神学」の可能性の条件をおもにギリシャ的ロゴス、哲学に求め、〈客〉の側はその規定をはみだす諸要素を想起してこの命題に執拗に懐疑を差し挟む。言語表現とそこに残された痕跡のかかわりをめぐる中盤の問答の果てに、〈客〉はこの命題を、それに(友)愛phileinと翻訳の不可分な問いを読み込む可能性を見出して、保持することに同意する。
そのとき、目立たないままに重要な役割を果たすのは、やはりギリシャ語系のひとつの言葉、類比analogieである。〈客〉は、アンゲルス・シレジウスの詩を駆動させるギリシャ的誇張、〈ヒューペルボレー〉hyperboleの運動が、類比の論理がギリシャ的思考において、またキリスト教信仰とギリシャ哲学との交差において、伝統的に果たしてきた和解と秩序形成の作用を、自壊に追い込むことを指摘する──。
「彼方へと自らを運びながら、この運動は存在と知、実存と認識を根底的に分離する。それは、(アウグスティヌス的ないしはデカルト的な)コギトが、「私が存在すること」のみならず、「私は何であるか」と「私は誰であるか」を私に知るべく与える限りでのコギトが、破折するようなものである。ところで、この破折は私にも神にも当てはまる。それは神と私、創造者と被造物とのアナロジーにまでその亀裂を走らせる。この場合、アナロジーはこの分離状態を、修復することも和解させることもなく、これをさらに切り離し、さらに悪化させる。
ひとは自分が何であるのか知らない
私は私が何であるのか知らない。私は私が知っているものではない。
私はある物であり、またある物ではない。私は点であり、また円である。
そしてこの件からさほど遠くないところに、次のようなアナロジー、「wie〔ように〕」がみられる。
私は神のようであり、神は私のようである。
私は神と同じくらい大きく、神は私と同じくらい小さい。
神は私を超過することはできないし、私は神の下にいることはできない。」(本書六九ー七〇頁)
先に〈主〉の命題を引き受けたとき、〈客〉はさしあたり「作業仮設」として、「否定神学」の歴史的場所、その固有語法の確定が、それに「固有の場を割り当てるものが、それを脱固有化し、そのようにして普遍化する翻訳の運動に投入=拘束engage」する可能性を示唆していた(本書六四頁)。アンゲルス・シレジウスの詩のなかでの、ギリシャ的な類比の論理の変容は、限界確定がそのまま限界解除になるという、このような事態の端的な例証にほかならない。〈分離する類比〉のこのような作用は、本書後半の軸をなす、「放下」Gelassenheitの思考のうちにも働き続ける。
惑星規模の技術の帝国主義の〈彼方〉を思考しようとしたとき、ハイデッガーがエックハルト経由のこの言葉を重視したことは知られている。本書はデリダがこの言葉に即して展開したもっとも貴重な思考の記録でもある。〈客〉はこの言葉を、一方で愛の定義とし、他方で来るべき民主主義のアポリアに結びつけつつ、無神論と祈りが、この言葉のうちで、ほとんど同義になっていくことを示す。神からその名を除きsauf le nom、あるがままに残すこと、否定的に把握を慎むだけでなく、放棄するすべを知ること、神に何も、頌歌も栄光も与えないことに一切の知の彼方でたくみであること、静謐に、穏やかに、別辞(アデュウ)も与えずに神(デュウ)を残し、離れ去ること、それこそはラディカルな無神論の挙措であり、しかし/そして、「否定神学」の言葉を、極限まで、砂漠のように希薄化させる、一切の言語活動以前の、祈りの運動でもあるだろう。
このようなGelassenheitは、つねに他者から、秘密のうちに、ほとんど秘教的に、学ばれるほかはない。記憶を喪失し、嗜眠状態のなかで生き延びる、「穏やかにわれわれを離れ去り、もはや名を呼ぶことのできない」〈主〉の母こそは、本書におけるこの「秘密の放下」の、「師」にして「神」ではなかったか。翻って、誰の声も「私の母」と言わないこのテクストは、この「母」、すなわち他なるものへとすでに生成を遂げた他者との<分離する類比>のうちで、みずから他なるものへの生成werdenを賭けて綴られたのではなかったか。
『割礼告白』は、著者のユダヤ教徒の母が、著者がまだ神を信じているかどうか、つねに気遣い、不安を抱いていたことを明かしていた。そのような母に、息子は彼の無神論を、どのように告げることができるだろう、その告白と祈りとを、「同じテクスト」に「織りなす」ことなくして、どのように。
(初出=『未来』2006年3月号、474号)
廣瀬浩司
『名を救う』の主題は否定神学である。一九六八年の「差延」という講演以来、デリダは否定に否定を重ねる自分の言葉遣いが、ときには「見紛うばかりに否定神学に似ているかもしれない」ことを認めつつ、その根本的な差異をも際立たせようとしてきた。『ブシュケ』所収の八六年「いかにして語らないか──否認」ではこの問題に正面から取り組み、エックハルトや擬ディオニュシオス・アレオパギテースらを論じていた。九二年初出の『名を救う』はこの問題をアンゲルス・シレジウスを題材に取り上げ直した作品であるが、ここでは差異を際立たせるよりも、むしろ対話形式を使って、否定神学そのものが内側から複数化し、翻訳可能な地平へと開かれていく運動がゆるやかに描き出されているようだ。
「贈与」に代表される後期思想の問題系をデリダは「不-可能なものの(不可能な)可能性」にまつわるアポリアとして追求していた。「不-可能なもの」だけが生起し、「場」を持つ。だがこの出来事はそれとしてけっして現前しない。『アポリア』(人文書院)における、ハイデガーの「死に向かう存在」の思想との対決においても重要なこの考え方は、否定神学的言説とも深く通底している。
否定神学的言説は、充実した直観による神の現前を回避しようとするため、極度に形式化されたものとなり、容易に模倣され、偽造され、空虚なものとなる「危機」(フッサール)にさらされている。それは究極的には、言語が言語そのものについて語るというモノローグ的な言説に到達するだろう。神について筋の通ったことは何も語られない──その名を除いて。「神」とはこうした「根底なき崩壊の名」であるとデリダは言う。
だがこうした否定的な操作の「痕跡」は、不-可能な出来事が残した傷として刻み込まれている。そしてこの傷は、言語を越えた語り得ぬ次元にあるだけではなく、言語そのものの内をも横切り、読解可能であると同時に読解不可能なテクストを、構成的な「縁」として織りなしているのである。いや、そもそも「縁」でないような言語などない、「否定神学にまったく汚染されていないテクストなど私は信じない。」こう断言することでデリダは、機械化と秘密化、名の消去とその回復のあいだの、無限の運動を描き出すのである。
不-可能なものが場を持つような不可能な場、それを晩年のデリダは、プラトン主義の縁にあるコーラという語へと集約させていく。「感性的でも叡智的でもあり」、また「そのどちらでもなく」、さらにはこの二つの命題の「どちらでもあり、どちらでもない」ものとして、コーラは脱構築そのものが到来する場、そしてまた、あらゆる神学的・存在論的・政治的な伝統に抵抗するような場に付けられた異名なのである。いわゆる湾岸戦争のときに、西欧諸国が国際法を語りながらキリスト教的な言説を増殖させていた状況のさなかで、デリダは民主主義を「コーラの試練」にくぐらせようとしていたのだ。
優れた翻訳であり、「訳者解説」も有益であった。
(『週刊読書人』第2619号、2006年1月6日)