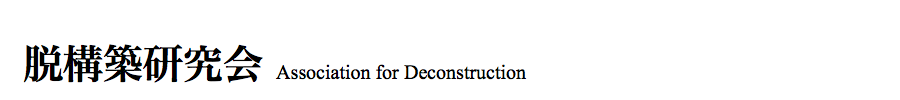Review

『信と知 たんなる理性の限界における「宗教」の二源泉』、未來社
評者:長坂 真澄(群馬県立女子大学准教授)
今日世界をその伝播により揺るがしている、宗教的原理主義者たちによる過激な暴力の応酬について、人は言うかもしれない。彼らは宗教者ではない。彼らは単に宗教の名を語って暴力の口実にしているに過ぎず、彼らの問題は別のところにある。確かにそうかもしれない。しかし、その名が語られることによって暴力を世界各地に飛び火させる、宗教とは、暴力の口実となる宗教とは、一体何なのか。一九九四年、カプリ島で、デリダは宣言する。宗教の名と遠隔―技術科学機械とが結託し、暴力として炸裂している今こそ、私たちは、宗教を考えることを避けてはならない。本書は、このように始まるデリダの論談と、後日の考察とからなるテクストの、日本語訳である。
まずデリダが明言するのは、知と信、理性と宗教、技術的科学と宗教的信仰等々を、二項対立的に捉えるならば、救いはないということである。一方で、知の遂行としての学問は、たとえ最小限であれ、何らかの信なしには始まり得ない。思考法則のような必当然的明証性でさえ、証明不可能な公理への信頼を出発点とするほかはない。他方で、信とは、何らかの知に対する信にほかならない。それはデリダが、独断的信と反省的信のカントによる区別に、限りなく忠実である最中においても、そうである。独断的信が知の標榜であるならば、反省的信は無知の知であり、やはり知と無縁ではない。信と知はその意味で始まりを共有している。デリダはその源泉を「証し=担保=保証[gage]」であるとする。知も信も、そのような根源的な担保なしには作動し得ない。
同時に、デリダが信と宗教を区別していることも忘れてはならない。信は、それのみでは宗教とはならない。デリダによれば、宗教は二つの源泉を併せ持つ。その一つは信の経験、もう一つは聖性の経験である。これら二つの源泉の合流点に位置するのが、「証言[témoignage]」という現象であるとデリダは言う。証言において、証言者は、対話者に彼を信じることを要求するとともに、対話者が決して接近できない絶対的な過去における出来事、すなわち対話者に対して無傷にとどまる(聖性となる)出来事を告げる。デリダは、信と聖性のいずれか一方を、他方に還元すべきではないと言う。両者の区別を試み、信に感染されることなき聖性を思索しようとしたのがハイデガーであり、聖性に感染されることなき信を思考しようとしたのがレヴィナスであるとされる(ただしデリダは、ハイデガー自身の自己解釈に反して、ハイデガーの思索のうちに、むしろ信への開けこそを読みとる)。デリダにおいて、信と聖性の区別は、他者への二つの応答の仕方の区別と重なる。すなわち、絶対的に他なるものへと自己を曝け出すこと(信の運動)としての応答であるか、あるいは、言い返し、応酬し、反駁し、自らを無傷なものへと復元しようとすること(聖性の運動)としての応答であるかの区別である。後者は自己―免疫性(自己自身に対して自己を守ろうとする過剰な免疫反応の働き)という病へと発展する。自己―免疫性の論理は、これもまた、宗教と遠隔―技術科学的理性の両方が共有するものである。その悪は、カントの根元悪(私たちの理解を超越する悪)の概念に結びつけられる。
デリダは、これら二つの応答の仕方の区別は、規定的判断によってはなされ得ないとする。つまり、個別の事象としての、今ここにおける応答は、信と聖性のいずれか一方のみの概念に属すことはできない。応答は、発されるやいなや、そのつど、信と聖性の両方へと同時に開かれてしまう。それでも、応答なしにはいかなるチャンスもない。一般化され得ない個別の状況において、そのつどの応答に賭けるしかないのである。
本訳書には、四二の訳註および「訳者あとがき」が付されており、宗教と暴力をめぐるデリダの考察に対する、私たちの理解を助けてくれる。自己―免疫性に対してさらなる自己―免疫性によって応酬しないために。今日こそ、多くの人によって読まれるべき書物であると確信する。
(週刊読書人、3174号、2017年1月)