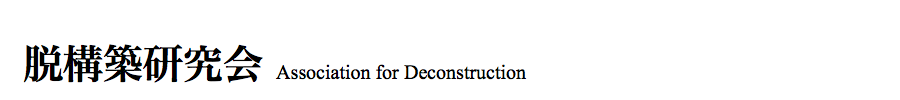Review

ジャック・デリダ『翻訳そして/あるいはパフォーマティヴ 脱構築をめぐる対話』、法政大学出版局
ジャック・デリダ『最後のユダヤ人』、未來社
評者:立花 史(早稲田大学非常勤講師)
「デリダを初めて読む者にとって手に取りやすい著作はあるか」と訊かれると、私は、特定のテクストを挙げる前に、こんな前置きをする。デリダの著書は大抵、多くの入門書がそうであるように、日常から出発して書かれている。彼が、身近なフランス語を分析したり、時事的な問題を参照したり、さらに身の上の出来事を語ったりするのはそのためなのだ。われわれは、他人や動物のみならず、宗教、伝統、制度、人工物、テクスト、言葉、名称、世界情勢、過去の経験など、さまざまなものと「共に生きている」。これら身近なものたちは、主体(sujet)ではないにせよ基底材(subjectile)として、つねにすでに、われわれに働きかけている。デリダの持ち味は、身の回りの基底材がもつ底知れなさを手がかりとして、みずからの哲学を語るところにある。またその身振りが伝わるかぎりにおいて、彼はいつも、全方位的な誘惑者であり続けてきたのだ、と。
今年は、デリダ翻訳ラッシュの年だった。管見では、初期の主著とも後期の代表作とも違う、別種のテクストが訳されつつあるように思う。例えばそれは、今年邦訳が完結した『獣と主権者』(白水社)のように、彼の執筆の一部にして母体をなす講義録であったり、『信と知』(未來社)や今回扱う二冊のように、デリダ自身のアイデンティティとも密接にかかわる宗教やユダヤ性をめぐる著作であったり、スタイルと内容が極度に複雑化した中期の思考に関する証言であったりと(ほかにも『精神分析のとまどい』と『他の岬[新装版]』が刊行されている)。
『翻訳そして/あるいはパフォーマティヴ』は、一九八〇年と一九八三年におこなわれたデリダと豊崎光一の対談を豊崎自身が翻訳して雑誌に掲載した二編に、今回の書籍化の際、監修者の守中高明氏が総題を冠したものである。雑誌掲載から数十年を経た書籍化までの経緯は、日本のデリダ受容の軌跡をあらためて思い起こさせる。この点については、監修者の「解説」とは別に付された「あとがき」に詳しい。フランス語圏や英語圏ではかなり用心深いデリダが、日本向けのメディアでは、率直というよりほとんど無防備に語ることは、すでに『他者の言語』で周知の事実だが、本書ではさらに豊崎が、デリダとの交友関係に乗じて、きわどい質問を投げかけ、デリダがとまどい気味に答える場面も見られる。くわえてインタヴューのテープを基に、「笑いを含みつつ」「ここで再び長い沈黙」「外で犬の吠える声」など、状況説明がト書きのように挿入されていることもあり、これまで公刊されたどの対談よりも生き生きとした内容となっている。
デリダは、書き下ろしたばかりの『絵葉書』について、一九世紀に郵便事業の大半が国営化されるとともに第三共和制期に絵葉書が登場したという歴史的経緯から、ハイデガーの「存在の歴運」にかかわる理論的側面まで、比較的多くの言葉を費やしている。とは言え、豊崎の質問は多岐にわたる。当時のフランスの著名な哲学者のなかでもとりわけデリダには、女性読者が多いのではないかという点について。『絵画における真理』を念頭において、ヴァレリオ・アダミのようなアーティストたちに言及したイマージュの主題、またデリダが七〇年代後半に三年連続でおこなった「物」を主題とする講義、ミシェル・セールとの関係についてなど。どちらの対談でも、ユダヤ的なものに話題が及び、特に二度目の対談は、デリダが、知人に請われて初めてイスラエルを訪問した後のものであるため、源泉への回帰ではないと断った上で、ユダヤ教との関係が慎重に語られている。
『最後のユダヤ人』は、一九九八年と二〇〇〇年におこなわれた二編の講演をまとめた書物である。一つ目の講演「告白する――不可能なものを」は、「共に生きる」ことを主題としている。「共に生きる」ためには、それを可能にする何らかの法が前提となる。しかし法のないところに法が確立されるとき、そこには法外な暴力が介在する。法を創設すると同時に既存の法を侵犯するこの法創設的な暴力の観点から、本講演では「共に生きる」の創設が論じられる。そして「共に生きる」の内実が、現代のグローバル化(とグローバル化疲れ)から古代のパレスチナでの多民族の共存まで、死者を含めた人間関係はもちろん、動物との共生、生と技術との共犯性に及ぶかぎりで、本講演における正義概念は、『法の力』の場合のような狭義の社会正義にとどまらず、世界正義や環境正義、動物に対する正義、技術を含めた“オブジェクト指向の正義”まで射程に収めている。
題名に見られる「告白する」という文言は、デリダの重要な術語でもあるが、過去の人道的な罪をめぐって当事者たちが告白し合うという九〇年代に世界各地でなされた営みが背景にある(日本の対アジア外交、奴隷制に対するアメリカ大統領の謝罪、ヴェルディヴ事件に対するフランス大統領の謝罪、南アの「真実和解」委員会の活動など)。こうした「告白の世界化」の一方で、告発された者に対してスケープゴートの論理が働く場合があることもデリダは見逃さず、そこに第一のアポリアを指摘する。次に、原理的に無条件であるべき赦しが条件的なものとして論じられてしまう事態、また、つねに開かれたものとしてあるはずの帰属が往々にして我有化されてゆく事態、そして、生が不可分なまでに技術と絡み合う「技術生物学的補綴」(六三頁)という事態のそれぞれに、現代社会のアポリアを認めて、我々に問題を突きつける。
二つ目の講演「アブラハム、他者」は、デリダが初めて正面から「ユダヤ性」について論じたものであり、誤解を恐れずに言えば、ユダヤ性を脱構築する試みである。幼少期に、ユダヤ人としての迫害と、ユダヤ人コミュニティの同調圧力とのあいだで板挟みを経験したデリダは、自分の立ち位置を、「最後のユダヤ人(le dernier des juifs)」という地点に求める。それは、「もっとも少なくユダヤ人である者、もっともユダヤ人にふさわしくない者」であるが、まさにそれゆえに「もっともユダヤ的な役割を担うことを楽しむ者、さまざまな世代からなる遺産を引き受けることを定められた最後の、唯一の生き残り」でもあることを意味する(九四頁)。みずからの帰属性を否定せずに、しかし帰属性の下で最大限の自由を行使することに帰属性そのものの可能性の条件を設定する。こうしたユダヤ性を引き受けるにあたって、さまざまな人称、本来性と非本来性、ユダヤ教とユダヤ性といった三つの対立が疑義に付される。デリダはその途中、サルトルの『ユダヤ人問題についての考察』を初めて俎上に載せ、敬意を表しつつも、きっぱりと批判を加える。
デリダが宗教を語るとき、単に宗教だけを問題としているわけではない。本書にあるとおり、重要なのは「あらゆる宗教よりもいっそう古い、ある種の信仰」(六七頁)である。伝統、信念・信仰、聖性と、哲学や政治文化の伝統にひそむ諸前提との関係が問い質され、言語や社会性が根本的にはらむ宗教的次元が思考される。ユダヤ教やユダヤ性にかかわる用語や概念が用いられるにせよ、中東の言語文化に詳しいコロンビア大学教授ギル・アニジャールの指摘するところによれば、デリダが頻繁に言及する「アブラハム的なもの(l’abrahamique)」は、そもそもイスラム的な起源をもつ言葉である。そこには、イスラム教・ユダヤ教・キリスト教の関係の、さらに言えばヨーロッパの歴史とアイデンティティそのものの再検討を可能にする契機がひそんでいる。ポスト世俗化の時代に対するデリダの鋭敏な感性を示すものと言えよう。
それでもやはり、晩年のデリダはユダヤ性に拘泥しすぎてはいまいか、という一抹の疑念を抱く読者もいるだろう。現代哲学における「ユダヤ」の問題の布置に関して、渡名喜庸哲氏の詳細な訳者解説がぜひともほしいところだが、あいにく未來社とガリレ社との契約上それが叶わなかったらしく、解題は季刊PR誌『未來』に近々掲載予定であると記されている。紙媒体での公刊とともに、ウェブ版での全文公開を期待したい。