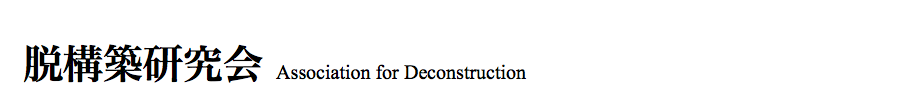Review

ジャック・デリダ『境域』若森栄樹訳、書肆心水、2010年
西山雄二
『境域』はデリダが七〇年代に発表したモーリス・ブランショをめぐる文章群と彼への追悼文から構成されている。同じ時期にデリダは『撒種』『弔鐘』などの実験的な文章表現や構成を実践しており、『境域』もまたそのひとつである。
ブランショは文学と死の等根源的な位相を考察し、死の不可能性がもたらす軽やかな厚みとでも言いうるものを表現し続けたたぐい稀な作家である。彼の作品をデリダは敢えて接近不可能なものとみなす。接近不可能なものの遠ざかりそのものの魅惑の力によって、ブランショ作品における「思考の本質的運動」を描き出そうとするのだ。その文体や構成からして、本書はブランショ「論」ではない。ブランショのフィクションの引用とデリダの地の文が相互に陥入し、寄せては返す波打ち際のように、ある境界上の反復運動が記述される。
表題Paragesは同時に「船が航海できる海の領域」と「船が座礁させてしまう目に見えない境界」を示す。ブランショの両義的な表現を借りれば、それは「彼方への歩み」と「彼方なし」の閾である。本書では、遠さと近さ、呼びかけ、死、物語、ジャンル、法、語りの声といった主題群に即して、現前することのないこの決定不可能な境位が記述される。なかでも「おいで」という呼びかけはブランショの全作品を貫く運動性とされる。「おいで」は命令形でも現在形でもなく、こうした境域に差し向けられた初源の言葉である。「おいで」は「…とは何か」「それは…である」といった同一性の掟を頓挫させ、他者の到来に対する肯定を導く。それは同一性の円環に帰着する弁証法的循環ではなく、遠ざかりによって自己への接近をもたらすという、分割された往来の歩みである。「おいで」はその都度一回的で、永遠に反復される出来事の到来をもたらすのである。
死ぬことの不可能性に滞留し続けたブランショが実際に死去した時、いかなる言葉を彼に手向けるべきか。末尾に収録された追悼講演はまさにこの作家の死を表現することの困難さから始まる。火葬されたブランショの遺灰を想起しつつ、死という不可能性の可能性のアポリアがハイデガーのWalten(存在者と存在の差異を生み出す中性的な力)分析とともに記述されていく。評者はこの講演を聴講したが、議論の時間にデリダはブランショのなかにむしろ「ウィ、ウィ」という独特の歓喜を確認できるとした。単に愉快なだけではなく、奇妙な厳しさを孕んだ歓喜は『境域』からも伝わってくる独特の情動であろう。
本書の論考は当初、フランスとアメリカでのセミネールなどで披露され、英語圏の読者に向けて書かれたものもある。たんなる抽象的で実験的な文章実験ではなく、ブランショを論じるための教育的規範の探求が考慮されているのだ。この時期デリダは哲学教育をめぐる運動GREPH(グレフ)に参加しており、本書にも教育および大学制度への言及が見られる(二〇三頁など)。彼は哲学の文学的表現で戯れていたのではなく、制度に対する新たな責任を模索していたことがうかがえる。
訳者・若森氏はデリダのやはり難解な『絵葉書』(水声社)の訳業も成し遂げており、『境域』も適切な訳語と文体でその読みやすさは賞讃に価する。七〇年代のデリダ翻訳の範例的スタイルが確立されていると言ってもいい。「あとがき」で「デリダの文章は論理的」という確信が語られるが、これはデリダ読解の第一の重要な分岐点だろう。ただ、訳註は一四個と数が少ない割に冗長な説明も目につく。訳註はもっと数を増やし、日本語訳への参照も付した方が読者への教育的配慮は増しただろう。(ちなみに、三六三頁の英訳者名はアヴィタル・ロネル。)装丁は実に素晴らしく、本書の通奏低音をなすブランショ『謎の人トマ』の海のイメージを見事に喚起させる書物に仕上がっていることを付記しておきたい。(『週刊読書人』2010年10月8日号・2859号)