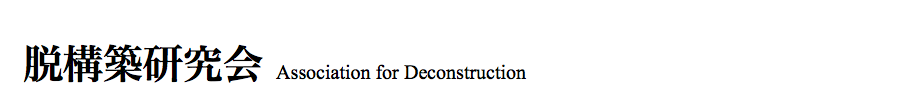Review

ジャック・デリダ『散種』藤本一勇、立花史、郷原佳以訳、法政大学出版局、2013年
大杉重男
その昔、文芸評論家として駆け出しの頃、何を思ったか神保町の某書店から突然本を出さないかという話があり、喜んで目次を見せに行ったら、こんな各章がバラバラで関連性のないテーマでは本にならないと言われて断られたことがある。呼び出しておいてとは思ったが、それ以来私にとって一冊の本を作るとはどういうことなのか、謎のようなものであり続けている。一応二冊なんとか単著を出すことはできたが、それらはいずれも作家名(徳田秋聲、夏目漱石)によって辛うじて統一性を持たせたものであって、私にとって満足できる本の在り方ではなかった(特に『アンチ漱石』は、編集者や出版社の無理解・無関心の中で、辛うじて作ったものだった)。その後も私は結構いろいろな文章を書いて来たつもりだが、それらをどう寄せ集めても、なかなか「本」になる気がしない。
ジャック・デリダの『散種』は、そんな私にとって勇気づけられるような(また絶望させるような)本である。この本は一つのテーマに貫かれているとは言える。ただしそのテーマとは、本であることの不可能性、本から絶えず逸脱して行かざるを得ないエクリチュールの運動なのであり、にもかかわらず見事な本としての統一性を持ってしまうそのエクリチュールの力業は見事と言う外ない。
この本は四つの章からなる。最初の章「書物外」は、後の三章に対する序文の役割を果しているが、それは「本文」と「序文」の間にある階層的な関係をラジカルに解体するものであり、そして続く三つの章(「プラトンのパルマケイアー」「二重の会」「散種」)は、それぞれプラトン、マラルメ、ソレルスについての独創的な読解とパフォーマンスを展開する。そこでは本来的なものとそれを代理=補足するもの、音声と文字、自分自身に回帰する嫡出子的な父子関係と回帰することなくとめどなく拡散して行く私生児的な父子関係、といった西欧思想の二項対立が、繰り返しずらされ、反転され、脱構築される。訳者の解説にあるように、この本は、数多くのデリダの本の中でも、論理的分析とパフォーマンスとのバランスが良く、最もコンパクトに分かりやすくデリダの核心的思想を語っている。
特に「プラトンのパルマケイアー」の章は、『グラマドロジーについて』よりも手っ取り早く、デリダのロゴス=音声中心主義への批判の論理をたどることができるように思う。プラトンの『パイドロス』は、恋愛をテーマにした哲学書として知られる。恋は善き狂気であるというその恋愛賛美は有名だが、後半は弁論術にテーマが移り、終り近くの部分では文字についての奇妙な神話的物語が語られる。それはテウトというエジプトの地方神が、文字を発明し、エジプト全体の王神であるタモスに見せたという物語である。その中でテウトは文字が「記憶力と知恵」の「治療薬」となると言うが、タモスは文字を学ぶと記憶の訓練がおざなりにされ、忘れやすくなると警告する。文字は尋ねても応答することのない死んだ記憶であって、「生きた記憶」を損なう毒薬になりうる。物語はここで終わっているが、デリダはテウトに代ってタモスに反論し、プラトンのテクストに現れる「パルマコン」というギリシア語が、治療薬と毒薬の両義性を持つことを指摘しつつ、生きた記憶と死んだ記憶(それは真と偽、内と外などの二項対立に言い換えられる)が相互反復的であり、同一的であることを主張する。プラトニズムに端を発するロゴス=音声中心主義に対する正面からの批判がそこに展開される。
「二重の会」も同様に刺激的な章である。マラルメの詩の分析はフランス語の問題もあり難解で分らないところだらけだが、マラルメが書いた「黙劇」という文章に対するデリダの読解はとても面白い。「黙劇」は「女房殺しのピエロ」(それは自分を裏切った妻をピエロがくすぐって笑い死にさせるという内容である)というパントマイムについての短い散文である。マラルメが描いて見せるパントマイムはいかなる口頭の発言によっても支配されることのない身体によるエクリチュールであり、プラトン的な真理の複写としてのミメーシス概念を拒絶する。ここでデリダが分析するミメーシスの問題は、たとえば近代日本の自然主義や私小説の問題を整理することにも使えそうな気がする。
最終章「散種」は正直言って私の手に余る部分が多い。ここではソレルス、そしてデリダのテクストがもともと「表音文字」で書かれたテクストであることが痛感される。デリダは「表音文字」と「表意文字」を接ぎ木的に接続することの革命性を熱っぽく書くのだが、「表音文字」と「表意文字」(最近は「表語文字」と言うべきだという意見もある)のハイブリッドである日本語を読み書きする者として、それをどう受け止めたらよいのか分らない。もちろんそれは私自身が考えるべき問題だろう。それにしても当時60~70年代のフランスにおいて毛沢東主義がいかに大きな他者としてあったのかを想像させるエッセーではある。またそこで展開される「数」の戯れが、蓮実重彦が志賀直哉論や『大江健三郎論』で展開させた「数」をめぐるテマティスム的戯れを連想させることが個人的には気になる。デリダが本書の「二重の会」において蓮実のテマティスムの源流であるリシャールのマラルメ論を鋭く批判していること(蓮実はこのデリダによる「リシャール殺し」を非難している)も考えると興味は尽きない。
ともあれ、一九七二年にフランス語で出版され、今年(二〇一三年)になってやっと出たこの日本語版を読んで私がまず感じたのは、文学と哲学とがかつては今と比べてずっと近い場所にあったということである。というよりデリダは、ちょうど『パイドロス』で出不精のソクラテスがパイドロスの持っていた書物というパルマコンに誘惑されて都市の外に連れ出されたように、文学を文学の外へ、哲学を哲学の外へ連れ出そうとしていたと言うべきかもしれない。この人文諸学の「出国」(エグゾード)の運動はデリダだけではなく、たぶん当時の「68年の思想」と言うべきもの全体が推進したものだった。しかしその結果はどうだったのか。
今、日本の大きい書店に行くなら、現代思想系の本がある場所と文学系の本がある場所は遠く隔たっていることが分かる。人文諸学は「ニューアカデミズム」でシャッフルされた後、またそれぞれの狭い穴に閉じこもり、また社会もそれで危険なものに蓋ができて安心しているように見える。社会のことは社会学者にでも語らせておけば安心というわけだ。
デリダに関して言えば、そのテクストは、冷戦構造の解体が言われた1990年代以降、難解なレトリックを括弧に入れた上で、分りやすい倫理的・政治的なメッセージ性(「他者」への「応答」につとめようとすること)に特化して読まれるようになったように見える。それはポスト・コロニアリズム批評の流行などと連動し、実際デリダ自身もかなりの程度同調して行ったように思われる。だがそれは結局プラトニズム(ロゴス=音声中心主義)への回りくどい回帰にはつながらないか。たとえば日本における有力なデリダ研究者である高橋哲哉は、また日本の戦争責任に対する最もラジカルな批判者の一人であるとも言えるが、その戦争責任論は、「従軍慰安婦」の「生きた記憶」に「死んだ記憶」がどのように代補的に混り合っているかといった問いを排除した、単純に現前的な「正義」に立っているように見える。これは、もともとマイノリティの思想であるデリダの思想をマジョリティに属する人間が習得してしまうと、極度にマイノリティ(「公定マイノリティ」?)の代行者的にならざるをえないということだろうか。別の意味で東浩紀もそうだが、デリダを読むと、そのあまりの用心深い決定不能性に反発して、反デリダ的衝動に駆られ、明快に断定的に書きたくなってしまうのかもしれない。これもまた「父殺し」の一種だろうか。
もちろん、そもそもデリダの思想が正しいのかどうかも問われなければならないだろう。デリダをくぐり抜けた先が単純な正義への回帰(自身への疑いの可能性を祓い落としたという意味では、単純以上の絶対的に単一的な正義かもしれない)だとしたら、やっぱりロゴス=音声中心主義は正しいということなのではないか。『パイドロス』が説く「善き狂気」としての恋愛が正しいように。
ともあれ現在、『散種』が予言的に演じてみせた「本」からのエクリチュールの逸脱は、ありふれた日常の現実となっている。そしてここ二十年の間発達して来たインターネットは、「本」から「出国」した(あるいは追い出された)エクリチュールが新たに集う「約束の地」となっている。液晶(紙のエクリチュールでは文字を書き込むインク=パルマコンが液体で、書き込まれる白紙は乾いていたのに対して、ここでは文字が書き込まれる画面の方が液体化している)ディスプレイの「窓」の中に「窓」が幾重にも入れ子するその「襞」には、あらゆることが書き込まれ抹消される。インターネットは書物に代わる新たなネオ・プラトニズム的監獄なのか、それともエクリチュールのユートピアたりうるのか。そのことを考える上でも、『散種』が上演する書物からのエクリチュールの離脱の光景は、繰り返し参照されなければならないだろう。
初出=WANDERING BOOKS http://megalopolitan.jimdo.com/