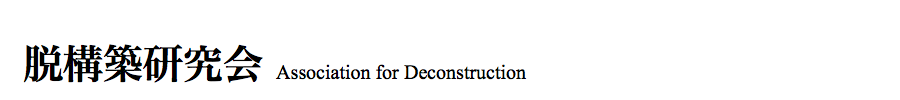Review

「読解の魔窟――エクリチュールとは何であり、そして何でないのか」
ジャック・デリダ『エクリチュールと差異〈新訳〉』合田正人・谷口博史訳、法政大学出版局、2013年
柿並良佑
一九六七年、フランス――「敷居(スイュ)」という名を持つ出版社から一冊の書物が世に送り出された。著者によって「仮縫い」と定義されたその論集は、既にフランスでは文庫化もされて久しく、おそらくは数え切れぬほどの手の中で繙かれ、摩耗した背からその紙片は次々に解(ほど)け、散っていったことだろう。
一〇年の後、その書物は日本語でも解読の試みを許すものとなる。上製二巻本の『エクリチュールと差異』(上巻、一九七七年;下巻、一九八三年)は、その著者ジャック・デリダの最初期の仕事を伝えるものとして、さらには「フランス現代思想」や「ポスト構造主義」と呼ばれる潮流を代表する著作の一つとして、その後長く読み継がれることになった。そこで提示された「差延」、「痕跡」、「現前の形而上学」批判、「刻印」等々、諸種の(準‐)概念ないし操作子を援用して繰り広げられる、時に織物(テクスト)の肌理への偏愛をも滲ませる読解の身振りは、やがてこの思想家の御紋(エンブレム)とも烙印(スティグマ)とも見做されていくだろう。
いわばデリダの「代表作」とも言える本書だが――しかしかくも「代理/表象」と格闘した思想家にこうした形容辞が相応しいだろうか――、それが今、新訳という過程を経て日本語を解する読者へ改めて届けられている。否、一巻本(および側註)という装いであればこそ、その本来の姿において、と言うべきかもしれない。その状況と歴史に見合う重みを携えた本書を手に取る新たな読者に向けて――しかしそれは初めてこの書を紐解く者を必ずしも意味してはいない――僅かなことながら事寄せておきたい。
「翻訳者の使命」。あまりに流布した句ではあるが、顧みられることの稀な作業の渦中にあって、それを反芻しなかった翻訳者がいるだろうか。鍵概念の訳語の選定、文体の決定、引用出典の確認、既訳との擦り合わせ、訳註の加味、等々。まして「新訳」となれば内容もさることながら全読書子の視線は否が応にもこれらの点に注がれよう。頁を繰れば瞭然だが、本訳書では全編を通じて訳註は最低限に抑えられた。既に註解の書物も数多手にすることができる現在、巻末の原註・訳註と本文を往還する労をとって繙読の律動を妨げるには及ばない(裨益するところの多い詳註もある。是非とも探されたい)。また(特に前半では)原語指示としてフランス語のルビが比較的多用されている点にも注意を喚起しておきたい。一つの語が複数の意味において用いられ、それに応じて訳し分けられていることを示す方途の一つだが、それを(程度問題であるにしろ)日本語に馴染んだ英語表記で行うのか、それともフランス語の原音に寄せることで敢えて微かな不協和音を忍び込ませるのか(一例を挙げれば「エレメント」ではなく「エレマン」)、それも議論を呼ぶ選択には相違ない。
ルビという形態であるか否かは措くとしても、仮名書きは些末な話題ではない。とりわけ本書の場合、書名が決定的な例となる。日本語という「一つの」言語体系に固有のものとならぬまま、時の経過による摩耗と拡散と濫費とに晒されながら、いつしかその内で一つの場を獲得してしまった語、それが本書の門口(スイュ)に掲げられた「エクリチュール」ではなかったか。新訳の扉にもまたこの語が訳されずに刻まれていることは、一つの提題として、あるいはまた躓きの石としても受け止めることができよう(対して、本文中ではいかに訳されているか、それも本訳書の読みどころである)。エクリチュールとは何であり、そして何でないのか――この仮名、日本語に正しく登録されぬまま、さりとてもはやフランス語でもないこの語と表記は今日なお、読者に新たなる不安を呼び起こし続けている。
もう一つの点、原語挿入に触れておこう。一例を挙げれば「着手する」と「傷つける」を意味する動詞entamerだが、デリダがしばしば援用したこの鍵語が本書にも撒き散らされていたことが、新訳(の前半)では明瞭になっている。無論、どの語を鍵語と見做し原語を併記するか、その案配は作品としての翻訳の完成度を大きく左右しようし、またその判断は本書以前以後に書かれたデリダの資料体(コルプス)全体との相互参照、および今日の研究の進展の影響を免れえない。その限りにおいて、この訳書もまた翻訳という名の煉獄ないし迷宮を容易に脱することはできまい。
そのことはまた、この書を眼下に据える読者にも言えることである。例えば、後に展開され論争にまで発展していった「隠喩」論という三稜鏡(プリスム)を通してこの著作に向かうこともできよう。いずれにせよ、今や新旧二種のレンズを通じて照らし出される初期デリダの横顔(シルエット)を頼りに、読者は書物の背後にいるはずの著者を捉える試みに再び乗り出す。しかしその二つの視線は複視のように、決して明瞭な像に収斂しないことも十分にありうる。その理由はデリダのテクストが(死後刊行の講義録等の形で)増殖を続けているという点には留まらない。この書物自体が包蔵する或る問題に存するのである。
フーコー論、レヴィナス論、アルトー論、バタイユ論等々によって編まれた一冊の論集、しばしばかように紹介されてきた――私も冒頭でその禁を犯した――この書物がしかしながら仮縫いではあれ一冊の「作品」だとするならば、畢竟そこでは何が語られているのだろうか。例えば敢えてこれを「デリダによるデリダ」論として読むとすればどうだろうか(ただし、自伝とそうでないテクストの境界をも問いに付す思想家にとって、「AによるA」式の立論がいかにして可能か、そのことも考え合わせるという条件も憑いてまわる。例えば『割礼告白』といった著作と本書はいかに呼応するのか)。ソクラテスの背後に鎮座し、筆を執らせ、息を吹き込むプラトンに倣うかのように、先達のテクストをして語らしめ、それら自身の結び目が解ける様を凝視して離さぬデリダ。その「消失の運動」を提示せんとするのは紛れもなくデリダその人でありながら、いざその消失点に目を向ければ常に逃れ去っているような書き手。現前と不在の往還ないし相互陥入を繰り広げつつ、それを書物の「内」のみならず、単に「外」に出るのでもなく、「限界」において上演するべく綴じられたこの紙葉群は、読解の魔窟に読者を引き摺り込んでいく。そこではもはや「存在」や「神」のような究極の語も歯止めにならない。コギトの狂気、笑い等々、哲学がその開始の地点において直ちに関わらねばならなかったものに譲歩しないこと――かくの如き狂える読解にあなたは身を投じることができるだろうか。
初出=『図書新聞』2014年6月21日/3163号