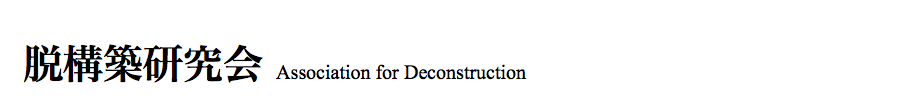Review

ジャック・デリダ『獣と主権者Ⅰ ジャック・デリダ講義録』(西山雄二・郷原佳以・亀井大輔・佐藤朋子訳)
立花史
日本で初めて、デリダの講義録の邦訳が刊行された。デリダは、若い時分からおよそ半世紀のあいだ、ほとんど毎年のように教鞭をとり続けたが、その講義のすべてがほぼ原稿の形で残されている。全四三巻とも言われる講義録出版プロジェクトの第一弾は、保存状態もよい最晩年の講義録(二〇〇一年‐二〇〇三年)である。
邦訳の方も第一弾ということで、訳者陣のただならぬ意気込みがうかがえる。丁寧な訳注にくわえ、講義一回ごと、そして主題ごとに詳述された訳者解説。巻末の付録「ジャック・デリダ講義録一覧」は、訳者陣が海外のアーカイヴやデータベースをフル活用して独自に作成したものらしい。年ごとに講義のテーマがリストアップされ、講義内容に直結する著作との対応関係も一望できる。今後の研究にとって必須の資料となりそうである。
本書を邦訳で読み直した私は、古代アステカの遺物として現存する火鉢をふと思い出した。それは三つの顔を持つ。真っ二つに割れた顔のなかに顔があり、中の顔も割れてさらにその中に顔があるという三層構造になった有名なものだ。この火鉢のように、本書のなかにデリダの第三の形象が垣間見えたと感じられたのである。“倫理的転回” の以前と以後という二種類のパブリック・イメージとはある意味で異なる相貌、それは教師としてのデリダの顔である。率直かつ明快。時にテクストの細やかな註釈を披歴し、時に軽妙な言葉で教室を和ませる。即興のように独特の間で語られながら、すべてが原稿の形で用意されたその独自の授業スタイルによって愛されてきた哲学者。講義録の刊行は、デリダのイメージのみならず、著作の読まれ方、研究のあり方を根本的に変えてゆくだろう。
開講の時期は、二〇〇一年の年末、つまり9・11同時多発テロとその報復として始まった対テロ戦争のさなかである。方や「悪の枢軸」と名指された諸国、方や国連の決定や国際法の違反をいとわない覇権的な主権国家アメリカ。WTCのビルに航空機が突っ込んで建物が倒壊する場面と、テロ首謀者の映像の亡霊的な出現が世界中に溢れ、その反復が大きな政治的効果を生み出す。そして「無限の正義」の僭称と、「バクダッドの狼」(サダム・フセイン)が率いる「ならず者」国家という寓話的かつ修辞的なレイベリングが、政治的なパワーゲームの一端をなしていた。
そんな折、ラ・フォンテーヌの寓話「狼と子羊」からの一節「最強者の理屈は、つねに最良のものである。すぐにそのことを示そう。」を引用しながら、デリダは初回の講義を始める。本講義では、『法の力』以来はっきりと主題化された「法の概念」の問い直しが核心をなしてゆくのだが、法を成り立たせ、法を縁取るフレームとして、獣と主権者という二種類の代補的存在に着目される(とりわけ第一回~第三回)。
主権性は、「国家の絶対的かつ永続的な権力」として規定した一六世紀のジャン・ボダン、法を作り出し法を宙づりにする権力と見なした二〇世紀のカール・シュミットを経て現在にいたるまで、国家を総べる主体性の形象である。そこに想定された自律性の契機が脱構築の対象となるのは明白である。実際、デリダにおいて主権性の問題系は古く、ヘーゲルとジュネを併読した『弔鐘』の時点から死刑と隣り合わせで論じられてきた。「死刑」の講義(一九九九年‐二〇〇一年)でも、哲学者たちの死刑擁護論が俎上に載せられる。例えばカントによれば、死刑は、主権性が十全に成立する例外的な契機だが、同時に主権性もまた、死刑を科すことのできない例外的な契機だった(合理性の自壊としての革命と弑逆)。
「獣と主権者」の講義では、主権が動物‐機械論的な国家機構との関係で再考される。デリダは、初めてホッブズを大きく取り上げ、リヴァイアサンたる国家を、人間の形をした巨大な人工動物というべき「補綴(ほてい)国家」として、またフロイトの文明論に依拠しつつ「補綴をつけた神」として描き出してゆく。ホッブズにとって国家は、神による権威づけを排して人間相互の信約に基づいた虚構であると同時に、神を模倣する機械、一種の「自動人形」のごときものである。こうした観点から国家の魂たる主権もまた、その自律性と自然性の根拠が仔細に検討されてゆく。
獣が、本書のもう一方の軸をなす。デリダは、政治哲学には執拗に獣たちの表象がつきまとってきたことを問題にする。獣のレッテルを貼られるのは、法に従わない無法者であったり、覇権をもつ主権者であったり、あるいは主権者にとっての民であったりと様々である。「人間は人間にとっての狼」というホッブズの文句はよく知られている(デリダによれば、実際には古代ローマの劇作家プラウトゥスにまで遡ることができる)。獣のアナロジーは、人間と動物を近づけることによって分断する。デリダがルソーとともに摘出するのは、人間の共同体を動物の共同体に還元する身振りである。そこには、他者を法の外部へと放逐し、非人間的な獣性の境界線を設定しようとする暴力が潜んでいる。
このように法の領域は、主権性と獣性という上下二つの法の外によって担保される(同じく法の外であるがゆえに時に主権者もまた獣として表象される)。デリダがアリストテレスの人間学からの訣別を目指すのもこの文脈においてである。というのもハイデガーが指摘するように、政治的かつ理性的な動物(ゾーエーを有する者)としての人間概念自体が、人間に優越した神と人間より劣等な生きものとのはざまで規定されるからである。
アガンベン批判(第三、十二、十三回)もまたアリストテレスに関わる。ただしデリダが問題にするのはまずもってアガンベンが出来事を思考する際の「論理とレトリックの連節方法」である。過去のある一点に始原を設定してそこからの「直線的歴史」を記述する身振りは、すでに主権性の罠に陥っているとデリダには映る。またアリストテレスのゾーエーやホッブズの「狼」を、一義的に「剥き出しの生」へと還元するアガンベンの議論に、かつての師は表象や翻訳の問いに対する鈍さを感じとらざるをえない(逆に言えばデリダにとって人間と動物の関係は「翻訳」の問いである)。
本書は、独自の主権論や動物論というより、むしろ従来のものの脱構築という点で示唆に富む。ラカンやドゥルーズは、デリダと同じく主体性の人間学を批判した側の思想家だが、前者の残酷さの概念と後者の愚かさの概念を糸口として、彼らの議論にひそむ人間中心主義が摘出される(それぞれ第四回と第五回)。
ただし「愚かさ」(la bêtise)の問いは、「獣」(la bête)と相俟って、デリダにおいても重要である(第六~第一〇回)。人物や宗教に向けられるような「侮辱」としての愚かさとは区別されて、「代補」としての愚かさが論じられる(愚かさは、頭部を有する生物のみが共有する性格とされる)。この文脈で、二種類の操り人形が愚かさの形象として登場する。一方は、愚かさに殺されないようにムッシュー・テスト(ヴァレリー)が自分の中で殺し続ける操り人形であり、際限なく愚かさと向き合う主権性である。もう一方は、リュシール(ツェラン/ビューヒナー)という名の生身の女性から生成変化を遂げた、子供をなさぬ芸術としての、操り糸を断ち切った人形であり、デリダはここで主権性の彼方を思考する。とりわけそれが、死刑台で「国王万歳!」と叫ぶ「抗う言葉」やその「不条理なものの威厳」に見出される点で、主権性の問いが、死刑や革命、さらには詩との関係で論じられている。またこの主権性の彼方は、翌年の講義の重要な主題となる。
ところでアステカの火鉢の顔は、一番外が死期を、真ん中が成熟期を、三番目が若年期を象徴しているらしい。しかしデリダが大学制度の周縁にとどまり続けたことを考えると、青くさい猿のような三番目の顔よりもむしろ、同じくアステカに棲息した別の獣の存在に思い至る。それは、かつてデリダを紹介する際に用いられたル・モンド紙掲載の風刺画のカイマンである(カイマンは高等師範学校の教官を指す隠語でもある)。
初出=『週刊読書人』2015年2月20日号