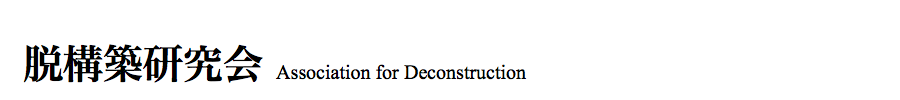Review

エレーヌ・シクスー+ジャック・デリダ『ヴェール』郷原佳以訳、みすず書房
西山雄二
本書は、雑誌「コントルタン」の特集号「ヴェール」への寄稿文だったエレーヌ・シクスーの「サヴォワール」とこの掌編をめぐるデリダの「蚕」から編まれている。
「サヴォワール」は、「彼女」が近視という感じられないヴェールを被った状態をめぐる「触れることの詩」である。「彼女」は手術によって近視を矯正するものの、ヴェールそのものから身をほどかれることで、自己の他者性の喪失に気がつく。「眼で世界に触れる」新生の契機と近視のヴェールという喪の経験を通じて、可視/不可視、能動/受動、自己/他者の様相が描き出されるのである。
デリダの「蚕」はシクスーの創造的注釈にとどまらず、自伝的イメージが散りばめられた彼自身の真理論となっている。ヴェールの真理論といえば、ハイデガーが依拠したギリシア的アレーテイアが有名である。ハイデガーは対象物との認識の一致ではなく、遮蔽物によって真理が覆い隠され忘却されているという真理観を提示した。デリダは誇張法的な口調で、ヴェールによる隠蔽と開示という真理論には疲労しており、消尽しているとさえ不平を漏らす。ヴェールの歴史から遠くへと再出発するためにデリダが取り上げるのが、ユダヤ教で男性が着用する祈祷用ショールのタリートだ。どの男性も自分自身のタリートをもっており、秘密の仕方で神的な言葉を自己へと想起させる。それは衣服を纏うというよりも、類例なきもうひとつの肌を所有する経験に近く、包み込まれた身体は法を呼び戻すという絶対的な秘密を分泌する。ヴェールによる隠蔽と開示とは異なり、タリートは反復される法を一回限り私へと出現させ、接触させるのである。
ただ、訳者解説で指摘されるように、ギリシア的ヴェールからユダヤ的タリートへの脱構築という単純化は不適切だろう。動物の皮から作られる点でタリートもまた供犠の論理を孕んでおり、ヴェールの歴史としての真理に汚染されているのだ。また、ヴェールの形象はギリシアには限定されない多様な解釈を誘発する。キリストの死に際して真中で裂けた神殿のヴェールをめぐって、ヴェールはむしろ覆いの終わりを露呈させるために引き裂かれたのではないか、と示唆される。また、フランスではイスラム教的なヴェール着用が非宗教性(ライシテ)の原則に抵触するという論争が起こっており、イスラム的なものへの不寛容への状況介入も考慮されている。
表題に示された蚕はタリートをめぐる考察を見事に引き継ぐ形で、最後に、語り手の幼年時代の自伝的描写とともに集約的に描き出される。真理論に即して蚕という自伝的動物を記述するデリダの圧倒的な詩的イメージには改めて驚嘆せざるをえない。蚕は桑の葉を食べて脱皮を繰り返し、繭の中に閉じ篭り、自らを絹として産出する。植物と動物の狭間で変成し、性的差異が識別しがたいこの絹の虫は、自らを作品化することで作品を産出する点で絶対的な自然と文化を指し示す。自己内を自己外へと生み出し、自己の根底で消失していく蚕は、成熟の時間のなかで自己の秘密を分泌させる。独特な自己性と時間性を通過するこの生きものの形象を通じて、別の仕方での真理論が告白されるのである。
訳者が十年の歳月をかけた本書は、的確な訳注と解説とともに実に成熟した訳書として洗練されている。解説では原著作成立の説明、問題の概観、著者の過去の著作への参照、先行研究の整理、訳者自身の考察が控え目な筆致で列挙され、多くを学ぶことができる。とりわけ、デリダのテクストを蚕のモティーフに即して「脱構築の告白」とする主張は斬新で説得的だった。シクスーとデリダのテクスト対話が適切な仕方で日本語に移されることで、実に美しい佇まいの書として仕上がってると言える。訳者自身が特異な自己性と時間性を経ることによってしか、良質な翻訳は生まれないのではないか、と考えさせられた。
初出=『週刊読書人』2014年5月23日号(第3040号)