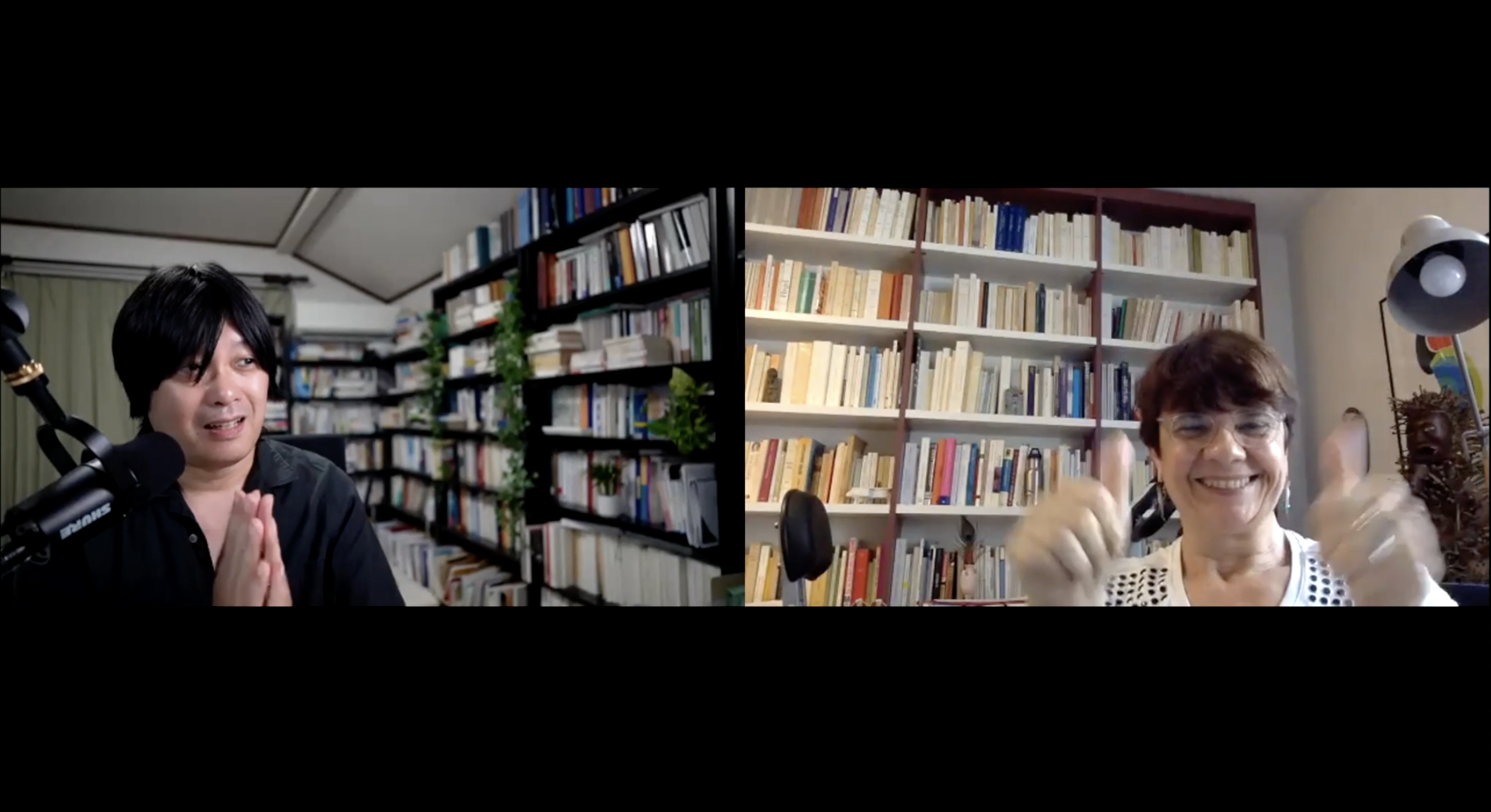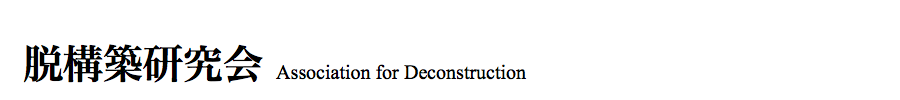Reports
講演・共同討議「カトリーヌ・マラブーの哲学」
(報告=西山雄二、中村彩)
2021年9月10日、Zoom配信にて東京とパリを結んで、共同討議「カトリーヌ・マラブーの哲学」が実施された(270名の参加)。Catherine Malabou(イギリス・キングストン大学、教授)氏を招いた、講演会と討論の二部構成である。通訳を渡名喜庸哲氏、馬場智一氏に依頼したが、両名とも見事な通訳で大変助けられた。脱構築研究会の主催で、日仏哲学会の提案型ワークショップの枠組みでおこなわれ、東京大学「共生のための国際哲学研究センター」(UTCP)、東京都立大学の後援を受けた。詳しくは、丁寧に編集した動画アーカイブをご覧いただくことにして、以下、討論の簡単な概略だけを記しておく。
-
YOUTUBEでの動画→https://youtu.be/IPaJXIRggYQ
-
第1部は、今年8月に日本語訳が出版されたマラブーの最新作『抹消された快楽 クリトリスと思考』をめぐって行われた。
-

-
マラブー氏がまず著書の第1章を読み上げる形で講演をおこなった。この章は、クリトリスと女性的なものについて考察した本書全体の導入となっている。曰く、クリトリスはそれ自体が「完成されたもの、統一されたもの、集約されたもの」(日本語訳14頁)なのではなく、様々な隔たり――ヴァギナとの、ペニスとの、ファロスとの隔たり、あるいは生物的なものと象徴的なもののあいだの隔たり、様々なフェミニストやフェミニズムのあいだの隔たり等――においてしか存在しえない。にもかかわらずクリトリスが特権視される理由は第一に、男性思想家たちがクリトリスについてほとんど語ってこなかったことである。そして第二に、この問題を解決しようとしたボーヴォワールやイリガライ、ロンツィといった女性哲学者たちも、その後のフェミニストに批判され今となってはある意味で抹消されてしまっているからである。そこでマラブーが本書でめざすのは、クリトリスをめぐる複数の声に耳を傾けつつ、「女性的なものを語るという極度の困難と極度の緊急性のあいだで自分のバランスを保」(21頁)つことである。
-
その後、司会の西山雄二(東京都立大学)がクリトリスという主題に関心を持つようになった理由、およびマラブーのフェミニストとしての立場に関する質問をした。これに対しマラブーは、クリトリスというテーマは彼女が近年取り組んできた、生物学的なものと象徴的なものの関係の脱構築という作業のなかに位置づけられると説明した。また自分は様々なフェミニズムを和解させようとは思わないが現在の分断を悲嘆していると述べた上で、「女性」という概念の可塑性、それが時代や理論ごとにどう再定義され変形していったかに興味があるということを述べた。
-
-
次に中村彩(リヨン第2大学)がまずフェミニズムと精神分析の関係について質問をした。フェミニズムにとって精神分析の理論的な視座は重要だが、実践面では現代においても両者が対立することも多い。両者はどのように折り合いをつけられるのか。次に、『抹消された快楽』の10・11章で扱われている女性器切除とクリトリスに関する考察は、スピヴァクが提示した「象徴的なクリトリス切除」をめぐる議論に近いものと思われるが、どう考えているかを質問した。
マラブーは、スピヴァクのテクストについては知らなかったが方向性は同様であろうと述べた。精神分析については、フロイトがジェンダーアイデンティティの構築を語る際に異性愛が規範化されていることや、ラカンにおけるファルス中心主義などがジェンダー論の側から問われるようになった。そうした点については精神分析を変えていかなければならないが、精神分析は解放の力を持っているし、無意識の概念は可塑的であるため、そうした変容は可能だろうと述べた。
-
-
郷原佳以(東京大学)は、プラトン『饗宴』やサルトル『存在と無』に見られるような、愛を挿入と生殖に結びつける哲学の男根中心主義の問題、そしてそれに抗するマルタン・パージュのエッセイ『挿入の彼方で』やイリガライの思想を確認した上で、クリトリスを特権化する必要はあるのか、あるいは身体のあらゆる部位は象徴的にクリトリスであると言えるのか、という質問を投げかけた。さらに文学においては、サド、クロソウスキー、ジュネのほか、仏訳もある松浦理英子の『親指Pの修業時代』が重要であると指摘した。
これに対しマラブーは、松浦の小説の紹介に感謝したうえで、セクシュアリティの成熟の問題について論じた。フロイトにとって女性のセクシュアリティの成熟は男性器のヴァギナへの挿入によってのみ可能であり、クリトリスの快楽は未熟と見なされた。このことは多くの問題を生んだと考えているが、かといって自分はクリトリスを特権化したいわけではなく、クリトリスはいたるところにあり、また性的に成熟するとは自分なりに快楽を見出すということである、と応答した。
-
第2部の共同討論「カトリーヌ・マラブーの可塑性の哲学」では、マラブー哲学全体について7名との討議が展開された。
-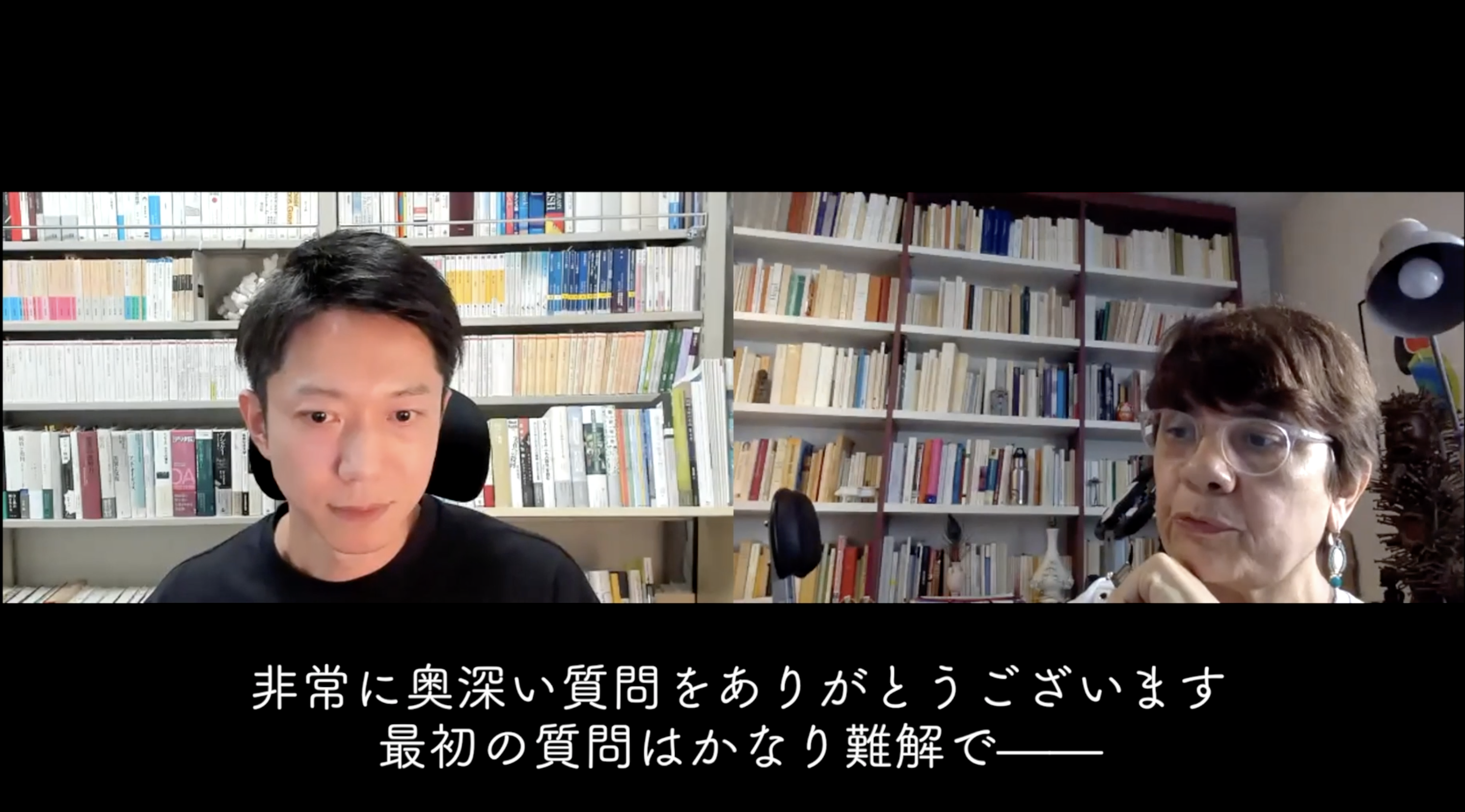
-
まず星野太(東京大学)から、「生(命)」の概念に関する二つの質問が投げかけられた。マラブーは「論文「ただひとつの生」(2015年)において、象徴的な生/生物学的な生という区別とは無縁な「ただひとつの生(une seule vie)」があると主張している。「生物の構造が露わにするさまざまな可能性——そこには、世代間の順序の転覆、遺産継承という概念の複雑化、血統の問いなおし、死や時間の不可逆性に対する新たな関係といったものがあり、さらには、それを通じて新たな有限性の経験がもたらされる」。生命と技術が絡み合うこの経験に対して、哲学は何をなすことができるのか。また第二の質問として、「可塑性」概念がもつさまざまな水準のあいだに差異はあるのか、と問うた。
マラブーは、自分が哲学史をどう考えているかについて返答することで、この複雑な問いに応じたいと断った。哲学史は科学の進歩とともに、存在と生との関係の問いによって突き動かされてきた。プラトンとアリストテレス、ハイデガーとデリダの二例が引かれ、現在の脳生物学まで、生がつねに存在を挑発し哲学はこの衝撃に応答するのだ。可塑性の諸差異の問いについては、可塑性は歴史的なもので、時代や言語によって異なって いるものの、存在の自己変容という問いはつねに同じであるとした。
- 
-
佐藤朋子(金沢大学)は、『新たなる傷つきし者』について二つの質問をした。まず、トラウマとその「破壊的可塑性」——形の破壊によって創造する能力——はフロイトの著作全体を通じての〈思考されざるもの〉なのか。マラブーはトラウマのような偶発事による心の破壊をフロイトが認めなかったとするのに対して、佐藤はフロイトの思索に見出される「痛み」の理論に着目するべきではないかと問う。また、第二の質問として、トラウマによって心的な地平が破壊される可能性を主張するために実証的な科学は必要だろうかと問うた。
マラブーはフロイトにおけるトラウマ理論も、痛みの理論も否定したいわけではないとした上で、みずからの問題関心を「出来事はどこから到来するのか」とシンプルに示した。外側から生じる偶発事を心の内的な傷に翻訳し尽くすことなく、いかに考えるのか、という問いである。第二の質問に対しては、脳科学と精神分析の双方から考察を深めたいとした。
-
-
宮﨑裕助(専修大学)は『明日の前に』をめぐる議論に対して疑問を呈した。カントにおける超越論的なものの生物学化をいかに説くのか。マラブーは後成説に着目するが、理性の統制的使用という批判哲学の基本的な議論は抜け落ちている。理性の後成説も、理性がアプリオリな理念として超越論的だが、統制的に働くと考えればより明快に説明できるのではないか。
マラブーは、カントによる後成説の表現はたんなる隠喩やアナロジーではなく、自然の後成説をまさに本質的に適用している、と自著での主張を確認した。その上で、第三批判で、統制的判断が価値をもつのは後成説によるからである、とした。この部分の対話については、時間の制約もあり、質問に発展的に答えられていないようにみえた。
-
-
小川歩人(大阪大学)は、まず「性的なものの他者」について問うた。セクシュアリティとは他なるものであるセレブラリティ(脳事象)は、現在のマラブーのフェミニズム論といかに関係づけられるのか。また、マラブーの目下の研究テーマであるアナーキズムに関して、直立したファルスと見紛うような超強力でアナーキーなクリトリスとはいかなるものか。エコノミーのうちで他なるエコノミーを見分けることはいかにして可能なのか、と問うた。
第二の質問への答えとして、マラブーは、現在のアナーキズムが「生の一般的水平化(Uber化)」に由来するとする。人々の生を管理する支配的な拠点はもはやなく、この非中心性は脳のあり方にも対応する。生と技術、脳のアナーキーな非中心的状態を私たちは日々生きていると言える。
-
-
藤本一勇(早稲田大学)は四つの質問を畳みかけた。まず、ファルスのクリトリス化は可能か、ありうるとしたら、どのような効果がもたらされるのか。第二に、クリトリス問題に関連して、オナニーズムをどう分析し、いかに肯定すればよいのか。第三に、クリトリス享楽を享楽主体としての女性の再主体化(従属主体を脱却する主体化)の鍵とした場合、一種の享楽中心主義に陥いる恐れはないか。そして、科学技術によって生殖と性とが切り離された時、「性」の問題は存続するのか。
マラブーは矢継ぎ早に応答を返したが、テクノロジーが伝統的なセクシャリティを終結させるのではなく、むしろ同じメカニズム、同じファロス中心主義を強化するのではないか、とした点は興味深かった。
-
-
増田一夫(東京大学名誉教授)は、デリダとマラブーとの関係から話を切り出し、人新世における可塑性にまで議論を展開し、次のような問いを発した。哲学と生物学あるいは神経生物学との境界線を踏まえると、脳はたんに人間的なものだろうか、より広義に動物的なものでもあるのではないか。人新世の危機的な状況を脱するために、私たちの脳はいかなる新たな addiction を獲得すべきか。
鵜飼哲(一橋大学名誉教授)は、昨今幅を効かせている「レジリエンス」概念を取り上げた。物理学から神経生理学を経て心理学まで、その適用範囲が広がっているこの概念に対して、マラブーは批判的な考察を加えてきた。マラブーによる可塑性の思考を、いわばレジリエンスとレジスタンスのあいだで、どのように方向づけるべきか、これまでの方向を再調整すべきか。
- 
-
増田と鵜飼のコメントに対するマラブーの返答は、その表情や息遣いも含めて感慨深いものなので、ここで安直に文字として定着させることは控えておきたい。ともかく、全9名のコメントと質問に対して、マラブー氏は真摯に考え、ときに戸惑いつつも、丁寧に回答を寄せてくれた。貴重な討論の時間をもてたことについて、参加者のみなさんにはあらためて感謝申し上げる次第である。
-