□ 2020年度研究成果
1. 曲げ降伏破壊する鉄筋コンクリート隅柱梁接合部の軸崩壊機構に関する研究
北山和宏・石川巧真・富澤良介・晋 沂雄(明治大学)
建物の崩壊は軸力支持能力の喪失によって生じる.軸力を支持するのは主として柱であり,一本の柱は層間の内法部分とその上下の柱梁接合部とに分けられる.地震動を受ける鉄筋コンクリート(RC)建物の崩壊は,日本では柱内法領域のせん断破壊や柱頭・柱脚の曲げ破壊による層崩壊によってもたらされることが多かった.しかし国外では,柱梁接合部が柱軸力を保持できずに建物の崩壊を招いた例が多々存在する(例えばMoehle 2003,Park・Mosalam 2013).国外の事例では,柱梁接合部に横補強筋が配筋されない,あるいは柱断面が小さい等の構造設計法の抱える問題を指摘でき,日本とは事情を異にすると見られてきた.
ところが2016年の熊本地震によって,5階建てRC庁舎が外構面の柱梁接合部の軸崩壊によってほぼ倒壊するという被害(向井 2016)が日本でも出現した.このRC庁舎は旧耐震設計基準に基づいて設計されたが,柱梁接合部が曲げ降伏破壊した後にその軸崩壊が生じたと推定される(斎藤・向井・塩原 2018).
RC柱梁接合部の曲げ降伏破壊は塩原(2008)によって提唱され,接合部降伏破壊を検討するための実験研究が行われ始めた.ただし,曲げ降伏破壊した柱梁接合部の軸崩壊挙動の研究はほとんどなく,ト形の平面柱梁部分骨組に水平力および変動軸力を載荷する実験(村上・前田ら 2017)が挙げられる程度である.実建物では三方向地震動を受けるが,立体隅柱梁部分骨組に二方向水平力および一定圧縮軸力を載荷する実験(片江・北山 2015)において柱梁接合部内の柱主筋が座屈して軸崩壊の兆候が見られたとする報告があるに過ぎず,系統立った実験研究は未だ行われていない.柱梁接合部が軸崩壊するときの骨組の限界変形についてはHassan・Moehle(2012,2013)の研究のみである.
そこで, RC骨組内の柱梁接合部が地震動によって曲げ降伏破壊した後に軸崩壊する過程を静的載荷実験によって追跡し,軸崩壊に至る変形性能および水平耐力保持性能の精査を研究の目的とした.実験では二方向水平力および変動する柱軸力を立体隅柱梁部分骨組試験体3体に与えた.上柱の軸力は引張り(引張り軸力比0.20)から圧縮(圧縮軸力比0.13)まで変動させた.接合部降伏破壊を提唱した塩原によれば,柱中段筋は接合部降伏破壊の防止に役立ち,前年度の実験で柱中段筋の軸力保持能力が確認されたことから,柱中段筋の本数を実験変数とした.コンクリートの圧縮強度は67MPa程度であった.
実験では層間変形角1.5%で接合部降伏破壊によって最大耐力に達したのち,水平耐力が低下した.層間変形角3%(D16の柱中段筋が各面1 本の試験体)から4%(D16の柱中段筋が各面2 本の試験体)で柱の圧縮軸力を保持できなくなって柱梁接合部の軸崩壊に至った.隅柱梁接合部の軸崩壊は,梁が取り付かない接合部出隅の柱主筋の座屈に伴い,下柱に対する上柱の回転角が増大することによって生じた.これは上柱および下柱が接合部を中心に「く」の字状に傾く観察結果と一致し,隅柱梁部分骨組に変動軸力(上柱軸力比0〜0.13)および二方向水平力を導入した前年度実験で見られた軸崩壊機構と同じであった.
柱主筋径を同一のまま中段筋の本数を柱断面の各面1 本から2 本に増やすことによって(柱主筋比は1.6%から2.5%に増大),柱主筋座屈時の層間変形角は2%から3%まで増加し,柱主筋の局部座屈が抑制された.軸崩壊時の柱頭水平変位累積値は16% 増加し,骨組の水平変形性能向上および柱梁接合部の軸崩壊防止に寄与した.ただし,柱主筋比が同等の場合(1.6%程度),柱中段筋本数を増やしても柱主筋径を小さくすると,接合部横補強筋および柱中段筋の降伏が早期に生じて柱梁接合部の損傷が激化し,接合部軸崩壊の抑止には不利であった.
上記の実験実施と並行して,柱梁接合部の曲げ降伏破壊から軸崩壊に至る力学モデルを検討した.しかし,柱梁接合部が降伏破壊後に軸崩壊するときの骨組の限界変形を定量的に評価する手法を提示するまでには至らなかった.今後の検討課題とする.


2. 鉄筋コンクリート梁の曲げひび割れ幅の評価に関する研究
北山和宏・トゥブシントゥグス
曲げモーメントのみを受ける鉄筋コンクリート(RC)梁に生じる曲げひび割れ幅を定量的に評価する手法として,鈴木・大野(1981)の提案式がある.この提案手法はひび割れ発生状況が安定した定常状態にあるときを評価対象としたが,そこに至るまでの非定常状態においても適用可能であることが彼らの研究によって示されている.
せん断力が作用する場合でも,梁のせん断スパンがある程度大きければ長さの限定される範囲においてはほぼ純曲げ状態と見なせる.そこで本研究では,十字形RC柱梁部分骨組の梁部材(せん断スパン長さ:1425mm)のヒンジ領域(梁付け根の梁せいと同じ長さ[400mmあるいは250mm]の範囲)を対象として曲げひび割れ幅の実測値と鈴木・大野の提案手法による評価値との比較・検証を行った.
対象とした試験体は王磊(2011)による3体および胡文靖(2019)による2体である.梁せいは400mmおよび250mmの二種,梁主筋径は13mm,19mmおよび22mmの三種である.コンクリートの割裂引張り強度は2.7MPaから3.4MPa,コンクリートの弾性剛性(圧縮強度の1/3強度時の割線剛性)は174GPaから205GPaであった.実験における曲げひび割れ幅はデジタル・マイクロスコープによって測定した.ただし梁危険断面でのひび割れ幅は柱梁接合部からの梁主筋の抜け出しの影響を大きく受けるために検討から除外した.
曲げひび割れの平均間隔は,鈴木・大野による評価値は125mm程度であったが,ヒンジ領域の実測値は40mmから102mmとばらつきが大きく,評価値は実験結果よりも過大であった.使用限界時(除荷したときの残留ひび割れ幅が0.2mmとなる加力サイクルの,直前の載荷ピーク時)の梁主筋の平均ひずみについては,鈴木・大野による評価値がひずみゲージによる実測値の1倍から2/3倍となり,実験結果をほぼ妥当に評価できた.使用限界時の曲げひび割れ幅の実測による平均値は鈴木・大野による評価値の0.65倍から1.36倍となり,ばらつきが大きかった.
 
3. アンボンドPCaPC外柱梁部分骨組における梁部材の復元力特性の評価法
北山和宏・晋 沂雄(明治大学)
プレキャストの鉄筋コンクリート柱および梁にアンボンドPC 鋼材を貫通させ,緊張力を導入することで両者を一体化するプレキャスト・プレストレスト・コンクリート(PCaPC) 圧着工法がある.この工法で構築されたト形の外柱梁部分骨組において,PC鋼材が降伏せずに梁コンクリートの曲げ圧壊により最大耐力に至る場合を対象に,その復元力特性の骨格曲線を定量的に評価するマクロ・モデルが筆者らによって既に提案された.提案手法は復元力特性における主要な三つの特性点,すなわち柱と梁との圧着接合面での離間が発生する点,アンボンドPC 鋼材が弾性限界に到達する点および梁のかぶりコンクリートの圧壊開始によって到達する終局状態点のそれぞれの耐力および変形を求めることができる.
外柱梁部分骨組では,梁断面の上下に配置されたPC鋼材の伸び量に差を生じる点が十字形部分骨組とは異なる.そこで梁断面の圧縮側の縮み量および引張り側の伸び量を用いた変形の適合条件から,上下のPC鋼材のひずみを定めている.
本研究では提案した評価手法の優位性を示すために,既往の同種の評価手法とともに実験結果を用いた精度検証を実施した.比較に用いたのはPampanin(2001)および津田(2015)によって提案された方法であり,前者は繰り返し計算による収束を要する一方で,後者は直接評価が可能である.曲げ終局時の耐力および変形については,筆者らによる提案手法は実験結果を精度よく評価したが,他の二つの手法では実験結果を過小に評価した.特に他の二つの手法によって得られた終局変形は実験結果の1/4から1/3と大幅な過小評価であった.
提案手法の正確性および設計への適用可能性をさらに検証するために,提案したマクロ・モデルを用いた多変数解析を実施した.選定した変数は,梁断面内に設置された上下のPC鋼材間の距離(0および梁せいの0.8倍),PC鋼材の量(鋼材係数として0.6以下)およびPC鋼材に導入する初期張力(PC鋼材の降伏点の0.4倍から0.9倍)の三つである.解析に必要な他の諸元は筆者らが実験した試験体PCJ04と同一とした.多変数解析の結果, PC鋼材への初期導入張力の大きさは終局限界状態点(耐力および変形)にほとんど影響を与えなかった.PC鋼材への初期導入張力の適切なレベルは鋼材間の距離にも依存した.例えば,上下のPC鋼材を断面中央にまとめた場合に鋼材係数を0.15とすると,コンクリートの早期の圧壊を避けるためには初期導入張力比を0.72以上にする必要があった.いっぽう,上下のPC鋼材間の距離が梁せいの0.8倍の場合に鋼材係数を0.15とすると,PC鋼材の早期の降伏を防ぐためには初期導入張力比を0.85未満にしなければならなかった.
4. 京都会館の保存活用を目指した再整備事業の意思決定過程に関する研究
北山和宏・嶋田ミカイル久幸・竹宮健司・角田 誠・木下 央・猪熊 純
文化的価値があると判断されたモダニズム建築の保存・再生および利活用は,地球環境の保全ともかかわって極めて今日的な課題である.その保存・活用の方針を決定するためには多数のステーク・ホルダーのあいだで様々な意思の確定を経る必要があるが,その意思決定の過程は十分に検証されてはいない.そこで本研究では,形態の変更を伴う改修が行われて再生された京都会館(前川國男設計,1960年竣工)を事例として取り上げ,再整備事業(2015年8月完了)の一環として行われた調査や検討の事実関係を整理することによって京都会館再整備事業の意思決定過程を明らかにした.
京都会館の再整備の過程を既存建築調査,再整備検討,基本計画策定および設計の四段階に区分して,それぞれの検討内容,要求項目および決定事項を抽出し,再整備計画の時系列認識を確定した.再整備の方針を決定した主要因が,世界水準のホール機能の充実および二千席規模の客席の維持の二つであることを示した.これによって第一ホールは全面的に改築されたが,琵琶湖疏水側のファサードを従前と同じ素材を用いるなどによって当初のデザインを継承することを目指した.
|

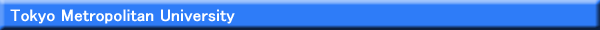
 トップページ > 研究について > 2020年度研究成果
トップページ > 研究について > 2020年度研究成果
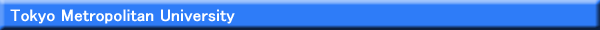
 トップページ > 研究について > 2020年度研究成果
トップページ > 研究について > 2020年度研究成果