 トップページ > メモランダム2009 トップページ > メモランダム2009
このページは北山の日々の雑感などを徒然なるままに綴るコーナーです。今まで、「掲示板」に載せていたような事柄も、これからはこちらに記述しようと思います。なお内容が内容なので、更新は不定期です。(2009年1月5日)
歳末点景 (2009年12月28日)
世間は今日で多分仕事納めでしょうね。私は若い頃のように年末・正月もがんがん仕事する、というスタイルはかなり前に廃棄しました。休むときはのんびり休んで英気を養いたいですな(でも、子供の遊ぼうよ〜攻撃から逃げるのは不可能ですが、、)。本当は仕事納めでスパッと今年の仕事はおしまい、としたいのですが、当然ながらそうは問屋が卸してくれません。昨日の日曜日には建築学会から自宅に宅急便が来て、RC規準の校正の締め切りが来年早々にセットされていました。宅急便が来たときに、年末なのでこりゃ丸餅かな、と一瞬儚い幻想を抱きましたが、クロネコのお兄さんが「建築学会からですよ〜」と爽やかに言うのを聞いて、なんだ宿題か、とがっかりしました。
昨日は、ボコボコになった我が家の車の板金修理が二週間の大手術の末にやっと終わって返ってきました。トヨタのディーラーに頼んだので、さすがにぴかぴかになっていましたが、中古車価格としての査定額の3倍近い修理代を支払ったのだから、まあ当然でしょう。代車として使っていたトヨタのiQという小さい車が、結構しっかりしていたのにはちょっとビックリしました。特に1.3リッターで革シートの試乗車(これを代車として1週間使いました)はエンジン・パワーにも余裕があって、超短いボディによる取り回しの良さと相まってセカンド・カーとしては極上だな、と思いました。でも、2ドアなので乗り降りはし難いし、後ろの席は申し訳程度で子供しか座れません。トランクも無いに等しいです。
今日の午後には、RC十字形柱梁接合部の試験体の作製打ち合わせをする予定です。入部工業(現アシス)の村上社長に学校に来てもらいます。最近は大学事務当局による納品チェックが厳しくなったので、契約通りの期日に試験体を作ってもらえるか、相当に危惧しています。村上のおじさん、宜しく頼みますよ(村上社長のお話では、会社は新しく生まれ変わった、とのことでした)。
PS三菱の浜田公也部長には、プレキャスト部分骨組実験の途中報告やPC鋼より線へのひずみゲージ養生実験の報告をする必要があって、年末から年始にお会いする予定です(今日の夕方、大学においでになりました)。
では、皆さんよいお年をお迎え下さい。
今年読んだ本ベスト3 (2009年12月19日)
今年もあと十日ほどとなりました。2009年に読んだ本の中で、ベスト3+αを挙げてみます。
田中克彦著『ノモンハン戦争 -モンゴルと満州国』(岩波新書、2009) この本については、このコーナーで以前に書いたので省略しますが、ノモンハン戦争の意義や歴史上の位置づけについて学ぶべきことが多かったことを再度強調しておきます。
新田次郎著『武田勝頼』(講談社文庫、1983) 同じ著者による『武田信玄』を以前に読んでから、「甲斐戦国もの」に興味を持つようになった。大学がある八王子は甲州にも近く、八王子近辺にも武田信玄ゆかりの武将が居を構えていたであろうし、江戸時代になって帰農した旧武田武士団が多摩地方の甲州街道沿いに住んでいた(八王子千人同心など)ことも身近に感じさせた。
武田晴信(信玄)は父信虎を駿河国に追放し、また長男義信を幽閉して死に至らしめるなど、非情なひとであったが戦国武将としては卓越していた。諏訪四郎勝頼は、そんな偉大な父親を持ったことこそが不幸の源であったようだ。武田家を滅亡に追いやった張本人としての勝頼は無能の凡将として語られるのが常であるが、真実はそうではなくて彼もまた父親に劣ることの無い優れた武将であった、というのが新田次郎の小説である。
武田家を滅ぼした主要なみなもとは、従兄弟の穴山梅雪や信玄の弟であった逍遥軒信廉などの一族であった、というのがその主張である。武田が押さえていた金山からの金の産出が激減し、諜報活動を支えていた碁石金(きん)が不足して情報戦に敗れた、という設定がなかなか新鮮だった。
コンスタンチン・サルキソフ著/鈴木康雄訳『もうひとつの日露戦争』(朝日選書、2009) 本書は、日露戦争当時の日本海海戦におけるロシア側の当事者であるロジェストヴェンスキー提督が、日本海へ至る航海の途上に故国へ当てた手紙を読み解いたものである。この三十通の手紙は2004年に新たに発見されたもので、その内容は大変に興味深かった。
われわれにとっては日本海海戦と言えば連合艦隊司令長官の東郷平八郎がヒーローであり、その敵役としてのバルチック艦隊のロジェストヴェンスキー提督は、司馬遼太郎の『坂の上の雲』(現在、NHKで放映中なので急に有名になったが)では為すところ無く破れた無能の将軍ということになっている。いわゆる司馬史観は良くも悪くも我々現代の日本人に大きな影響を与えていることは論を待たず、ロジェストヴェンスキー提督も司馬遼太郎によって不当に低く評価されたひとり、ということがこの本を読むと分かる。
わずか百年前の出来事にもかかわらず歴史の真実が闇に埋もれていたことに驚くし、歴史上の通説がある特定の個人の説諭によって広く流布して、いつのまにか真実であるかのように扱われるというメカニズムには、十分に注意する必要がある、ということを強く認識させてくれた書籍である。
海道龍一朗著『北條竜虎伝』(新潮文庫、2009) 戦国前期に関東に覇を唱えた北條家を扱った小説で、主人公は三代め北条氏康とその弟分である北條綱成である。伊勢新九郎(北條早雲)後の北條氏を主人公とした小説は読んだことが無かったので、結構楽しめた。
一番の興味は、私が毎日通っている通勤路にかつての古戦場や城があった、ということである。調布から三駅めのよみうりランドの辺りにかつて小沢城という北條方の城があった。京王線の車窓から見ると確かにこの辺りは小高い丘陵状になっており、かつ小さな谷が複雑に入り組んだ地形であり、天然の要害には相応しそうだ。多分この頂上からは多摩川がよく見えたのだろう。その多摩川の川原では、矢野口辺りから分倍河原にかけて幾度か戦があったらしい。
多摩川の北にある深大寺あたりにも城があって(この城は神代水生植物園の敷地内にある)、小沢城の支城としての役割を果たしていたそうだ。調布の北にあたる深大寺も小高い丘の上にある。北條と武田とは国境を接していたことから、敵対したり同盟を結んだりしたが、武田家が織田信長によって滅ぼされたあと、北條家は豊臣秀吉によって滅ぼされ、そのあとに徳川家康が入った(いわゆる関東討ち入り)。北條家の被官たちの多くは主家滅亡後には野に下ったはずである。
そのような武士のなかには関東の地に土着して、庄屋などとして江戸時代を生きたひと達もいたことだろう。その子孫のひとりが、高校のときの同級生だった飯田氏である。かれの先祖は北條家の家人だったらしいが、江戸時代には世田谷で庄屋をしていたのである。
私が住んでいる多摩東部には富永さんという名前が異様に多く、彼らは結構な土地持ちで立派なお屋敷に住んでいたりするのだが、やはりかつては北條氏に仕えた武家が先祖だったようである。だんだんと脱線してきたが、身近にある歴史上の遺物をのんびりと巡ってみたい、というのが最近の私の夢である。我が家のすぐそばを流れる野川の流域には、国分寺崖線に沿って古代人の生活遺跡が数多く発掘されており、私もそのうち土器なんかを発見したりするかもね?
先端研ゼミ終わんぬ (2009年12月17日)
昨日、三年生後期の先端研究ゼミナールのパネル展示発表会が終了した。今年は今までのパワーポイントによる発表会形式ではなく、A1版横長のポスターを作ってもらって、9号館1階のアトリウムにおいてポスター形式で発表することになった。
学生諸氏のポスターはなかなか力作ぞろいで、一所懸命に取り組んだ様子がよく分かった。北山研に配属となった伊藤君、平井さんもともになかなかよい出来であった。三年生はこれからいよいよ、卒論の研究室の配属に向けて、研究室ショッピングに廻ることになる。来年度はどんな学生さんが来るだろうか。RC構造をやりたい、という熱意のあるひとに来てもらいたいものである。

 
聴くひとによって (2009年12月15日)
昼休みの今、iTunesに保存してあるリストの交響詩『前奏曲(Les preludes)』を聴いている。カラヤン指揮のベルリン・フィルである。この曲は中学生の頃に初めて聴いて以来、そのメロディ・ラインと様々な楽器が繰り広げる音色の重畳とによってお気に入りの楽曲のひとつとなっている。しかしそのことを、オーケストラに所属するあるバイオリン奏者に話したところ、「私は大嫌い」との返事が戻ってきたのでビックリしたことがある。
さらにその理由を聞いてみて、再度ビックリした。この曲は弦楽器による通奏低音(いわゆるユニゾン)が長く続くために、弓を長時間シャカシャカ小刻みに動かさないといけず、腕が大変疲れるというのである。バイオリンのそのパートが主要旋律ではなくて、背景として沈んでいる、ということが疲れに拍車を掛けるらしい。なるほど、同じ曲でも聴くひと(あるいは立場?)によって180度異なる感想となるらしい。作曲したフランツ・リストもまさかオーケストラの一員からこんなことを言われるとは思っていなかったのではないだろうか。ちなみに2011年はリストの生誕200周年の年にあたっている。もうすぐ、である。
このあいだのゼミ (2009年12月14日)
今年も残すところあと三週間となった日に開いた研究室会議は、近来まれに見る面白さで、途中に休憩を挟んで4時間近くもやってしまった。私自身はあまり調子が良くなかったのだが、学生諸君の説明する資料を聞いていくうちに、そのことを忘れるくらい充実したゼミだった。
その最たる理由は、2009年度にはM1学生が3名いる(嶋田、白井および王)、ということであろう。それとM2の矢島君が自身の実験結果を精力的に検討・検証し、かつ下級生に対してお目付け役的な役割を果たしてくれることが大きい。これらの修士課程の学生諸君はいずれも見どころのある、将来有望な面々であると私は思っているので、どんどんと成長することを期待している。
ゼミで何が良かったかと言うと、各人とも実験や解析の結果を詳細に示し、それがどのような理由で生じたかを考察して披露してくれたことである。研究を進める上ではあたりまえのプロトコルではあるが、その当たり前のことを実行することがいかに難しいかは、学生さんを教育した経験のある大学教員であれば理解できるであろう。
卒論生の宮木さんはJ.コンドルについての研究に取り組んでいるが、既往の文献や先行する研究を丁寧に調べていることが非常に良い。この日のゼミでは、コンドルが暗黙のうちに考えていたかもしれない地震力の大きさについて、検討してみてはどうか、ということを議論した。芝浦工大の岸田慎司研究室からは今年は学部4年の浅野君が実験に参加し、我が社のゼミにも出て来て、実験結果についての資料を提出して説明してくれた。4年生なのでそんなに専門的なコメントはできないが、一所懸命にやっていることは伝わり、好感が持てる。きっとそれなりの卒論が仕上がることだろう。
博士課程に在籍する苦労人の田島さんも、力作の博士論文を提出した(正式な受理はこのあと、教授会において決定する)。黄表紙も書いたし、実験もたくさんやったし、田島さんはもう立派な博士に該当する、と私自身は思っている。とは言え、博士論文をまとめることは大切な作業なので、最後まで気を配って仕上げて欲しい。
こう見てくると、2009年度のメンバーは急速に成長したような気がする。何年かが過ぎて「北山研ヒストリー in 2009」を書くときには、どんな感想が記されているのだろうか。楽しみである。
開戦の日に (2009年12月9日)
12月8日は太平洋戦争開戦の日です。この悲惨な戦争のことを考えるとき、なぜそのようなことになったのかという疑問に常に行き当たります。そしてその疑問に対して、我々は今も明瞭な回答を得られないでいるのです。ABCD包囲網によって世界から孤立させられたからとか、帝国主義に蹂躙された東亜細亜をその苦役から解放するためとか、表層的には言われますが、多分真実はそんなことではなく、戦争へと突き進んだ日本人全体のメンタリティとか気質とかが重要なのではないでしょうか。
もちろん旧日本軍を指導した人たちがいたことは確かでしょうが、そのような人たちの突出を許したのは、結局は日本国民だったからです。しかし敗戦と同時に、一億総懺悔というスローガンに代表されるように日本国民全体が戦争の責任を取ろうじゃないか、というような内実の伴わない反省しかなされず、結局誰も責任を取らなかった、ということが問題の本質だと思います。
このような状態のまま戦後60年以上を経過しましたが、未来においてこのような悲惨な戦争を避けるために我々戦後生まれの人間は何をなせば良いのでしょうか。自分たちが来た道を総括してこそ、これから歩んで行こうとする道も見えて来るでしょう。確かに戦争の記録や戦争に参加した方の個々の経験などは広範に発表されていますが、それらをいくら読んでも、戦争が悲惨であることは分かりますが、では我々が今後どのように行動すればあのような悲劇は起こらないのか、という行動規範への直接の解答は得られないような気がします。赤紙一枚で戦場へと送られ兵士となった市井の人々にとっては、それは抗えない運命だったのですから。
結局、太平洋戦争へと至った真のメカニズムを解明することが必要なのですが、この戦争を戦った人たちの多くは既に鬼籍に入っているでしょうから、今までできなかったこの作業が今後急速に進展するとは思えません。残念ながら遅きに失した、と言わざるを得ないのでしょうか。
寒い日 (2009年12月3日)
今日は卒論の中間発表会(卒業設計をとるひとは最終発表会)が行われている。いつもの204番教室である。毎年12月の初めに発表会をやっているが、この行事のときにはいつもながら「薄暗くて、寒い」というイメージがある。今日も冷たい雨が降りしきる、陰鬱な天気である。おまけに階段教室である発表会場は暖房の効きが悪いのか、室内にいてもコート無しではいられないほど寒いのである。お陰で眠くはならないが、恐ろしく早口の発表を聞いたり、もの凄く小さな表を見せられたりすると、身も心もさらにさむ〜い気分になるのでした。
ただ、パワーポイントに代表されるプレゼンソフトが発達したために、昔に較べると学生さんの発表は格段に良くなっていると思う。写真や図が見やすいのもよいことである。北山研の4名の学生諸君の発表も練習の介あってか、上手に出来ていました。これから2月の最終発表までさらに検討を続けて、立派な論文に仕上げることを期待しています。
文明の利器 (2009年12月2日)
今日、理学部棟の廊下を歩いていたら、前を行く学生さんとおぼしきひとが「今日のスカイプ会議でさあ〜」と話しているのを耳にした。そのひとはすぐに廊下を曲がって行ったので、その先の話しは聞こえなかったが、研究室会議をスカイプでやっているのだろうか。いやあ、いつも言っていますが本当に便利な世の中になりましたな。会議も旧態依然とした雁首を揃える形式ではなくて、ネットを介した映像によるバーチャルなものへと変わって行くのでしょうか。
しかしなんだかそれでは味気ないような気もする。あるソサイエティに属するひと達が一つ所に集まることによって醸し出される、場の雰囲気みたいなものって、やっぱりあるじゃないですか。そういう人間の暖かみって言うんでしょうか、それこそ会議の場の空気を読みながら、あるひとつの方向へ議論を収束させて行くというやり方は、長い経験を通して堆積した人間の知恵であるような気がします。
時間の短縮や合理性の追求も大切ですが、それによって失われる手法や知恵も必ずある、という(当たり前の)事実に、またもや突き当たりました。メール審議も良いのですが、ある程度議論が出尽くしたら、皆で集まってそれまでの議論を整理し、顔を突き合わせて肉声でやり取りすることによって、驚くほど急転直下に問題が解決する、何てこともあると信じたい。でも、これって、古き良き時代を懐かしむある種のノスタルジアでしょうか。時代に取り残されつつある旧人類の独り言、みたいになってしまいました。もっともこんなことを言っていても、大学内の会議に出ていると時間の無駄だなあと思うこともしばしばですが、、、。
懐かしいひと (2009年11月27日)
昨晩、女房が視ていたテレビを何気なくみていた(私はテレビを滅多に視ないのだが)。それはNHKなのに民放の『タモリ倶楽部』そっくりな番組で、タモリが日本橋界隈をコメンテータと一緒にブラブラ歩く、というものだった。NHKも随分変わったな、こんな下らない(でも、民放に比べたら格段にお金をかけていることがすぐに分かる)番組を作るなんて、と話しながら視ていた。
しかししばらく視ていたら、あれ、このコメンテータの横顔はどこかでみたことがあるような、という気がしてきた。そしてよくよく食い入るように見つめたら、それは何と鈴木博之先生(西洋建築史・近代建築史がご専門)であったのだ。博之先生との関係については、このコーナーの「卒論の研究室を選ぶ」というところに詳しく書いたが、私はもともと建築評論とか建築史とかで卒論を書きたいと思っていて、大学四年生のはじめに当時助教授であった博之先生を訪ね、テーマまでいただいたことがあった。
そんなことが四半世紀も前にあったのだが、久しぶりにその先生のお元気なお姿を拝見して、とても懐かしかった。番組の中で「地霊」という話が出てきたりして、博之先生の面目躍如たるものがありましたな。でも、テレビの撮影だと言うのに先生はデジカメで写真を撮ってばかりいて、かなりリラックスしていた、という感じだった。学部三年から四年になるときの春休みに京都・奈良見学旅行があって、その引率が博之先生だった。京都の旅館で学生たちとお酒を飲みながら、後藤治君(現在は工学院大学教授で日本建築史が専門)のバカ話にお酒を吹き出していたことを、よく憶えている。博之先生、これからもお元気でわれわれをご指導下さい。
ちなみに本家本元の『タモリ倶楽部』には、坂本功先生(木質構造が専門)が出てきたこともあった。
場所によりけり (2009年11月25日)
昨日の夕方、授業を終えて教室から出て、教室棟のロビーを通りかかったとき、学生たちがマージャンをしているのを見かけた。建築都市コースの学生ではなかったが、角田誠先生から「教室棟でマージャンをやっているけしからからん奴らがいる」という話を聞いていたので、ははーん、こいつらか、と思った。
私が学生だった頃には大学のそばに雀荘があったので(というか、昔は大学のそばには必ず雀荘はあったものだが)、製図室を含めて1号館でマージャンをやったという記憶はなかった。最近の学生さんはマージャンもしない、という風潮だったから、複数でやる頭脳ゲームを嗜むこと自体は私としてはむしろ望ましい、と思っているくらいだ。しかし、やっぱり教室棟のエントランス・ロビーはまずいでしょうな。
そこで私は、にこやかに微笑みながら「マージャンをやるのはいいけど、ここは場所がまずいよね。ご配慮をお願いします」と言って、やんわりと注意した(私にしては、非常に紳士的なやり方です。普段は「お前ら、そんなことやっていい分けないだろ」と怒鳴るところです)。するとひとりの学生さんが「静かにやりますから」と言うので、「いや、ここはまずいよ」と言って再度注意した。多分、納得してくれたと思う。でも、半チャンが終わるまでは続けていたかも。
しかしよく考えると、大学の外はおろか内部においてさえ、学生さんが気軽に溜まれて、マージャンなんかしても怒られないようなスペースが全く用意されていない、ということこそ問題なのである。以前にも書いたが、お客さんである学生さんが居心地よく過ごすことができるようにキャンパスを整備することが、最重要課題なのだ。ここのところの本学は、学生諸君のことを忘れているのではないだろうか。大変に心配である。ただ私は、大学を管理する側には回りたくない。そんな窮屈な大学生活はご免である。体制側に対しては常に距離をおき、決して取り込まれない、これが肝要だと思っている。
インフルエンザ (2009年11月23日)
子供がついにインフルエンザにかかってしまった。昨日までは元気に遊び回っていたのに、深夜に急に熱が出て、今朝病院で受診した。そして検査したところ、発熱後24時間経たないと分かりませんが多分インフルエンザでしょう、との診断であった。通っている保育園でも、新型インフルエンザが流行し始めていたので、危ないかな、と思っていた矢先であった。
しかし子供を病院(街にある診療所)に連れて行って、インフルエンザ症状の患者さんがあまりにも多いのにビックリした。これはただ事ではないし、病院のお医者さんや看護士さんの多忙ぶりは非常なものがある。診て下さったお医者さんもインフルエンザに対する予防としてタミフルを服用している、と話していた。建築都市コースの医学博士・星旦二教授は、「新型インフルエンザを極度に恐れることはなく、むしろ早く感染して免疫を付けることです」と常々仰っており、そのご意見は朝日新聞にも取り上げられた。先生のご意見には、理性的に考えれば賛成である。しかしながら、医療の現場や一般の市井の人びとの感覚から言えば、なかなかそのように割り切れないものがあるのではなかろうか。
いろんなうた (2009年11月23日)
最近、稲垣潤一(歌手にしてドラマー)がいろんな女性ボーカリストとデュエットするアルバムを買った。歌っている曲はほとんどが他人のもので、いわゆるカバー・アルバムである。どんな曲が入っているのかほとんど見ずに買って、iPodに入れて聴き始めた。
すると、すっかり忘れていた、私の聴きたくない歌が流れてきたのである。それは竹内まりやの『けんかをやめて』という歌である(この曲はその昔、アイドルだった河合奈保子も歌っていた)。ご存じの方は知っているだろうが、このうたの歌詞がはなはだ鼻持ちならないのである。二人の男ごころをもてあそんだ挙げ句に、その二人の男性が喧嘩をしたらしく「私のせいで争わないで、もうこれ以上」とのたまっている歌詞である。全く、何て傲慢でイヤな女なんだろうか、と聴くたびに感じるのだ。メロディはなかなか良いので、この歌詞をなんとかして欲しいと思います。
もうひとつ、こちらは十代の頃にレコードを買ってよく聴いていたハイファイセット(男女3人のコーラス・グループ、既に解散している)の1975年頃のアルバムがCDになったので、懐かしさのあまり衝動買いした。レコードはいまだに大事に持っているのだが、如何せん、レコード・プレイヤーがありません。
そして、聴き始めて我ながらビックリしたのだが、三十数年振りに聴くにもかかわらず、イントロが流れてきた途端、そのあとに続く歌詞をスラスラと口ずさめるのである。そんな曲があったことさえ忘れていたというのに、である。さらに、そのメロディによって海馬の奥深いところが刺激されたのだろうか、その曲を聴いていた頃の(それはちょっとキザな言い方をすれば、青春真っただ中のころであるが)、ちょっと甘美でほろ苦い思い出もがよみがえって来たのである。
その頃は、愛とか恋とか人生の機微とか、若くて分からなかったのだが、半世紀近くも生きてくるとその頃とはまた違った感想を持って聴いている自分自身に、「やっぱりそうなんだあ」と妙に感心してしまった。
この調子でゆくと、もっと年とってお爺さんになっても、ロックとかポップスとか聴いているんでしょうな。よぼよぼになって杖ついても「物わかりの良い大人にはなりたくないぜ(by佐野元春)」ってシャウトしていたいもんです(そのまんま、血管が切れてイッちゃったりして)。アリスとかチューリップとかの往年の名フォーク・グループが再結成されて、おじさん・おばさんたちが熱狂しているのも分かる気がします。アリスの『今はもう誰も』なんか、今聴いてもビビッと来ます。
いやあ、うたって、やっぱり素晴らしいですね。
(おまけ)iPodを聴きながら、というかイヤホーンを付けて、歯磨きしたことはありますか。歯ブラシがカシャカシャ動くたびに歯にぶつかってアゴの骨に響く固体音(?)のせいで、Good Vibrationが台無しでっせ。
ジブリ美術館って誰のため? (2009年11月19日)
よく晴れた、ある秋の一日、三鷹市・井の頭公園の脇にあるジブリ美術館に行って来た。カーナビによれば我が家からは車で6.6 kmのところにあり、本当に直ぐに到着した。ただし駐車場はないので、近所のコイン・パーキングを捜し回らねばならなかったが。
さてこの美術館は、宮崎駿監督が彼のアニメのキャラクターを展示するための美術館らしい。我が家では「となりのトトロ」や「崖の上のポニョ」、ずっと昔の「未来少年コナン」などに親しんでいたし、俳優の内藤剛志さんが宮崎監督の案内でまだ建設中で開館まぢかの美術館内を探訪する、というDVDの特典映像を何度も見ていたので、初めて行ったという感じはしなかった。
建物のプランではいろいろな小空間に通じる階段やスカイデッキ、また建物内部とサンクン・ガーデン的なパティオなど外部との関係など、建築的に見るとよく出来ていると思う。ステンドグラスも美しいし、いたるところに小細工が施されており、それを見つけるのも楽しい。
建物最上階にある猫バスルームでは、子供たちが嬉々として遊び回っていた。ただしここは人気があるため5分ほどの交代制になっており、子供とその付き添いの親たちとでごった返していた。「水グモもんもん」という15分の短編アニメも、まあ面白かった。特別展示では、「崖の上のポニョ」の原画やセルが飾ってあった。

このように総体的には楽しくて面白かった、というのが感想なのだが、帰ってから、この美術館はどういう人をターゲットとしているのだろうか、ということが気にかかり出した。一見、子供向けではあるが、我が家の息子を見ていて分かったのだが、子供が喜んだのは猫バスルームと小さな螺旋階段くらいで、展示物にはほとんど興味を示さなかった。
それでは大人向けかというとそれほどの展示物はなく、アニメ・ファンというわけでもない人々にとっては、ふーんってな感じである。どうも中途半端な気がして、しかたがなかった。しかしそのわりには、休日のジブリ美術館は子供を連れた家族やカップルで大賑わいであった。まあ、宮崎駿監督のアニメ・ワールドの魅力で集まってきたひとびと、ということであろうか。
ちなみにジブリ美術館は完全予約制(我が家では、ひと月ほど前にローソンでチケットをゲットした)ということだが、この日の館内は大混雑で、本当に入館制限しているのかと疑問に思った。帰りにコイン・パーキングへの道すがら、和菓子屋さんで買った串団子が美味しかった。
図書館 (2009年11月17日)
先日、久しぶりに大学の図書館に行ってきた。それにしても最近はとっても便利になりましたな。図書館の蔵書をネット経由で検索して、目当ての本がどこにあるのかを自分の研究室で座って調べることができるのだ。その結果、地下一階の開架書庫にあることがわかったので、いそいそと出掛けて行った。
静かでひんやりとした印象のある書庫には無数の本たちがひっそりと並んでおり、手に取って表紙をあけてくれる人が来るのをじっと待っていた。私が捜していた二冊の書籍は(それはかなり古い本であったが)、どうみても久しぶりにページが開かれたという本であり、開いてくれてどうもありがとう、とその本に言われたような気がした。
文系の研究者は、自分の研究を進めるために書庫に入り浸って、本たちに取り囲まれた雰囲気の中で思索にふけり、どこに行けばどのような本があるのかというイメージマップが頭の中に構築される、という。そのような体験は研究遂行上、大変に重要なことだそうだ。
私にはそういった経験はあまり無かったような気がするが、書庫の中にいると本に集中できることは確かであり、研究室で座っているときとは違った脳内活発化が生じるような感じがする。ところが現代においては、あらゆる書籍や資料がデジタル化されつつあり、書庫に行かなくても自分の部屋のパソコン経由で資料を閲覧することが可能である。そうすると、デジタル化された情報の海で溺れることはあっても、上述のように本たちのあいだを彷徨して物思いに沈潜する、という体験は不可能になる。デジタル化の恩恵は計り知れないとは思うが、失うものもまた確実にあるのである。
日本地震工学会年次大会2009(代々木にて) (2009年11月12日/14日)
今日から三日間の予定で、代々木の国立オリンピック記念センターにて日本地震工学会(JAEE)年次大会が開催される。我々東京都立大学のJAEEメンバーが実行委員会の主体となって、この日まで約10ヶ月余りのあいだ、準備に当たってきた。なので、今日からの本番において、できるなら盛況な学会となることを望んでいる。
しかし初日は午後からセッションが開始、ということもあって、何とも寂しい幕開けとなった。午後一に開かれた開会式には、20名程度が座っているだけであった。初日は午後のみ、二日めは終日、三日めは午前中のみ、という日程であるが、普通に考えれば正味二日で足りることになる。それがそうはならなかった最大の理由は、会場側の都合にある(と私は思っている)。
会場の設営は当日に行うのだが、部屋の解錠が朝8時半と決まっており、そのために会場設営の時間として午前中を当てざるを得なかった。全く非効率的である。さらに発表用居室は技術フェアの会場を含めて5つなのだが、その5室が3階から5階までご丁寧にも完全にバラバラに割り当てられたので、使い勝手が悪いといったらない。
申し込み時に事務局に掛け合ったのだが、そのような便宜はどの団体に対しても計ったことは無い、という超お役所的対応によってあっさり拒絶され、かくなる仕儀と相成った。この施設はいろいろな催し物に利用されているようで、大勢の人達が行き交っていたが、こんなに融通の利かない対応をしていると、民主党の事業仕分けによって“運営は民間に委ねるべきなので、廃止”という烙印を押されかねないと思っている。
さらに会場の設備の話しが続くのだが、11月も半ばになるとかなり寒い。それなのに会場には暖房が入っておらず、寒いことこの上ない。そこでエアコンのスイッチの脇の小さな注意書きを見ると、見にくい黄色の字で「暖房は12月1日から」と書いてあるではないか! 国の省エネルギー対策基準に従って、という言い訳まで書いてあるのだ。いったいどういう神経をしているのだろう。寒くて風邪をひいて、その結果として病院で受診すると、それだけ国費が使われる、というのに。

大会三日めは午前中しかセッションは無かった。それまでの二日間は終日どんよりした天気で雨も激しく降ったりしたのだが、お昼になって日が射してきた。気温も高くなって暖かくなった。何という巡り合わせの悪さだろうか。
何だか今ひとつ盛り上がりに欠ける大会だったが、会長の濱田先生がお昼頃に受付にお見えになって、実行委員やアルバイト学生にねぎらいの言葉を残して去って行った。ちょっとだけ暖かな気分になった。
マンダラ (2009年11月11日)
武澤秀一さん執筆の『マンダラの謎を解く 三次元からのアプローチ』(講談 社現代新書、2009)を読んだ。そんなにマンダラに興味があったわけではない。密教美術である曼荼羅図には、何かしら神秘的なイメージがある。以前に武澤さんが書いた『法隆寺の謎を解く』(ちくま新書)を読んで面白かったことを憶えていた。 社現代新書、2009)を読んだ。そんなにマンダラに興味があったわけではない。密教美術である曼荼羅図には、何かしら神秘的なイメージがある。以前に武澤さんが書いた『法隆寺の謎を解く』(ちくま新書)を読んで面白かったことを憶えていた。
武澤さんは、私が学部学生だった頃に短いあいだだったと思うが助手を勤めており、何度かエスキースを見てもらったという体験が記憶の底にあって、その無意識が著書を読ませた、というのが正しそうだ。その当時の武澤さんは、何だかこむずかしそうであった(本当のところは知りません、悪しからず)。ご自分の設計事務所の名前も、建築界の聖人ヴィトルヴィウスの“用美強”をそのまま冠したものであった。
だが、この本は一般向けということもあって非常に読み易かった。私の読書はほとんどは電車の中であるが、それでも数日で読み終わった。中身も楽しく、インドや中国の石窟寺院が実は立体的なマンダラそのもので、塔のまわりを時計回りにぐるぐる廻る礼拝行為がその底流にある、と言う。
大陸での宗教建築の空間(すなわち立体マンダラ)が日本に渡来して、飛鳥寺から法隆寺まで、その伽藍配置や諸仏の配置方法などがどのように変遷して行ったか、という説明は多少こじつけ気味のところもあるが、よくぞ考えた、といった感じである。われわれがよく目にする紙布に描いた曼荼羅図は(武澤さんによれば)立体マンダラを二次元にしたものであるが、これからは中心に対して時計回りに拝見することにしよう。
困ったひと (2009年11月7日)
今日の朝日新聞朝刊の一面に東京都知事の写真が載っていたので、こりゃ都政に嫌気がさして辞任表明かな、と思ったら、あに図らんや、2020年のオリンピック招致に東京都として再度チャレンジしたい、という意思表明であった。いやはや、その執念には恐れ入った。
しかし記事をよく読んでみると、もうすぐ都知事の任期が切れるのだが、そのあとは都知事選に立候補する意志はないので、オリンピックについても次期の都知事と都議会とが決断することである、と書かれていた。ああ、ひと安心である。
しかし、じゃあ、一体何のためにこの時期に再度のオリンピック招致再挑戦を表明したのだろうか。こうやって旗を立てることによって、オリンピックがもたらす巨額の経済的恩恵にあやかりたい、という人達に“夢”を持ってもらうためだろうか。今までの承知合戦で使った多額の税金の使い道に何か後ろ暗いところがあって、それを糊塗するためにさらに活動を継続せざるを得ないのだろうか。
まあ、私たち市井の善良な市民には分からないような奥深い理由があるのだろう。でも、一番の理由は、ここらで一発また世間をアッと言わせて目立ちたい、というところが案外、真実に近かったりするんじゃなかろうか。ホント、困ったひと、ではある。
お久しぶり (2009年11月3日)
今日は「第2回東京を歩く会」に参加したが、その前後にゆえあって東急・田園都市線のたまプラーザ駅を利用した。この駅で乗降したのはかれこれ十数年ぶりである。私が利用していた当時は、何の変哲もない橋上駅舎の改札を通り抜けて南口の階段を下りると、そこにはほどほどの大きさのバス乗り場があるほかは、取り立てて何もないところであった。ここで大昔、大学の同級生だった松原和彦くんや宮本佳明くんにばったり出会った、という思い出もある。
ところが昨日行ってみると、駅およびその周辺が再開発されて、すっかり様変わりしているではないか。南口の駅前広場が立派になり、コンプレックスには本屋とかスーパーマーケットとかフィットネスクラブなどが出来ていた。改札に向かう階段にはエスカレータが設置され、そこを上がって行くとビックリするほどの大空間が広がり、巨大なトラス屋根が覆っていたのである。何だこれ!ってな感じである。地方の小さな空港なんかよりも、よほど立派な施設に生まれ変わっていた。
 
しかし、なぜ、これほどまでに巨大なトラスをかけて駅を改造しなければならないのか。確かに広々としていて、明るい雰囲気にはなった。だが今後、日本の人口は減少し、駅を利用する人たちは確実に減るのである。そうなったときにも、魅力的な街の中心として人気を保持したい、ということであろうか。
どうせお金をかけるなら、電車の本数を増やすとか、車両を増結するとか、鉄道本来の輸送力の増強を実現したほうが利用者にとってはずっと良いのではなかろうか。実際、田園都市線に乗って都心まで行ったのだが、祭日の午後だというのに渋谷までものすごく混雑しており、京王線のようにのんびり座って移動しようと夢想していた私はこれまた仰天したのである。
両国近辺で「東京を歩く会」に参加してひと仕事したあと、ふたたび、たまプラーザ駅に帰ってきた。駅舎から通りを渡るブリッジ(これも新しく造られたもの)に出ると、綺麗な満月が迎えてくれた。その風景がいやに目に映えた。
公聴会にて (2009年10月31日)
10月も晦日の土曜日(学祭の前日である)、博士論文の公聴会があって出勤した。五洋建設に務める都祭弘幸さんが本学に博士論文を提出し、芳村学先生が主査、私と高木次郎さんが副査として審査に当たった。今日は土曜日で会社や学校はお休みだったこともあり、北は青森の津村さん(弘前大学)から、南は北九州の毛井さん(九州工業大学)まで、大勢の方がお見えになった。
都祭さんの研究テーマの総元締めだった平石さん(明治大学)、芳村先生が建研時代に共同研究者であった和泉さん(千葉大学)、稲井さん(山口大学)、島崎さん(神奈川大学)、それからURの井上さん、鹿島技研の丸田さんも来て下さった。休日に遠路はるばる八王子まで足を運んでいただいたことに御礼申し上げる。しかしこれらのメンツを見てみると、その昔、民間企業から建研に派遣されて研究していたひとの多くが大学の先生になっていることに、あらためて驚かされる。大学の先生って、やっぱり魅力的な職業なんでしょうか、私にはよく分かりませんが。
都祭さんは東京都立大学建築工学科の遠藤利根穂先生(故人)の研究室のご出身で、私より二つ学年が上である。私が学生の頃には、東大・青山研究室と都立大学RC系研究室との野球の対抗戦(“野球”をご覧下さい)があり、都祭さんがしましまのユニホームを着て、ピッチャーをやっていたことをよく憶えている。
その後、彼が卒業してから建研で研究するようになって、今度は建研と青研との野球戦があって、そのときにも都祭さんはピッチャーをやって勝利投手になった、ということを今日うかがった。そのことは私はすっかり忘れていたが、言われてみるとそんなこともあったような気がする。ここでも青研時代の野球がキー・ポイントになっている。
また、私が宇都宮大学の助手だったときに、那須にある五洋建設技術研究所で宇大構造研の大学院生(江藤啓二くん)がRC立体柱梁接合部実験を行ったが、そのときの共同研究者のひとりが都祭さんであった。いずれにせよ、学生時代に野球をやって交流し、その後も共同研究をしたりしたひとの博士論文を審査した、というのも何かの縁であろう。
授業のはなし (2009年10月29日)
授業は教育の柱なので、いつも一所懸命にやっている(まあ、当たり前でしょうが)。で、後期のRC構造の授業が始まって1ヶ月が過ぎようとしているが、今年はちょっと変である。私が芳村学先生からRC構造の講義を引き継いで3年めであるが、今年はギャラリー(学生さんのこと)の入りが極端に悪いのである。
朝(と言っても10時半だが)、私が教室に入ると、そこには三人ほどしかいない。私は定刻に授業を始めて時間内に講義を終えることを信条としているので、三人しかいなくても講義を始める。しばらくすると、パラパラと学生さんが入ってきて、終了する頃には十数人になっていた。昨年までは25人くらいは毎回、出席していたので、その半数にも満たないのである。
学生さんがデザイン系を指向するのはいつものことなので、それが主要な原因とは考えにくい。第一、設計デザインの授業が例年以上に賑わっている、という話しも聞かないので、結局のところ、だいたいの単位を3年前期までに修得して、3年後期はのんびり過ごす、というBehavior(これは悪弊だと私は思う)が学生さん達に根付きつつあるのかも知れない。
いずれにせよ、こちらは突貫作業で教科書を改訂したりして万全の体勢で望んだのに、とんだ肩透かしである。でも、こんな話しはいつの時代にもごまんとあったらしくて、梅村魁先生(青山博之先生の前の教授、故人)なんか「学生さんがひとりでも来ていたら、よく来たよく来た、と言って授業はするもんですよ」と仰っていた記憶がある。
私が学部3年生だった頃は、設計製図が忙しくて(自分のだけでなく、先輩の手伝いも大変だった)、製図室に寝泊まりしているくせに授業には出ないことが多かった。当時の製図室は3階にあったが、プランが口の字をしていたので、真夜中に部屋の扉を全開にして自転車でサーキットのように走り回ったり、製図室の真ん中の机を片付けてスタイロフォームで作ったボールをT定規で打つ“野球”をやったりした。
ありゃ、脱線してしまったので、元に戻す。しかし、授業に出ないと期末の試験が危ないので、仲間内で当番を決めて数人が授業に出てノートを採ってくる、ということをやっていた。製図室に寄りつかずにまじめに授業に出るひともいたので、どの授業も最低でも数人は必ず講義に出ていたと思う。
ところがある日のこと、松尾陽先生だったような気がするが、先生が授業に向かったところ講義室には誰一人として学生がおらず、怒って帰ってしまった、という事件が出来した。そして「松尾さんの授業に誰も出てなかったらしくて、先生、激怒して帰っちゃったらしいぜ」という噂が製図室に流れ、これは大変だあ、ということになった。
これはさすがにまずい、と皆思ったらしく、殊勝な学生が(誰だったかは忘れたが)先生のところに謝りに行って、事なきを得たのである。でも、何と言って謝ったのか、まさか「決めていた当番がサボったもので、、、」とも言えないしなあ。
[先端研究ゼミナールについて]
後期には3年生対象に先端研究ゼミナールという演習があり、こちらも開設されてから3年めである。各研究室にクジ引きで三名程度の3年生を配属して、各教員が自由にゼミナールを行う、というものである。いろいろな分野の先端研究の雰囲気を少しでも3年生に味わって貰おう、というのが当初の趣旨であったが、私のような構造系では初学者が1、2ヶ月で先端研究を理解する、というのははなから不可能である。
そこで私は先端研究を理解させることはあっさり諦めて、もっぱら“日本語力”を養うことを目標にしている。駒場の東大教養学部で使われるテキストである『知の論理』(1995、小林康夫/船曳建夫編、東京大学出版会)を読んでレポートを書かせ、それをもとに皆で議論する、という文系のようなゼミをやっているのだ。
この効果がどのくらいあるかは分からないが、本を読むことが少なく、自分の考えを理路整然と文章にして他人に説明する、という経験がほとんどない学生さんにとっては、よい訓練になるのではないか、と思ってやっている。今年の先端研究ゼミナールがどうなるか、今後が楽しみである。
カード・キー破損せる事 (2009年10月23日)
今日は本当に驚いた。
午後1時から大手ゼネコンのリクルーターの方が見えて、私の部屋(研究室)で我が社のM1ふたりに説明をして下さることになった。そのうち2時になり、別の会社の方々が今度は私に相談にやってきた。私の部屋にはリクルーターさんとM1二人がいるので、私は会議室に移動することにした。そこで学生に「○○さんの説明が終わったら、私の部屋を施錠してから鍵を私まで届けてね」と言って、私の身分証明書兼用のカード・キーを手渡した。
私は会議室に移って相談に入ったが、いつまでたっても学生がカード・キーを届けに来ない。どうしたんだろう、随分熱心に会社の話しを聞いているのかな、とチラッと思ったりした。やがて4時頃に私の会議が終わったので、自分の部屋の前まで戻ると部屋が解錠のままになっている(ドアの脇に取り付けてあるカード・リーダに、解錠のランプが点灯していたので直ぐ分かった)。あれっ、どうしたんだろう。鍵を掛けるように言ったのになあ、と思って扉を開けると、学生二人がガン首揃えてちょこんと椅子に座っているではないか。
私:「あれ、まだやってたの? ○○さんは?」と、衝立ての向こう側を見るが、○○さんは既にいない。
学生ふたり:「もう帰られました。それより先生、非常事態です」
私:「えっ、どうしたんだ!何が起こったんだ?」と、あたりを見回す私。
学生ふたり:「先生のカード・キーが割れました。もう使えないそうです」
私:「えっ、、、(絶句)」
そして衝撃の真実が明らかになった。リクルーターの方の説明が終わった後、彼らは私の指示通り、私の部屋を施錠しようとした。しかし、実は私のカード・キーはICの接触が悪くて、解錠や施錠にはちょっとしたコツが必要だった(カードを軽く面外に曲げて、優しくなでるようにカード・リーダにかざすのである)。そのことを知らなかった彼らは、なかなか鍵がかからないので、カード・キーを曲げたり撫でたりしているうちに、たぶんイラついたのだろうが、思い切って曲げちゃったらしく、バキッと割れてしまったのだ。
ありゃりゃと思っただろうが、あとの祭りである。彼らは非常にまずいと思ったらしく、予備のキーを借りて来たり、2階の事務室に行って新しいカード・キーを申請するための用紙を用意したりして、私が戻ってくるのをひたすら律儀に待っていたそうだ。しかし、「非常事態です」はないだろう、え? 非常事態という言葉には、自分は関与してないが重大事が出来したというイメージがある。でも今日の出来事は、君たちが引き起こした事態だろう。まったく何言ってんだか。
事の次第を理解した私が超不機嫌になったのは当然である。何て事してくれたんだ、お前たち。ホンマかいなあ、かなわんなあ(エセ関西人です)、今まで騙しだまし使って来た大事なキーなのに!と、ひとしきり文句を言ってから、まあしょうがないな、形あるものはいつかは壊れる、ということでお開きとなった。
これから新しいカード・キーが交付されるまで、不便な日々を過ごさなければならないかと思うと、とっても憂鬱である。でも、これで私も接触のよいカード・キーを使うことができるようになるのか(お隣の市川先生もやはりカード・キーの具合が悪くて我慢ならず、再発行してもらったそうだ)、とちょっぴり嬉しい気もするのだった。
(追記 20091030 新しいカード・キーがやっと出来上がって、通常の生活に戻りました。)
半分終わったWPC実験 (2009年10月22日)
このコーナーでも二度ほど紹介したWPC立体耐震壁の実験だが、見波進さん(助教)や和田芳宏くん(M2)たちの涙ぐましい努力のかいあって、4体の載荷が終了した。全部で8体なのでちょうど折り返し点に到達したわけだ。試験体は4体とも形状が異なり、無垢の耐震壁、壁板に開口をあけっぱなした試験体、開口脇にRC柱を増設して補強した試験体、および開口脇に鉄骨部材を添わせて補強した試験体である。
感想めいたことを言うと、4体とも変形モードが異なり、予想とは違う現象が次々と起こって、加力中に「なるほどなあ」と感心したり、「なんで?」と首を傾げたり、の連続であった。試験体ごとに破壊性状がこのようにドラスティックに変わる実験は、私の今までの長い実験ライフでも無かったことなので、見ていてとても楽しいし、考えることも次から次へと出来して休む間もない感じである。

開口を設けた試験体では、変形が大きくなると開口左右に分割された壁板とフランジ壁とのあいだが離間して、フランジ壁とウエブ壁とはもはや一体とはみなせない状態になった。しかしこのような隙間やセッティング・ベースの降伏後の伸び変形によって、立体耐震壁自体の靭性は相当に向上したように思える。
もともとプレキャストのRC版を接合して組み立てた構造ではあるが、開口を設けることによってウエブ壁の変形モードが無垢の壁とは異なるものとなり、いろんな部分の“隙間”(学問的ではない表現はお許しいただきたい)が大きくなって剛性は低下するが、全体の変形は大きくなった、という感覚である。この辺りの機構の解明や現象の合理的な解釈は、和田君の修論、黒倉さんや長谷川君の卒論に期待しよう。
以上の4体はいずれも開口を単層に設けた場合であったが、来週からは開口を連層で設けた場合の実験が始まる。そうするとCoupled Shear Wallのような構造となるので、実建物における曲げモーメントの反曲点位置が変わると想定される。
そのあたりの設定は、高木次郎さん(准教授)と坂元さん(M2)の解析の成果を待って決めることになる。いずれにせよ、まだまだ実験におけるサプライズが続くんだろうなと思うとワクワクする。実験するほうにとっては大変だろうが、WPCプロジェクト実験チームの皆さんのさらなる健闘を期待している。
渚のカセット (2009年10月18日)
テクノロジーの進化によって、何百もの曲をわずか数センチ四方の箱に格納して持ち歩けるようになった。iPodのことである。私のポケットには8GBのiPod nano が入っていて、クラシックや日米のポップス・ロックなどをいつも聴いている。せっかくの音楽はいい音で聴きたいので、ちょっと奮発したSONYのイヤホーンを使っている(iPod付属のものとは格段に音質が違います、聴けばすぐに分かりますよ)。
しかし私が高校・大学生だった頃には、音楽を手軽に聴くと言えばカセット・テープであった。LPレコードやFM放送からカセット・テープに録音して、それを手持ちのラジカセやカー・ステレオ(この言葉もよく考えるとおかしいですよね。でも当時はラジオとカセット・デッキがセットになったカー・オーディオのことをこう呼んだのです)にセットして聴くのである。マクセルやTDKから発売されていたカセット・ テープにはいろいろなグレードがあって、クロムテープなどが高価だったと思う。 テープにはいろいろなグレードがあって、クロムテープなどが高価だったと思う。
真夜中に車で大学の製図室に行ったり、実験が終わって深夜に車を飛ばして帰るとき、いつもカーステからは佐野元春、浜田省吾、安部恭弘といった和製ポップスが流れていた。しかしiPodよりもずっと大きいカセット・テープに収録できる曲といったら90分程度が限界であり、アルバム10枚分のカセットを持ち歩くとなると、相当のスペースと重量とを必要とした。
夏になると友人たちと車でよく海へ遊びに行った。駒場時代の友人たちとは大学の寮があった戸田(へだ、と読む。西伊豆の小さな浜辺で、高足ガニが穫れることで有名。福永武彦の長編小説『草の花』の舞台である)によく行ったな。ここの太平洋側の堤防から眺める夕日は絶景だった。茂山俊和くん(現在は東大でビッグバンを研究する天文学者)が小振りなバスケットに一杯のカセット・テープを持ってきて車に乗り込んだことをよく憶えている。
大学院生になると九十九里浜によく行った。そして浜辺にはラジカセを持ってゆき、お気に入りのGood Vibrationをかけるのである。さすがにBeach Boysは聴かなかったが。そんななか、ビールと一緒に食べる焼きハマグリは最高だった。この頃の思い出とともに、杉真理(すぎ・まさみち)の「夢みる渚」という曲の一節“渚のカセットが〜”というフレーズが必ずよみがえってくるのであった。
私の手元にはこのころの名残のカセットが今も多量に残されている。一本一本のカセットには、ロットリング(製図ペンのこと/今はもう死語かな)で丁寧に書いたアルバム・タイトルや曲目が今も鮮やかである。しかしそれらを聴くことは、残念ながらもうない。でも上述のように思い出がいっぱい詰まっているので捨てることも出来ない。皆さんは、一体どうしてますか。
新しい鉄筋コンクリート構造の教科書 (2009年10月16日)
 東工大の林静雄先生、坂田弘安先生、東京理科大の衣笠秀行先生と一緒に改定作業を行ってきた、新版「鉄筋コンクリート構造」が10月初旬に市ヶ谷出版社より刊行されました。値段も2,800円に値下げし、表紙も明るい緑色系にしてデザインも一新しました。 東工大の林静雄先生、坂田弘安先生、東京理科大の衣笠秀行先生と一緒に改定作業を行ってきた、新版「鉄筋コンクリート構造」が10月初旬に市ヶ谷出版社より刊行されました。値段も2,800円に値下げし、表紙も明るい緑色系にしてデザインも一新しました。
中味ですが、初学者を対象とすることを明瞭に打ち出し、基本的な事柄と応用的な内容とを分割して、授業で使い易いように工夫しています。
私が執筆を担当した「せん断」の部分は、基礎編と応用編とに整理してまとめ直しました。そのほか出版社によって、本文のレイアウトや字体など随所に改良が施されています。ぜひ一度、手に取ってながめてみて下さい。
改定の経緯ですが、編集者の方が「こんなに売れない教科書も珍しいですよ」と言ったことから、2009年4月頃から突貫作業で見直し・修正を行ってきました。私のRCの授業は後期ですので、それに間に合って良かったです。教室で3年生たちがこの教科書を持っているのを見たときには、正直嬉しかったですね。
鎌倉でお好み焼き (2009年10月13日)
子供が路面電車に乗りたい、というので乗りに行くことになった。「どの電車がいい?」と聞くと、いつもDVDで見ている函館のレトロ電車に乗りたいと言う。函館はちょっと無理なので、私が昔よく見ていた都電荒川線はどうか、と思ったがあれは専用軌道を走っているので却下された。
そこで女房が昔よく乗っていた江の電に乗りに行くことにした。江の電もほとんどは専用軌道を走っているが、江ノ島の近くだけ車と同じ道路上を走るのである。まず藤沢まで車で行って、駅近くのコイン・パーキングを探した。最近は小規模な24hパーキングがあちこちにあるので本当に助かる。藤沢駅の近くにも案の定あった。
そこから江の電に乗った。私は大昔に乗ったかも知れないが、記憶が全くないので、初めて乗るようなものである。子供はもちろん初乗車である。観光電車なのにパスモが使えるのが嬉しかった。江の電は単線であり、1時間に5本走っているが、今日は休日だったのでダイヤが7、8分遅れていた。終点の鎌倉までは約40分であるが、途中駅には腰越とか極楽寺とか由比ケ浜など、歴史好きにはたまらない地名がバンバン出てくる。七里ケ浜から稲村ケ崎あたりまで海がよく見えて、キラキラと輝いていた。

さて鎌倉に着いて、遅い昼食をとることにした。我が家は歩くのが嫌いなので、手近で済ませたい。江の電鎌倉駅の真ん前から細い路地を入ったところに、お好み焼きの「津久井」という店があった。女房が言うには、この店は昔からあるが一度も行ったことがない、とのこと。そこで折角なので食べてみることにした。
お店に入ると小じんまりとした、レトロな雰囲気の和風で、中庭があって涼しい風が吹き抜けた。空にはトンビがぴーぴーと鳴いていて、おそい午後のけだるい雰囲気を盛り上げてくれた。お好み焼きはまあ美味しかったが、自分で焼くのは面倒だったな。マヨネーズが無かったのも不満であった。お好み焼き、というくらいだからいろんな嗜好に合わせた品揃えをして欲しいものだ。
ご飯を食べ終わって、さあ小町通りや鶴岡八幡宮へ行くか、と思ったが、子供はそんなところには興味のあろうはずも無く、早く江の電に乗って帰りたいという。「早く、は〜や〜く〜」を連発してもう辟易だ。仕方なく、駅前のコンビニで鎌倉ビールを買って藤沢へと戻っていった。鎌倉ビールは一本515円もしたが、有名な地ビールなので躊躇無く購入した。
何のことはない、鎌倉へ行ってお好み焼きを食べて帰ってきました、というちょっとした笑い話(小旅行?)でした。
「織田信長 最後の茶会」の話し (2009年10月09日)
戦国時代の信長モノには興味があるので、いろいろと読んでいる。最近刊行された小島毅著「織田信長 最後の茶会 ー『本能寺の変』の前日に何が起きたかー」(光文社新書、2009)は、「茶会」がタイトルとなっているので、今までとは異なった「本能寺」を賞味できるものと期待して読んでみた。
しかし結論から言うと、なぜ「茶会」なのか、どうもピンと来なかった。著者は東アジアの視点から「本能寺」を論じようとしたそうだが、その必然性について、よく理解できなかった。確かに当時東アジアで使われていた太陰太陽暦についての指摘は、今まであまり論じられなかったように思う。しかし石見銀山にせよ、茶の湯の名物茶道具にせよ、それ自体に対する論考はそれなりに納得できるが、そのことと信長の本能寺での横死とはどのような関係にあるのか、明瞭には説明されていない。
信長が天皇に代わって暦を支配しようとしていたことはよく知られているが(そしてそのことの重要性を、小島氏が中国・明の話から説明する点には説得性はあるが)、暦と「本能寺」との関係については、やはり不明確である。本書を「本能寺」の頃の日本国内や東アジアの状況を説明した解説書と思って読めば、それなりに満足感もあるだろう。しかしながら「本能寺」の前日に安土で催された「最後の茶会」で何が起きたのか、という副題にもなっている事柄に対しての回答を期待していたひとりとしては、はなはだ欲求不満かつ消化不良の論説であったと言わざるを得ない。
本書では「本能寺の変」の黒幕についても、その候補者数名を簡単に紹介している。しかしそれも別に目新しいものではなく、黒幕は豊臣秀吉であるという話は、最近話題になった加藤廣の小説「信長の棺」や「秀吉の枷」ですっかり有名になった。公家で関白だった近衛前久であるという説は、安部龍太郎の小説「信長燃ゆ」で取り上げられている。
そのほか、小島氏は示していないが、黒幕を室町幕府第15代将軍・足利義昭とするもの(「謎解き本能寺の変」藤田達生著、講談社現代新書、2003)、さらには奇想天外にもキリスト教を日本にもたらしたフランシスコ・ザビエルが所属していたイエズス会であるとするもの(「信長と十字架」立花京子、集英社新書、2004)さえある。これら二冊の新書における論旨はそれぞれ明快なので、読み物としておもしろかった。
お昼の生協 (2009年10月6日)
今、大学生協の食堂で昼ご飯を食べてきました。開店直後の11時半に行ったのですが、学期始めと雨天とが重なったため、店内はもの凄い混雑で、朝の新宿駅並でしたよ(ちょっと大袈裟かな?)。学生さんにとっては昼食をとる場所として事実上、生協しかないので、全くもって気の毒です。
4大学が統合して学生数は1.5倍程度に増えたのに、学内のインフラは全くと言っていいほど整備されていません。学生会館のような、学生さんが誰でも気軽に溜まれる場所もありません。カリキュラムの充実はもちろん必要ですが、物理的なスペースについてもう少し手を打たないと、本学の人気低下にもつながるのではないかと危惧しています。
さらに言えば、ひと昔前には事実上、教員専用と言ってよいレストランがありましたが、経営が成り立たないために潰れてからは、そのようなファカルティ・クラブを兼ねて教員がゆっくりと昼食をとれる場もなくなりました。生協に行くと上記のような具合なので、肩身狭くせかせかと昼ご飯を食べる、という悲しいことになります。
教員にとっても魅力的な食事のためのスペースがない、ということです。そうすると忙しい場合には生協食堂にも行けないので、コンビニのおにぎりで済ます、ということが多発します。しかしそんなものばかり食べていると、さすがに健康が気にかかります。すなわちこの問題は、教員の健康にも害を与えかねない、労使上の重要問題と捉えるべきなのではないでしょうか。
以上のように本学の食事事情は、学生にも教員にも著しく不適切と判断せざるを得ないでしょう。建築都市コースの上野淳先生が副学長を務めておいでなので、是非とも対応していただきたいと思っています。お金をたくさんとって来たひとのための研究施設を建てるよりも、ずっと重要ではないでしょうか。
JAEE年次大会のプログラム編成 (2009年10月4日)
先月末に投稿受付を締め切った日本地震工学会(JAEE)年次大会の論文ですが、結局投稿総数は175編で昨年の仙台大会並みでした。内訳は以下の通りです。
自然現象 40編
構造物 104編
社会問題 19編
その他(オーガナイズド・セッション含む) 12編
本日、都立大学の実行委員の先生方および事務局の鴫原さんにお集まりいただき、プログラム編成を完了しました。各セッション(全部で22セッションになりました)の座長をお願いする会員の皆様には、これからメールでお願いが届くと思いますが、どうぞよろしくお願いします。
モノつくりの危機 (2009年10月2日)
JCIの「プレストレス技術の有効利用研究委員会」の報告会がお茶の水であった。特別講演として、建築家にして東大土木の教授である内藤廣さんのお話を伺った。その話しが思いのほか(失礼しま〜す)面白かったのである。
現代の建築家の大多数は構造に対する興味もなければ素養などあろうはずがない、ということは、我々構造屋にはまあ周知の事実であろう。だが内藤さんはどうも違うようである(例としてプレストレス技術や木造の仕口について大いに勉強した、ということを述べておいでだった)。
ためになったのは、現代の建物つくりにはFail-safeの機構が決定的に欠けており、そのことが大変に心配である、という指摘である。ひと昔前なら、建築家といえども構造に対するなにがしかの“感覚”を有しており(その例として、数寄屋建築で有名な堀口捨巳を挙げておられた)、構造技術者も“カンどころ”をわきまえていた。また現場でも所長さんや職人さんが経験に基づく“直感”を持っていて、それら三者が何かおかしいことがあったときに、それを見抜いて間違いを阻止するFail-safeの役割を果たしていた、という。
ところが現在は、建築家については先に述べた通り、構造のことは全く分からない。構造技術者もコンピュータの発達とともに、自分が設計しているものと現物、すなわち“モノ”との乖離がはなはだしい、そして現場の所長さんは経費削減などに地道を挙げるだけでモノつくりのことを分かっていない、これは非常な危険性をはらんでいる、というのである。全くその通りですな。将来、何かとんでもない事故が起きるのではないか、ということを危惧する。
日本のモノつくりが危ない、と言われている。最近、私が体験したことだが、某会社の製作・販売するスイッチボックスや変位計にたて続けにトラブルが発生した。それも何年も使い続けた製品ではなく新品に、である。今までそんなトラブルは経験したことがなかったので、いったいどうしたことかと思った。
そのことを長岡テクノの五十嵐さんに漏らしたところ、「それは多分、モノつくりを知らないことから生じるんでしょうね」とおっしゃった。そうか、こんな身近なところにもモノつくりの危機が浸食していたのか、とビックリしたものである。そして今日の内藤さんによる建物つくりの危機に対する警鐘である。
内藤さんはその他にも、そろそろ技術を文化にまで高めるべき時代に入ったとか、プレストレスのような優れた技術をもっと建築家にアピールする努力をするべきである、とか耳が痛いことも指摘された。内藤さんのように構造技術に対してエールを送って下さる建築家を大事にしないといけないし、そういう建築家を増やすように構造サイドが尽力すべきである、ということを強く感じた次第である。
みんなでやろうぜ (2009年9月29日)
「みんなでやろうぜ」、この文句は私には歯切れのよい響きとともに爽やかなイメージを運んでくれます。よい言葉だと思います。研究室で取り組む実験なんかも、みんなでやろうぜってよく言っています。
ところが、新しく自民党の総裁に選ばれた谷垣さんが言うと、なんとも白々しく、嘘くさく感じてしまいます。そもそも一体何を、みんなでやろうって言うんでしょうか。このセリフの裏には、我々国民のことを考えているぞ、という意気込みが感じられませんね。
結局、自分たちの党を立て直して、派閥支配も再確立して、そして政権を奪取して今までみたいにやりたいね、そのためにみんなでやろうぜ、と言っているようにしか感じられません。これではますます国民から遊離した「自分党」となってしまうでしょう。
結局この総裁選で、彼らが国民のために何をやろうとしているのか、日本をどのようにしたいのか、というメッセージはなかったように思います。候補者の三名の方が主張していた、派閥をどうするとか、長老には退場してもらって若手を登用するとか、って自分たちの組織の中だけの話しに過ぎません。民主党の政策はそのうちボロが出て破綻するでしょう、と言うに及んでは、ひとのことよりまず自分でしょ、と国民の失笑を買ったことだと思います。
二大政党制がやっと日本にも現出した、なんて言っていますが、このままでは自民党と民主党とが入れ替わっただけ、ということにもなりかねません(当面はそれでもいいですけど)。自民党の皆さんには政策のプロとして、是非とも自分たちのレゾン・デートルを示して欲しいものです。
WPC構造のプレキャストRC耐震壁に開口を設けても大丈夫? (2009年9月26日)
先日、WPC構造のプレキャストRC耐震壁に開口を設けるとどうなるか、という実験に関わる命題を提起した(このページの9月15日分をご覧ください)。そして現在、壁板中央に開口をあけっ放しの試験体を実験中で、9月25日の晩に変形角0.5%まで載荷した。この段階までに、耐力は無開口耐震壁とほぼ同じであり、変形性能も無開口より優れているようだ、ということが明らかになった。
ただし最大耐力に達する変形は、無開口の場合よりも大きくなったようだ。また繰り返し載荷による復元力履歴形状は、開口ありの場合には顕著な逆S字形を示し、エネルギー吸収性能の観点からは無開口よりも大幅に劣っている。
 
さて、この実験結果をどのように解釈すべきなのだろうか。もともとWPC構造は、壁の強度に期待する典型的な強度抵抗型の建物である。そうすると開口を設けたことによって剛性が若干低下することは問題であるが、壁耐力はほぼ同じなので建物の保有水平耐力上は十分である。
靭性依存型ではないので、変形が大きいところでのエネルギー吸収性能は問題にしなくてもよいだろう。このように考えてくると、WPC構造の(連層ではなく単一層の)PCa耐震壁に開口をあけっ放しにしても、今回の実験における外力状態であれば大丈夫、ということになりそうだ。
当初は開口脇のコンクリートが圧縮力を受けて損傷し、コンクリートが圧壊したり剥落したりするのではないか、と危惧した。ところが、局所的な変形の測定やひび割れ状況から、開口左右の壁板は両方とも剛体回転のように変形し、引張り側の壁板脚部は全体に浮き上がった。すなわち、開口両脇の脚部コンクリートは圧縮力を受けることが無いのでDamage-freeの状況にある。
もっともひび割れ状況を見ると、無開口の場合とはかなり異なってきた。開口を設けた試験体では、開口左右の壁板に斜めせん断ひび割れと曲げひび割れとが明瞭に発生したのである。無開口の場合には、ウエブに相当する壁板にちょろっとしたせん断ひび割れが生じただけだった。すなわち地震後の補修という観点から言えば、開口を設けると明らかに補修費用がかさむことになる。
ただし地震時の外力分布は刻々と変動するため、当該層における曲げモーメント分布が、我々の実験で採用したような台形状に常になるとは限らない。すなわち、WPC構造のPCa耐震壁に孔をあけても大丈夫、と言い切ることはまだまだ早計であろう。まだ実験は継続中で、最終的な破壊状況を注意深く観察する必要もある。
実験を担当する見波進さんや和田芳宏くんとひび割れ状況を見ながら、こうでもない、ああでもない、といろいろ議論したことをもとに、上述のようなことを考えてみた。実験の醍醐味は何といっても、思いもしなかったことが精緻な測定と丁寧な観察から見えてくる、ということに限る。今回の実験も期待に違わず、われわれに多くのことを語りかけてくれるだろう。今後が楽しみである。(これは9月25日の時点での文章です)
遊ぶ子供は… そして、わたくしの少年時代(2009年9月24日)
保育園に通う息子は毎日、四六時中遊び回っている。女房はそろそろ子供の教育のことが心配になってきたらしく、保育園で少しは勉強を教えて欲しいなどと言ったりする。しかし私は子供の仕事は遊ぶこと、と思っているので、今は大いに遊べばよいと言う。さらに言えば小学校時代も大いに遊んで、勉強はほどほどにすればよいと思っている。
こんなはなしを以前に壁谷澤先生の直子奥様にしたところ、奥様は「なに言ってるの、北さん。今は私たちが子供の頃と違って、小学校のときからしっかり勉強しないとダメなのよ」とあっさり否定された。うーん、そんなもんかなあ。でも、二人のご子息をともに東大・地震研究所壁谷澤研究室に進ませた奥様のお言葉なので、千金の重みがある。そして思いは自分が子供だった頃に飛んでいった。
-------・-------・-------・-------・-------・-------・-------・-------・-------・-------・-------・-------・
少年時代は目黒区の公立小学校で過ごした。「窓より望む富士の嶺、朝夕渡る目黒川、、、」という校歌であった。さすがに六年間も歌い続けると、大人になっても忘れないものである。その目黒川から細い坂道(この道はなぜか鎌倉街道と呼ばれていた)を上ってゆき、さらに細い道の行き止まりの奥に我が家はあった。今思えば小高い台地の上だったのだろう。
そこから小学校までは歩いて直ぐである。その近くにはむき出しの崖地があって、この崖の上から、段ボール紙をソリ代わりにして滑り降りる、という遊びが楽しかった。崖地を降りるとそこには神社があって、鬼ごっことか隠れんぼ、缶けりをする絶好のスポットであった。そうそう、「泥棒と警官」というチーム型鬼ごっこもあったな。
また、神社の境内にはイチョウの木がたくさんあって、秋には銀杏拾いに精を出した。子供だから銀杏の匂いも何のその、たくさん拾ってきては種のまわりの実(くさい臭いのもと)を取り除き、きれいに洗った実をフライパンであぶって、殻を割ってモチモチした銀杏を賞味した。とても美味しかった。
夏の早朝には、青葉台の虫取りスポットへクワガタやカブトムシを採りに出かけていった。ここは公有施設の敷地内にあるのだが、坂の脇にある大谷石でできた3mくらいの高さの擁壁をよじ登って侵入した(この壁に登れるようになるまでが大変であった)。まあ、正確に言えば不法侵入という犯罪だろうが、毎朝たくさんの子供たちが集まっており、悪いことをしているという意識はあまりなかったな。ここで私はコクワガタを捕まえた。
小学校には1学年につき3クラスがあり、2年ごとにクラス替えがあった。さて5・6年生のときのクラスには、秀才と言われる同級生が二人いた。ひとりはコマッチ、もうひとりはマコちゃんである。この二人とも鎌倉街道の坂道の脇に住んでいた。
私はといえば、夕方になるまで近所の子供たちと一緒に外を駆け巡って遊び回る、という生活を送っており、夜にちょこっと勉強する、というのが日課だった。皆さんも憶えているでしょうが鶴亀算という文章題の算数問題があって、私はこれが理解できずにえんえん泣いていた。xとかyとかの変数を使えばすぐに解ける(このことに中学生になってから気がつくのだが)のに、なんでこんな問題を解かにゃならんのでしょうかね。
小学生の高学年になってからは日曜模試を受けに行くこともあったが、成績はつねに中くらいかそれ以下だったと思う。ニヒルなコマッチはもの凄く勉強していたみたいで、6年生のときの修学旅行の電車内でなんと高校数学の参考書を勉強していたのだ(微分か積分のような記号を見た記憶がある)。僕たちフツーの子供は将棋とかトランプをして遊んでいたのだから、えらい違いである。
そのかいあってか、彼は東京の御三家と言われる私立中学校に見事合格した。しかしその後、彼がどのような人生を歩んだのか、全く分からない。私は小学校6年生の終わりに新宿区へと引越したため、小学校時代の友人たちとは全く縁が切れてしまったためである。
しかしマコちゃんとは進学した都立高校でバッタリと再会した(当時の都立高校入試は学校群制度であり、新宿区と目黒区とが同じ学区に属していたこと、二人とも某群を選択して合格し、くじ引きでこの高校に配属になったこと、など多くの偶然の賜物であった)。クラスは違ったが、マコちゃんが私のクラスに訪ねに来てくれた。
マコちゃんは背が高くなってちょっとニキビがあったが、私にはすぐに分かった。小学校では私は「キタちゃん」と呼ばれていた。しかし高校生になったマコちゃんは、もうそのあだ名では呼んでくれなかった。私は本当は彼のことを昔のようにマコちゃんと呼びたかったのだが、小学校を卒業して三年の歳月が、我々に否応なく少年時代との訣別を告げたのだった。
やっぱり子供時代には、泥んこになって遊び回ったほうがよいのだと私は思っている。
大きな夢 (2009年9月19日)
もうすぐ、東京でオリンピックが開催されるかどうか決まる。今更オリンピックでもないだろう、と私は思うのだが、今朝の朝日新聞に安藤忠雄氏の「東京でオリンピックを開くことで、日本中がひとつになって、ふたたび夢を追い求めることが大切だ」みたいな趣旨の記事が掲載されていた。なぜ皆開催に向けて盛り上がらないのか、とも。
なるほど、確かに今の日本は元気がなく、誰も夢など持っていないし追い求めてもいないように思える。将来を背負う子供たちには夢を持ってもらいたい。そのためのきっかけとして東京オリンピック2016があるのだと。
安藤さんの高邁な理想自体には別に反対しないが、東京オリンピックが開催された四十数年前とは較べようもないほど成熟した現代日本では、国民がひとつになって夢を追い求める、ということ自体がそもそも夢物語ではないだろうか。
多様な考え方が是認され、自由に生活できる社会に暮らすわれわれにとって、国民一丸となって追求すべき目標(それがオリンピックらしいが)など必要なのだろうか。国民が等しく追い求める“大きな夢”などなくても、ひとりひとりがささやかな“小さな夢”を持って日々暮らしていることは間違いないと思う。
そういう普通の生活を何ものにも制約されずに過ごすことのできる幸せをこそ、守るべきではないだろうか。安藤さんの言うことは文化人としての思慮であり、そこに他意などはないだろうが、オリンピックを開きたいと思っている人達には様々な思惑があることは事実であろう。大方のひとは、そこに脈々と息づく旧態依然とした胡散臭さを感じてしまうはずである。
日本を支配していた悪役自民党が下野して、民主党政権が成立した今、少しは明るい兆しが見えているように思う(これもまた、夢まぼろしかも知れないが)。日本のあり方が変わる予感のほうがよっぽど大切な“夢”を私たちに与えてくれるのではなかろうか。
(付記) 2009年10月2日のIOC総会で、東京はリオデジャネイロにあっさり敗れた。
思いもよらない (2009年9月17日)
先日の建築都市コースの会議でこんなことがあった。
T教授が「今週、学生を連れて見学旅行に行ってきます。インフルエンザが猛威を振るっていますが決行します。何か必要な対策があればアドバイスをお願いします。」と発言された。そうだなあ、世間では豚インフルエンザへの対策に追われているな、と誰しもが再確認したと思った。
と、そのとき、建築都市コースにおける唯ひとりの医学博士であるH教授が、以下のような趣旨の発言をされたのである。
「インフルエンザに対して、こんなに大騒ぎしている国は世界中で日本だけです。普通に健康に暮らしている人にとっては、インフルエンザに感染しても発症しないことも多く、発病しても重篤化することは少ないでしょう。それよりも、日本では毎日百人近いひと達が自殺して亡くなっています。また、交通事故でも一日に数十人が亡くなっています。このような現実を認識したとき、インフルエンザにこれだけ大騒ぎするのはどうでしょうか。」
なるほど、国民が健康な生活をおくるという観点から、このような見方をするひともいるのか、と非常に感心した。よく、日本の常識は非常識、ということが言われるが、今回のインフルエンザ禍についてもどうやらそれが当てはまるようだ。いかに我々がマスコミの報道によって物事を一面的にしか見ていないか、ということを痛感した。
ただ、どんな原因で亡くなるにせよ、ひと一人の命は何ものにも代え難い。費用対効果だけでそれらへの対策の優先順位を決める、というのも心情的にはしっくり来ない。結局、問題点を皆で共通に認識して、それに対して議論する、という地道な作業が必要なのであろう。
WPC構造のプレキャストRC耐震壁に開口を設けるとどうなるか (2009年9月15日)
国土交通省が研究費を助成するWPCプロジェクト(本学の建築家・小泉雅生准教授が言い出しっぺで、研究代表者である)も2年目となり、WPC造5階建ての集合住宅をモデルとした連層耐震壁実験がいよいよ始まった。試験体の製作は、WPCプロジェクトに加わっているプレハブ協会の会員会社である安藤建設にお願いした。
プロジェクト研究なので実験実施もチームを組んで行っている。実験全体の統轄と差配は見波進助教にお願いし、学生側のチーフはプロジェクト研究コース(特定の研究室には所属せずに、数名の教員の集団指導を受けるという建築学域特有の修士課程コース)に所属する和田芳宏くん(M2)とし、卒論生として北山研の黒倉花さんおよび高木研の長谷川君が担当している。
5階建ての2階部分を検討対象として、試 験体ではその上下に約1/4層分ずつを付加した形態とした(写真はこちら)。直交壁および床スラブも付いている。連層耐震壁が対象なので、その曲げモーメント分布は逆対称曲げではなく、上下に逆方向の曲げモーメントが作用する台形状の分布である。 験体ではその上下に約1/4層分ずつを付加した形態とした(写真はこちら)。直交壁および床スラブも付いている。連層耐震壁が対象なので、その曲げモーメント分布は逆対称曲げではなく、上下に逆方向の曲げモーメントが作用する台形状の分布である。
このような応力状態を再現するため、試験体頂部のRCスタブの上方に取り付けた2基の鉛直ジャッキによる軸力を、水平力に比例して増減させることにした。これを理研精機作成のソフトウエアによって制御したのだが、配線やらアルゴリズムやら複雑な事柄をひとつずつクリアせねばならず、見波さんはさぞ大変だっただろう。
長岡テクノの五十嵐さんが折に触れ親切かつ丁寧に説明して下さるのだが、電気に詳しくない私には正直言って理解できないことも多々あり、既に私の手には負えなくなっている。
さて、実験のオープニングを飾る試験体は、開口のない無垢のPCa耐震壁である。結果として無事、加力することができて一体目は終了した。プレキャスト版同士を接合するセッティング・ベースが降伏したあと破断して終局に至った。担当の和田君曰く「もう少し、派手に壊れると面白みもあったんですが」。
まあ、これはこれでよいのだが、ちょっと困った結果でもあった。高木次郎さんの検討によってうすうすは分かっていたのだが、プレキャストの壁板にはわずかなせん断ひび割れが生じたにとどまったのだ。そのせん断ひび割れも直交壁と床スラブとで囲まれた入り隅部分にちょこっと生じたものに過ぎず、壁板の中央部分は無傷で残ったのである。
すなわち壁板中央には少なくとも斜めせん断ひび割れが生じるほどの力は作用しなかった、ということになる。このことから得られる推論は、壁板の中央部分にはコンクリートがなくてもたいして不都合はないのではないか、すなわち中央部に開口を設けても、それほど耐力は低下しないのではないか、ということである。
そうだとすると、壁板に開口を設けてもそのための補強などいらない、という結果になってしまう。げげっ、そうだとすると一年間、大勢で雁首揃えて補強方法を考えたのはどうなっちゃうの?
でも、本当にそうだろうか。開口を設けたのに壁耐力が減少しない、などということは直感的には理解しにくい。壁板に引張り力は生じなくても、ある程度の圧縮力は流れていたはずである。という訳で2体目は、壁板に開口を設けたままの試験体に加力する予定です。その結果や如何に?、答えはもう直ぐ明らかになります。これから暫くはワクワク、どきどきの毎日を過ごすことになりそうです。
広尾というところ (2009年9月10日)
地下鉄・日比谷線の駅に広尾(ひろお)というところがある。私は子供の頃、この地下鉄線の始発駅である中目黒駅から歩けるところに住んでいたが、広尾で降りたことはなかった。多分、生まれて初めて今日、広尾駅で下車したのだと思う(なんて、大袈裟なものではありませんが)。設計事務所を営んでいる青木茂先生(リファイン・ファイターと私は密かに呼んでいる)の東京事務所が広尾にあり、研究の打ち合わせのために北山研のM1・白井遼くんと一緒に伺ったのである(ちなみに研究対象は、神戸市灘区にあるF医院のRC5階建ての建物である/こちらをどうぞ)。
青木先生は私の研究室の隣の住人なので、大学内で打ち合わせすることはもちろん可能なのだが、たまには気分転換も兼ねて都心にでるのもいいかな、でも実は青木先生から「広尾には、美人が多いですよ」と言われたことのほうが決め手だったであろう。ちなみに広尾はローマ字表記では「Hiroo」であるが、この綴りを見た外国人は「ひろお」とは発音できないのではないか。地下鉄の駅から地上に上がってきて、この綴りの看板を見たときには日本人の私ですら、なんじゃこりゃあ、と思ったのだから。
広尾の街をちょっと歩いてみて、外国人が多いこと、アメリカに良くあるような雰囲気を持ったスーパーマーケットや飲食店が多いことにすぐに気がついた。しかしそのような表通りから、車は通れないような狭い路地を入ってゆくと木造の住宅が続き、そこのどん詰まりに青木事務所はあった。何とギャップの大きい街であることか!
東京都心のど真ん中にこんなところがあるとは知らなかった。すぐそばには有栖川公園があり、緑も意外と豊富である。うーん、こんなところに住んでいる人たちは日本人だろうと外国人であろうとお金持ちなんでしょうな。このような場所を事務所に選んだ青木先生に脱帽、である。
 
研究打ち合わせのあと、青木先生に御馳走していただいたイタリア・レストランには、ほとんど女性のお客さんしかいなかった。「ここは男一人じゃ入れませんよ」と青木先生も言っていた。そこで白井君は白トリフをのせた鳥唐揚げを食べたのだが、「今まで食べたこともない鳥唐です」などと言う。確かに見た感じは日本の鳥唐とは違っていた。へーえ、てな感じである。
青木事務所の神本さんが白井君と全く同じものを食べていたのが、ちょっと可笑しかった。青木先生からいろいろと面白いことを伺ったのだが、安藤忠雄は双子の兄貴である、という話しに一番びっくりした。さらに安藤忠雄の一番下の弟は建築家の北山孝二郎氏である、ということも初めて知った。
こうして、短時間のささやかな異次元体験は終わったのであった。お忙しいところお付き合いいただいた青木先生、神本さん、ありがとうございました。面白かったのでまた伺います。
幼稚園バスの話し (2009年9月6日)
先日の朝日新聞に、幼稚園児の送迎バス(幼稚園が運用するもの)にはシートベルトがついておらず、法令でもそれが例外として認められている、という事実が載っていた。なぜそうなのかと言う理由として、園児のシートをなるべくたくさん配列するためと、送迎バスの運行時間をできるだけ短縮する(シートベルトを締めたり外したりするとべらぼうに時間がかかる)ためとが指摘されていた。
私の家のそばにも毎朝、幾つかの幼稚園の送迎バスが通ってゆく。制服を着たかわいい子供たちがたくさん乗っているのもよく見かける。しかしそのバスにシートベルトがない、ということには全く気がつかなかった。この事実に驚愕するとともに、そのことに迂闊にも気がつかなかったということに、さらに驚愕したのである。
自家用車にはチャイルドシートが義務づけられているのに、多数の幼児が乗る送迎バスにはなぜシートベルトを付けないでもよいのか、全然理解できないし、上記の理由も何ら論理的なものではない。お上よ、おかしいですぞ! こんなところにも子育て支援の行き届かなさが現れているのだと思った。世の中の矛盾のしわ寄せは常に弱者に対して為されるのである。
うちにも小さい子供がいるのでよく分かるのだが、子供を車に乗せているときにもしもシートベルトをしていなかったら、加速や減速のたびに子供はゆさゆさと揺さぶられ、危なくてとても運転などできやしない。この日頃の体験から敷衍すると、幼稚園の年頃の子供は送迎バスの中で、大変に危ない状況に置かれている、としか言いようがない。
前述の新聞記事は、送迎バスの運転手をしている方の投稿みたいなものだったのだが、一番安全を図らなくてはならない幼稚園の送迎バスのお寒い実体を指摘し、早急にシートベルトを配備すべきである、という意見には全く同感である。我が家では幼稚園に通っていないので直接に関係はないが、同じ年頃の子供を持つ親として、とにかく早く対策を講じて欲しい。
暑い夏 (2009年9月1日)
台風が去って、空には秋のうろこ雲が流れているものの、名残を惜しむ夏が戻って来た。9月になったが、まだまだ暑い。
8月末の衆議院総選挙では、少しは予想していたものの、ドラスティックな政権交代が実現した。自民党から民主党へと議席数がそっくり入れ替わる現象を、マスコミでは「オセロ現象」と言っているようだが、まさにその通りである。
表面的には、これだけの人びとが自民党政治に不満を抱き、政権交代を希望した、ということの現れだろうが、本当にそうであろうか。四年前の小泉政権による劇場選挙を思い出すとき、周りの人たちの振る舞いや、マスコミの論調に煽られて、今回は民主党に投票しよう、と付和雷同したひとが多かったのではないかと想像する。
何といっても我々は、周囲の顔色を見て判断し、自分の過去を反省しない「日本人」ですからな。民主党をこんなに勝たせるつもりは無かった、などと言う市井の人びとの反応を聞くと、それなら社民党や共産党に投票すればよかっただろう、などと思ってしまう。
まあそうは言うものの、今回の選挙に対する一般市民の関心の高さは、投票所にひとが溢れていたことからも実感することができた。私がいつも行く投票所は、昔の野川を埋め立てた上の遊歩道沿いにある、小さな地域センターであるが、雨の午前中にも関わらず、投票所の入り口には長蛇の列が並んでいたのである。
そんなことは今まで無かったので、少なからずビックリした。私の住む狛江市は、全国でも珍しい共産党員市長が治めているところなので、比較的共産党のシンパが多い地域だと思うが、それでも今回は民主党の候補者が(最終的には)圧倒的に強くて当選した。
民主党が政権を奪取したのはいいが、ちゃんとした政治ができるのか、と不安がる人たちがいるが、それは大丈夫だろう。だって民主党議員の半数くらい(?)はもともと自民党にいた人たちなんだから。選挙結果の大勢が判明した深夜に会見した鳩山さんが、「三つの交代」を宣言したのをテレビで聞いたとき、この人はそれなりの決意を持って日本の政治の改革に望むだろう、という感触を得たし、その態度には感銘を受けた(私は民主党員ではありません、念のため)。
これからしばらくは、民主党の政治改革に期待したいと思う。特に、官僚主導の政治を廃して官僚には実務的なお仕事に徹して貰うような、国民主導の政治を実現するように頑張ってもらいたい。
暑い夏はまだしばらく続きそうである。
夏の苦行が終わって (2009年8月30日)
日本建築学会の大会が八月末に終わった。今年の会場は、仙台駅から市営地下鉄に20分ほど乗ってから、シャトルバスに10分ほど揺られて到着する東北学院大学であった。今年の会場となったキャンパスはコンパクトに建物がまとまっていて、会場間を延々と歩かされるということは無かった。
しかし、朝、地下鉄の泉中央駅を降りてからシャトルバスに乗るまでに、もの凄い人数の参加者のために、べらぼうに待たされたことには本当に参った。地下鉄出口を出る前から延々と続く行列に、地元の人々は一体何事が起きたのか、ときっと驚いたことだろう。バスに乗れば乗ったで、すし詰めにされるため、会場に着いたときにはもう、ひと仕事したかのように「やれやれ」という疲労感でいっぱいとなる。
大学の建築学科に所属する身にとっては、大会の梗概2枚を書くことは最低の義務だと思っているので、大学院生になって以来、必ず大会で発表してきた(もちろん、最近では北山研の学生さんに梗概を執筆してもらうことも多い)が、だんだん年をとってくると会場までの道のりが苦痛になってきて、この難行苦行を何とかしてくれと言いたくなってきた。
思えば昨年は広島大学が会場であったが、広島駅からJRのローカル線に延々と揺られ、そこからまたシャトルバスに乗ってやっと会場に着く、という有様であった。JCI年次大会のように駅そばのホテル等の交通至便な場所で学会大会を開けないのは、大会の規模が余りにも大き過ぎて、これを収容できるのは大規模大学くらいしかない、ということと、延べ人数一万五千人?にも上る多数の参加者を収容できるキャパシティを持った都市でないとダメである、ということであろう。
あまりにも膨れ上がった大会を、コンパクトに縮めることをそろそろ考えた方がいいだろう(多分、学会執行部はそのことは認識しているのだろうが、今までの経緯としがらみから、構造系、計画系、環境系といった系別の大会開催に踏み切れないのではないか)。
発表時間も一題あたり五分しかなく、これではほとんど何も発表できず、PPTの発表だけ聞いても何も理解できない、という状況である。このままでは、学会大会に参加しようという意欲は減退するばかりではなかろうか。それとも、今後学生数の減少にともなって、建築学会員も減るだろうから、大会参加者も自然と減少する、という穿った見方をして、何も手を打たないのだろうか。
聞くところによると、来年の大会開催地は富山らしい。私の知る限り、富山での開催は初めてである。私は富山には行ったことがないので、これを機会に行ってみたいとも思う。しかし富山出身の塩原等さん(東京大学)によると、30万人都市の富山市に、学会大会の参加者を収容するだけのキャパシティはとてもない、ということである。そうなると我々はどこに泊まればいいのだろうか。まさか宇奈月温泉というわけにも行くまい(笑い話としては皆さん口にするが)。今から来年の大会が心配なのは、私だけだろうか。
追記(2009年09月01日): 来年の富山での大会について、昨日、吉川徹さん(本学教授で都市解析が専門)と話していたら、何でも富山からの熱烈なラブコールによってこれが実現したらしい。宿泊の収容人数についても、地元がちゃんとしたデータ(数字)を示した、とのことである。うーん、本当かなあ。宇奈月温泉の旅館もかずに入っていたりして。それにしても恐ろしい地獄耳である、吉川さんは。さすがは、都市計画研究者!
追記2(2009年09月03日): 昨日、PC構造運営委員会に出席した。そこで、来年の大会の場所・日時が明らかになった。
開催場所:富山大学五福キャンパス
開催日 :2010年9月9日(木)〜11日(土)三日間
鹿島の丸田さんは、明日にでも宿を予約する、と言っていました。冗談にもなりませんぜ、まったく。
モンゴルの草原から (2009年8月24日)
「ノモンハン事件」という今からちょうど70年前の出来ごとをご存じでしょうか。1939年5月から9月にかけて、旧満州国軍および旧日本軍(関東軍)がソ連およびモンゴルの連合軍と戦った戦争のことで、この事件を契機に日本軍部は関東軍の暴走を止めることができなくなり、やがて日本は破滅への道を歩むことになった。この戦争の舞台となったのは、旧満州国とモンゴル人民共和国との(曖昧な)国境付近の草原であり、通常われわれはその地を「ノモンハン」であると思っている。
しかしながらモンゴル学者・田中克彦氏の著書「ノモンハン戦争」(岩波新書、2009)によると、ノモンハンとは地名ではなく、チベット仏教の「法王」という意味だそうだ。この著作は、私が今まで全く考えたこともなかったような事柄や視点を教えてくれたという点で、きわめて示唆に富んだ良書である。
日本では「ノモンハン事件」と呼んでいるものが、モンゴルの人々にとっては(ソ連からの)真の独立を勝ち取るための「戦争」であったということ、当時のモンゴルはソ連の衛星国家と見なされており、モンゴルの多数の指導者がスターリンによって粛清されたこと、ロシアやモンゴルでは「ノモンハン戦争」についてソ連崩壊後にやっと自由に研究できるようになったこと、などである。
われわれ日本人はモンゴロイドであると言う。ということは、その祖はモンゴル人ということになる。しかしながら、私はモンゴルと言う国に行ったことがない。さらにモンゴルの地誌や文化についても何にも知らない、ということに気がついた。
田中克彦氏の著作で初めて知ったことは多いが、モンゴル人は姓を持たない、ということにびっくりした。近代になってパスポートなどで姓を示す必要が生じると、父親の名を前につけて「誰々の子」○○と名乗るようになったそうだ。横綱・朝青龍の名前は「ドルゴルスレンギーン・ダグワドルジ」というそうだが、これは「ドルゴルスレン」の子である「ダグワドルジ」という名前、とのことである。
もうひとつ気がついたことは、「ノモンハン戦争」に大きく関わり、この戦争の集結を妨害した人物が関東軍参謀・辻政信少佐だったことである。この事実は、やはり最近読んだ「沈黙のファイル 〜『瀬島龍三』とは何だったのか」(共同通信社社会部編、新潮文庫)の中にも記述されており、それによると辻政信は「ノモンハン事件」の責任を問われることなく旧陸軍内部で野放しとされ、その後、大本営の中枢にいて太平洋戦争におけるガダルカナル島などの悲劇の作戦を立案・指導することになる。戦後は逃亡を続けて戦犯としての訴追を免れ、国会議員となったことはよく知られている。
田中克彦氏はそのことにも触れ、最後に「私たちが、占領軍としてではなく、日本人として裁かなければならないのは、このような人物である。このような人物は、過去の歴史の中で消えてしまったわけでは決してない。今もなお日本文化の本質的要素として、政界、経済界のみならず、学界の中にまで巣くっているのである。」という警世の句でその著作を結んでいる。
八月十五日の終戦の日も過ぎたが、日本人は中国との戦争および太平洋戦争についての責任の所在を追求することなく曖昧なままに戦後64年を経過した。このことの報いが今日の日本社会に重くのしかかり、さまざまな社会的ひずみを生み出している、と考えざるを得ないだろう。「ノモンハン戦争」から70年後、モンゴルの草原からの風は結局、日本人とは何であるのか、という自己に沈潜する重い問いを私に吹き寄せたのであった。
今年のお盆 (2009年8月14日)
今年の夏は雨が多くて、日本の夏らしいカンカン照りの日はあまりなかったように感じたが、お盆になってやっと例年通りの「日本の夏」がやって来た。ギラギラ輝く太陽に向かって「暑いぞ〜」と叫びつつ天の恵みに感謝、である。
さすがに今日はキャンパスの人影はまばらであったが、私はと言えば、お盆のお陰で学外での会議は全くないため、今まで溜まりにたまったお仕事を片付けるために学校に登校した。学部2年対象の「建築構造力学1」の成績付けをまずやったのだが、過去の成績分布を参照しようと思って昨年の帳面を開くと、なんと昨年成績を付けた日付も「8月14日」とドンピシャ、今日と全く同じである。何だかなあ、去年もお盆に仕事していたんだあ、という感慨が新たになる。
阪大の岸本さんとメールでボヤキ合ったんだが、大学の教員ってなんでこんなに忙しいのでしょうか。昔の大先生がたが過ごした「古き良き時代」は二度と来ないんでしょうな。こんなことを思いながら、成績のマークシートを一つずつ、ぐりぐりと塗りつぶして行く。これをやる度に、高校三年生のときに受けた「共通一次試験」を思い出す。あのころは問題を解いた上に、この“ぐりぐり塗り”をやっていた訳で、ものすごい集中力&パワーだなあと若い頃を懐かしむのである(なんだか老人臭くなって、気が滅入ってきた)。
ところで「建築構造力学1」の成績だが、大学が新しくなってから毎年70名程度の学生が受験する。そして、ここ3年間の平均点の推移を見ると50点、55点、65点とだんだん高くなっているのだ。それも今年に至っては平均点が一気に10点も上昇し、満点ホルダーまで登場したのである(これは素晴らしいことである/拍手拍手)。
例年、試験の点が足りなくて落第する学生諸君が必ず数名いるのであるが、今年初めて受験者全てが単位を取得する、という快挙?(誰の快挙だろうか、学生?それとも教師たる私?)を達成したのである。問題の質・量とも例年同じようなものであるので、これは学生の平均的な学力が上昇した、と考えるのが合理的である。これも私の教育の成果であると素直に喜べばいいのかも知れないが、どうもそんな気はしない。私の授業では、毎回演習問題を提出させて添削して返却するのだが、その出来は逆にだんだん悪くなっているのが明らかだからである。これっていったい、どういうメカニズムなんでしょうか。
そのあと大学院のレポートを採点し、書き直し作業中の「RC構造」の教科書(市ヶ谷出版社)の校正をやったり新しい写真を準備したりした。さらに、2010年出版予定の改定RC規準・同解説のうち16条(付着・重ね継手)の最終版を作って、建築学会のサイトにアップした。
そんなことをしている合間に、京大の西山峰広先生から「PC部材の構造性能評価指針(案)・同解説」に対する査読意見がメールで届いた。その直ぐあとに、こちらも京大の田中仁史先生からメールが届いた。京都は多分東京よりも暑いだろうに、皆さん仕事熱心なことだなあ、とひとしきり感心したが、同様の我が身に思い至って、このお盆に仕事しているひとが遠い京都の地にもいるんだ、ということに妙な連帯感を持ったりしたのでした。
筑波大学の境有紀さんからは、先日の震度6弱だった静岡の地震の現地調査写真をHPにアップしたとの連絡を貰ったので、ちょっと覗いてみた。いつもながらの素早い行動には本当に感心する。このお盆の時期に、しかも東名高速が不通になっているのに、どうやって行ったんだろうか。
木造家屋の屋根瓦が落下するという被害が多かったようだが、甚大な建物被害は生じていないようなので、とりあえずひと安心だろう。ただ、浜岡原発の5号機で観測された加速度が、他の建屋よりもずば抜けて大きかったことが気になる。これでまた仕事が増えるんじゃないかと、ビクつく私でした。
こうして今年のお盆も過ぎていったのである。やれやれ(ため息)。
駒場へ行く (2009年8月8日)
日本建築防災協会に設置された「耐震診断法の高度化検討委員会」のRC部会が、主査の中埜良昭さん(駒場・本郷を通じた同級生で、現在は東大教授)の勤める東大生産技術研究所(生研と略す)で開かれることになり、本当に久しぶりに京王・井の頭線の駒場東大前駅で下車した。駒場には東大教養学部があり、東大に入学すると必ず2年間は通うキャンパスである。一方、生研はかつては六本木にあったが(私が大学院生の頃には、授業で毎週六本木に通ったものである)、10年ほど前に旧宇宙研があったキャンパスに移転していた。その移転した生研を訪れるのは今回が初めてである。
駅の改札を抜け、坂下の道に出ると、学生の頃によく行ったそば屋「まるが」の変わらぬ佇まいが眼に飛び込んできた。まさに、懐かしいなあ、である。しかしそのあとは、教養学部キャンパスとは反対方向への道行きなので馴染みはなく、汗を拭き拭き、旧前田侯爵邸などがある高級な感じの住宅街を歩いて行くと日本民芸館があって、やがて細い道の民家の真ん前に、壁のようにそそり立つ生研の建物が見えて来た(左下の写真はキャンパス内から撮影したファサード)。
うーん、どうも場違いである。ジュラルミンのように銀色に輝く外壁を持つ中層建物が、こんなところに建っていていいのだろうか。あとで中埜さんに聞くと、設計者は原広司先生とのこと。そう言われると、何となく京都駅と似たところもある。ただ、街並みのコンテクストは、全く考慮されていないのではなかろうか。そんなものを考慮していては、機能的な大学キャンパスは設計できないのかも知れないが。
 
しかし建物の中に入ると、内部とも外部ともつかないアトリウムがあったりして、楽しさを感じさせてくれる(右上の写真)。会議で使用したスペースは、立派な机と椅子とがあり、バーのカウンターのようなコジャレた流しが付いていたりした。またこのスペースは、全面ガラス張りで廊下とアトリウムに接しており、明るい陽の光が差し込んでくる利点はあるものの、通り過ぎるひとが容赦なく視線に入ってくるため、落ち着かない気分もした。建物自体は南北に非常に長く、廊下の長さは何と200mもあるとのことで、ちょっと異様な感じもした。
陽が傾いて会議が終わったあとには、中埜研究室の夏の懇親会が開かれ、私も本当に久しぶりに参加した。名誉教授の岡田恒男先生もおいでになっていた。かつて学生の頃には、六本木の旧近衛部隊の隊舎をそのまま利用した生研の建物の中で、どんちゃん騒ぎをしたものであるが、時代が変わって今は、なんだかスマートな空間のなかで品よく行儀よく飲んでいる、という感じであった。回りが住宅街のため、キャンパスのそばには飲み屋はないらしく、飲みに行くには渋谷まで行くしかない、と中埜さんが言っていた。
こうして宴会の中締め後に、ひっそりと生研キャンパスをあとにして帰途についたが、駒場から我が家まで一時間ほどで辿り着き、案外近いんだと思った次第である。
あるレクチュア、もしくは転換するパラダイム (2009年8月2日)
先日、日本建築学会の柱梁接合部WGという部会が建築会館で開かれた。これは東大の塩原等先生が主査を務めるWGで、ひとことで言うと、RC柱梁接合部の耐震性能評価法を確立して、その設計法を作成するというタスク・フォースである。通常のWGであれば、委員各自が自身の研究成果に基づいて分担範囲を定めて作業し、主査はそれぞれの仕事の成果をアセンブルして成案を得る、という形態をとることが一般的であり、かつ効率的に作業を進める最善策であろう(私自身が主査を務めるWGでも、この手法によって運営している)。
ところがこの日のWGは一風変わったものであった。WG冒頭から、主査の塩原さん(私の3年先輩である)が、ご自身の提案している柱梁接合部パネル四分割回転モデルを検証するための極めてシステマティックな実験結果を紹介して、塩原理論の正しさを説明する、というレクチュアが延々と続いたのである。その挙げ句、3時間の会議時間はあっと言うまに過ぎてしまった。
このWGには10名近い委員が出席しており、その間、塩原さんの説明に質問したり反論したりするのだが、その度に塩原さんに「あなた、今まで何聴いてたの」とか「あなたは間違っています」とか「まだ、そんなこと言っているんですか」とか、もうさんざんに叱られてしまった。ああ、またかと、いつものことながら辟易とした(すいません)。
確かに塩原理論は、さすがに天才と言われるひとの自信作だけあって秀逸であり、「なるほど」と頷かされるものが随所にある。RC柱梁接合部の力学挙動について、相当程度に統一的に解釈できているようにも思う。そういう彼の先進的な理論に対して、私を含めた多くの委員が「ええ? そうかなあ」などと首をかしげ、「そうは言っても、今までのこれこれの実験結果はどう解釈するのか」などと言っているのを見て、私は次のような妄想?に捕われた。
その昔、宇宙の中心は地球であると誰もが信じて疑わなかった頃、コペルニクスが「地球は太陽の周りを回っている」と言ったときの周囲の反応は、もしかしたらこんなものだったのではないだろうか。
サイエンス・ライターのサイモン・シンが著書の中で言っていたが、自然科学上のパラダイムの転換とは、たったひとりのトップ・ランナー(例えばコペルニクスとかニュートンとか)が提唱した理論がはじめは世間からソッポを向かれて反駁されたり無視されるが、やがてそれらの抵抗勢力が死に絶えたのちに、その理論が真実であることが再発見されて、やっと実現するものらしい。
塩原さんがウンザリとした眼で我々を見回すのを見ていると、この感を強くせざるを得ない。さしずめ、今までひとかどの研究をしてきたとの自負を持つ我々WG委員が抵抗勢力、といったところであろうか。
しかしその一方で、今まで我々が研究してきたことの全てが的外れであったり、間違っていたとも思えない。結局、学問の進歩とは、多くの研究者たちによるこのような議論の成果として達成されるものである、とも考えるのである。
約30年前、私がRC構造の研究を始めた頃、RC柱梁接合部のせん断強度を与える式として、接合部横補強筋によるせん断補強効果を考慮した上村式というのがあって、よく知られていた。しかし実験結果からは、接合部横補強筋によるせん断強度増大はほとんど見られなかったことから、私を含めた何人かの研究者は、接合部せん断強度は主としてコンクリート圧縮強度によって決定される、という風に考えるようになった。やがてこの「接合部コアコンクリート圧壊理論」が多くの研究者の受け入れるところとなって主流を形成し、学会の終局強度指針や靭性保証指針では採用された。
そして今、ほとんどの人は気づくことはないが、次代の転換点はもうすぐそこまで来ているのかも知れない。この是非は、やがて歴史が示してくれるであろう。
今は唯、自分ができることを精一杯やるだけである。
RCの教科書 (2009年7月22日)
市ヶ谷出版社から出している「建築家のための鉄筋コンクリート構造」(共著)という教科書があります。自慢じゃありませんが、この教科書は全然売れていません。編集者からは「こんなに工夫して作った本なのに、これほど売れない本は今まで無かった」と言われる始末です。教科書のタイトルに「建築家のための」と入れたのが逆に仇となって、大学や高専の学生向けの教科書とは捉えられなかったようです。われわれ執筆者の意図は、構造系以外の学生にも十分に理解することができる、ということだったのですが。
また、内容も基礎的なものと応用的なものとが混ざっていて、授業で使いにくいという声もいくつかいただきました。そもそも、この教科書を使って「RC構造」の授業をやっている北山自身が、この教科書通りには教えていない、という問題点?もありました。ただ、中味はわれわれの自信作ですので、手前味噌ですが「この教科書はいいぞ〜」と胸を張って言うことができます。
そこで、4名の執筆者(林静雄、衣笠秀行、坂田弘安そして北山和宏)が相談して、この教科書を大幅に改定することにしました。基礎編と応用編との二つに大別して、半年の講義や通年の講義、あるいは大学院の講義に明確に対応できるようにします。また、文章もさらに平易にするように見直しています。現在、これらの作業中ですが、2009年10月には書店に並ぶようにやっています。
と言う訳ですので、新版「鉄筋コンクリート構造」をどうかご期待下さい。
室町幕府を開いた兄弟 〜尊氏と直義〜 (2009年7月21日)
突然ですが日本の中世史のなかでは、室町時代ってあまり馴染みがないと思いませんか。後醍醐天皇による建武の親政は有名で、その後に起こった南北朝の争乱も楠木正成の活躍や大塔宮の悲劇などでよく知られています。しかし室町幕府の覇権がどのような経緯で確立したのか、京都・室町幕府の征夷大将軍と鎌倉府の鎌倉公方との二本立ての日本統治はなぜ成立したのか、などについてはあまり馴染みがないと思います。時代小説でも、足利尊氏や二代将軍・義詮(よしあきら、尊氏の長男)を主人公にしたものは見かけません(私が知らないだけでしょうかね)。私にとってはまさにこのような認識でしたが、最近本学名誉教授の峰岸純夫氏の「足利尊氏と直義」(吉川弘文館、2009年6月)という本が刊行されたので読んでみました。
足利尊氏と直義(ただよし)とは兄弟です。鎌倉幕府の執権・北条氏を倒して足利政権を樹立した頃は、この兄弟の二人三脚で政権が運営されましたが、やがて尊氏・高師直(こうのもろなお)、直義・上杉憲顕、という派閥が形成されて相争うようになり、最後は直義方が破れて、直義は兄・尊氏に降伏しますが、その直後に直義は没します。「太平記」などでは直義は尊氏に毒殺された、ということになっており、テレビの時代劇などでもそのように脚本されることが多いようです(NHKの大河ドラマ「太平記」では、真田広之扮する尊氏が、高島弟の扮する直義に泣く泣く毒を飲ませるシーンがあったことをよく憶えています)。しかし本書の著者は、そのようなことは史実ではなく、戦乱に疲れた直義は急性肝炎で病死した、という立場をとっています。う〜ん、どうでしょうかね。降伏してお寺で謹慎生活を送りはじめた直義が急死した、というのはどう考えても胡散臭いですな。そこに何かあった、と勘ぐるのは常人の性というものでしょう。
ちなみに上下関係で結ばれた、歴史上有名な兄弟は、すぐに何組か挙げられます。源頼朝と義経、豊臣秀吉と秀長、江戸時代初期の徳川家光と保科(のち松平)正之、などです。秀長と正之とは兄を補佐した名脇役と言われており、直義のように悲劇的な最後を迎えた弟は、源義経だけですね。頼朝は肉親に冷酷でしたが、尊氏はそのようなことはなく慈悲に溢れた武将であった、ということを古文書の記述などから著者は説明します。しか〜し、これもどうでしょうかね。室町幕府を開くという偉業を成し遂げたひとですから、綺麗ごとばかりでは済まなかったということは容易に想像できます。徳川家康も幕府を開くまでに、長男・信康と婦人・築山殿を亡き者としたくらいですから。
鎌倉の政庁は、はじめは鎌倉将軍府として直義がその長を務めていたようですが、やがて鎌倉府となって尊氏の次男・基氏が鎌倉に下向してきて、関東一円を支配する政庁として確立したようです。しかし、京都の室町幕府と関東の鎌倉府とは、同族だけに憎さも百倍といった感覚で、しだいに骨肉相食む泥沼へと踏み込むことになります。このあたりのことについては、歴史小説ではさらに取り上げられることはないのですが、人間ドラマとしては大変に興味があります。そしてこの京都と鎌倉(関東)との争いは、足利氏自体の権力の衰退の主因となって、やがて応仁の乱から戦国時代へと突入することになるのです。
さて、この本を読んでいて一番びっくりしたのは、尊氏は躁鬱病だった、という筆者の主張です。躁状態のときはスーパーマンで合戦でもガンガン勝つのですが、一旦鬱状態に入ると家に籠って人には会わず、その代わりを弟・直義が務めていた、というのです。これは、ありそうですな。尊氏の父、祖父ともに異常性格者であった、とも言っています。それから直義方に討ち果たされた高師直は、江戸時代の歌舞伎の影響があって希代の悪人というイメージが定着していますが、実際にはそんなことはない、ということにも、いかにもありそうで納得しました。とにかく歴史に対する先入観って、恐ろしいですね(これは多分に小中学校の教育にも関わってきます)。
最後は、足利尊氏が京都・清水寺に出した願文(がんもん)のセリフで締めくくりましょう。
この世は、夢のごとくに候、……
人生の無情 (2009年7月04日)
梅雨の時期は不順な天候が続くせいか、この6月末から7月初めにかけて訃報が相次いだ。鬼籍に入ったRC研究の偉大な先輩方に続いて、7月初旬の週末には中学時代の同級生の悲しい知らせを受け取らねばならなかった。新宿区立の某中学校(少子化のために既に他校と統合されて、今はもうない)の同級生とは、現在ではわずかに4名しか付き合いがなかったが、そのうちの一人であった。中学を卒業してからも、時々は同級生4人で雀卓を囲んだものであった。だが、最後に会ったのはもう十年も前だったろうか(彼も私もともに調布に住んでいた頃、調布駅脇のラオックスでばったり出会ったのである)。
高校のときの担任であったN藤先生が教えて下さった「Man is mortal.(人間は死すべき運命にある)」という警句は、折にふれ私の脳裏によみがえって来るが、今日ほど人生の無情を強く感じたことはない。織田信長の「人間五十年,,,」ではないが、もうすぐ人生を経ること半世紀を迎えようとする我が世代からも、彼岸へと旅立つ者が出始めたかと思うと、全く気が滅入った。S君の冥福を祈る。
巨星墜つ さよならPaulay先生 (2009年06月29日)
RC界の巨星にしてGentlemanだったTom Paulay先生の訃報に接し、大いなる悲しみを感じます。ここに衷心より哀悼の意を表します。RC構造を研究する遥か異国・日本の若手研究者に対しても、常に親しみと暖かみを持って接して下さったPaulay先生、お疲れさまでした。どうか天国にて永遠のお休みを楽しんで下さい。合掌

ニュージーランドでの太平洋地震工学会議にて(1987年) 左端は”マオリ・ジョー”こと城攻先生(当時、北海道大学助教授)、右端は師匠・青山博之先生

ニュージーランドでの太平洋地震工学会議にて(1987年) 右は師匠・小谷俊介先生
以下の文章は、日本地震工学会の会誌に投稿した「日本地震工学会大会2009のご案内」の抜粋です。
日本地震工学会大会2009のご案内(2009年06月22日)
首都大学東京/東京都立大学 北山和宏
(1) 開催場所
東京・代々木の「国立オリンピック記念青少年総合センター」(東京都渋谷区代々木神園町3-1)のセンター棟を予定しています。この施設はもともとは、1964年の東京オリンピックの際に選手村として利用するために建設されました。国立の施設のためその賃料は、都心の同種の施設と比較すると格安ですが、その反面制約も多く、論文発表用に使用する部屋や技術フェアの会場が異なるフロアに割り振られたこと、大会用の案内表示を、決められた大きさで、かつ限られた場所にしか掲示できないこと、本会以外の同センター使用者が大勢出入りすること、などをやむを得ない事情として、ご理解いただければ幸いです。しかし立地はよく、小田急線参宮橋駅(新宿駅から二駅め)から歩いて5、6分で到着します。代々木公園や明治神宮と隣接しているために、都心とは思えない緑が広がり、訪れるひとを清々しい気分にしてくれます。また、同センターを利用するひとには学生さんのような若い方々が多く、芳村学実行委員会委員長に言わせると「とても活気があっていいじゃないか」というアクティブな雰囲気です。
(2) 開催日程
2009年11月12日(木)から14日(土)です。
〜途中省略〜
5.おわりに
日本地震工学会大会は、土木・建築・機械・地震・地盤・防災等々の異なる分野の研究者や実務者が一年に一度、一堂に会する貴重な場を提供します。日本地震工学会のそもそもの設立趣旨は、地震工学に携わる者を分野横断的に束ねてその英知を結集し、もって人類の安定居住と幸福とを実現する、ということだったと私は理解しています。たった一回の地震が、平和に暮らしていた民草を絶望の深淵に突き落とす、という悲惨な経験は、数限りなく繰り返されていますから。
自戒の念も込めているのですが、ともすれば自分の専門分野という狭いSocietyに籠りがちである研究者が、本大会の一冊の論文集を手に提げて、未知の分野の研究セッションをフラッと覗いてみる、というのも一興かと存じます。専門分野内で濃密な議論をたたかわせることは当然ですが、上述のような場(地震工学をキーワードとした異分野交流の場、と言ってもよいでしょう)として、本大会にご参加いただくのが、肩肘張らなくてよいのではないでしょうか。そのような異分野からの情報によって知的刺激を受けて、今まで眠っていた脳内のフィールドが活性化されること請け合いです。その結果として、考えたこともなかったようなアイデァが、天啓のごとく沸き上がるかも知れません。(以下、省略)
クラス会 (2009年6月16日)
先日、高校のときのクラス会が5年振りに開かれた。都会にある某都立高校を卒業して既に30年近くになるが、当時の担任だったN藤先生をはじめ、全部で23人が集まった。卒業以来初めて会ったひともいたが、会った瞬間から高校生の頃に戻れるのは、ホント不思議である。同級生達と話していて、「過去に戻れるって言われたら、俺は迷わずに高校生の頃に戻るな」という奴がいたが、私も同感である。
高校生はまだ親掛かりで、お酒の味もそれほど分からず(というか、お酒を美味いと思って飲んでいる高校生っているんだろうか?)、大人に較べたら全く自由がないように思うが、それでも前途洋々たる未来が待っており、何よりも背負っているもの(責任、と言ってもよい)がほとんどないので、これくらい自由な時期も無い、ということだろうな。
とにかく、高校生の頃は楽しかった。日々の授業や受験勉強は当然あったのだが、そういうつらい事はそそくさと忘却の河を流れ去ってしまうものらしい。そして残るのは甘美な思い出だけ、ということか。授業中の教室から窓を乗り越えてエスケープしたり、授業をサボって部室でたむろしているのをN藤先生に見つかって「お前たち、そんなことをしていいと思っているのか」と言われて出席簿で頭を叩かれたり、放課後に学校の向かいにあるボーリング場で遊んだり、文化祭の準備のあとN藤先生にラーメンをご馳走になったり、遠足のバスのなかで皆でフォークソング(風とかオフコース、荒井由実、サザンなんかだったな)を歌ったり……。
今どきの高校生がどういう日常を送っているのか、私は知らない(ということをクラス会で言ったら、「大学の教員のくせにそんなことも知らないのか」と叱られた)が、少なくとも私が高校生だった頃には、些細な「悪事」を共有できる悪友達との日常が充実していたことは確かである。
こうして至福のひとときはあっというまに過ぎて、皆、よき父親、母親はたまた社会人としての毎日へと戻って行った。「またね」と別れの言葉を交わして去って行く友人の背中たちが、なんとなく寂しげに思えたのは私だけであろうか。
ツバメ2 (2009年06月12日)
2009年3月末日に、このコーナーでツバメについて書いた。それから約2ヶ月が過ぎて、ファミリーマートの回転灯の上の巣には3羽のヒナが大きく育って、そろそろ巣立ちの季節を迎えている。親鳥が忙しく食事を運んで来るたびに、大きな口を開けて「ピーピー」かしましく鳴いているのが愛らしい。道行く人びとも、足を止めてその様子をほほ笑ましそうに眺めている。ヒナたちは早晩、自分の巣から思い切って飛び立つことであろう。自然界で生きてゆくのは、さぞかし大変なんだろうな。そんなツバメの若鳥たちに幸あれ、と願わずにはいられない。
北山研OB会 (2009年5月29日)
先日、久しぶりに北山研のOB・OG会を現役学生諸君が企画して開いてくれた。東京都立大学から首都大学東京へと大学名は変わったが、その間、北山研究室はすでに18年目に入っている。この日、現役諸君を合わせて20名近くが集まってくれた。忙しいなかを参加して下さったOB・OG諸氏は以下の通りである(敬称略)。
小山 明男(元助手、明治大学准教授)
岸田 慎司(元助手、芝浦工業大学准教授)
姜 柱
豊田 浩一
深海謙一郎
白山 貴志
原田 玄
中沼 弘貴
宮崎裕ノ介
林 秀樹
今泉麻由子
しばらく振りで会った顔、つい先日卒業・修了した顔、などいろいろで、とても楽しいひとときであった。皆さんからは思いがけず、私の教授昇任を祝っていただき、とても嬉しかったし、このように心優しい弟子たちが社会で活躍していることをあらためて誇らしく思ったものである。皆さんの今後の公私にわたる活躍を楽しみにしているよ。
昔、北山研の助手として一緒に研究した小山先生と岸田先生とが二人一緒に参加してくれたのも、とても嬉しかった。彼らの活躍のお陰で、素晴らしい学生達を世に送り出すことができたし、研究室の教育・研究活動も大いに発展した。そのことを思うとき、北山研の現在あるのは彼らに負うところが非常に大きい、と断言してよい。初代の助手だった李祥浩先生(い さんほ、韓国・釜山大学校工科大学教授)とお二人には本当に感謝している。思い返せば、これら三人ともその時々の全くの偶然によって都立大学・北山研にやって来た。そしてその三人が三人とも北山研にとっては「大当たり」(失礼!)の人材であったことは、ラッキーだったと言えるだろう。得難い人材を手にした私は、本当についている。
RC構造の研究は独りではできない。否、独りでもできるかも知れないが、独りでやっても楽しくない。大勢の叡智と努力との結果として、真実の一片をつかむことができるのだ。そのためのチームに人材は欠かせない。その意味で、今まで一緒に研究してくれた諸氏に大いなる感謝の念を抱くとともに、現役の学生諸君にはそのようなチームの一員として知恵を絞って欲しいと願っている。皆さん、どうもありがとう。
作 文 (2009年5月26日)
この週末、久しぶりに乱雑な部屋を掃除しながら整理した。もうじき高校のクラス会があるので、そのときの写真や思い出の品などを捜したのだが、思いがけないものが出て来たりした。そのひとつが、小学生の頃の作文である。小学校1年生のときの作文は全てひらがなで書かれていたが、それをみた女房は「あなた、1年生のときのほうが今よりも字が綺麗じゃないの」などと失礼なことを言う。
内容は、と言うと、その当時の我が家での生活が記されていた。例えば「お父さんは朝は寝坊して、夜は遅く帰って来る。夕飯は父抜きで食べる」等々。これでは家庭内のありさまが先生に筒抜けである。ああ、子供って純真なだけに恐ろしい。自分の子供を見ていてつくづく感じるが、子供の観察眼って馬鹿にできません。しっかりと何でも見ています。また「妹と将棋をすると、妹はいつも負けて泣いたり怒ったりします」と書いてあった。これも我が家の息子そっくりである。
さてその晩、子供と一緒にアニメの「ちびまるこちゃん」を見ていたら、何と「まるこ」のお父さんが小学生の頃に書いた作文と「まるこ」の書いた作文がそっくりだった、という巻を放映していてビックリした。これはデジャブ、と言うべきか、はたまた未来予想図と言うべきか。いずれにせよ、そのタイムリーさに驚いた一日であった。
ある委員会で (2009年5月25日)
電気協会が主催するある委員会に出席した。これは幾つかのWGの上にある親委員会みたいなもので、私は久保哲夫先生(東大教授)のもとでWGの副主査を務めているため、この会議に呼ばれる。この委員会には、私の師匠である青山博之先生も委員をつとめておいでである。青山先生は言うまでもなく重鎮であるので、会議の席次も議長の直ぐ横である。これに対して私はぺいぺいの未熟者であるので、通常は端っこの方に座っていた。
ところが先日の会議では、何と青山先生のお隣に私の席が指定されていたのである(右下の着座図参照/これは委員会で配布されます。出席者は40名以上です)。あちゃ〜、何てこった! これじゃ緊張して内職もできないやあ、ってな感じである。私がその席に座っていると、会議開始直前になって青山先生がお出でになって、いつものようににこやかに「やあ、どうも」と仰った。出席者の視線が議長に集まりつつあるタイミングであったのだが、私は反射的にほとんど席を立ち上がらんばかりになって青山先生にご挨拶した。
こうして私は自分の師匠と並んで委員会に出席するという栄に浴したので あるが、いやあ本当にコチコチになりましたな。昨年の暮れに芳村学先生の建築学会賞受賞記念パーティのときに、芳村先生が「私は青山先生のもとで鍛えていただいたおかげで、どこへ出てもビビらなくなりました」とスピーチされたが、青山先生ご本人の前ではビビらないんでしょうか。 あるが、いやあ本当にコチコチになりましたな。昨年の暮れに芳村学先生の建築学会賞受賞記念パーティのときに、芳村先生が「私は青山先生のもとで鍛えていただいたおかげで、どこへ出てもビビらなくなりました」とスピーチされたが、青山先生ご本人の前ではビビらないんでしょうか。
さて会議が始まって議事が進行し、やがて久保先生のWGでの仕事に関連する議題となった。これは指針のようなものを世に出すための最終討議であったのだが、かなりシビアな意見が出たりして、場が緊迫してきた。そこでそろそろ久保先生にご発言いただこうか、と思って議長の隣の久保先生を見た。
そして我が目を疑ったのであるが、何と先ほどまでおいでだった久保先生が知らないあいだに退席されて、そこにいないじゃないですか。こりゃ大変だ! なぜなら議題になっている件に関しては、私はサボっていてほとんど関知していなかったのである。そのため意見らしい意見も言うことができず、青山先生のお隣で固くなっていた上にさらに肩身が狭くなって(これじゃ煮すぎたロース肉だよ、トホホ)、もう針のムシロとはこのことでしょうな。会議が終わったときには、ぐったり疲れ切っていた。まだまだ修行が足りないことを思い知りました。幾つになっても人間、鍛錬を怠ってはいけません。
星新一と山本周五郎 〜由井正雪の橋渡し〜 (2009年5月11日)
本当に久しぶりに星新一の小説を読んだ。中学生の頃に「ボッコちゃん」を始めとするSFのショートショートをむさぼり読んで以来だから、30年以上ぶりである。星新一と言えばウイットに富み、ユーモアに溢れたショートショートで有名であるが、時代小説も残していたことを最近になって知り、それらを読んだのである。
その中に由井正雪のことを描いた「正雪と弟子」という短編があった。由井正雪は江戸時代初期のひとで、徳川幕府が出来てまだ間もない世情不安定な時期に、丸橋忠弥などの食い詰め浪人達を率いて徳川幕府に叛旗を翻そうと画策した、ということで有名である。しかしこの小説の主人公は実は紀伊国屋文左衛門であり、彼は由井正雪の弟子だったという奇想天外なお話なのである。
偶然に星新一の「正雪と弟子」を読んだことから、ふーん由井正雪か、と今まで興味を持ったことのなった人物の名前が私の脳内にインプットされた。それから暫くして、またもや偶然にも山本周五郎の「正雪記」という、こちらは正真正銘、由井正雪を主人公とした小説に出会って読み始めた。そして初めて知ったのだが、由井正雪というひとについては、実はほとんど分かっていないようで、徳川幕府転覆を画策したということ自体が事実かどうか疑わしいようだ。ということは、時代小説家にとっては存分に話を組み立てることのできる格好の題材、と言うこともできるだろう。
実際この小説では、山本周五郎の手によって由井正雪の人間像が明瞭に設定され、波瀾万丈な生涯が描かれている。テレビの時代劇などで、由井正雪は紀州徳川家から多額の資金提供を受けて幕府打倒の策を練った、というようなことが言われるが、この小説ではもう少し伝奇的で、正雪の資金源は信州の山奥に隠された埋蔵金ということになっている。また、正雪は島原の乱に浪人部隊を率いる指導者として幕府軍に加わって、そのことによって幕府の浪人に対する弾圧政策の非を確信することになる。
ここで山本周五郎は島原の乱をキリシタンによる宗教戦争ではなく、統治する大名の苛政によって抑圧された島原・天草地方の住民たちによる一揆である、というふうに描いた。しかしこのような見方は、この小説が書かれた昭和三十年代には相当革新的な意見だったのではなかろうか。
現代でこそ、島原の乱はキリシタンによる宗教闘争の一面は否定できないものの、本質的には民衆による土一揆だったという明治以前の認識を再発掘して指摘する学者もおり(大橋幸泰著「検証島原天草一揆」吉川弘文館、2008)、2008年に出版された飯嶋和一の「出星前夜」もそのような背景を前提として描かれた小説である。これらを思うとき、山本周五郎は小説家といえども卓抜した一流の歴史観を持っていた、と言うことができるだろう。山本周五郎はやっぱりすごい、「正雪記」を読んでいて、そんなことを考えた。
GWを考える (2009年5月6日)
今年のゴールデン・ウイーク(GW)後半は曜日の並びがよいため、5連休になった。また政府のばらまき政策によってETC搭載車の高速道路料金が一律千円になったことから、行楽地は大混雑、往復の高速道路は大渋滞、といういつもの現象が出来した。テレビのニュースでは高速道路に延々と続く車の列を報じていた。
渋滞による時間のロスを経済効果の損失に置き換えると、莫大な金額になることが指摘されている。渋滞や混雑に巻き込まれることが分かっているのに、なぜ日本人はGWとお盆、年末年始の決まった時期に大挙して出掛けるのか。平日にはどうしても休みが取れない、という人もいるだろうが、裁量労働制や勤務時間の24時間化など多様な労働形態が広まっている日本社会を考えると、平日に出掛けることが可能なひとも多いのではないか。
物理的な理由でないとすると、あとはメンタルな理由しか考えられない。大勢のひとが働いている平日に遊ぶことに罪悪感を抱くとか、回りに休暇をエンジョイしているひとがいないと落ち着かないとか。でも今ひとつピンと来ない。結局GWというものの存在自体が、ひとびとに「お出かけ」そのものを強迫しているとしか思えない。お上が民草のために休みを作ってやっているのだから、休んでさあ遊びに行け、という感じである。
休日をぞろぞろ並べるよりも、例えば一年の水曜日に適当に休日をわりふって貰った方が、仕事をする身にとっては中休みできるし、少し長く休みたいと思ったら、月曜日と火曜日に有給休暇を取るとかすればよい。このように考えている私であるが、このGWには河口湖に出掛けて恐ろしいほどの混雑に身を揉まれ、帰りの中央道ではお決まりの小仏トンネル付近の渋滞にはまったのである。何をか況んや、ではある。お土産に信玄餅を買って来たのであるが、翌日近所のスーパー・マーケットに同じものを売っているのを見て、とどめを刺された。もうガックリ、でした。
ことしの四月 (20090430)
2009年度の最初のひと月も、そろそろ過ぎようとしている。私にとって、今年の四月は例年とは相当に異なっていた。その理由は幾つかあるが、第一には実験が進行中である、ということが挙げられる(主担当者はM2の矢島龍人君)。PS三菱(浜田公也氏が相手先)との共同研究としてスタートした実験研究であるが、PRC試験体の作製が予定よりも2ヶ月近く遅れたり、大型実験棟の載荷装置を一式入れ替えたために今までの治具が使えないとか、新しい三軸一点クレビスの具合をチェックするための予備試験を行ったりとか、諸事あって実験開始が四月にずれ込んだのである。
この時期に実験した記憶は今までにないが、いいこともあるということに気がついた。まず、新しい卒論生が入って来て、すぐに研究テーマとして取り組めること、次に気候がよいのでさわやかな空気のなかで実験できること、である。本来であれば、昨年度の卒論生(嶋田洋介君)の卒論テーマであったのだが、申し訳ないことにそれには間に合わなかったので、怪我の功名といったところであろうか。また実験は通常は秋から冬にかけて実施することが多く、氷のように寒い大型実験棟で震えながら実験するのが常である。それに較べると春の実験は、本当に快適である(と、私は思うのだが、実験している学生諸君はいかがかな?)。この実験のほかにも、さらにWPCプロジェクトによるプレキャストRC耐震壁試験体の作製も現在進んでいる。結局は本来の予定から大きくずれ込んで、斯くなる仕儀に至っただけ、とも言えるのだが。
この四月が例年と異なる第二の理由は、建築学会の大会論文締め切りが例年よりも一週間ほど早く設定されたことであろう。新年度になったらすぐに論文提出、ということになって相当にあわてたが、研究室の学生さん達に北山チェックのためのデッドラインを設定したところ、これが意外と上手くいったような気がする。いつもは締め切り日の午後5時ギリギリまで論文を書いていたのだが、今年はそういうことはせずに済んだのである。もっとも、学生諸君が大いに努力してくれた賜物、とも言えるであろう。
さらには我が家のなかでも色々な出来事があったのだが、それには触れない。こうして2009年の四月は過ぎていったのである。
以下の文章は青山耐震フォーラムにて企画中の「十勝沖地震40年記念行事」に寄稿したものです。
十勝沖地震(1968)の遺したもの (2009年04月16日)
東京都立大学 北山和宏(1984年学部卒業)
1968年に十勝沖地震が発生したとき、私は東京の小学校に通う1年生だったので、何にも憶えていない。この地震の意義などがおぼろげながら分かってきたのは、1983年に卒論生として青山・小谷研究室に入ってからである。そして、この地震によって被害を受けたRC建物が梅村・青山研究室の先輩方によって詳細に調査されたことを知った。しかし当時の私にとっては写真や図だけで見る未知の世界であり、授業や研究室の実験で見聞した知識とかろうじてリンクする程度の感覚であった。
ところが十勝沖地震から四半世紀を過ぎた1994年の三陸はるか沖地震によって、かつて被害を受けた幾つかの建物たちが突如として私の眼前に現実のものとして姿をあらわしたのである。八戸市庁舎、八戸市立図書館、青森県立八戸東高校、八戸高専などで、いずれも前述のように青研では有名な建物たちであった。この地震は暮れも押し迫った12月28日に発生し、その被害調査に出掛ける相談のために、明けて1月2日に東大11号館7階の青山研究室輪講室に集合した。
そしてその翌日の3日には八戸入りして、午後には被害調査を行った。八戸高専では1968年の地震で1階の短柱がせん断破壊したので、この部分に耐震壁を増設する補強を施したところ、1994年の地震では未補強だった2階の柱がせん断破壊した。耐震補強によって弱点が移動した典型的な例であろう。八戸市立図書館を見たときには、こんな小規模な平屋の建物が1968年には顕著なねじれ破壊したことが信じられなかった。
青森県立八戸東高校管理棟の詳細調査を李祥浩さん(当時、東大大学院D3)および前田匡樹さん(当時横浜国大助手)と担当した。この建物は十勝沖地震で中破したのちも補修して継続使用されてきたが、1994年の地震では1階のほとんどの柱がせん断破壊して、崩壊と判定された。建物のなかで被害状況を調べているときに余震がやって来てぐらぐらっときたときには、慌てて外に飛び出したことを憶えている。
下階壁抜け柱がせん断破壊して、軸崩壊寸前という状態を初めて目にした。北山研究室ではこのときの被害調査を契機として、この建物の耐震診断や各種の地震応答解析を実施して、四半世紀を経た二つの地震による被害の差異(中破と崩壊)の原因を探る研究に取り組んだ。そして骨組解析によって実被害を追跡することの困難さを思い知った。むしろせん断破壊後の耐力低下を考慮できる多質点系解析のほうが、ザックリとではあるが実被害を再現できるということも体験した。
 
せん断破壊した下階壁抜け柱 左の写真と同じ柱の裏面 軸縮みが生じて
主筋がクランク状に折れ曲がっているのが分かる
以上が、十勝沖地震が私に遺してくれたものである。そして先輩方のひたむきな努力によって集積された知の偉大さを認識し、そのことに感謝したのである。
桜 (2009年04月04日)
やっと春らしい暖かい日和になりましたね。登校する道すがらの野川沿いの桜や京王線・柴崎駅の桜もやっと満開に咲きそろいました。ただ、南大沢の気温は多摩東部よりは低いらしく、大学正門わきの遊歩道の桜並木は五分咲きといったところです。
桜にもいろんな種類があって、開花する時期もまちまちです。また、日本人にとって桜は特別の花であることに間違いありません。散りぎわの桜の美しさを人生に見立てるのは、日本人独特の感性のなせる技でしょうね。昭和初期には桜が軍国日本の象徴になったりもしました。このあたりの日本文化論は佐藤 俊樹著「桜が創った「日本」」(岩波新書、2005)に詳しく書かれています。
桜と言えばお花見がつきもので、毎年大勢の人たちが桜の名所に繰り出して、飲んだり食べたりを楽しみます。私も大学院生の頃には一升瓶を下げて、先輩や後輩たちと歩いて上野公園の花見に出かけたものです。しかし日本では当たり前のこの光景(風俗)も、どうやら日本独自のもののようです。少なくとも欧米では、飲み食いのともなう日本のような「お花見」は存在しない、ということらしいです。
と言うことで、桜を見ながら思いつくことを徒然なるままに書いてみました。これから2008年度のアニュアル・レポートに取り組みます。まったくもって、昨年度の仕事がまだ終わっていません。とほほ、状態です(最後はぼやきになってしまいました/お見苦しくて恐縮です)。
ツバメ (2009年03月31日)
今日は年度末である。しばらく肌寒い日が続いているため、ほころびかけた桜もしばらく足踏みといった感じである。それでも春は着実にやって来る。三月中旬には大学の松木緑地から、まだ唄い初めといった響きのウグイスの初音を耳にした。そして今日、我が家のそばにツバメたちが例年通りにやって来たのである。
「ぴちぴちぴちっ」という歌声におやっと思って見上げると、電線に小さなツバメがちょこんと留っていた。彼らは毎年、三月末から四月はじめにかけて決まったようにやって来る。昨年は確か四月一日であった。柴崎駅の近くのファミリーマートの垂れ壁に毎年、決まって営巣するのだ。そこは街灯のそばであり、夜は明るくて眠れないのでは?と思うが、カラスなどの外敵から身を守るのには都合がいいのだろう。ツバメたちはこれから秋口まで、場合によっては二回ほど子づくり・子育てをする。そのうちかわいい雛がたくさん見られることだろう。楽しみである。
ちなみに大学正門脇の桜は、一分咲きといったところである。こちらもこれから盛りを迎える。
卒業式に寄せて (2009年03月23日)
今日は本学の卒業式・修了式である。今年は暖冬で東京大手町の桜は開花したとのことだが、ここ八王子ではまだである。ただ、国際交流会館の前にある桜は例年通りに満開になった。有楽町の東京フォーラムでの卒業式も今年で2回目となり、卒業生・修了生たちは午前中は都心で、午後は大学での式典に臨み、夕方からはまた都心で謝恩会と、この日ばかりは教授陣並みの忙しさで都心と大学を往復することになる。

建築都市コースの卒業式と大学院建築学専攻の修了式は、今年は正門左脇にある小ホールで合同で開かれた。特に学部は首都大学東京になって初めての卒業生ということもあり、感慨もひとしおである。学部定員が60名となり、実際の入学者はそれよりも一割以上多かったので、相当の大所帯になったという感じである。都立大学時代の学部定員がA類では40名であったので、それから較べると「増えたな」というのが正直なところである。
人数がこのように多くなったこともあって、この学年は集中力が無くて騒がしいというのが2年生までの感想であった。ところが3年後期の「先端研究ゼミナール」という授業で学生さんと個別に接するようになって、その感想は大きく変わった。話してみると、学生一人一人はそれぞれしっかりとしており、自分の考えを持って勉強をしていることがよく分かった。結局、集団になると没個性となり、個々人の良さや特徴が消されてしまう、という典型例だったのだろうか。それとも、卒論生の今泉さん曰く「うちの学年はみんな仲がいいんです」ということの裏返しだったのだろうか。式典会場の小ホールの椅子に座りながら、そんな想念に耽っていた。
コース長の山田幸正教授の送辞が終わって、皆がぞろぞろと会場を後にしたのち、正門前の看板わきで北山研究室の集合写真を撮った(あいにくの曇り空で、写真映えのしないどんよりとした写真になってしまったが)。ここで写真を撮ったのは初めてである。今年は卒論生3名、修論生1名の計4名が巣立ってゆく。進路は皆それぞれであるが、どんな場所でも自分の持てる力を存分にふるって前進していって欲しい。諸君の研究室での活動は、そのための「考える力」を養うのに大いに役立ったはずである。皆さんの今後の活躍を楽しみにしている。
卒業・修了、おめでとう。

国立オリンピック記念青少年総合センターへ行く (2009年03月09日)
2009年度の日本地震工学会年次大会(11月12日から14日まで)を、ここで開催することになったので、実行委員会委員長の芳村学先生たちと実地見学に行って来た。必要な諸室の予約は既に済んでいる。外観は写真のようで、古い施設(なんせ東京オリンピックのときに建てられたのだ!)のわりにはきれいであった。

ここは国立の施設で青少年向けのイベントを優先、とのことで、われわれの年次大会用の部屋の割り振りはまだ教えられない、とのことであった。この口振りから、既に内々に部屋割りは決めてあるが言えない、ということらしい。なるべく部屋はかたまって押さえて欲しい、というこちらの要望に対しては、そんな特別待遇はできない、とのこと。また、大勢の人たちが利用するので立て看板は基本的には不可、だそうだ。まったくもってお役所的な発想and応対であった。私はそのやり取りに結構、憤慨したのだが、芳村先生から「使用料がべらぼうに安いんだから、仕方がないだろう。我慢しろ」と言われて、はあ、そう言うものかと妙に感心して帰ってきました。
という訳で、皆さん、今年のJAEEの年次大会には是非とも論文を出して下さい。少なくともわが大学の構造系の大学院生は一人一編が義務となります(なんちゃって)。
RC規準の改定に向けて〜月下の独白〜 (2009年03月05日)
現在、日本建築学会のRC規準改定小委員会(主査:市之瀬敏勝名工大教授)では、2009年秋の出版・講習に向けてRC規準の改定作業が大詰めに差しかかっている。前回の改定が1999年だったので10年振りの改定ということになるが、作業自体は2005年から始めていた。当初は17条の定着関係だけを見直して修正するくらいの小規模改定の予定だったが、作業をしているうちに風向きが変わって、前回以上の(いや、思想的にはそれを遥かに上回る)改定を実施することになった。その引き金となった要因は例の「姉歯事件」であるが、これは不愉快なことなのでこれ以上は言及しない。
最も大きな変更点は、タイトルから「許容応力度設計法」という文言を削除することに端的に表れている。構造設計のスタイルとしては、今までの設計慣習や法体系の問題から許容応力度設計法を踏襲するが、実際の設計は使用性、損傷制御性および安全性という三つの限界状態を対象としてそれらを確保するという観点から為されることになる。許容応力度設計の体系を借りた限界状態設計、という風に言ってもよいだろう。
そんな面倒くさいことをするなら、全面的に限界状態設計法に移行すればよいのでは、と言われそうだが、現実にはRC規準がRC建物の構造設計のバイブルとして使われてきた役割を考えると、そんなにドラスティックなことはできないだろうし、学会ではすでに終局強度設計指針や靭性保証設計指針を別に発表しているので、そちらを利用する手がある。21世紀に入って、許容応力度設計は時代遅れになってその役割は終わったのでRC規準のメンテナンスも取りやめにしよう、という「RC規準野垂れ死論」がいっときは優勢になったときもあったような気がするが、前述のように現実の設計のことを考えるとそう言うわけにも行かない、ということだろう。
現在は、構造本委員会の査読が終わり、その査読意見を反映した最終原稿を作成する段階にある。ここでRC規準改定の具体的な作業方法をお話しする。RC規準は条文スタイルをとっており、本文があってそのあとに解説がくる。1条から22条までを幾つかに分けて、柱梁WG、耐震壁WG、定着WG、二次設計WGおよび解析WGといったワーキング・グループ内で原案を作成する。しかし結局は、ある条を担当するのはひとりか二人程度であり、各個人がばらばらに作業するので、全体としての統一感は失われる。
ただし改定と言っても、先人の仕事を全て改廃するわけではなく、使える部分はもちろん尊重して残すことになる。そうすると1933年から営々と続いてきたRC規準の文章の中には、様々な執筆者による、それぞれの時代を背負った文章や文体が所々に顔を見せるということになる(それはそれで化石探しのようで楽しい、というひともいるだろう)。これらのトーンを全て揃えて統一感を持たせる、ということは現実には不可能であろう。
何故このようなことをくだくだと述べてきたかと言うと、実はこのような“不統一感の統一”を実行できないかと思って、私が査読原稿を通読するという作業を行ったからである(ただし19条「耐震壁」と20条「基礎」は未読)。結論から言うと、思ったほどのトーンの不一致はなかったのである。ただ、これは改定作業に携わったひとりとしての偏見が大いに作用した結果かもしれない。
最も気になったのは、「骨組」を表す用語である。昔のひとはドイツ語が達者だったせいか「ラーメン」が常用されていた。そのためRC規準にもそこかしこにラーメンが溢れている。ところが改定を重ねてきて執筆者も変わると、それが「骨組」だったり「剛接架構」だったり「剛接骨組」だったり、いろいろ現れてくる。私個人としては、今さらラーメンでもないだろうと思うのだが、どうだろうか。私が学生の頃、青山博之先生が構造力学の講義の中で「ラーメンと言っても支那そばではありません」と仰っていたことを思い出す。笑い話でしょうな、やっぱりこれは。
このようにして先人から引き渡されたRC規準は改定されてゆく。私たちの仕事も後世、どのような感慨(あるいは感想)を持ってばっさりとやられるのだろうか。もっとも次の改定が10年後だったら、また担当にされるかも知れない。ちょっと怖い気がします、自分で自分をばっさりするのは。
ここのところ、RC規準改定のための大詰めの作業(今年2009年の出版を目指してます)や、PC部材性能評価指針(案)の査読原案つくりに忙しくて、このコーナーの更新が滞ってしまいました。コツコツと書きためた文書を以下に掲載します。
以下は『卒業論文を書いていた頃(2009年01月19日)』のつづきです(2009年3月3日)
3 卒論を書く、もとい田才晃先生
この雑文のタイトルは「卒業論文を書いていた頃」というのに、なかなか卒論の内容にまで到達できなかった。が、わが大学では卒論の発表会が既に終了した今時分になって、やっと卒論本体についてお話しする機会がやって来た。
卒論のテーマは、地震によって被災したRC部材をエポキシ樹脂やエポキシ樹脂モルタルを用いて補修することによって、力学性能がどの程度回復し、その効果を発揮できるかを実験によって検討するものであった。ここでは曲げ挙動におよぼす影響を主な研究対象とした。
これは助手の田才晃さんが研究されていたもの(後年、田才さんはこのテーマで博士論文を執筆された)で、私はそのお手伝いをすることになった。最初はエポキシ樹脂補修に関する既往の論文(英文および和文)を渡されて、その要旨をまとめるように言われた。建設省の総プロで実施された「震災構造物の復旧技術に関する研究」の成果がこのころちょうど取りまとめられていたような気がする。なのでこのテーマは、当時としてはタイムリーなものだったのだろう。
こうして私の研究生活は既往の論文を読むことから始まった。これは至極真っ当なコースである。ただ、エポキシ樹脂補修に関する論文だけでなく、RCの基本である(主筋に沿った)付着に興味を持ち、京都大学の六車・森田両先生が執筆した、付着の基本的な機構の解明に迫る金字塔的な論文(建築学会の黄表紙に発表されたもの)を読んだりした。これは付着応力度とすべり量との関係を二階の微分方程式で表し、その一般解をエレガントな数式で表現する、というもので、RC構造の奥の深さをかいま見た気がして、とても感銘を受けたことを思い出す。この論文はRCの付着を研究する人にとっては必読で、かつ、これによって付着問題は基本的には解決したような気がしていた。
ところがその後、1987年に土木・コンクリート研の島弘さん(工学部11号館地下二階の実験室仲間で、現高知工科大学教授)が付着応力度をすべり量だけでなく、主筋ひずみとの関数で表現するべきである、という論文を土木学会誌に発表されて、異形鉄筋に沿った付着作用についてもまだまだ研究することがあるんだなあ、と感心した。
こうして既往の研究を調べながら、田才さんの指図に従って実験の検討もはじめた。この当時、田才さんは鉄のAging(時効効果)に関心を持っておられ、まずこの問題を異形鉄筋の引張りおよび圧縮試験によって検討する、ということになった。
そのためには地震時に梁の主筋がどのようなひずみ履歴を受けるのか、知らなければならない。そこで青研で過去に行われた静的載荷実験のうち、鈴木紀雄さん(鹿島技研)がD論研究で実施された立体柱梁接合部実験の結果から、梁主筋のひずみ履歴を調べて、そのうちの幾つかを基本として鉄筋の引張り・圧縮繰り返し載荷用の非定常ひずみ履歴を決定した。
鈴木さんの実験の生データはHPのコンピュータ用のカセットに記録されており、それを取り出すために塩原さんにプログラムを作って貰った(塩原さんはいつものようににこにこ笑いながら、あっという間にプログラムをCoding したので、これはすごい人だな、と思った。今思えば、塩原さんは富山の生んだ天才だから、これくらいは朝飯前だったのだ)。
この当時のコンピュータは今で言うと電卓みたいなもので(?)、現在のブラウン管や液晶のような表示装置はなく、たった1行の蛍光表示器のみであったから、プログラムといっても私には何がなんだか分からなかった。そう言えば駒場のころ、逆ポーランド式電卓というのがあって、そのためのゼミに参加したことを思い出した(全く関係ありませんが、はまった人もいたでしょうね)。
やっとひずみ履歴ができ上がったので、いよいよ実験である。しかしここで問題が出来した。鉄筋を引張る分にはよいのだが、これを除荷してさらに圧縮力をかけると鉄筋は細いのですぐ座屈してしまい、圧縮降伏するまで載荷することができないのである。
そこで、座屈を防止するための鋼製の治具を浅野キャンパスにあった工作施設に作って貰った。森勇さんという豪快な技官の方がいて、いつも快く引き受けて下さった。実験自体は、当時巨大な2000 tonf試験機が鎮座していた大型構造物試験室内の油圧式試験機(これは小さいもの)で行った。
実験するときには田才さんと一緒に二人でやるのだが、田才さんは助手なので青山先生や小谷先生の授業の手伝いや学科のお仕事などいろいろあって、予定通りになかなか捗らなかった。実験する予定の時間になっても田才さんが現れない、ということが度重なったある日、今日もどうせ田才さんは来ないだろう、と思って1時間ほど遅れて試験室に行ったことがある。
ところがその日に限って、田才さんは時間通りに試験室に来ていたのである! 「北山君、集合は今日の○○時って、僕、言ったでしょ」と言う、そのときの田才さんの不機嫌そうな表情は今でもよく憶えている。ちなみに私も後年、大学の助手となり、田才さんの苦労の一端が分かったような気がした。
次は、エポキシ樹脂の物性を把握することになった。しかし我々はRCの専門家なのでエポキシ樹脂のことはさっぱり分からない。幸いこの研究ではエポキシ樹脂を専門に扱うショーボンド建設の協力を得ていた(その経緯は私は知らない)。そこで埼玉県の与野にあったショーボンド建設の技術研究所に何度か田才さんと通った。
出掛けるときにはたいがい田才さんの車(それも知り合いからの借り物だったらしい)で行くのだが、とにかくその頃は毎晩研究室でお酒ばかり飲んでいて、滅茶苦茶な二日酔い状態で助手席に乗っていた記憶ばかりがある。そこの担当者が宗(そう)栄一さんという方で、田才さんはショーボンドへの電話で「宗さんいますか、、、そうですか」というギャグをいつも飛ばしては「だって、おかしいんだもん」と一人でニヤニヤ悦に入っていた。
ここまでで既に秋も深まっていたような気がする。なかなか梁部材を用いた実験に入れない。田才さんがやっと梁試験体の寸法を設定したので、部材の曲げ強度やせん断終局強度を計算することが私の次の課題になった。三点曲げ載荷によって区間中央は純曲げとなるような実験である。
曲げひび割れの幅や部材の在軸方向の変形を詳細に測定することを目論んだので、変位計をたくさん設置した。コンクリートにネジ棒を埋め込んでそれに変位計を取り付けるのだが、ネジ棒の曲げ剛性と変位計先端のスプリングのバネ定数とから、ネジ棒のたわみがどの程度なのか計算したりした。通常はこのような面倒かつ不必要に思われる数値計算は行わないのだろうが、私にとってはその後、自分で実験を計画するに当たって、いい勉強になった。

写真1 変位計をセットした試験体 たくさんついています!(うしろに小林さんの内柱梁接合部試験体の右梁が写っている)
この実験で、田才さんはいろいろと工夫していた。主筋のひずみ測定法もその一つである。通常は鉄筋の表面にひずみゲージを貼ってコーティングしたあと、リード線を鉄筋表面に這わせて取り出す、という方法をとる。しかしこうすると主筋表面の付着性状に影響を与える可能性が大きい。というか、大なり小なり必ず付着に影響する。
これを嫌った田才さんは、主筋を在軸方向に二つに切断して、それぞれの中央に在軸に沿って溝を掘って、そこにベースの小さいひずみゲージを貼り付けるという方法を採った(ちなみに元ネタは1972年のACI Journal に掲載されたNielson の論文である)。リード線も通常のビニル製のものではなく(これだとリード線が太くなってしまうので)、導線を何かでコーティングした特殊なものを用いて、溝の両端から取り出すようにした。これなら鉄筋表面の付着に影響を与えることはない。
ただしこの鉄筋を作るのは大変だったようだ。またもや浅野の工作施設に頼んで、溝付き二つ割りの鉄筋を加工してもらった。届いた鉄筋片は油まみれでそのままではひずみゲージを貼れない。そこでバケツ一杯のアセトンのなかにその鉄筋片を突っ込んでジャブジャブと洗った。ちなみにアセトンは発がん性物質である。アセトンを浸した脱脂綿を腕に擦り付けて「ああ、涼しくて気持ちいい」なんて言ってるヤツもいたが、ああ、おそろしや〜。
溝のなかにひずみゲージを貼るのがまた、ひと苦労であった。研究室の先輩方がみな手伝って下さったのだが、だれかが消しゴムを溝の幅に切って来て、それで押さえながらゲージを貼る、という技を編み出したのである。すばらしい、感動した!。ちなみにひずみゲージを貼るときには十分に押さえることが肝要だ、ということで、青研には押さえているときに「逃げた女房」を歌う、という伝統があった(これは遠藤利根穂先生がやり出したことらしい)。皆で「に〜げたあ、にょう〜ぼうにゃ、みれんはな〜い〜がああ」と歌ったのである。はたから見ると相当に異様な光景かもしれません。
試験体は当時、高島平駅の北方の戸田橋にあった大成建設のPC工場で作製した。そこで下請けとして働いていた人たちが入部工業の面々である。この話しはまた別にしようと思う(なんせ青研での研究生活のなかで、相当の時間をこの工場で過ごしたのだから)。試験体の鉄筋にゲージを貼って組み立て、型枠にセットしてコンクリートを打設するのであるが、コンクリート打ちが迫ってくると作業が夜遅くにおよぶことも度々であった。そんなときは、田才さんは家に帰るのが面倒だったのだろう、この工場の休憩室によく泊まっていた。
作業する場所は屋外である。冬の夜なので、とても寒い。PC版を作るとは言ってもそれは屋外であり、コンクリート打設後の養生のときだけ移動式のテントで覆って、シューシューと音をたてながら蒸気養生をしていた記憶がある。試験体ができ上がったあと、そのうちの一体ではかぶりコンクリート部分をハツリとって、そこにエポキシ樹脂モルタルを詰めて補修する、というものがあった。田才さんや私がどうやってハツろうか、とまごまごしていると、入部工業の親父さん(康隆さんや浩輝さんのお父さん、故人)がやって来て、「こうやるんだよ」と言ってちょうなのような道具でもの凄い勢いで、コンクリートをそれこそ剥ぎとったのには、本当にビックリした。やっぱりプロはすごいですな。
梁の曲げ試験は11 号館地下二階の実験室で行った。単純梁形式なので、一端ピン、他端ローラー支持である。加力は島津製作所製の100tonf試験機で行った。ネジ式のシャフトが両側に付いているので、ひび割れの観察は極めてやりにくい。さらに加力は実験室のフロア・レベルにある載荷台の上で行うので、ひび割れを観察するときにはかがんだ姿勢になって、首と右手とをシャフトの間から差し入れてひび割れをなぞった。結構しんどい。
地下二階なので日は射さない。そこで一所懸命に実験していると時間を忘れてしまい、夜なのか昼なのか分からないということになる。ただ、建設業のならいで三時の休憩は必ず取った。地下二階の実験室から西側の螺旋階段を使って地上に出て、お八つを買いに走るのである。そのときだけ、娑婆の空気を吸うことができた(って、別に実験室が牢獄だ、と言っている訳ではありません)。
この研究は地震被害を受けたRC部材を補修してその効果を調べる、というものなので、載荷が終わったらそれを補修して、再度実験しないといけない(コメント1)。二度手間なのである。ひび割れにエポキシ樹脂を注入するのだが、それがとてつもなく面倒であった。まずひび割れをシールして、エポキシ樹脂を注入するためのゴム風船を取り付ける口金を所々に固定する。それから二液を混合してエポキシ樹脂を練り上げたあと、ガンタイプの道具を使ってゴム風船にエポキシ樹脂を注入して低圧でじわじわとひび割れ全域に浸透させるのである。
エポキシ樹脂はご想像通りベタベタとするので、体じゅうにくっついたのには閉口した。この作業を田才さんと二人きりでやり遂げ、終わったのは例によって深夜であった。おまけに雪が降っており、あまりに寒いのでエポキシ樹脂が固まらない恐れがあった。そこで窮余の一策として大型の投光器で試験体を照らして暖めておいて、帰宅したのであった。
(コメント1):補修をする前の試験体を何と呼ぶか、論文を書く段になって問題となった。既往の論文ではそれを「処女試験体」と呼んでいるものが多かったが、あまりにも生々しいし、学会などで発表するときにはギョッとするだろうからということで、田才さんは英語混じりの日本語で「オリジナル試験体」と名付けた。

写真2 エポキシ樹脂注入のためのゴム風船を取り付けているところ(這いつくばって作業しているのは田才晃師匠です)
そんなわけで実験は年が明けてもまだまだ終わらなかった。それどころか、卒論提出後もまだ実験していたのである。記録を見ると先輩、同級生が総出で手伝ってくれたことが分かり、感謝感激あめあられ、である。当時の卒論はまだ手書きであった(NECの名パソコン9801がちょうど世に出た年であったが、そこで動くワープロが青研に届いたのは1984年になってからだった。管理工学研究所の「松」というソフトである)。
卒論はぎりぎりまで書いており、卒論ノートを見ると、提出日にはまだ曲率分布の検討をやっていた(ノートの欄外に「あせるぜ〜」という落書きが書いてあった。リアルである)。卒論を提出にゆくとき、11号館7階の研究室からエレベータで1階まで降りるあいだに、卒論冒頭の謝辞を鉛筆で書き上げたくらいである(ホントですぜ)。田才晃さんには表現できないほどお世話になった。青山先生、小谷先生のみならず田才さんもまた、私の師匠なのである。この一年間で経験したこと、勉強したことは、私の研究者人生の基盤となった。本当に感謝しています。
こうして私は卒業した。(つづく)
パソコン (2009年02月23日)
私はMacintosh のエヴァンジェリストである。自慢じゃないがWindows マシンは一度たりとも購入したことが無いし、使ったこともない(もっとも1999年にトルコ・コジャエリ地震の被害調査に行ったときには、Macのノートパソコンがあまりにも重くて持って行けず、やむなく研究室で購入したWindowsノートを持っていったことはあった)。北山研のなかでMac使いは私だけで、学生達は全員がWindows派である。1994年くらいまでは私はNEC・9801シリーズのデスクトップ・パソコンを使っており、そのときにはまだWindowsは一般的ではなかった(確かWindows 3.0だったかな)。98はMS-DOSというOS上で動いており、メモリの管理などがべらぼうに面倒だったが、パソコンと言えばそれしか知らないため、面倒なのが当たり前という感覚で日々使っていた。
ところが1994年度卒論生だった香山恆毅くんが、だいのMac党で「だまされたと思ってMacを買って下さい」としきりに頼む。そこまで言うなら、ということでPower Macintosh 8100(だったかな?タワー形で結構大きかった)を1台導入したのである。そして香山君にいろいろと教わるうちに、これは98とは全く異なる思想で作られている便利なマシンである、ということに気がついた。
まずGraphical User Interface(GUI)を取り入れており、ファイル等を視覚的に扱うことができた(これは現在では当たり前だが、十数年前は革新技術だったのだ)。エイリアスという発想も、はじめは理解できないくらいだった。しかし何よりも、98では必須だったユーザーによるメモリ管理などシステムの根幹に関わる部分を自分で構築しないといけない、という煩わしさとは全く無縁だったことに大いに感心した。今では当たり前だが、ワープロ文書に図や表を貼り付けるときに、それぞれ異なるソフトによって起動するファイルのあいだでカット&ペーストして簡単に実行できる、というのも新鮮だった。
こうしてMacの便利さ・優秀さに気がついた私は、98を廃してPower Macintosh 7100を愛機に据えたのである。それ以来、Power Bookなどのノートパソコンを含めて常にMacを使い続けている。確かにWindowsマシンは種類も多く、軽いマシンもあるし、値段も安い。しかしそこには、人間が使い続ける、という視点(人間工学って言うんでしょうか)が決定的に欠けているような気がする。プロダクト・デザインという発想も全くない。Macが先に実現した便利な機能をWindowsも後追いで可能にして、Intelとの二人三脚の戦略の巧みさで全世界に広まった、というのが実情だろうが、Macにはある「使う楽しさ」というものがないのではなかろうか(使っていないので分かりませんが)。
それを端的に思わせるものが、Windowsに未だに存在する「A:」とか「C:」とかのドライブ名称だ。これは明らかにWindows以前のMS-DOSの名残である。なぜこんなつまらない名称を残しているのだろうか(何かのおまじない?)。またMicrosoft のWordもワープロとしてこんな使いにくいものはないのに、なぜ皆がこれを使い続けるのだろうか(何て言いながら、この雑文もWordで打ってますが。まあ、エディタ代わりです。ちゃんと図表を張り込まなければならない文書はMac専用ワープロで作っています)。とは言え、最近のMacのCPUはモトローラからIntelへと鞍替えしたので、MacでもWindowsが動くらしいが、私はやったことがないので知らない。
Macのノートパソコンとして、軽量のMacBook Airが発売されたのも大きい。これはMacとしては、はじめての“モバイル可能マシン”ではなかろうか。研究室のメインマシンとして私はPower Book G4 17inch(画面サイズが17インチのノートパソコン)を使っているくらい、ノートパソコンとは言っても持ち運びは今までは非現実的であった。かつてコテコテのMac党だった京大の西山峰広教授は、軽いノートパソコンがないということでWindowsに乗り換えたが、最近またMacを使い始めたそうである。何とも喜ばしい知らせではある。
と言うわけで、私はこれからもMacを使い続けるだろう。Windowsを使わざるを得ないような状況が現れるのだろうか(例えばAppleがつぶれてMacを販売しなくなるとか?)、私には分からないが、今更Windowsを使おうという気はしないですな。Windows Userの皆さん、いかがお考えでしょうか。
最後に私の歴代愛機一覧です。17年間で6機種ですが、多いのか少ないのか、どっちっち? このなかで物理的に壊れた(HDがぶっ飛んだ)のは、Power Mac G4/400だけでした。Power Mac 7600はいまだに起動します。
NEC・9801→Power Mac 7100→Power Mac 7600→Power Mac G4/400→Power Mac G4/1.25(Mac OS 9.2.2)→Power Book G4 17inch(OSはひとつ前の10.4です。現在、これに20インチの液晶ディスプレイをつけて二画面で作業しています)
このほかにサブ・マシンとしてiMac G5 20inch(Mac OS X 10.5)を使っており、これでHPのコンテンツ更新などを行っています。
電話のはなし (2009年02月17日)
突然ですが、私の研究室には公設の電話はありません。いや、電話線はちゃんと来ているのですが(大学の名誉のために断っておきます)、受話器のコネクタを繋いでいないのです。これは大学で一日仕事をしていると、どうしようもない(くだらない)宣伝の電話があまりにもたくさん掛かってきて、そのあと決まって不愉快な思いをするからです。
このような迷惑電話に対してはコネクタ断線は最高の自衛策です。じゃあ、まじめな仕事の連絡などはどうするか、ということになります。ときどき親しいひとから「いくら電話をしても通じない。お前はそんな大物か」というお小言や皮肉も頂戴しますが、それでも本当に大事な話や要件であれば、何とか連絡はつくものだと思います。それに何と言っても現代では電子メールがあり、これほど自分の都合にあわせられるものはありません。見たいときに見て、返事を書きたいときに書けば良いのですから。タイピングのストレスがないことは以前お話しました。
昨年末に同級生の中埜良昭くんから仕事のメールを貰いましたが、その冒頭に「何度か電話したが留守みたいなので、メールで失礼します」みたいなことが書かれていました。申し訳ないと思ったのですぐに返信して「実は電話を切っているんだよ」とやると、「そんな素晴らしい手があったのか」と言って感心されたくらいです。まあ東大教授の電話が不通、という訳にも行かないでしょうがね。込み入った話や文字に残すのはちょっと?というような、どうしても電話でないと意思疎通できない場合には、メールでこちらから電話します、という連絡を差し上げることにしています。
最近、京大防災研の中島正愛先生から仕事のメールをいただいたのですが(先生はビッグネームですからもちろんお名前は知っていましたが、直接に仕事をご一緒したことはなかったのでビックリしました)、そこには「詳しくお話ししたいので電話してもよろしいですか」と言うふうに記されていました。これにはビックリ!です。何て丁寧な方だろうか、と。しかし私の部屋の電話は切ってあるので、中島先生からのお電話を待つこともできません。そこで「私の方からお電話したいので、ご都合のよいお時間をご指定ください」とメールしました。
というわけで、電話を置かなくなってから約一年くらいになりますが、皆さんが考えるほどの不便や不利益は蒙っていません。まあ、直ぐに連絡がつかないことによる不利益は(電話連絡を受けられない)私自身には分からない訳ですから、何とも言えないところもあります。しかし、知らなければ残念がることもないわけで、別に問題ないでしょう。大学内の事務連絡も今ではほとんどメールになりました。また、私が電話を切っていることの認知度も随分と高まりましたので(どうだか?)、これからもこのままゆこうと思っています。
アンパンマンとドラえもん (2009年02月16日)
この日はものすごく暖かな陽気の、いいお天気だった。前日から子供が「アンパンマン・ミュージアムに行きたい」と言い出したので、行くことにした。横浜の港みらい地区にあるこじんまりとした子供用の施設である(建築としては何の面白みもないプアな空間であるが、本題ではないためこれ以上は触れない)。ここには既に2回行っているが、いずれもべらぼうに混んでおり、アンパンマンの人気にはいつもビックリする。
ところで、小さい子供はどうしてアンパンマンが好きなのだろうか。キャラクターとしては非常に単純で、素朴な感じはするが別に格好が良いわけではない。色使いも単純で、ハッキリしている。ストーリー展開としては、バイキンマンが懲らしめられて最後は仲良くなる、というものが多い。と、ここまで書いてきて、はたと気がついた。もしかしたらこの単純さが、子供にとっては分かりやすいのかな。アンパンマン、バイキンマン、ドキンちゃん、などのネーミングも、幼児にとっては聞き取りやすく憶えやすいような気もする。ただ、好きな理由を幼児に聞いても明瞭な返事が得られるはずもなく、私には謎である。
子供に人気のキャラクターとして、ドラえもんもある。我が家では最近になってドラえもんを見るようになった。アンパンマンに遅れること2年くらいである。ただ番組を見てみると、アンパンマンに較べてストーリーが相当に複雑(小学校の中学年くらいをターゲットにしているのではないだろうか)で、幼児には相当に難しいなあ、という感じを受ける。そのせいで、アンパンマンよりはだいぶ遅れたのだろう。ただドラえもん自体の造形は、アンパンマンと似て非常に単純であり、このあたりにやはり人気の秘訣がありそうな気がするが、皆さんいかがお考えでしょうか(と言っても、この二つのキャラクターは子供がいないと見ないものなので、どうでもいい、という方も多いでしょうが)。
さて館内をひとしきり楽しんだあと、アンパンマン・ミュージアムのパン屋さん(よく考えてみるとアンパンマンはパン屋さんで生まれたので、パン屋が併設されているのは至極当然なのだ)で一個300円もするアンパンやらクリームパンやらを買って、帰途についたのであった。
花 粉 (2009年02月13日)
それはある朝、突然やって来た。花粉、である。もう目玉が痒くてたまらない。またいやな季節が近づいてきたな、でも早く暖かくなると良いな、という相反する二つの気持ちが交錯する。大学に行くと角田誠先生が「もう一週間も前から完全防備」と言っていた。花粉症はひとによって感度が非常に異なるので、発症もまちまちだ。
私の花粉症歴は非常に長い。小学生の頃には、春になると風邪でもないのにくしゃみ・鼻水が止まらなくなるので、回りからへんな奴というような目で見られるのが途轍もなくイヤだった。その当時は「花粉症」などという立派な名前はなかったからだ。現在では「花粉症は文明人の証拠」などと呼ばれて世間に認知されたので大いに嬉しい(と言って、別に症状が緩和されるわけでもないが)。20年ほど前、宇都宮にいたころには日光からの杉花粉がもの凄く、学生さん達も大勢が花粉症だった記憶がある。
そう言えば、2月初めに土木の小泉明教授にお会いしたときにマスクをされていたので「お風邪ですか」と問うと、「もう花粉が飛んでいるんですよ」とのお返事。ちなみに小泉明先生は、土木の上下水道などに関する衛生工学を御専門とされており、私の叔父と同業という縁で存じ上げている(学内の委員会などでご一緒したことは一度もない)。教授会の席で「あなた北山さんですか。私、あなたの叔父上とは学会などでよく一緒になりますよ」と小泉先生から話しかけていただいたのが最初である。
私はそのとき、ドキッとした。なぜかと言うと、叔父は相当の変わり者だからである。その当時、叔父は武蔵工大の土木の教授をしており、そこでも変人ぶり?はかなりのものだったらしい。10年ほど前、日本地震工学シンポジウムの実行委員をしていたとき、アルバイトの武蔵工大・土木の大学院生と話したことがある。
私:「君の大学にA(叔父のこと)っていう先生がいるだろう。そのひと、相当に変わっているだろ?」
学生:「ええ、まあ」
私:「そうだろうね。どんな風に変わってるのかい?」
学生:「A研究室に入ると最初に、下水を処理してきれいになった(?)という水で、コーヒーを沸かして飲まされるそうです」
私:(げげっ)「そのひと、実は俺の叔父さんなんだ。あははっ、まあ血はつながっていないけど」
学生:「えっ。。。。」(絶句)
とまあ、こんな感じである。今は、大学を定年で辞めて社交ダンスに精を出しているらしい(これも小泉先生から伺った話である)。
そうだ、花粉の話だった。ううっ、これを書いている今(夜中ですが)も、目が痒くて鼻ぐずぐずでくしゃみ連発である。もうやめて寝よっと。
以下は『卒業論文を書いていた頃(2009年01月19日)』のつづきです(2009年2月12日)
タイピング
キーボードのブラインド・タッチも青研で習ったことのひとつである。私が研究室に入ったときにはまだパソコンというものが普及し始める直前であり、日本語ワープロもまだなかった。確か初夏の頃にNECの名機PC-9801が1台、研究室に導入された。そして塩原さんから、キーボードのブラインド・タッチの初歩を教わったのである。
今でこそ、ストレスを感じること無くワープロを打つにはブラインド・タッチは必須であるが、その当時はまだワープロ自体がなかったので、純粋にキーボードを見ずにタイピングできたら格好いいなあ、くらいに思っていたのだろう。塩原さんはそれこそ機関銃のごとくにキーボードを打つことが出来たので、それにも刺激されたことは間違いない。塩原さんからホーム・ポジションを教わったあと、CRTを見ながら何でも良いから英語をたくさん打つように、と指導された。しかしパソコンは1台だけなので、タイピングの練習ごときに卒論生が使うわけにはいかない。そこで朝、少し早く登校して実験が始まる前に30分ほど毎日練習することにした。
その後、一年ほどのあいだにパソコン(98)の台数も増え、日本語ワープロも導入された。そしてこの練習のかいあって、私も機関銃のごとくがんがんキーボードを打てるようになっていた。それを見た小谷先生が「凄いねえ」と感心していたくらいである。また宇都宮大学に赴任したときにも、「もの凄い早さでキーボードを打つ先生が来たぞ」という話に尾鰭も付いて広まって、構造研のパソコン室まで見に来る学生が現れる始末であった。卒論生のときに塩原さんからいただいたアドバイスと自分自身の訓練のお陰で現在、私は何のストレスもなくワープロを打ち、メールを打ちまくっている。ありがたいことではある。
以下は『卒業論文を書いていた頃(2009年01月19日)』のつづきです(2009年2月10日)
高田馬場
これは青山博之先生のお住まいの地名である。高田馬場と言えば忠臣蔵の堀部安兵衛の仇討ちで有名だが、ここでは関係ない。ちなみに私の祖父は隣町の早稲田に住んでいて、その近くにある水稲荷神社では流鏑馬が行われることで有名であった(もっと関係ありませんでした)。私が卒論生だったときには先生のお宅は改築中であったから、ご自宅に伺ったことはなかった。ただ、学部3年生のときの内田祥哉先生の「建築構法」という授業で、建築のさまざまなディテールを街に出てスケッチしてこいという課題があって、自宅周辺を自転車で走り回っていたときに、偶然青山先生のご自宅を発見した記憶がある(当時は百人町に住んでいたので近かった)。
さて卒論も提出し終わってひと段落ついた3月に、先生のRC造のお宅が出来上がって引越しされることになった。そのときにお手伝いしたのが4月からM1に進学することになっていた私と中村哲也くんである。
その当時、先生の荷物は逗子の別宅に保管されており、引越し前夜に二人でそこにお邪魔した。その晩は青山先生が運転される車に乗せていただき、たしか逗子(葉山?)マリーナで御馳走していただいた。そんな立派なレストランにはそれまで行ったことがなかったので、何を食べてよいのか分からなかった。そして逗子のお宅に戻ると、今度はご長男の趣味であったロックのレコードなんかを聞かせて下さった(何を聞いたかはさすがに憶えていない)。
翌朝、青山先生に起こされて朝食をご馳走になったが、何と先生が御自ら目玉焼きを作って食べさせてくださったのだ! 多分、数多い教え子のなかでも青山先生に朝ご飯を作っていただいたのは、我々だけではないだろうか。
逗子での搬出が終わると、今度は高田馬場の新しいお宅で搬入作業である。私は先生のお宅の台所用品を運んだので、その後、青山先生のお宅に遊びに伺うたびに紀久子奥様から「北山くん、○○持ってきて」と頼まれて、「は〜い、わかりました」と勝手に台所へ行って取ってきたものである。その晩は青山先生ご一家と夕食をご一緒させていただき、私は歩いて家に帰った(高校生の頃はよく歩いて高田馬場のBig BOXという商業ビルに遊びに行っていたので勝って知ったる夜道だった)。
その後は幾度となく青山先生のお宅に伺い、ときには泊めていただいた。柱梁接合部の三国共同セミナーなどのときには、外国の先生方をお招きしたパーティにもお呼びいただいた。私が宇都宮大学の助手になってからは、今度は宇都宮大学で私についた卒論生(小嶋千洋くん)ともども泊めていただいて、翌朝、青山先生はとっくに出勤されているのに、われわれ二人で奥様から朝食をご馳走になった、なんてこともあった。こう見てくると大学の先生も大変だなあ、と感慨深い。ちなみに私のところは家も狭くてあばら屋なので無理ですから、悪しからず。
2008年度の卒業設計に寄せて (2009年02月09日)
今年も学部の卒業設計の審査が行われた。昨年同様、9階の製図室を綺麗に片付けて、全部で26名の作品を一同に展示するポスターセッション形式での審査である。朝9時から11時半まで、それぞれの作品ごとに作者に説明させたあとさらに議論しながら採点をするのであるが、つい学生さんと議論したり、場合によっては説教したりするので、時間はどんどん過ぎてゆく。
学生さんの話しを聞いていくうちに、思いもかけない発想に出会ったり、奇抜な着想に感心したりしたが、そういうものは本来図面を見ただけで伝わるようでなければいけないものである。例年のことであるが、図面表現やプレゼンテーションの方法がなっていない、と感じざるを得ない。ただ今年は、毎年必ず数件は見られるコンセプチュアルな、しかしながら建築としての実体は空虚な、そういった作品は無く、ちゃんとした?建築がそれなりに設計されていたので安心した。卒業するときの記念として何か概念的な発想でプレゼンテーションしたいという欲求は理解できなくもないが、私はそういう実体のない作品は評価しない、という主義である(これは“主義”なので、良いとか悪いとかは言わないで下さい)。
私は鉄筋コンクリート構造を専門とする教員なので、卒業設計も構造的な視点で採点するんだろう、と思うひとが多いらしいが、そんなことは全くない。建築はあらゆる分野のコラボレーションの結果として存在するのだから、あくまでも総合的に判断している。ただ、個別の作品に「これは何構造か? どうやってフロアを支えるのか」という質問をすることはあるが、このような質問はデザイナー氏だってするでしょう?
現在の審査方法は、どの分野の教員も同等の点数を持っており、それをトータルして最優秀賞が決まる仕組みなので、構造系だとか環境系だとか言っている場合ではなく、審査するこちらも真剣そのものである(そこで採点が終わると、もうぐったり、という感じである)。しかし教員によって評価基準は異なっているだろうから、全体の評価で上位に入らなかったからと言ってがっかりする必要は無い。このような採点方法では最大公約数的な、ある意味優等生的な作品の評点が高くなる傾向にあるからだ。それ故、過激な提案や風変わりなコンセプトに基づく作品は、それを高く評価するエキセントリックな評価者がいたとしてもトータルとしての評点は低くならざるを得ない。ちなみに私が最高点をつけたのは、知的障害者のための学校を設計したS君の作品である。
個々の学生さんには辛口の批評をしたかもしれないが、どの作品にも必ず売り文句や良さがあることは理解できた。その意味では、若い建築家の卵たちのパワーを感じることが出来た、楽しいひとときであったとも言えるだろう。一所懸命に卒業設計に取り組んだ学生諸君、ご苦労様でした。これで卒業して社会に巣立つひともいることでしょう。大いに頑張って下さい!
以下は『卒業論文を書いていた頃(2009年01月19日)』のつづきです(2009年2月06日)
スキー
青研では野球と並んでスキーも盛んであった。毎年3月に研究室をあげて春スキーに出かけるのが恒例の行事になっていた。行く場所と泊まる宿はだいたい決まっていて、八方尾根ならヒュッテ・ニポポ、志賀高原なら発甫温泉のホテル東館、野沢高原なら旅館魚安、などであった。この頃は空前のスキーブームで(原田知世主演の映画「私をスキーに連れって」はご存知ですか?ユーミンの主題歌が懐かしい)、猫も杓子もスキーに出かける時代であった。スノーボードなどはまだなかった。スキー場はどこも混んでいて、リフトやゴンドラの待ち時間が半端じゃなかったし、お昼どきのレストハウスも大賑わいであった。
青研の面々はとにかく酒好きが多いことは既にことあるごとに話してきたが、スキー場でもその特性はいかんなく発揮された。まず、お昼でも何でも休憩するときには必ずお酒を飲むのである。ビールが多かった気がするが、ところによってはワインだったり、日本酒だったりした。
それまで私は、スキーは純粋なスポーツとして楽しむもので休憩中にお酒を飲んだりすることは考えたこともなかった。それが青研の先輩達ときたら、レストハウスに入るなりビールを持ってきて、ぐびぐび飲むのである。仕方がない、Do as Romans do. である。これで私も酔っ払いスキーを覚えることになった(ただしこれは相当に危険なので、お勧めしません。酔っぱらうとどんな急斜面でも直滑降で突撃できる気がするので、大変に危ないです)。この青研スキーにはOBの方もたくさん来た。レストハウスでお酒を飲むことにかけてはお金に頓着せず、気前よくポンっと払って下さった。お金のない学生にとっては本当にありがたいことでした。
青研スキーのもうひとつの特徴が雪上ワインパーティーである。また酒の話しか、とウンザリしないで下さいな(昔のひとの娯楽と言えば、お酒を飲むくらいのものだったんでしょうね。ちなみに小谷先生がその昔作った質点系用地震応答解析プログラムはその名も「Sake」と言うんです。さらに付言すると、壁谷澤先生が作った骨組用地震応答解析プログラムは「Dandy」でした。う〜ん、分かるような気がする)。
これはゲレンデの適当な場所にワイン、つまみ、スープなどを運んでみんなでワイワイやるもので、何せ運ぶものが多いからワインなどを詰め込んだ段ボールを両手で抱えて、スキーを履いてストックなしで滑って現地まで運ばなければならない。私なんかは八の字のボーゲンがやっとであったが、長野育ちの本多さんはとてもスキーが上手で、ストックなんかなくてもパラレルやウエーデルンですいすい滑ってきた。
ワインパーティーの設営場所が決まると、こんどは各自のスキーを並べて座るところを作り、研究室でひずみゲージのコーティング材(ワックス)を溶かすときに使う固形燃料用コンロ(こんなものまでわざわざ東京から持ってくるのだ!)に火をつけてスープを作る。それを紙コップについで先輩達たちへ配るのである。そうやって大勢で飲み騒いでいると、「楽しそうだな」という風に思ってやってくる赤の他人もいたりする。ただ青研の人たちはみなどちらかというと硬派だから(中埜みたいな軟派もいたが、、)女の子を呼んで来るということは少なかったようだ。ワインがまわって酔っぱらうと、上半身裸で滑って行ってしまう輩まで現れるから面白い(これはT君という後輩で現在は清水建設にいる)。
この研究室スキーには小谷先生やときには青山先生も参加されたようだ。青山先生のスキーは大変に堅実で、ストックで三角形状のトラス構造を形成して安定した滑りをなさるという伝説が、私が青研に入った頃にはすでに流布されていた。残念ながら私はそのお姿を拝見したことはない。小谷先生は、と言えば、せっかちな性格そのままに弾丸のようなスピードでビュンビュン滑っておいでだった。
(つづく)
以下は『卒業論文を書いていた頃』のつづきです(2009年1月27日)
建研へ行き、芳村学先生と出会ったはなし
夏休みのお盆を過ぎた頃である。先輩方(加藤大介さん、Yoshie Halimさん、塩原さん、小林さん)と筑波にある建設省建築研究所(建研)に遊びに行った。この頃はまだ実大7層RC建物実験の余韻が残っていて、先輩方は研究のためによく筑波に行っていたらしい。この当時、青研の先輩である芳村学さん(現首都大学東京教授)や岡田研出身の勅使川原正臣さん(現名古屋大学教授)が研究員として勤めておられた。建研は田舎にあるせいか、福利厚生施設に恵まれており、25mプールやテニスコートで大いに汗を流した記憶がある。ここのテニスコートで大久保全陸先生(現九州芸術工科大学名誉教授)に初めてお会いした。
さて夜になり、経緯は忘れたが芳村さんのお住まいの官舎に伺うことになった。芳村さんとはもちろん初対面である。そして今に至るまで忘れることのない痛烈な思い出がひとつ、刻まれることになった。その日、建研に遊びに行った卒論生は私一人であった。同級生の多くは大学院を受けることになっており(もちろん私もそうである)、その入学試験が一週間後に控えていたために、私以外は誰も参加しなかったのである。
その事実を多分芳村さんにお話ししたのだろう、彼はこともあろうに私に(いつもの冷静な口調で)こう言ったのである、「いやあ、君は多分、試験には落ちるよ」と(芳村先生はとっくにお忘れでしょうが)。この言葉に私は激しく動揺した(と思う)。いくら研究室の先輩後輩とはいえ、初めて会った人間にこんなショッキングなことをズバッと言うだろうか? 「多分、大丈夫だよ」とか何とか言って元気づけるものではないだろうか。それまでも勉強していなかった訳ではないが、このお言葉にはガツンとやられた。そしてそのあとの一週間は猛勉強したのである(まあ泥縄ですが)。そのかいあってか、私は無事試験に合格することができた。よかった、よかった。
ちなみにその後も何度も建研には遊びに行き、建研に泊まって今井弘先生(当時筑波大学助教授)たちと麻雀をしたり、勅使川原さんのお宅や芳村さんのお宅に泊めていただいたりもした。勅使川原さんには、生まれたばかりのお子さんのお食い初めのビデオを「かわいいだろう」と延々と見せられて閉口した。中田慎介さん(現高知工科大学教授)にはウナギをご馳走になったり、大洗に遊びに連れて行ってもらったりした。
こうして芳村さんは私に鮮烈な印象を与えたのである。その後、青研でのRCD研究会などで芳村さんには大変に親しく接していただいた。後年、私が都立大の専任講師候補者となり、西川先生に面接のために南大沢キャンパスに呼ばれたとき、西川先生は「おい北山、誰にも会わずに帰れよな」と言われたのだが、芳村先生のお部屋の電気がついていたため、ついフラッとそのドアを叩いてしまった。当時は助教授だった芳村先生はこの人事をご存じなかったようで驚いておいでであった。私は昼ご飯を食べていなかったので、芳村先生にそのことをお話しすると、カフェテリア(その当時はここでもランチを提供していた)に案内して下さった。こんなどうでもいいことって、意外に憶えているものです。翌年私は、西川先生と芳村先生のお部屋のあいだに研究室をいただいた。そして同じ大学の教員として芳村先生には今に至るまで大いに助けていただいてきた。いやあ、やっぱり青研の先輩って、い〜いもんですねえ。
卒業論文を書いていた頃 (2009年1月19日)
わが研究室では、卒論梗概の提出まで1週間を切って、卒論生たちがその作成に心血を注いでいる(?)、今日この頃である。先日、WPCプロジェクトで耐震補強のためにエポキシ樹脂を使えないか、ということを高木次郎准教授から相談され、そう言えば私の卒論はエポキシ樹脂やエポキシ樹脂モルタルをコンクリートのひび割れに注入したり、剥落したところに詰めたりして補修する技術に関するものだったことを思い出し、久しぶりに自分の卒論を取り出してみた。そこで、今回は私が卒論を書いていた頃の思い出をお話しする。
1 研究室を選ぶはなし
私は学部4年生に進級した1983年4月に、鉄筋コンクリート構造を専門に研究する青山・小谷研究室に入った。このときの卒論生は今村晃、中埜良昭、中村哲也、溜正俊、山上敬、小出敏弘と私の計7名で、その頃としては近来まれに見る多さであった。
私自身は学部3年の頃には建築評論やロシア・アバンギャルド(エル・リシツキー、ウラジーミル・タトゥリンやエイゼンシュタイン)、フランスのビジオネール建築家(ショウの製塩工場を設計したルドゥーやニュートン記念堂のブーレー)たちに興味があり、そのような本をたくさん読んでいた。そして数名の学友達(誰がいたかはもう忘れたが、日色真帆はいた)と稚拙な建築評論をしたためては、製図室のアルコーブを仕切る壁に張り出したりしていたのである。
そんなこともあり、最初は西洋建築史をやろうと思っていたので、鈴木博之先生(当時助教授、「建築の世紀末」という著書でサントリー文芸新人賞を受賞されたころ)の研究室の門を叩いた。そこで卒論のテーマまでいただき、19世紀の修復建築家ヴィオレ・ル・デュクのことを調べるために、英語やフランス語の書籍を三冊ほど与えられていた。
しかし、それらの本を読み始めてから、何も分からない私は「こんな本を読んで、卒論が書けるのか」という(今にして思えば鈴木博之先生には何かお考えがあったのだろうが)疑問を持つに至った。さらに歴史をやっても飯は食えないのではないか(歴史家の皆さんご免なさい)、という大それた疑問も沸々とわき上がり、博之先生(当時は鈴木成文先生が教授でいらしたので、区別するために「博之」先生と呼んでいた。ちなみに師匠の青山先生もお名前は「博之」である)には甚だ申し訳なかったのであるが、「卒論やめた」と言ってヴィオレ・ル・デュクに関する書籍をお返ししたのである。
でも、そのときさすがに一人では博之先生にお話ししにくかったので、同級生でまだ卒論の研究室が決まっていなかった野嶋慎二(彼とは駒場のクラスも一緒であった。現福井大学教授で都市計画が専門)を一緒に連れて行って、「私の代わりにこいつが先生の研究室に入りたいと言っています」と人身御供?として提供したのであった(こう書くと随分悪いヤツなような気がします、私って)。ちなみに鈴木博之先生はその後も私のことは覚えていらしたようで、後年、私がRCを専門とする大学教員になってから再会したとき、先生から「逃がした魚は大きかったな」などという過分のお言葉も頂戴した。
さて、では何を卒論でやるか。その当時、製図室の黒板に学生達が自主的に希望する研究室名を書き込んでおり、青山・小谷研究室には中埜良昭(彼も駒場の同級生で、現東大生産技術研究所教授)だけが名前を記入しており、じゃあここにするか、と気楽に考えたのである。私が学生の頃には、「鉄筋コンクリート構造」の講義(小谷俊介先生担当)は4年生前期にあったので、鉄筋コンクリート構造についてはまだ何も知らなかった。また、小谷先生のお名前の読み方すら分からず、同級生の後藤治(現工学院大学教授、日本建築史が専門)は「こたに」先生と呼んでいたくらいである。
青山先生からは構造力学を既に習っていたので多少なじみはあり、また私の父親が青山先生とは知己であったこともあり、何かメリットもあるかな、という下心もあったような気がする。ただ、鉄筋コンクリート構造ってどういう原理で成り立っているんだろうという疑問や、耐震構造を知りたいという欲求があったことは確かである。
そこで小谷先生にお話を伺うと、研究室に入るためには「酒が飲めること、野球ができること、勉強はできてもいい」という三条件を挙げられたのである。私は当時お酒はほとんど飲めなかったし(その後の大学院生時代を見ると信じられない方もおいででしょうが)、野球じゃなくてサッカーをやっていた。あえて言えば、勉強も並みいる秀才と比べてできるわけではなかったので、三番目の条件を「勉強はできなくて当たり前」と読み替えて、かろうじてこの条件だけをクリアしていた、という感じである。
それでも、小谷先生はパキパキとしていたし、研究室の先輩達もよってたかって親切に説明してくれたので、「じゃあここにするか」という訳であった。その後、青研(あおけんと読む、青山・小谷研究室のことをそのように略していた)にはどういうわけか結局は7名もの卒論生が集まったことは前述した。ちなみにそのときの大学院生には、博士課程に加藤大介さん(現新潟大学教授)、ヨシ・ハリムさん(在インドネシア)と塩原等さん(現東大准教授)、修士課程に小林裕さん(現大成建設技研)、蔡さん(在台湾)と江村勝さん(現大林組)がいた。助手には細川洋治先生と田才晃先生(現横浜国立大学教授)のゴールデンコンビが座っていらした。また技官として東京理科大学建築学科の夜学に通いながら仕事をしていた本多健裕さんがいた。
さて研究室は目出度く?決まったので、次は卒論のテーマ選びである。目端の効く中村哲也君(現国土交通省)などは「この先輩の下についたら間違いは無いし、楽できそう」と言って塩原さんのテーマをさっさと選んだ(この選択が正鵠を射ていたことは後日、明々白々となった)。まごまごしているうちに他の同級生達もどんどんテーマを選んでゆき、私は最後に残ったテーマをやることになったのである。まあ、RCのことは何も知らないので何でもいいや、くらいの気持ちだったのだろう。それが田才さんの指導による「震災構造物の復旧技術に関する研究」であった。
2 青研のこと
研究テーマも決まり、毎日青研に通学するようになった。工学部11号館の7階である。ちなみに現在の都立大学での研究室も7階にあり、7階には不思議な縁を感じる。青研の研究室の窓からは安田講堂がよく見えた。青研は7階ワン・フロア全域を占有しており、ソファーやテレビのほか、二階建てベッドまで置かれており、研究に忙しいときや泥酔したときにはよく研究室に寝泊まりした。
卒論の最後の追い込みの頃、そのベッドからの起き抜けにM2の小林さんが「ルオー(東大正門前の喫茶店の名前、昔からあることで有名)のカレー食いにいこうぜ」と威勢良く言うので付き合った。ルオーでは朝早すぎてまだカレーを煮ているところだったが、無理を言って食べさせてもらった。さすがにまだ味が熟れていなかった。「ルオー」はその後、私の行きつけの店となり、マスターからいつもクッキーやゼリーなどをおまけで御馳走してもらったものである。今でも東大に何か用があるときには、ついでに「ルオー」に立ち寄ってカレーを食べるようにしている。おいしいですよ。
東大の正門前から赤門前にかけては、われわれの行きつけの店が幾つかあった。ちゃんこ鍋の「浅瀬川」、お寿司の「松よし」、「梅寿司」、「きずし」、飲み屋の「鳥八(とりはち)」、定食屋の「森食」、洋食の「モンテベルデ」や「バンビ」、おそばの「あさひや」や「万盛庵」、鉄板焼きの「ピグ」、カレーの「万定(まんさだ)」などである。
小谷先生は特に「鳥八」がお好きで、研究室でひとしきり飲んだあとや、飲み会の三次会などでよく行ったものである。はっきり言ってあんまりおいしくないのに(失礼!)、どうして小谷先生があんなに好きだったのか、今もって疑問である。ここの女将がいつも田才晃さんに向かって「あ〜ら、太郎さん、元気ベや」と言うのも不思議であった。
お寿司屋さんはさすがに値がはるので自分たちでは行けず、青山先生や時には名誉教授の梅村魁先生(故人)に連れて行っていただいた。「浅瀬川」にはいつも研究室の焼酎ボトルがキープされており、飲み尽くすとそこを利用する先輩方が新しいボトルを入れて通し番号をふる、というのが暗黙のルールであった。痩せの大食いで有名だった甲斐芳郎さん(清水建設)が自分の顔くらいもある大おにぎりを完食した、という伝説もお店に流布していた。
六本木から本郷においでになった岡田恒男先生が「北山君、カレーでも食べに行こうか」と仰るので、「ルオー」かなと思ったら、岡田先生がお好きなのは「万定」だったようでそちらに連れて行って下さった。「万定」のカレーはちょっと焦げたような香りがするのが特徴で、それはそれなりにファンがいるようであった。ここのレジスターはレトロなもので有名であった。また、バナナ・ジュースは絶品である。正門の真向かいにある「モンテベルデ」には、夕方の時間に余裕があるときなどよく行ったものである。だいたい小一時間くらい掛かるのであるが、備え付けのマンガを読みながら待っていた。ポーク・ジンジャーやミート・ドリアをよく食べた記憶がある。
研究室には卒業して社会人となった先輩方がよくやって来た。そしてソファーにどっかりと座って、いかにも我が家にでもいるかのように冷蔵庫を開けてはビールを飲み、戸棚を開けては日本酒やウイスキーを飲むのである。はじめてその光景を見たときには本当に驚いた。塩原さんと同級の勝俣英雄さん(大林組技研)が午後にやってきて、まだ日が高いのに、初対面の私に「ビール飲む?」と誘ってくださったことを昨日のことのように思い出す。研究室の先輩後輩の絆が如何に強固であるか、ということはその後、多いに実感することになる。
ワインパーティー
青研では小谷先生の発案で、月に一度、「ワインパーティー」なるものが開かれていた。当番の学生がワインを数本選んで買って来て、フランスパンだけを肴にしてあれこれ論じながらワインを楽しむ、というものである。多分、正統派酒飲みのワインの嗜み方なのであろう。青研には小谷先生の「酒はいくらでも飲めるぞ」という宣伝文句に魅力を感じて入った人が多く、おしなべて酒好きなので、皆それぞれに蘊蓄を語るのだが、私は全然ワインの味の違いが分からず、ただ酔っぱらうだけであった。
壁谷澤寿海先生
そのワインパーティーに当時横浜国大で助手をしていらした壁谷澤寿海先生がやって来た。私はそのお名前を初めて漢字の字面で見たときに、「珍しい名前の中国人だなあ」と思ったのである(例えば三国志の諸葛亮孔明も五文字の漢字でしょ)。甚だしい誤解であった。壁谷澤先生はせいが高く、今よりも当時はスマート(失礼!)であったが、立派な福島県人であったのだ。
かべさん(壁谷澤先生はそう呼ばれていた)は私のことを気にかけて下さり、いつも「北さん」と親しげに呼んでくれた(今もそうですが)。その後、壁先生はいろいろと飲みに連れて行ってくれたし、その流れで先生の代々木のお宅に深夜に乱入し、そのまま田才さんと一緒に泊まる、というコースがいつしか定着した。その前に代々木のスナックで閉店までカラオケを歌い、その後、別のスナックで焼うどんを食べてから壁谷澤邸へ、というのが定番のコースであった。その当時は壁先生の二人の息子さんともまだ小さく、今思えば大変に迷惑だったと思うのだが、奥様はいつも楽しそうに我々を迎えて下さった。
はじめて泊めていただいたのは確かM1の頃で、同級の定本照正君(現竹中工務店)と一緒だった記憶がある。壁さんはさっさと寝てしまったが、奥様が我々の相手を夜明けまでして下さったことをよく覚えている。私は研究室からジャージにサンダル履き、頭には手ぬぐいで鉢巻き、というみっともない姿で出かけて、紆余曲折の末に壁邸に辿り着いたため、一文無しであった。そこで奥様に千円をお借りして、夜明けの山手線にのって自宅に帰った(当時は新大久保に住んでいた)。
壁邸の玄関脇のコタツ部屋で田才さんと二人で雑魚寝していると、朝早くに二人の息子さんが起きて来て、寝ている我々を見て「わあ、怪獣が寝ている」と言っては、バシバシと踏みつけられて目を覚ました。そしてその部屋にあったファミコンを始めるのであった。その二人が寿一君と寿成君で、その後ふたりとも東大地震研の壁谷澤研究室に進学したことを思うと隔世の感があり、感無量である。ちなみに寿一君が大学受験でうんうん言っていた(はずの)高3のある深夜にも、田才さんと二人で壁邸にお邪魔した。かずくんに「東大受けるのか、大丈夫か」なんて無責任なことも言ったかも知れない。本当に申し訳ありませんでした。
余談であるが(なんて、この文章自体が全部余談なんですが、あはは)、私は青研の学生時代、先輩方と飲みに行ったときには自慢じゃないが一円も払った覚えがない。初めてお会いする先輩でも、青研の後輩というだけですぐに打ち解けたし、多分そういう後輩に御馳走することが当たり前、という研究室文化のなかで皆、成長したのだと思う。現在は東京都立大学で研究室を主宰しているが、このときのご恩返しを若い学生さん達にしているつもりである。
野 球
小谷先生の言葉とおり青研では野球が盛んで、Drinkers という、この研究室にぴったりの名前のチームを作っていた(ちなみに京都大学森田研究室にはSpirits というこれまた酒に関係する名前の野球チームがあり、何度か対戦した)。軟球であるが、ユニホームもあり、私は背番号27番をいただいた。
御殿下の運動場(注1)や農学部の東大球場を借りて、他の研究室やゼネコンの技研チームとよく試合をした。細川先生は少年野球の指導をされていたこともあり、球の投げ方やバッティング・フォームについて教えていただき、それなりに野球ができるようになった。ちなみに同級の中村君は灘高では野球部だったので、Drinkers では豪速球投手として活躍した。ただ、コントロールはあまり良くなかった。
私は自作の年間スケジュール表に、試合の結果のほかに何打数何安打かを記入して研究室の諸氏と競った。毎年春先には、11号館に入っている構造系の研究室対抗の野球の試合が行われ、優勝カップも作られていた。そこで優勝するのが最初の目標である。加藤研にいた木村匡君(現都市再生機構)が放った打球を見た外野の中埜がどういうわけか前進したのだが、目測が全然違ってあっという間にボールが彼の頭の上を超えてゆき、結局ランニング・ホームランになった、ということをよく覚えている。そのあと、中埜がDrinkers の面々からぼろくそに言われたのは無理もない。
(注1)御殿下の運動場を借りるためには、月に一度、運動会の本部に申請して希望する時間帯をゲットする必要があった。そのためには順番取りで何時間も並ぶ必要があり、授業すらサボっても良いと言われるほど、優先順位の高い行事であった。私はこの順番取りのために農学部・塩田先生の「造園」という講義をサボったのだが、そのことを塩田先生にお伝えすると「それじゃあ、仕方がないよな」とあっさり了解していただいたくらいである。物わかりのよい、いい先生であった(感謝してます)。
小谷先生は運動神経がよく、野球にも大いに参加してがんがん打ったが、青山先生は「ゴルフボールよりも大きいボールは苦手です」と仰って、ご自身でされることはなかった。ただお忙しい時間の合間を縫って、よく見に来ていただいた。大林組の技研に行って試合をしたときには、所長だった武田寿一先生もお見えになり、試合のあとに愉快にお酒をいただいた。ちなみにこの武田さんは「Takeda Model」を提案したご本人で、RC界では知らぬ人とていない有名人である。そんな訳で我々は、本末転倒ながら武田先生のことを「歩く武田モデル」と呼んでいた。
ちなみに清瀬の技研で泥酔した私は、小谷先生とともに何とか池袋駅まで辿り着いたが、それから延々横浜の自宅まで帰る自信が無く、やむなく早稲田に住んでいた叔父(綾 日出教といって当時は東大都市工学科の助教授であった)の家にタクシーで乗りつけて一晩、泊めてもらった。
他流試合では4大学対抗野球というのがあった。これは明治大学、芝浦工業大学、東京都立大学および東大のRC系研究室の対抗戦であり、こちらも年に一度開かれた。いずれも東大の梅村研究室を卒業した我々のOBが主催する研究室で、明治は狩野芳一先生、芝浦は山本泰念・清田清司・上村智彦先生、都立大は遠藤利根穂(故人)・西川孝夫先生である。
このときはじめて都立大のRC系研究室の人たちと交流が始まったが、まさか後年、自分がそこの教員になるとは思いもしなかった。ただこのときに西川孝夫先生に私のことを知っていただき、先生が主宰される地震工学講座の専任講師として1992年に都立大に呼んでいただいたことを考えると、何が縁となるか、人生って本当に分からないものですな。ちなみに私が都立大に赴任した当初は、この4大学対抗戦はまだ行われていたがその後、いつのまにか立ち消えになってしまったのは大変に残念なことである。ただ、学生さん達が対抗戦を企画しなくなったのだから、どうしようもない。これも時代の流れ、学生気質の変化の為せる技か。
試合になると絶対に負けたくないので、各チームとも本気モードになる。なかには女性がいてバッターボックスに立ったりすると、相手チームのピッチャーはたいがいは手加減して緩い球を投げるものだが、勝負にこだわりすぎて本気で投球したりすると、その大人げなさを大いに避難されて険悪なムードになったりした。
この対抗戦のあとは親睦をかねた飲み会となるのだが、明治の狩野研の学生達には驚かされた。私学だから人数が多いのだが、日本酒をなみなみと注いだ紙コップを机の端からはしまで並べておいて、「狩野ゼミ、かのうぜみ〜」と歌いながらひとりずつ一気飲みしてゆくのである(良い子は絶対に真似しないで下さい)。そしてひとりまたひとりとトイレに駆け込んでゆき、ついに狩野研は誰もいなくなった、となるのであった。ちなみに狩野芳一先生は橘高義典先生の岳父である。
西川研のピッチャーだった豊島学くん(現東急建設)のことを生意気だと言って、一年下級の香田伸次君(現清水建設)をけしかけて彼に酒を無理強いしたのは、大変にいけないことだったと反省しています(豊島さん、ご免なさい)。西川先生は大酒を飲んでは、唇から血を流しながら(多分、お酒のせいで唇が充血するのだろう)、いつものように「ガハハッ」と大笑いしておられた。
前述のように京都大学森田研究室のSpiritsとも野球の対戦が何度かあった。京都のひとは無骨な東男の東大とは違って芸達者なひとが多く、六車先生(故人)や角徹三先生(豊橋技術科学大学名誉教授)のお話や歌声はすばらしかった。付着で有名な森田司郎先生がSpiritsのピッチャーをされており、私が情け容赦なくガンガンとヒットを打ったため、お陰でその後森田先生には覚えよろしくとてもかわいがっていただいたが、小谷先生からは「北山くん、少しは手加減しろよ」と言って叱られた(後年、小谷先生が森田先生の京大退官記念文集に書かれた一文にこのときの逸話が載っており、そこには「無礼な北山君が」と記されていた。そんなに〜?)。
その当時、新婚だった助手の藤井栄先生(故人)は京大の学生達から大いに冷やかされていた。藤井さんからはその後、いろいろとアドバイスをいただいたりしたが、惜しくも若くして亡くなられた。森田先生のもとで藤井先生はその卓抜したアイデアによってRCの付着割裂破壊の機構を解明し、その強度を求める方法を提案されるなど大いに活躍された(このあたりの御業績は北山の大学院講義で詳しく説明している)。それだけにご存命であればRC界の発展は今まで以上であったろう、と悔やまれてならない。もって瞑すべし、である(合掌)。
閉室パーティー
青研ではお盆の頃と年末に「閉室パーティー」なる盛大な飲み会を開いた。これは青研の先輩方をはじめ、先生方と付き合いのある会社の方などが大勢見える一大イベントであった。このときは、われわれ在学生が鶏ガラスープを採っておでんを作ったり(青研には由緒正しい「おでんの作り方マニュアル」が存在した)、ベランダで炭火焼の焼き肉を作ったり、年末には杵と臼を使って7階のフロアで餅つきまでした。杵を臼へと振り下ろすと相当の衝撃があるため、構造を専門とする我々は臼を大梁の真上に据え置く、という配慮をしたのは当然であろう。ただしその振動は当然、上下の階にも伝わり、そうすると餅つきしていることがすぐにバレて、8階の坂本功先生(小谷先生と同級で、木造の大家)や、6階にいた加藤研助手の向井昭義さん(現建築研究所)などが食べに来たりした。
閉室パーティーでは研究室の学生一同がお金を出し合って、日頃お世話になっている先生方にプレゼントを贈る、という習慣があった。閉室パーティーは武藤研究室出身の先生方の研究室が合同で行う、というのが建前であったから、プレゼントの対象も青山、小谷、岡田、大沢などの諸先生であった。学生が出費するのだから、その額など多寡が知れている。そこで、先生方がプレゼントを開いたときに何とか笑いが取れるようにとか、先生方を唸らせることができるような前口上の屁理屈を考えだすとか、相当に苦労してプレゼント選びをしたものである。パーティーの前日とか当日に、プレゼント担当の学生は池袋界隈のデパートや東急ハンズなどに買い出しに出掛けた。
さて閉室パーティーでは、その年の卒論生が自己紹介するのが慣例となっており、黒板に氏名と出身高校名を記したあと、ドンブリに注いだビールをいただく、というのがコースであった。しかし私は、大きなドンブリのビールを一気に飲み干す自信など全くなかったし、そのときには慣れないお酒に相当に酔っていたこともあり、「こんなもの飲めるか〜」という勢いとともに何を思ったのかそばにいた勝俣さんの頭へドンブリビールを一気に降り注いでしまったのである!(プロ野球選手がやるビールかけを思い出して下さい)。
これにはさすがに温厚な勝俣さんも激怒した(当たり前です、返す返す申し訳ありません)。酔っぱらっていた中埜が「お前、先輩に向かってそんなことしていいのか」と叫びながらものすごい剣幕で私の胸ぐらをつかみながら振り回したので、勝俣さんも呆気にとられて、お怒りも少しは納まったようであった。しかしこんな傍若無人な卒論生は今までにいなかったらしく(当たり前ですな)、これ以降しばらくは先輩方から「勝俣にビールをかけた阿呆なやつ」という枕詞とともに私は呼ばれるようになった。ちなみにこんな無礼なことがあったにもかかわらず、勝俣さんはその後も親切に接して下さった。その度量の寛さに、ただただ感謝するばかりでありました。
浜田山
ワインパーティーや何かの飲み会が終わったあと、小谷先生が元気なときには「みんな、うちくるか〜」とおっしゃるので、よく先生のご自宅にお邪魔した。先生のお宅は浜田山の閑静な住宅街にあるRC壁式構造3階建ての瀟酒なタウンハウスである。先生のお宅のリビングの床にべったり座って、またお酒をいただくのであるが、小谷先生はいろいろな銘酒を揃えておいでで、「こんなのがあるけど飲む?」と言ってはすすめて下さるのである。小谷先生はこの当時はご自分のことを「小酒飲み」と言っておいでであったが、どう考えても「大酒飲み」である。私はもうすっかり酔っぱらっていることが多かったので、どんなにおいしいお酒でもその味が分かることはなかっただろう。「猫に小判」とは正にこのことである。そしてそのまま眠ってしまった私が目覚めると、大抵は田才さんや加藤大介さんが横に寝ていたものである。
小谷先生はワインがお好きなため、ご自宅にワインを貯蔵するセラーを欲しがっておられた。温度の変化が少ない地下が通常は選ばれるようである。そうして、このように何度も小谷先生のお宅にお邪魔しているうちに、どういう訳か私がそのワイン・セラーを小谷先生のお宅の地下に掘る、ということになってしまった。この話はその後、多くの先輩方の耳に触れるところとなり、「おい北山、小谷先生のうちの地下室は掘ったか」とよく冷やかされたものである。ちなみに現在に至るまで、私は何もしていない(当然です)。
(つづく)
カーズ考 〜年末年始に考えたこと〜(2009年1月2日)
昨年末に女房が子供に見せるためにウオルト・ディズニーのアニメ映画「カーズ(Cars)」のDVDを買ってきた。アニメ映画など子供が生まれるまでほとんど見たことがなかったが、見てみて驚いた。コンピュータ・グラフィックがとても精緻で、まるで実写のように美しい画面である。3歳の子供はもう夢中で、一日に4回も見るくらいである。私もしかたがないので付き合って見ていたが、いかにもアメリカ映画らしいストーリー展開および画面構成である。よく出来た話だし、映像も凝っていて作り込まれた画面という感じである。
しかし何度も見るうちにこれはやはり典型的なアメリカである、ということに気がついた。すなわちアメリカ全体を覆っている差別社会あるいは階級社会を見事に体現していたのだ。登場するのは全て車で、人間や動物は一切出てこない。主人公のレーシング・カーは空気力学を駆使したかっこうのよい造形で、ツルツルピカピカに描かれている。そこまではよいのだが、上流社会のメンバー達はポルシェ、フェラーリ、マセラッティなどいずれも世界の高級車であるのに対して、一般庶民は普通の乗用車やバンであったり、薄汚れて錆びていたりする。脇役のレッカー車はぼろぼろである上に、出っ歯である。さらに牧場のトラクターは明らかに牛扱いで、牛並みの知性しか有さないものとして描かれている。すなわちアメリカの実社会における差別や階級制を人間ではなくて、車に置き換えただけで作り出していたのである。
もともと「カーズ」は子供向きではなく、あきらかに大人向けに作られている。それでも、このことに気がついた私は、ウオルト・ディズニー社が提供する夢がいかに表面的であり、現実に拘束されたものであるか、ということに暗澹たる思いをいたしたが、これは考え過ぎであろうか。しかし日本のアニメ映画「となりのトトロ」などとは全く異質のコンセプトによって「カーズ」が支配されていることは確かであろう。
2008年の本ベスト3 (2008年12月22日/2009年1月5日改)
今年もそろそろおしまいですね。そこで、私が読んだ本のベスト3を記したいと思います。
はじめに飯嶋和一著「出星前夜」です。今日の朝日新聞に大仏次郎賞の受賞が報じられていましたが、それもうなずける傑作でしょう。江戸時代初期の島原の乱を題材にしていますが、主人公はいつものように一般庶民です。物語が幾つも折り重なって進む手法は彼独特のもので、主人公も一人ではありません。彼の他の作品では主人公が途中であっけなく死んでしまう、ということもあるくらいです。この著者は寡作でも知られており、作品は多くはありません。飯嶋和一の小説を一つだけ選べと言われたら、私は迷わず「神無き月十番目の夜」を挙げます。江戸時代の初期に起こった一村大虐殺をテーマとしたもので恐ろしい内容ですが、手に汗握る展開で一気に読んでしまいました。
次は若桑みどり著「クアトロ・ラガッティ」です。秀吉から徳川家康の時代に九州の大名たちがヨーロッパに送った天正少年使節の壮大な物語で、歴史学者でもない著者がよくぞ調べあげた、という大作です。人間の営みに対する著者の暖かい眼差しが随所に感じられる作品です。若桑先生がお亡くなりになったことは残念です。なお時代的な流れで言うと、天正少年使節が苦難の末に帰国したときにはすでに江戸幕府によってキリシタン弾圧が始まっており、その後に「出星前夜」の背景である島原・天草一揆が勃発します。
最後は、小島清文著「投降」です。これは太平洋戦争の戦記ものですが、帝国陸軍の下級将校が米軍に投降し、その後の収容所での生活を語ったもので、その事実には結構びっくりしました。旧日本軍の戦陣訓は「生きて虜囚の辱めを受けず」でしたから、戦後60年たってやっと投降の実態を語れるようになった、ということでしょうか。戦争の悲劇を改めて感じました。
以下の文章は宇都宮大学建設学科建築学コースの創設30周年記念文集に寄稿したものです。
建築学コース創設30周年によせて (2007年10月23日)
宇都宮大学の建築系学科もいろいろと変遷があったようですが、2007年に無事30周年をお迎えになったそうで、こころからお慶びを申し上げます。
私の所属する大学はさらに劇的な変化を遂げました。東京都立の4大学が統合して大学名も変わりました。建築学科も都市系の専攻と一緒になりました。大学の変化は主として社会からの要請と大学自体の自浄作用によって生起しますが、学問の本質や教育の理念は本質的に不変であると思います。大学人であるわれわれは常に自己を磨き、新しい課題に挑戦し、その成果を社会に対して発信することが大切だと思っています。
大学も全入時代を迎えて、いかに良い学生諸君を集めるかが大学の浮沈を握る重大事になりつつあります。高校への出前講義も始めました。宇大の先生方も大変でしょうが、ともにこの難局を凌いでやって行きましょう。何だか自分自身へのエールのようになってしまいましたが、宇大建築の益々のご発展を祈っております。
以下の文章は千葉大学工学部長・野口博先生の還暦のお祝いに際して著した一文です。
野口研究室の思い出
北山和宏(首都大学東京 准教授)
野口博先生、還暦をお迎えになったとのこと、心よりお慶び申し上げます。日月の経つのは早いもので先生が60歳になられたと聞いてびっくりです。でも、まだまだお若いようにお見受けしますから、赤いちゃんちゃんこが似合うような気は全くいたしません。
さて、私は1991年1月から1992年3月までの約1年、野口博先生のもとで助手を務めました。短いあいだでしたので研究室OBの方々もあまりご存じないと思います。当時の野口研究室は大型実験棟に先生や学生さん達の部屋があり、私も2階に常駐していました。野口研では月1回、実験棟で飲み会とカラオケ大会を開いていたことが一番の思い出です。当日は野口先生御自ら焼き肉の買い出しに出かけたりして、相当気合いが入っていました。カラオケも当時最先端だったLD(今はもう、ないですな)を野口先生がたくさん買って保管していました。野口研究室でのバカ騒ぎを今でも懐かしく憶えています。
研究の方では、平面柱梁接合部の実験や高強度材料を用いた柱のせん断実験などをお手伝いしました。柱梁接合部の実験は冬の寒い時期に当たりましたが、実験は真夜中にやったりして(本当はいけないんでしょうが)、学生さん達(柏崎、米澤、竹崎、瀬尾、阿部、蛭田などの諸君)とストーブに手をかざしながら作業しました。柱の実験は鹿島技術研究所との共同研究として実施しましたが、鹿島側の担当者が丸田誠さん(野口研OB)でした。高軸力を載荷しながら逆対称曲げ加力する実験装置を組み立てるのがひと苦労でした。そのときのメモ書きをここでは載せておきます。
野口研の担当学生は大学院生だった二村有則君で、彼はこれが縁となって鹿島に就職したんだと私は思っています。加力装置を組み立てるときにクレーンのワイヤが鉄骨治具に引っかかって、それがはずれたひょうしに鉄骨治具が大揺れしてヒヤッとした記憶があります。このとき近くに確か二村君がいて、怪我しなくてよかったなあと今でも思い出します。言うまでもありませんが、実験では安全第一です。
その後、私は東京都立大学に転出しましたが、快く送り出して下さった野口博先生には今も感謝の念を忘れることはありません。所属は変わりましたが、文部省科学研究費補助金による共同研究や、JCIや日本建築学会での活動など、いろいろと野口先生にはお世話になっています。これからもまだまだ野口先生にはご活躍いただき、私のようにぶら下がっている後輩を叱咤激励していただきたいと思っています。
最後になりましたが野口博先生とご家族の皆様のご多幸をお祈りしながら、擱筆いたします。
2006年9月吉日

鹿島と共同研究の実験メモ(1991年7月15日の記載あり)
以下の文章は宇都宮大学教授・田中淳夫先生が退官されるときの記念文集に寄稿したものです。宇大構造研のOBの皆さん、お楽しみ下さい。
宇大構造研と田中淳夫先生 (2005年11月29日)
東京都立大学大学院 助教授 北山和宏
私は田中淳夫先生に呼ばれて宇大構造研の助手となったが、先生のご専門である鉄骨構造の研究に関しては何ら貢献することはなかった。その当時、私は博士論文を纏めていたこともあり、鉄筋コンクリート構造の研究を好き勝手にさせて貰っていた。今思えば、これは甚だもって申し訳ないことであったのだ。多分田中先生は私のことを鉄骨構造の助っ人とはハナからお考えでなかったとは思うが、それでもデッキプレートの実験など、宇大実験棟で先生が実施された静的実験などをもう少し、お手伝いできたはずである。今更反省してもしょうがないが、私も研究室を主宰するようになって田中先生の偉さが分かったのだから、これまたしょうがない。
ここ十年ばかり、既存建物の耐震診断や耐震補強に関わってきたが、その際には鉄筋コンクリート造建物だけでなく、鉄骨造の体育館や渡り廊下なども審査することが多々ある。そのようなときに時々お目にかかるのがH鋼の両側にカバープレートを溶接した所謂「日の字H」断面の柱である。この柱の挙動について当時の田中先生がご研究されていたのを憶えている(植田君のゼミ資料だったか)。このときの印象のお陰で、「日の字H」柱を見ると「うーん。靱性がなくてダメですね」などと、知ったようなコメントが吐けるのである。田中先生に感謝、である。
構造研の学生たちはよく「田中先生はわがままだから、、、」と言っていた(先生、ご免なさい)。学生達がまた勝手なことを言いがやる、と思っていた。しかし反面、真実でもありそうだったので、学生達の洞察力の鋭さに感嘆した記憶がある(またまたご免なさい)。田中先生の「北山君、いるか。みんな、飯食いに行くぞ。」という決まり文句が懐かしい。今の学生さん達は一緒にご飯にも行ってくれませんもの(泣きごとです)。
古い写真を探していたら、1990年頃の宇大建設学科懇親会の写真があったので掲載した。誰がどこにいるかは皆さん、探してください。懐かしい顔がたくさん出ています。ただ、田中先生はこのときも綺麗な銀髪をしていたことがわかります。
 
第13回世界地震工学会議 宇都宮大学建設学科懇親会のひとこま
(バンクーバー、2004年8月)にて (1990年頃か、宮沢先生の退官記念のようである)
田中先生と筆者
以下の文章は小谷俊介先生(東京大学建築学科)の東大退職記念文集に収録するために執筆したものです。この文集は未完ですが、せっかく書いたのでここに掲載します。私が大学院生当時の話です。
青山・小谷研究室での柱梁接合部の研究 (2003年9月26日)
東京都立大学大学院 北山和宏
私が青山・小谷研究室に学生として在籍したのは1983年4月から1988年3月までであるが、その後も1992年までは両先生の共同研究者として工学部11号館地下2階の実験室で柱・梁接合部の実験に従事させていただいた。そこでこの期間に生起したいくつかの事柄について書いてみたい。
青山・小谷研究室で最初に立体柱梁接合部の実験を行ったパイオニアは鈴木紀雄氏(現鹿島)であろう。その後、小林裕氏(現大成建設)、Joshie K. Halim 氏(現在インドネシア)がそれぞれ柱梁接合部の実験を担当された。私は卒論生のときに修士2年だった小林さんの平面柱梁接合部試験体の製作や実験のお手伝いをしたが、難しそうでかつ大変そうだなという印象を持った。しかし修士1年になって小谷先生から何を研究したいかと問われて「付着です」と答えたら、「それだったら柱梁接合部がいいよね」と言われたので仰天した。それまで柱梁接合部についての知識などなかったので、主筋の付着と柱梁接合部とがとっさには結びつかなかったのである。
あまりに動転したので(そして、なぜ私が柱梁接合部を?という疑問もあって)、そのあと小谷先生がお話された研究内容など全く覚えていない。しかし今になって思えばこれこそまさに天の声であったのであろう。その後、私は柱梁接合部で博士論文を執筆し、現在もまだ研究を続けているからである。曲げ、せん断、付着といった鉄筋コンクリート構造の基本原理のエッセンスが凝縮している柱梁接合部を研究するよう導いて下さった青山先生と小谷先生には大いに感謝しなければなるまい。
さて、地下2階での実験について書く。写真1は実験風景である。地下2階は湿っぽくて、ピットの上部にある窓から日が差すのは朝だけであった。今思えばとにかく暗いところであるが、学生だった当時は不思議とそういうイメージはない。いつも田才晃さん(当時、助手/現在、横浜国立大学教授)と一緒に楽しく実験していたせいであろう。
11号館のエレベータは夜8時半頃に警備の牧野さんの手によって停止したので、夜遅くまで実験すると7階の研究室まで階段で上がらなければならず、大変だった。そのあとは、小谷先生のロッカーから先生備蓄のインスタント・ラーメンを勝手に取り出して、食したものである。あるとき、あんまり食べてばかりでは悪いと思って先生のロッカーにラーメンを補充しておいたら、「そんなことはしないでよろしい」と言われて、これは偉い先生だ、と思ったりした(学生だから単純である)。
しかし小谷先生との忘れられない出来事は、私が博士課程2年のときのことである。これは大変に恥ずかしいことであるので一部省略するが、書いておかなければならぬ。11号館1階の大教室で鈴木成文先生の最終講義があるのでそのあいだは地下2階で実験するな、と言われたのである(ポンプの音がうるさいから、と言う理由であった)。そのとき、私は実験を急いでいた。その年の3月末には大学院を中退することになっており、とにかく早く実験を終えたかった。その気持ちを理解してもらえず、全くもって気が滅入った。そして最終講義が終わった夕方から加力を開始したのである。
そのとき、小谷先生が地下2階においでになった。その日、小谷先生は具合が悪くて自宅で静養していらしたが、私のことを心配された先生はおでんの材料を持って慰問に来て下さったのである。小谷先生、田才さん、田中清さん(当時、研究生)とおでんを食べながら、小谷先生にもひび割れ書きをしていただいた。このとき地下2階で小谷先生が撮影してくださった写真は、私の博士論文の冒頭を飾っている。小谷先生は常日頃は大変に厳しい方であったが、学生に対してかくも優しい一面をお持ちであった。

写真1 : 東大工学部11号館地下2階での立体柱梁接合部実験
相当に話が脱線した。柱梁接合部の実験に戻ろう。3国セミナー(後述)の研究の一環として東京大学では、スラブ付きの立体柱梁接合部試験体を用いて水平二方向力および鉛直一定軸力を加える実験を1985年に実施することになった。私の修士論文の一部である。青山・小谷研究室では十字形柱梁部分架構の柱脚をピン、梁端をローラーとして柱頭に水平力を載荷するシステムを採用している。しかし柱頭の軸力用クレビスと水平力用クレビスとが一致していなかったため、大変形になると柱頭の付加モーメントの影響が無視できなくなるなど、力学的に不明確な問題が生じていた。
そこで鉛直力と水平の二方向力とが一点で介するユニバーサル・ジョイント(三軸一点クレビスと呼ぶ)を細川洋治先生(当時、助手)が設計してくださり、浅野キャンパスにあった工作室で作製していただいた。細川先生の卓抜したアイデアの賜物である。その後、高強度コンクリートを用いた柱梁接合部の実験を可能にするため、三軸一点クレビスの耐荷容量増加が必要となり、細川先生のご指導のもとで二代目を私(当時は宇都宮大学の助手をしていた)が設計した。1990年のことである。あの三軸一点クレビスはどうなったんだろうか。ちなみに東京都立大学でも類似の三軸一点クレビスを作製して実験を行っている。
さて、柱梁接合部に関する三国セミナーを説明しよう。これは日本・アメリカ・ニュージーランドの三国(後に中国が加わって四国になる)の研究者・設計者が柱梁接合部の力学特性や耐震性能に関わる諸問題に対して共同して解決を試みたものである。三国セミナーについては青山先生や小谷先生が別に詳細に説明されているので、ここでは繰り返さない。その共同研究期間は1984年から1989年であり、青山・小谷研究室における私の研究生活は三国セミナーとともに始まった。
第2回の三国セミナーは1985年に日本で開催され、私もお手伝いとして討論の場に同席することを許された。それとともに米国、NZからの出席者を筑波万博に案内したり、青山先生のご自宅でのパーティに伺ったりもした。そのとき私は、第1回の三国セミナーでの合意事項に従って立体柱梁接合部試験体を設計しており、ラフな配筋図を仕上げたところであった。ちょうどテキサス大学のJ. O. Jirsa 先生をホテルから青山先生のご自宅まで案内するよう言われたので、山手線の電車の中でその図面をJirsa 先生に見ていただいたことをよく覚えている。
当時私は立体柱梁接合部パネルのせん断強度を実験によって検討したいと考えていたが、三国セミナーでの合意は梁降伏先行形の試験体を実験することであり、「そんなのイヤだ、接合部破壊形を設計する」と言っては小谷先生を困らせたものである。もしかしたらこれが小谷先生を困らせた最初かもしれない(その後はたびたび先生を困らせる次第となったが、小谷先生はその都度丁寧に説明をしてくださった)。
第3回の三国セミナーからは私も正参加者として出席させていただいた。そのために相当数の英語の論文や報告を作成したが、小谷先生はそれら全てに対して大変丁寧な添削をして下さった。初稿に対しては?印が無数に書かれていた。おかしな英語なので通じないのである。その後、第2校、第3校と重ね、最後に小谷先生は「君が言いたいのはどういうことかい」と聞かれながら、私の答える日本語に対してすらすらと英文を連ねるのであった。教育とはこういうものか、と思ったものである。しかしこの指導の恩恵は非常に大きく、現在の私の基礎となった。ちなみに現在は私も小谷先生のように、学生の作る論文に対して?マークを連発している。
最後に1987年にニュージーランドで開催されたPacific Conference on Earthquake Engineering に関連するひとこまを紹介する。写真2には威勢のよさそうな三人が写っている(右から小谷先生、Paulay 先生、筆者)。このとき私は、青山先生と小谷先生のお陰で始めて海外に出かけた。ニュージーランドに向かう飛行機(このときは小谷先生と千葉大学の野口博先生とご一緒した)の中で朝を迎え、目覚めた小谷先生が起き抜けに一番、「せん断がね…」と仰ったのには本当にびっくりした。私は寝ぼけていたが、この強烈な印象だけは未だに海馬の奥深くからときどき湧き戻ってくるのである。いやあ、やっぱり偉いひとって違うなあ、と感じたのでありました。
完

写真2 : 小谷俊介先生、Thomas Paulay 先生というRC界の巨頭お二人と
補遺: T. Paulay 先生(ニュージーランド・カンタベリー大学)は本当に気さくな先生である。私に話すときにはいつもゆっくりとした丁寧な英語を使って下さった。Paulay 先生の研究室にお邪魔したときには、先生の論文冊子を「Here present!」と言いながら渡して下さった。大勢で群れているわれわれ青山・小谷門下の若い研究者たちのことを、いつも「University of Tokyo Mafia」と楽しそうに呼んでいたことを思い出す。(2009年1月5日)
|

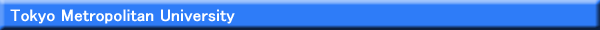
 トップページ > メモランダム2009
トップページ > メモランダム2009




 社現代新書、2009)を読んだ。そんなにマンダラに興味があったわけではない。密教美術である曼荼羅図には、何かしら神秘的なイメージがある。以前に武澤さんが書いた『法隆寺の謎を解く』(ちくま新書)を読んで面白かったことを憶えていた。
社現代新書、2009)を読んだ。そんなにマンダラに興味があったわけではない。密教美術である曼荼羅図には、何かしら神秘的なイメージがある。以前に武澤さんが書いた『法隆寺の謎を解く』(ちくま新書)を読んで面白かったことを憶えていた。


 テープにはいろいろなグレードがあって、クロムテープなどが高価だったと思う。
テープにはいろいろなグレードがあって、クロムテープなどが高価だったと思う。 東工大の林静雄先生、坂田弘安先生、東京理科大の衣笠秀行先生と一緒に改定作業を行ってきた、新版「鉄筋コンクリート構造」が10月初旬に市ヶ谷出版社より刊行されました。値段も2,800円に値下げし、表紙も明るい緑色系にしてデザインも一新しました。
東工大の林静雄先生、坂田弘安先生、東京理科大の衣笠秀行先生と一緒に改定作業を行ってきた、新版「鉄筋コンクリート構造」が10月初旬に市ヶ谷出版社より刊行されました。値段も2,800円に値下げし、表紙も明るい緑色系にしてデザインも一新しました。


 験体ではその上下に約1/4層分ずつを付加した形態とした(写真は
験体ではその上下に約1/4層分ずつを付加した形態とした(写真は





 あるが、いやあ本当にコチコチになりましたな。昨年の暮れに芳村学先生の建築学会賞受賞記念パーティのときに、芳村先生が「私は青山先生のもとで鍛えていただいたおかげで、どこへ出てもビビらなくなりました」とスピーチされたが、青山先生ご本人の前ではビビらないんでしょうか。
あるが、いやあ本当にコチコチになりましたな。昨年の暮れに芳村学先生の建築学会賞受賞記念パーティのときに、芳村先生が「私は青山先生のもとで鍛えていただいたおかげで、どこへ出てもビビらなくなりました」とスピーチされたが、青山先生ご本人の前ではビビらないんでしょうか。










