仏文バンドavec西山先生
2016年7月2日(土)、首都大 七夕祭・野外ライブにて、「仏文バンドavec西山先生」がJ-POPとシャンソンを4曲演奏しました。動画はこちらにアップしました。
Vo. 西山雄二 G. 中野慎太郎、西あかね B.吉田あんず Dr. 志村響
-
-
終わりへ向け継続が大事 平岡敦(フランス文学者)
2014.8.3 産経ニュースより
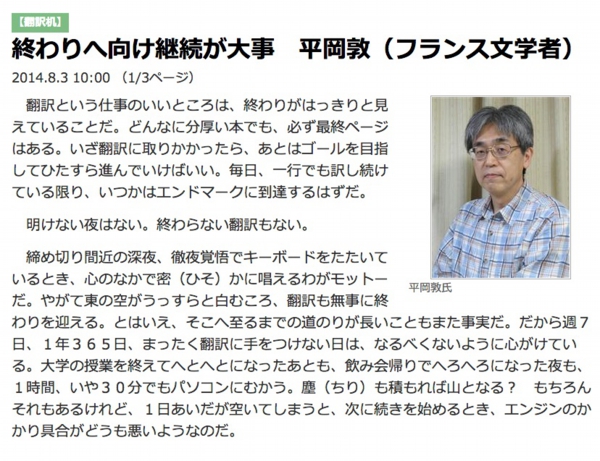
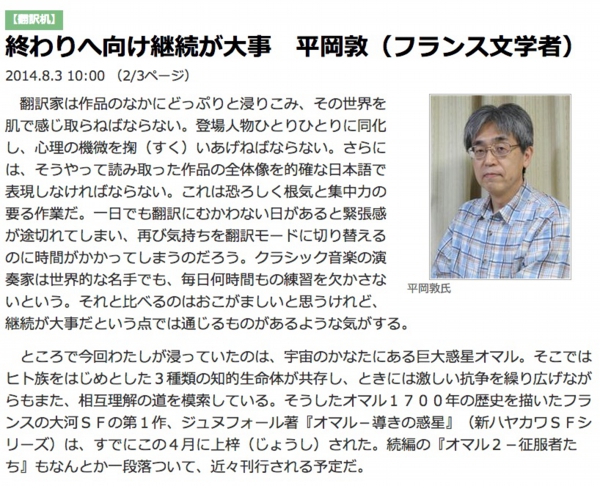
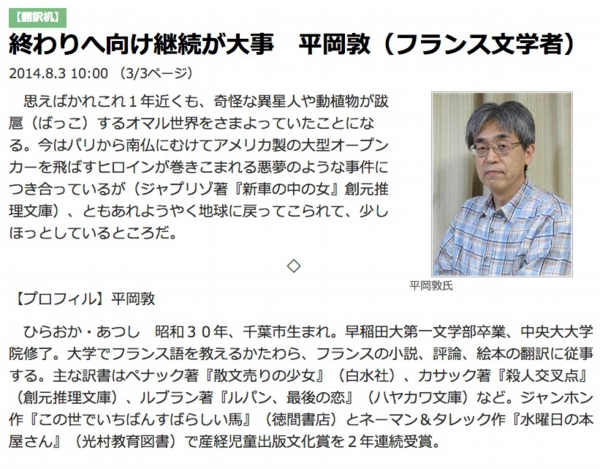
映画「無常素描」上映・討論会
映画「無常素描」上映・討論会

2012年5月30日、首都大学東京(南大沢)にて、映画「無常素描」上映・討論会が開催された。討論会では、映画作品を通じて震災を伝える映画祭「Image.Fukushima」を主宰している三浦哲哉(映画研究者)、乾彰夫(教育学)、山下祐介(社会学)、西山雄二(フランス文学)が登壇した。首都大学東京の教職員、学生、他大学の学生、一般市民の計100名が参加した(主催=人文社会系FD委員会 協賛=学長裁量傾斜研究費・研究環「カタストロフィと人文学」、NPO日本記録映像振興会)。

映画「無常素描」(監督・大宮浩一)は、東日本大震災の状景をいち早くカメラに捉えて話題となっているドキュメンタリー映画。2011年のゴールデンウィークに尼崎の町医者に同行して、岩手から福島までを南下した現地の記録である。報道番組に見られるような編集はストイックなまでに抑制され、本作では音楽やナレーション、地名や人名を指示するキャプションまでも使用されていない。被災地の音や映像を直に体験することはいかにして可能か、という問いに向き合った映画と言っていい。

(山下、三浦、乾氏)
三浦哲哉氏は、「なぜ震災映画を観なければならないのか」という本質的な問いから話を切り出した。TVのみならずネット上でも震災のイメージは膨大に放映されており、ある種の飽和状態のなかでなぜなおも映画を観なければならないのか。単純な「情報」に回収されない「現地の時間のゆらぎ」と向き合うためであるだろう。映画館がどこか幻影的な空間である以上、映画を観賞する経験を通じて、現地の時間のゆらぎを保ち、観者に開いておくことが大切なのだ。
映画「素描無常」はTV関係者に言わせれば、編集以前の「素材」にすぎない。過度に加工されていない映像が物語性を欠いたまま断片的に呈示されるだけだ。この手法について、三浦氏によれば、「映画が破局を撮る」という映画の安定した主体性こそが審問されなければならない。ユダヤ人大虐殺や広島・長崎の表象においてすでに問題となったように、映画の表象機能が揺らぐ地点を示すことこそが、「映画=破局」のイメージの倫理なのではないか。

山下祐介氏は早い時期から現場に足を運んだ経験をもとに観察力溢れる議論を展開した。映画は「無常」と題されているが、この表現は一義的に被災各地に一様に当てはまるわけではない。岩手県沿岸部ではかつてから津波が起こっていたため、自然の無常さに曝される人間の営みがある。ただし、宮城県では、沿岸部に住宅地が造成されていたため、さほど巨大な津波ではなくとも被害は多大だった。これはむしろ都市災害に近い事例であり、「無常」というある種の宿命性で形容できるだろうか。そして、福島の原発事故は無常を通り越して、「異常」な事態を引き起こしている。
本作は加工されていない映像を提出しているとはいえ、やはり編集はなされている。例えば、津波は水が侵食した線まで被災地域をきれいに分断する。まったく津波の被害のない地区が存在するけれども、本作では登場しないことからも被災地のみによって構成された映像作品であるだろう。
その上で、山下氏は「東京でこうした震災映画を観ること」の意義を自問した。東京は大地震が起きると言われてきたが、実際は神戸と東北で大地震が起こった。東京で私たちはまだ「災間」を生きている。震災映画を観ることは過去の災害を体感するだけでなく、起こるであろう災害に対するいかなる効果を発揮するのだろうか。震災が起こることを知っているが信じないという想定外の思考に抗して、映像作品はいかなる未来への配慮をもたらすのだろうか。

乾彰夫氏は、たしかに本作は難解で、二回観なければわからなかった。物語性がないために、観者が主体的に解釈していかなければならないと感想を述べた。体育館に掲示された所有者不明の家族写真、破壊された防波堤の残骸などの映像を見ていると、記憶を体現している事物の存在感に驚かされる。都会とも違う集落の集合的な記憶に導かれるようにして、すでに無くなったもの――固有名をともなう人間のドラマ――が浮かび上がってくる。ただ、本作では玄侑宗久だけの語りが出てくるが、彼の講話的語りはやはり不自然ではないか、と疑義を呈した。
西山は、まず本作における写真の特徴的な使用を指摘。本作では、津波で流され、地面に散乱した家族写真が映し出される。終盤では、おびただしい数の家族写真が体育館に掲示され、持主を待ち受けている様子が五分間の長回しシーンとして挿入される。写真は「かつて在ったもの」を表象するが、本作の写真は所有者に送り届けられようとする途上にある。写真が被写体の不在感と所有者の不在のあいだで宙づりになるなかで、過去と現在の接点さえもが浮遊しているように見える。こうした二重の不在は、人々と街の〈かつての姿〉と〈被災後の姿〉の繋ぎ目とも重なり合い、その独特の浮遊感が本作の「無常」性を際立たせている。

報道番組と本映画が異なるのは、ストイックなまでのイメージ群を支える沈黙(ゼロ記号)が作用している点だ。瓦礫の風景のなかで「チョーキレイだからまた海の近くに住みたい」と言う少女は、最後にも登場し、物言いたげな眼差しで観者を射抜く。ある種不気味な存在である彼女のイメージは、観者が被災地を物語化する欲望を途絶させ、逆に、観者そのものの立場を問う。また、本作は、撮影後に東京に帰る際にゴールデンウィーク末の高速道路の渋滞に巻き込まれた様子、といういささか意地悪なイメージで終わる。渋滞の向こうにはいつもの日常が待っていて、撮影者、そして観者は日常のなかで被災地の無常を観察し、観賞する。私たちは「被災地の無常を観賞する日常になかにいること」の内省を迫られるのである。
会場からは次のような質問が出た。「構築された生のイメージによる作品とは危険な言い方かもしれない。むしろ伝わらないことを表現する点に芸術の可能性があるのではないか」「震災映画の感想はひとりひとり異なり、観者自身がつくりあげる点が興味深い」「無常と日常が対比されていたが、むしろ大震災のような無常な出来事は日常的に起こりうることではないか」「本作では登場人物の言葉が聞き取りにくいため、観者は前のめりになって映画に耳を傾けてしまう。これは肯定的な効果ではないか」
なぜ震災映画を観なければならないのか?――それは、映画館で孤独に鑑賞する経験を起点として、映画が提起する問いを共有し議論する公共空間が誘発されるからだろう。その重要性を確認することのできた会だった。


