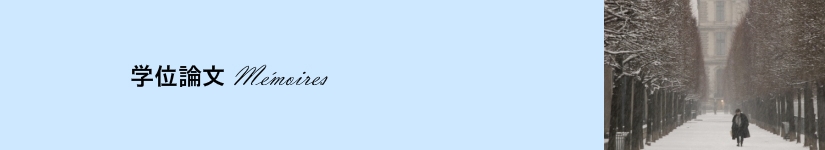2010年度 修論・卒論
小玉司「ルイ=フェルディナン・セリーヌ、コペンハーゲン亡命以前の作品における衣服を表す言葉について」
小玉司「ルイ=フェルディナン・セリーヌ、コペンハーゲン亡命以前の作品における衣服を表す言葉について」

一つのまとまった分量のものを書いてみるという作業は、苦しくもあり勉強にもなりました。課題や反省点は無限にあります。論文を1日1ページの目標で、実際に書き始めたのは、2010年の3月です。それ以前に必要とする資料は、ある程度は読んでいました。それにしても、始めたのが遅すぎたと思います。パリ8大学への論文提出は、2010年の11月でした。帰国が遅れ、首都大学東京への修士論文の提出や質の改善等全てが、押せ押せになってしまいました。指導教官の大久保先生やその他の先生方にも本当にご迷惑をお掛けしてしまいました。
渡仏したらフランス語が自然に上達するというのは、多分ある部分では本当なのですが、「読み」「書き」の部分においては日本国内で十分に訓練を積むことのできる分野だと思いました。私はコツコツ勉強するという作業が非常に苦手なために、フランス語自体を正確に「読み」、「書き」、「話す」ということが最後までできませんでした。
首都大学東京へ提出した修士論文は、パリ8大学へ提出した論文を自分なりに翻案、翻訳したものです。グローバリゼーションに伴う学位の世界的な互換性や、レベルの違いなど色々な点で外的環境の問題点も幾つか発見しました。今後の課題はやはり、どうにかこうにかフランス語を武器として、また思考の道具として使いこなすレベルにまで達し、仏文学の博士号を取ることです。(小玉司)
目次
序文
第一章 主人公の服装
第一節 主人公の服装、『夜の果てへの旅』におけるフェルディナンの場合
アメリカ、フォード社において/フランス、劇場において――パシャの扮装/トゥールーズ、ブルジョワの船に招待された場面/『夜の果てへの旅』における帽子と大きな頭/その他の衣服の描写
第二節 主人公の服装、『なしくずしの死』におけるフェルディナンの場合
Vera Mauriceの先行研究について/『なしくずしの死』における帽子と大きな頭/いつも小さすぎるか大きすぎるかする靴/ズボン、上着及びワイシャツ等/死に直面して――経帷子色
第三節 パンフレにおける話者の服装
小説における「je」とパンフレにおける「je」/ズボン/靴
第四節 主人公の服装、『ギニョルズ・バンドⅠ』におけるフェルディナンの場合
衣装描写の変化/外套と入隊/帽子と運、不運/ロンドンと靴
第五節 主人公の服装-結論
第二章 民族衣装
第一節 『夜の果てへの旅』における民族衣装
着物とエロチシズム/フランス三色旗と女性の肉体
第二節 『なしくずしの死』における民族衣装
中国風衣装/洋服と釈迦牟尼ネクタイピン
第三節 パンフレにおける民族衣装
ファン・バガデンからヴァン・クラーベンへ/黒色ターバンから『千夜一夜物語』のシャイロックへ
第四節 『ギニョルズ・バンドⅠ』における民族衣装
ヴァン・クラーベンの東洋風衣装/ソステーヌの中国風衣装と着物への仕打ち
第五節 民族衣装-結論
結論
参考文献
要旨
本論文においては、ルイ=フェルディナン・セリーヌのコペンハーゲンへの亡命以前の作品における、衣服を表す言葉について考察した。「なぜ『ギニョルズ・バンドⅠ』におけるヴァン・クラーベンはパシャの衣装を身に付けているのに、イデイッシュ語を話すのだろうか?どのような理由から、『なしくずしの死』において、本国では洋服を身に付ける中国人高級官僚は、釈迦牟尼のネクタイピンをこれ見よがしに身に付けようとするのだろうか?」といった疑問が本論の原点である。衣服を指し示す用語及びそれらの描写を通して、一見したところでは分かり難いセリーヌの表現をより詳細に理解することをその目的とするものである。
セリーヌの作品における、文学作品、パンフレ及び作家の個人的経験という三つの要素を関連付ける幾つかの研究は、ヨーロッパを未だに震撼させるユダヤ人大虐殺の歴史の影響を大きく受けていると言えるだろう。ともあれ如何なる理由があると言えども、作家の一連の作品の生成過程を理解するにおいて、作品群の一部をなおざりにするべきではないように思われる。かくして、ある作品に先立ってもしくは同時期に執筆された作品を関連付けることにより、我々は作者の思考過程を辿ることにした。本論における手法は、セリーヌの全作品を通してあるテーマ、例えば衣装を指し示す表現といったような特定のテーマに注目することによって、作家の執筆の工程、首尾一貫した主張、一言で言えば作家の長所及び短所といったものを明るみに出すことができるという展望に基づいて採用された。作家が選択した色彩効果もしくは象徴体系は言ってみれば、点描画法に例えることができるだろう。セリーヌの描くカンバスは、点描画の絵画を眺めるように、多少離れた位置からその描写を眺めるべきなのだ。こういった観点はセリーヌの作品における視覚的観念の利用といったような視点を明るみに出し、それらをより良く理解することを可能にした。
まず手始めとして、この論文においては作家がモンマルトルを離れ、デンマークへ亡命する以前に執筆された作品までを取り扱うこととした。より正確には1926年から1943年に書かれたテクスト、つまりは1926年末から1927年初頭に執筆された作家の最初の戯曲『教会』から、1940年末から1943年末(あるいは1944年始めと推定されている)に執筆された小説『ギニョルズ・バンドⅠ』までを対象テクストとした。亡命生活は作家にまた新たな主題を提供したと判断されるために、亡命生活の期間及びその後に執筆された作品は、本論文においては研究対象から除外した。
本論における主たる問題提起は、ルイ=フェルディナン・セリーヌの作品における、衣服を表象する言葉にどのような機能が割り当てられているかということであった。我々は、まず上で述べた期間に執筆された作品を通して、同じような表現、例えばいつも主人公のサイズに合わない背広、ズボン、靴、帽子と主人公の大きな頭、スータン、パシャの衣装、中国風衣装、それから着物等、が繰り返されていることに気付いた。よって、このような繰り返し現れる衣装描写にどのような機能が割り当てられているのかを大きく二章に分け、一章目においては主人公の衣装(背広、ズボン、靴、帽子等)、二章目においては民族衣装(パシャの衣装、中国風衣装、着物等)について論じた。
文書の変遷を何よりもまず、パンフレ執筆以前と以降の変化について、観察するために、対象テクストを年代順に辿り考察した。この様な手法は、セリーヌ作品における衣装描写の目録を作るといったような目的で採用した訳ではなく、このテーマ研究から、ある意味が他の意味合いと相俟って織り成される一つの大きな意味の体系を読み込むためのものであった。また、セリーヌのパンフレについての批評に関して、できる限り中立な立場に留まることを心がけた。
本論における研究においては、詳細な記述、衣装のディテール、短い抜粋の分析からまず取り掛かった。こういった手法は、一つの断片からもう一つの断片へ、一つの分析からもう一つの分析へ徐々に全般的な解釈へと論旨を展開することを可能とした。当該の手法は、色彩と形状の筆触が少しずつカンバスに画家の作品を形作り、鑑賞する者の目に意味を織り成す新印象派の絵画に分けても類似すると言える。本論で採用したような描写的詳細に留まる分析は、描写の意味合い、利用法、ある種の衣装描写の反復、視覚的描写の曖昧性を判読し、我々が形式と内容を取り違えることを回避させた。我々はセリーヌの表現における審美的側面よりも社会文化的側面に注目した分析を志し、セリーヌの方策に取り込まれない読解を心がけた。また、我々はセリーヌの作品を、第一章において、主人公及び話者の衣服描写を取り扱う際に、特に心理学的側面から分析することも試みた。
本論文における手法が、歴史的な文脈の中において、また作品中で描かれる共同体の慣習及び風習を通して、同時代の宗教などへの作者の視線といった 、衣服描写の背後に隠された意味への理解を促した。また、作品生成過程における時系列的取り組みが、作品中におけるフランス人、外国人、ユダヤ人などの精神性を作家が、特有の表現方法を用いて描こうと意図したその方法を浮き彫りにしつつ、セリーヌ作品を再読することを可能にしたのだ。
坂巻美穂「モリエール喜劇における最後の従僕――ペテン師スカパンと優越感による笑い」
坂巻美穂「モリエール喜劇における最後の従僕――ペテン師スカパンと優越感による笑い」

私が卒業論文を本格的に考え始めたのは夏を過ぎてからでした。7月の中間発表では、まだどの作品で書くか悩んでいる段階でした。夏休みに『スカパンの悪だくみ』で書くことを決め、後期に入ってから頭の中にあるものをなんとかまとめ、先生に見ていただいてようやく書き始めました。初めは何処に向かっていくのか自分でもわからない状態でしたが、石川先生や他の先生方にも様々なアドバイスをいただいて、ようやく道筋が見えてきました。スタートが遅かったのもあり、11月の中間発表が終わってから本格的に書き始め、提出日当日まで書いていました。書いている間は上手くいかず辛いこともありましたが、非常に達成感を得ることができました。120%書きたいことが書けたのではないかと石川先生がおっしゃいましたが、本当にそうだと思います。
今回は先生方からもご指摘されたように、原文をあまり参照できませんでした。時間が足りなかったことや私の実力不足が原因だと思います。今後はさらにフランス語の勉強に励んでいきたいと思います。また、始める時期が遅かったことも反省点の一つです。修士論文では、もう少し早めに動きだすことも意識していきたいです。今後はさまざまな本を読み、文章能力の向上や知識の増加を図っていきたいと思います。卒業論文では、自分の好きな作品で自分勝手に楽しく書かせてもらえました。とても良い経験だったと思います。(坂巻美穂)
目次
序論
1章 『スカパンの悪だくみ』と笑劇
1-1.笑劇との関連性 1-2.登場人物
2章 『スカパンの悪だくみ』の笑い
2-1.喜劇における「笑い」とは何か 2-2.『スカパンの悪だくみ』における手法
2-3.ペテン師と二人の父親
3章 「スカパンの悪だくみ」とは何か
3-1.なぜ『スカパンの悪だくみ』なのか 3-2.道理を説く人物
結論
要約
モリエールの喜劇の多くは滑稽な人物が主役となり、笑いを生みだしている。1671年に初演された『スカパンの悪だくみ』では従僕スカパンが物語を動かしていくが、この喜劇で滑稽な人物はスカパンではなく、ケチな父親たちだとされている。『スカパンの悪だくみ』はモリエールの喜劇の中では笑劇に分類され、笑劇の類型化された筋や登場人物を用いて作られている。しかし、モリエールはそこに独創的なものを盛り込むことで彼独自の喜劇を作り上げ、特に二人の従僕、スカパンとシルヴェストルは今までのモリエールの作品の中でも類を見ないものになっている。
では、それらの人物を使い、『スカパンの悪だくみ』はどのように観客を笑わせているのだろうか。この喜劇には、「繰り返し」「取り違え」「転換」「逆転」「操り人形」などの喜劇の手法が見られるが、この根底にあるのは「優越感」だと思われる。観客はペテン師スカパンと共犯関係をつくり、彼が翻弄する人物を自分が翻弄しているつもりになって「優越感」を得て笑う。ここでは主人と従僕の立場は「逆転」し、ペテン師スカパンは舞台を支配していく。ただし、ケチで滑稽だと思われていた父親は実はそれほどの吝嗇家ではなく、スカパンによって滑稽な役割を与えられていると言える。つまり、スカパンがペテン師であって、他の登場人物を動かしていくという設定が『スカパンの悪だくみ』では重要になっているのだろう。しかし、棒叩きの後、スカパンは途端に舞台に上がらなくなり、代わりに父親たちが舞台を支配するようになる。ここで、父親たちに代わり、今度は彼が滑稽な人物となる。彼の悪だくみは暴露され、意味のないものであったことが明らかになる。
タイトル『スカパンの悪だくみ』Les Fourberie de Scapinには、スカパンの悪だくみが彼の悪徳であり、彼が滑稽となる要素を持っていることが表れている。また、従僕シルヴェストルはモリエール喜劇に出てくる道理を説く人物の一人であり、彼に止められた棒叩きをやってしまったスカパンはやり過ぎてしまった従僕だと言える。
このように、自分の社会的地位や役割から外れた行動をとる人物はモリエールの喜劇では滑稽だとされる。観客は優位な立場から落ちるスカパンを見て優越感を覚え、ここで観客とスカパンとの間に立場の「逆転」が起こることになる。『スカパンの悪だくみ』はこのように「逆転」と「優越感」を使い、モリエールがまた新たなものを生み出そうとした結果出来たものだと言える。この作品から、健康状態が悪化していた中でも新しいものを生み出そうとする彼の喜劇作家としてのあり方がうかがえるだろう。
下東香月「フランソワ・モーリヤック『愛の砂漠』における”砂漠”とは?」
下東香月「フランソワ・モーリヤック『愛の砂漠』における”砂漠”とは?」

今まで卒業論文ほどの分量(原稿用紙50枚分程度)の文章を書いた経験がなく、本論文を書くことを通して、文章を書くことの大変さを痛感した。これが、まず私が感じたことである。書くことに慣れていくことが、これからの課題であると思う。
そして何より、今回私が書いた論文の反省点は、“結論を出そうとしたこと”である。論文を終わらせようという気持ちの焦りから、特に第3章(『愛の砂漠』の主要人物3人の関係を論じた)では、のびやかに論じることができなかった。第3章は、論文の核心部分であったのでとても心残りである。そしてこの“結論を出そうとしたこと”により、カトリック作家であるフランソワ・モーリアックが書いた『愛の砂漠』の特徴、複雑さを汲み取ることができずに終わってしまった。作品そのものの良さを、消してしまった。この問題点を解消するためには、作品とよく向き合うこと、逃げ出さないことが大事だと思う。そのためにも、テキストを読み込み、1つ1つの表現について深く考える作業を怠らないようにしたい。
振り返ってみると反省点ばかりを挙げてしまうが、学んだことも多い。文章を書く行為の困難さを身を持って経験できたことの収穫は大きいと感じる。論文を読み返してみると、自分の文章を書くときの癖や頻出してしまう表現などが良く分かった。また、誤字・脱字なども目に付いた。多くの作品に触れ、様々なものを吸収していくことで豊かな表現力を身に着け、これらの問題点を克服していきたいと思う。(下東香月)
目次
序章
第1章
第2章 マリア・クロスについて
第3章『愛の砂漠』における三角関係
結論
参考文献
要旨
本作品は、男女の三角関係の形で物語が展開する。しかし、マリア・クロスを中心とする男女関係というよりは、レエモン、ポールの親子関係を中心に描かれているように感じ、特殊性を感じる。そこで、そのような登場人物たちの関係を考察し、そこから導き出される『愛の砂漠』の意味を考えていく。
本作品を読んで最初に感じるのは、主要人物たち(レエモン・クレージュ、ポール・クレージュ、マリア・クロス)がそれぞれの孤独を抱えていること、つまり世間や家族とは距離を置いた人物として描かれていることである。そこで、彼らの様々な場面での言動を詳しく考察すると、彼らの“孤独”の要因が、それぞれの弱さであり、またその弱さを覆い隠すために創り上げた自分たちの姿から周囲の者が抱くイメージにあることがわかってくる。それらのイメージに抗うことができず、常に真の姿が自分たちの内奥に閉じ込められている。そして、3人の間でもお互いが相手に対するイメージを抱き、意思の疎通が困難な状況となっている。
また、3人の登場人物の中でマリア・クロスはクレージュ親子を惹きつける不思議な魅力をもつ人物である。レエモンは彼女を“罪深い女”として捉え、一方ポールは“聖女”として捉え、各々にその魅力を賛美する。この全く逆ともいえるマリア・クロス像を、彼らの視点から考察すると、レエモンは、“額”の描写が示すように、一方では知的な女性としてマリアを眺めていながら、同時に“罪深い女”のイメージで彼女を捉えており、それが彼の征服欲をかきたてている。しかし、そのイメージはマリアの言動により揺らいでいく。ポールから見たマリアは、彼にとって従順な弟子のような存在である。そして、彼女の偽善的態度を認めつつも、ポールは寛容な態度で受け入れる。ポールとマリアの関係は、イエスとマグダラのマリアの関係と相似的である。キリスト教強化のために“聖女”と“罪深い女”の像を投影されてきたマグダラのマリアは、彼女とは切り離せない存在である。マグダラのマリアの姿が、『愛の砂漠』のヒロイン、マリア・クロスに投影されているのである。
この魅力的なヒロイン、マリア・クロスを同時にクレージュ親子が愛する。この三角関係の中で、彼らは「宇宙」の中の惑星のように互いを引き寄せ、引き離すような関係である。そして、マリアにクレージュ親子が引きつけられたのは、彼女へのこの「情熱」、激しい恋心のためである。しかし、この「情熱」を傾けても越えることのできない、愛し方の行き違いによる愛の「砂漠」が生じてしまう。クレージュ親子は、マリアとの間に愛の「砂漠」が横たわり、それでも内奥に存在する「情熱」に苦しめられ続けなければならないという同じ運命を背負うことになる。
そして、マリアを愛していても自分のものにできない共通の苦しみからクレージュ親子は、彼らが同じ「情熱」を持っていた事を認め、お互いの存在を認める。『愛の砂漠』により、彼らは同じ苦しみの中でお互いの同じ部分に気づくのである。
久津間靖英「ジャン・コクトー『恐るべき子供たち』における夢想による空間の想起と死の関係性について」
久津間靖英「ジャン・コクトー『恐るべき子供たち』における夢想による空間の想起と死の関係性について」
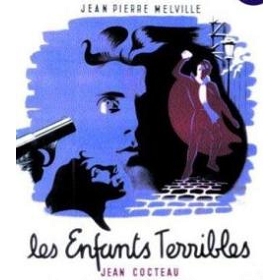
今までは授業のレポートぐらいでしかまとまった文書を書いたことがなかった自分にとって、その何倍以上もの文字数の論文を書くことは新しい体験でした。いろいろと感じたことはありますが、中でも一番味わったのは言いたいことが文書に出来ないという体験でした。自分の考えがまだまとまっていないから書けないのか、それとも自分の文章力が不十分なのか、論文を書く過程で今まで考えたこともなかったような課題が浮かび上がってきました。うまくいかない点もいろいろとありましたが、論文を書く中で自分の考えに新しい形が与えられたように感じるときは、いままで経験したことのない面白さでもありました。
卒業論文を書くにあたっての二度にわたる中間発表会は、先生方のご指摘を受けるたびに漠然としていた自分の考えに指針が与えられたように感じる、とても刺激的なものでしたが、今回の論文審査会はそれ以上に楽しいものでした(もちろん、もっとも緊張した場でもありましたが)。審査会でのご指摘の後でもう一度自分の論文を読んでみると、それまではあまり気にかけていなかった論の穴や矛盾、意味がうまく通じていない文などが気になって仕方なくなってきました。自分の文章力の欠如を改めて痛感しました。
一番気になったのは、各章がうまくつながっていない点です。主に第二章で論じた作中の空間が持つイメージは、自分にとっての本論文を書くきっかけでもあり、書き始めた時期も一番早かったのですが、それだけに、今になってみると最後に書き上げた第三章とのつながりがあまりないようにも感じます。第三章で論じた「死」というテーマに注目して『恐るべき子供たち』を再度読みなおしてみると、第二章を書いていたときにはあまり重要視していなかった箇所が目に付くようになりました。とりわけ登場人物の1人であるダルジュロスは、第三章を書いている段階でも、非常に重要な存在のように感じていましたが、時間の関係もあり本論文ではあまり触れることが出来ませんでした。この点は自分でも気になっていただけに、審査会でのご指摘もあって、もったいないことをしたなと感じています。論文では「通過」を論じる箇所のみで触れた、子供たちの部屋とダルジュロスの関係性は、いまの自分にとって、『恐るべき子供たち』読解の一番の課題です。それぞれの登場人物たちとダルジュロスの関係性、そして子供たちの部屋の中でダルジュロスが果たしている役割について、本文に触れながら、改めて考察していきたいと思います。
今後は、コクトー作品と死生観をテーマに自分の研究を進めていく予定です。まずは審査会で見つかった課題にとりくむことで、研究をより深いものとしていきたいです。(久津間靖英・仏文学)
目次
序文
第一章 空間の想起
1.子供たちと部屋の関わり
2.子供たちによる想起とその要素
1)雪 2)光
3. 空間の移動性
第二章 聖域と舞台
1. 聖域
1)保護と隔離 2)ラシーヌの宗教劇『アタリー』 3)低俗なもの 4)通過
2. 舞台
1)出かけること 2)演じること 3)舞台と演技
第三章 死の回帰
1. ポールの臨終
2. 子供たちと死
3. 上空と地上
4. 運命的結末としての死
5. 死の回帰
要旨
本卒業論文では、ジャン・コクトー『恐るべき子供たち』を取り上げる。この作品についてコクトーは『阿片』の中で、最後の場面の着想がこの物語を書くきっかけとなったことを述べている。ここでは彼のこの言葉に注目し、物語終盤のポールとエリザベートの死の場面と作品全体のかかわりについて考察する。この場面では、ポールは死の間際に物語冒頭の場面を想起している。それゆえ、この場面を読み解くためには、作品全体において、空間の想起と死がどのように扱われているかを理解しなくてはならない。
第一章「空間の想起」では、おもにポールがギャラリーにかつての空間を見た場面に注目し、空間の想起は主人公たちの考察や回想によって生じたのではなく、彼らを取り巻く外部に存在するさまざまな要素が子供たちの直感に働きかけることによって生じていることを明らかにしている。第二節では、外部的要素のうち、雪と光に注目することで、それらの影響力によって、空間の時間的、位置的限定性が弱められていることを論じている。
第二章「聖域と舞台」では、子供たちの行う「遊戯」と彼らの住みかである部屋の関係について、聖域と舞台という部屋が持つ二つの姿を通して考察していく。第一節「聖域」では、子供たちの部屋を、ラシーヌの『アタリー』における神殿を参照しながら聖域として読み解き、部屋の持つ〈保護・隔離〉の性質を明らかにする。第二節「舞台」では、子供たちは、部屋による保護と隔離の中で、「遊戯」によって現実の世界から抜け出し、自分たちの作り上げた夢想の世界を作り出していること、そしてその時、部屋もまた現実から漂い始めることを明らかにしている。
第三章「死の回帰」では、死の力について考察する。第二節では、死は現実の世界に生きるものを抽象化し、夢想の世界へと引き入れる力を持つこと、そして母親やミカエルなどの登場人物らの死を通じて子供たちはそのことを無自覚に理解していたことを明らかにする。第四節と第五節ではポールとエリザベートの臨終を描いた「おわりの数頁」について論じ、彼らは逃れることのできない部屋の崩壊に対して、死の持つ力を自覚しそれを行使することで立ち向かっているということを明らかにし、それまで部屋による保護と隔離によって可能ならしめていた夢想の世界の創造を、彼らはその時、真の意味で自由に行うに至ったということを示し結論とする。