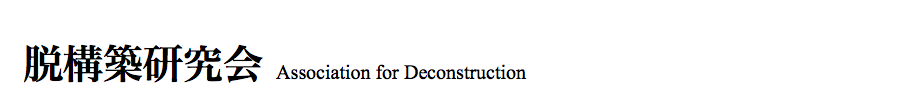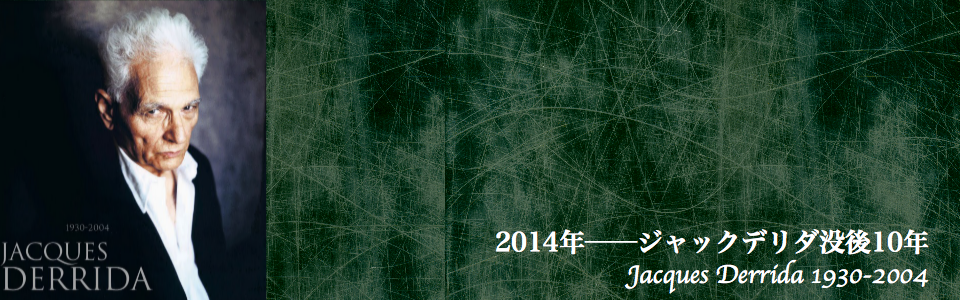Reports
脱構築研究会ワークショップ「ラディカル無神論以後の現代思想──デリダ、レヴィナス、メイヤスー」(2017年12月23日 東京大学駒場キャンパス)

宮﨑裕助
2017年12月23日の脱構築研究会では「ラディカル無神論以後の現代思想」と題し、6月に訳書が出たマーティン・ヘグルンド『ラディカル無神論──デリダと生の時間』(吉松覚・島田貴史・松田智裕訳、法政大学出版局)の合評会を目的としたワークショップを開催した。これはしかしたんなる書評会にとどまるものではない。訳者三人に加え、さらに三人のコメンテーターの諸氏(小川歩人、渡名喜庸哲、岡嶋隆佑)を登壇者として迎えることにより、本書のうちに、デリダ死後のデリダの思考を介し、しかしデリダ研究の枠組みを超えた射程において、現代思想のフロンティアを模索することを試みるものである。
それなりに専門的な内容をもったワークショップにもかかわらず、当日は予想をはるかに上回る50人以上の参加者があり、その関心の高さがうかがわれた。そしてそれと呼応するように、行われた発表および討議の内容は非常に充実したものとなった。
そもそも本書は、デリダ研究として傑出した評価を得てきた。2008年に出た本書は、2004年のデリダ死後に出たデリダ研究のなかで、晩年の著作まで十分に考慮に入れることにより、これまでの研究が必ずしも十分に明らかにしてこなかったデリダの思考の論理を、きわめて明晰に一貫したしかたで解明したデリダ論である。刊行後、英語圏ではまもなく雑誌特集が組まれたり、さまざな論争を引き起こしたりするなど、異例の反響をもって遇されてきた。(その概略はヘグルンド自身のホームページからうかがい知ることができる。)
とりわけ90年代以降の後期デリダは、これまで倫理・政治的転回、あるいは、フランス現象学全般にみられるように神学的転回といった観点から整理されることが多かった。ヘグルンドはそうした転回がデリダのうちにあったという類いの議論をはっきりと斥け、デリダの思想を「生き延び(survival)」の論理、すなわち、生に内在する死によって生そのものが可能になっているという「生き延び」の論理によって一貫して読み解いてゆく。この論理は、時間の有限性のうちにあるわれわれの生をラディカルに肯定する思考であり、実のところこれは、デリダが初期から唱えている痕跡の構造によって説明されるものである。
これは極めて強力な観点であり、この読解格子により、しばしば曖昧に見えていたデリダの思想の根幹というべき構造が鮮やかに浮かび上がってくる。と同時に、本書は、これまでの多くのデリダ研究やデリダ論が犯していた誤解をえぐり出している。デリダの思考を、他者の無条件な肯定としての倫理や、神の絶対的な無限といった線から、たとえばレヴィナスの他者論や否定神学に重ね合わせて読むようなデリダ研究は厳しく批判されることになる。本書の筆致はきわめて挑発的であり、かつその論理展開は明晰かつ徹底的である。本書は言うなれば、デリダの死後、真剣にデリダを読み思考しようとする人であれば、最低限クリアしなければならない後戻り不可能な一線を画すものになっているのである。

ワークショップではまず訳者の三人より、自分の担当した箇所の翻訳経験に基づきつつ、その内容紹介とヘグルンドの議論に対する問題提起が行われた。
まず吉松氏の発表「思弁的実在論の試練にかけられる脱構築?──ヘグルンドのメイヤスー読解から」は、本書の補遺として付されたヘグルンドによるメイヤスー批判の章を中心にとりあげ、ヘグルンドとメイヤスーとの対決に、現代思想の前線を形成する本書の賭け金を見出そうとするものであった。あわせてヘグルンドの議論自体への疑義(生命概念、絶対的なもの、時間概念)も呈され、本書が残している課題や論点(写真や映像メディアの問い、デリダの生命論、ニーチェ・フロイト・ハイデガーの不在)が指摘された。
つぎに島田氏の発表では、ヘグルンドの時間概念を介してラディカル無神論の要約と紹介が行われたのち、その時間概念とデリダ自身の時間概念との差異が二点にわたって問われた。すなわち、ヘグルンドにおける前未来ないし未来完了時制の不在、および、仮言的言辞(s’il y en a)の扱いの不十分さという論点において、デリダは、ヘグルンドの立論に回収しえない別の論理を提出していることが明らかにされた。ヘグルンドによる時間概念の単純化、とりわけ「継起」の概念が孕む問題性は、本ワークショップ全体において一貫して問題となる論点であった。
訳者発表の最後は、松田氏によるものであった。松田氏は、ヘグルンドの生の時間の要点を紹介したのち、デリダとフッサールの対決を論じた章を中心に、やはりヘグルンドの時間概念の問題が提出された。過去・現在・未来の差異化として時間を論じる一方で、生が時間によって絶えず変質し他化するというときの時間は同じものだろうか。差異化として考えられた時間から、時間の力に曝された生の問題を語るには飛躍があるのではないか、といった根本的な問題点が提起された。

次に、コメンテーターから、より視野を広げた観点からの本書への応答があった。
まず小川氏の発表「「ラディカル」であるかのように「相続」すること──『ラディカル無神論』への注釈」では、本書の英米圏における位置づけのなかでの重要性を評価したのち、その眼目がデリダからウルトラ超越論的条件としての時間・空間論を引き出すことであることが時間、理念、相続の各テーマに即して主張された。それに対して、ヘグルンドの議論の問題点、すなわち、時間の空間化における「継起の必然性」、二義的な意味をもつ undesirable(望ましいもの/欲望しえないもの)の同一視、超越論的シニフィアン批判の不在という問題点が提示された。とりわけ最後の論点はヘグルンドの否定神学批判に関連しており、かつて東浩紀『存在論的、郵便的』が批判していた意味での否定神学が、まさにヘグルンドの否定神学批判自体に適用しうることになり、この問題の深刻さがうかがわれる。
次のコメンテーター渡名喜氏の発表「「ラディカル無神論」は無神論たりえるのか──ヘグルンドのレヴィナス解釈批判を通じて」は、ヘグルンドのレヴィナス批判における誤解を指摘したのち、実は反対に、ヘグルンドの主張の方向がレヴィナスのテクストそのものにある種の「レヴィナス的ラディカル無神論」として見出されうるのではないかというものだった。映画『メッセージ』における未知なる他者との出会いの場面に言及しつつ、渡名喜氏は、レヴィナスが想定している「顔」の平和そのものが暴力を孕むことを指摘していた点はとりわけ興味深いものだった。ただし、レヴィナスの無神論の用法はここでのヘグルンドの無神論とは正反対の意味であり、やはりレヴィナスは「無神論」というタイトルは採用しないであろうとも氏は付け加えた。
最後の発表は、岡嶋氏による「ヘグルンドによるメイヤスー批判について」であった。メイヤスーの哲学に通じている岡嶋氏からは、博士論文『神の不在』から『有限性のあとで』と現在に至るメイヤスーの思考の軌跡について紹介があり、それを踏まえたうえで、ヘグルンドのメイヤスー批判が検討された。そこから明確になるのは、結局のところ、ヘグルンドとメイヤスーの議論のすれ違いである。偶然性と継起の必然性との関連、生命の発生、死者の復活、不死への希望、いずれの論点においても、ヘグルンドがメイヤスーの概念を誤解しているか、そもそも異なる前提のもとに論じているため、実のところ対話になっていないという事態であった。

その後全体討議が一時間半程度行われ、さらに以上の論点が掘り下げられた。ここでは逐一紹介できないが、報告者にとって議論を経てもっとも問題と感じられたのは「ラディカル無神論」という用語の危うさだ。そもそもデリダは無神論を標榜したと言えるのだろうか。たしかにこの言葉は「神の記憶をもち、神のことを覚えていようとするラディカルな無神論」というデリダの言葉に由来しており(« Penser ce qui vient »)、それによれば、宗教批判のみならず、既存の宗教批判以上の徹底した批判をも可能にするとされている。
しかしデリダは、むしろそうであるがゆえに神を前提とした伝統や記憶の継承を命じているのに対して、ヘグルンドのラディカル無神論は分割不可能とされてきた神をも分割可能な有限性とみなすことにおいて神の観念をあらかじめ低く見積もり、そうした伝統との実質的な対話を不可能にしてしまっているように思われる。
他方、「ラディカル無神論」という言葉でもって、脱構築に「信ずること」の宛先がないかのように端的に言い切ることできるのだろうか。ヘグルンドにとって「生き延び」がその最後の言葉ということになるのだとしても、これはそれ自身のラディカル無神論としての主張により、無神論そのものをあたかも神のように信じるということになり、自己破壊的な帰結に至らざるをえない。そこに何が残っているのか。
ヘグルンドは、脱構築を分析的に記述しうる対象としてしか説明しようとしない。これは、脱構築をどこまでも中立的な形式として扱うことを意味するが、学問の対象としてそうするのは正しいとしても、そのような中立性はどこまで維持しうるものなのだろうか。デリダが繰り返し述べていたように、脱構築は中立的ではありえない。脱構築はとりわけ系譜学的な介入を試みており、歴史的にであれ政治的にであれ、それ独自のスタンスを打ち出すものである。脱構築に規範的な価値が一切ないかのように述べることには限界がある。
実際、ヘグルンドのラディカル無神論は、このデリダ論以降も継続されている実質的な思想的プロジェクトというよりは、一種のスローガンにとどまっている。おそらく問われているのは、ラディカル無神論そのものにとっての剰余、それは結局のところ、ラディカル無神論よりもミニマル有神論、あるいはジャン=リュック・ナンシーがかつて述べていたように「無・無神論」のような神へのアプローチでなければならないはずだ。
他にも、すでに述べたように、今回のワークショップで一貫して問題視された論点としてヘグルンドの時間論がある。これはいっそう詳しく検討される必要があるだろう。とりわけ継起の必然性と瞬間の否定性による時間構成は、痕跡の構造によって説明されるべきものとして提示されているが、未来と過去の非対称性が十分に考慮されていないなど、それ自体がいまだ形而上学的な前提を払拭できていないように思われる。この点が、時間概念そのものの形而上学性を警戒する他のデリダ派(ジェフリー・ベニントンなど)からすれば不徹底にみえる一方、そうした前提を明示しないかぎりで、メイヤスーとのすれ違いの起因にもなっている。これは、どこまでヘグルンドにとって必要な有限性の条件なのだろうか。
以上、当日議論されたことの一部にすぎないが、こうした問題点の多くは、ヘグルンドの『ラディカル無神論』が打ち出している議論のたんなる不手際や欠陥というより、本書があくまで明確な主張をデリダの思想のうちに堅持しようとするその首尾一貫性がかえって引き起こしてしまった問題だとも言える。明快すぎる議論はその洞察そのものによって盲目を抱えざるをえない。とはいえ、ワークショップでの議論がきわめて活発だったのも、デリダのしばしば重層的で複雑化したテクストを一貫して読み抜くきわめて強力な読解モデルを本書が提出していたという事実があってのことである。本書の特筆すべき卓越性は、本書とともにあらためてデリダを読むことで人々を新たな思考と対話へと誘うというその喚起力にあるということに疑いの余地はない。
メイヤスーの本のタイトル通り、「有限性以後」がいわば21世紀の現代哲学の合い言葉だとしたら、本書はメイヤスーとは対照的な理路を示している。ヘグルンドとメイヤスーの両者のあいだの議論のすれ違いないし並行線からわかるのは、ヘグルンドが徹頭徹尾有限性の手前にとどまることによって──メイヤスーからすれば、相関主義にとらわれていると見えようとも──いわば「有限性以後のラディカルな有限性の思考」のひとつの強力な範例を提示しているのだということである。有限性の彼方への一歩を踏み出すか、その手前で踏み出さないでいることに可能性を見出すか──おそらく今後この二人が指し示している思考の力線のあいだ、その狭間に張り渡された磁場のなかでこそ、現代思想は引き続き更新されてゆくにちがいない。