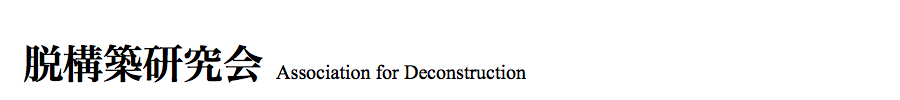Review
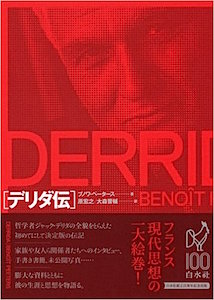
手紙とアーカイヴの思想家の伝記――ブノワ・ペータース『デリダ伝』書評
郷原佳以
本書の原書は二〇一〇年に刊行された。哲学者が逝去してから六年、なるほど伝記が出てもおかしくない頃合いではあった。しかし初の伝記、しかも著者はデリダ研究者としても哲学研究者としても知られる人物ではなく、むしろBD(フランスの漫画)の原作者として知られる人物だという。デリダがいかにしても抵抗できない状況であるだけに、不安は高まった。デリダのテクストを綿密に読み込むことなくその生をただ面白おかしく語ることでデリダ思想を矮小化するような著作なのではないか、と。しかし、『デリダ』という端的な表題を冠したその本の序章を読みながら、それが杞憂であったことを安堵と共に確信した。と同時に、そうした陥穽に陥らずにデリダの伝記を書くということがいかに困難で、ほとんど不可能ともいうべきことであるかに思い至り、それを三年足らずで成し遂げた著者の力量に舌を巻き、ブノワ・ペータースとはいったい何者なのかと呟かずにはいられなかった。
ペータースはその後、原作を提供したBD『闇の国々』が邦訳され、日本ではBD 読者の間で知られるようになった。そこで紹介されたのは、ロラン・バルトの指導のもと『タンタンの冒険』をめぐる博士論文を書きながら小説を書き始め、BD 原作や映像作品も手がけながらエルジェやヴァレリー、デリダの伝記も著している、という多才な人物である。しかし、それだけでは彼がデリダの伝記に取り組む動機も、その仕事の的確さの理由も見えてこない。その意味で彼が何者なのかわかるのは、やはり本書の序章からである。
本書の序章に、ペータースが一九八四年、写真家マリ=フランソワーズ・プリサールと共に作った写真集『視線の権利』の解説をデリダに依頼し、原稿を受け取ったことが書かれている。このテクストには邦訳もあり、デリダ読者としてはここで合点が行く。世界的な名声を高めつつあった哲学者に彼がコンタクトを取ったのは、『グラマトロジーについて』以来つねにその著作に馴染んできたからであり、そしてこのとき以来、彼は「デリダを読むことを止めなかった」。『デリダ伝』の著者が何者であり、なぜそれが成功しているのか、その答えはこの一事に尽きる。つまり、デリダの忠実な読者だということである。ペータースは、デリダの私的資料の調査を始める前に、公刊されたデリダの著作を読み込んでいる。七百頁を超える本文を読んでいるとそのことがよくわかる。デリダ読者の一人として、本書が暴露趣味によるものではなく――とはいえもちろんしっかりと私生活に踏み込んでいるのだが――信頼に足ると判断するのはそのゆえである。
著者がデリダを読み込んでいると思えるのは、著書からの引用や要約が実に的確だからである。本書は、アルジェリアでの幼少期から高等師範学校生時代を中心とする第一部「ジャッキー」、「『幾何学の起源』序説」でデビューしてから八面六臂の活躍をする七〇-八〇年代を描く第二部「デリダ」、友人たちの死や私生活上の厄介事に悩まされながら世界各地でエネルギッシュに講義し続ける晩年の二十年を描く第三部「ジャック・デリダ」の三部から成るが、第二部以降は基本的に、講義・講演およびその展開としての著作の執筆と刊行が驚くべき速度でデリダの生に積み上げられてゆくのを辿る形となっており、そのつど著作の簡潔な位置づけが精確な理解に基づいて行われている。しかし、実は第一部にこそデリダ読者としての著者の本領が発揮されているとも言える。なぜなら、アルジェリア時代については私的資料が欠けており、この時期の歩みはデリダの著作の自伝的記述から再構成されているからである。それでいながら、歴史的背景と併せて後のデリダの「アルジェリア望郷(ノスタルジェリア)」の由縁を説得的に描き出すこの第一部の構成力は並外れたものである。
先述したデリダの伝記を書くことの困難さは、この自伝的記述に関わっている。というのも、デリダ自身が「伝記=生の記述」を哲学的問題と切り離さずに思考し、言い換えれば、私的な記述(手紙、手稿、手記)と公的な記述の境界を問い直し続け、かつ、自身のテクストに自伝的記述を織り交ぜることによってその思考をエクリチュールにおいて実践し、いわばつねに過去を振り返り、自身の「伝記」を書き続けた稀有な哲学者だったのであり、そのような者の伝記を書くということは、対象の掌の上で踊らされているようなところがあるからである。序章を読む限り、ペータースはデリダにおける「伝記」の問題の存在に十分自覚的である。自覚的であった上でその伝記の執筆に挑むことはきわめて困難だと思われるが、結果的に、この困難の見事な乗り越え方が本書の成功を導いている。
どのように乗り越えたか。第一に、私的資料のみに拠るのではなく、あくまで著作の理解をベースにした上で、膨大な私的資料(関係者との談話、手紙、手記等)を適切に援用、配置したこと。これによって、公的著作が私的アーカイヴと関係づけられ、デリダの人生と時代のなかに位置づけられた。読者は自分の読んできた、あるいはこれから読む著作を、それが生まれた文脈のなかに置き直すことができる。第二に、デリダ的(デリディアン)にならず、淡々と書くこと。ここを間違ったら本書は読むに堪えないものになっていただろう。「伝記」に関して「デリダ的」になったらデリダに敵うわけがないのだ。この点をペータースはよくわきまえている。本書は一切デリダ的ではなく、またデリダ論でもない(悪しからず!)。先に、著者をデリダの忠実な読者と呼んだのはこのためである。著者はデリダを模倣することも研究者として論ずることもなく適切な距離を保って紹介と描写に徹している。これは困難な立ち位置であるに違いないが、一種の浅さとも見えるこの抑制が実は著者の深いデリダ理解を示している。第三に、以上を通して、デリダにとって「伝記」の問題が根源的なものであったことを浮かび上がらせること。「伝記=生の記述」の問題とは、言い換えれば、生を記述する手紙の問題、手紙を差し向ける友の問題であり、手紙で振り返られる過去の問題、アーカイヴの問題、記憶の問題、子ども(自分であった子ども、非嫡出子を含む自分の三人の子ども)の問題、家族の問題、性の問題であり、そしてこれらに通底する死の問題である。「伝記=生の記述(ビオグラフィー)」へのデリダの関心はたえまない死の予感と不安から生まれたものだ。
私たちは、これらがデリダの著作の主題であることを知っているが、これらがデリダの人生においても、いや、人生においてこそたえまなくデリダを悩ませた「問題」であったことを本書は教えてくれる。本書にはデリダの書簡がふんだんに引用されているが、そこからは、講演や著作の準備に追い立てられ、常人には及びもつかないような多忙のなかにありながら、デリダが献本への礼状を律儀に認め、近しい友人(ミシェル・モノリ、リュシアン・ビアンコ、ガブリエル・ブーヌール、ポール・ド・マン)に近況を書き送り続けたことがわかる。しかしそれは、おそらくデリダにとって必要なことだったのだろう。本書を読んでいると、デリダのエクリチュールのベースは限られた友人への私的な手紙の執筆にあったのではないかという気がしてくる。本書から浮かび上がるのは、不特定多数に向けた公的な演説を好む人物ではなく、相手との関係性や文脈において手紙を書くように言葉を差し向ける、友愛に満ちた人物である。そして近しい者たちへの手紙において、デリダは傷つきやすい自分を曝け出した。そこには何と多く「意気阻喪」という言葉が出てくることだろう。手紙から現れるのは、落ち込みやすく、たえず死に取り憑かれた、繊細な人物である。
しかし、それらの手紙は熟慮されたうえで選ばれた言葉で、つまりは彼のエクリチュールで書かれている。それらは受取人たちに取っておかれ、死後、ペータースという伝記作者によって再び集められた。自分の出した手紙の多くを母親が処分してしまったことを知って深く傷ついたというデリダは、自分の手紙が死後に残ることを当然予感していただろう。彼は、受け取った手紙はみな取っておき、晩年、IMEC(現代出版記憶研究所)のデリダ・アーカイヴに託した。それらが自宅から運び出されるとき、「あなた方がそこから運んでいくのはわたしの人生なんですよ」と不安げにもらしたというデリダ、この手紙とアーカイヴの思想家の伝記が、いま、彼の予想通り、私たちの手のなかにあり、それを読む私たちを見て、彼は微笑んでいる。墓のなかで。
初出=『図書新聞』2015年4月4日号(第3201号)
+++++++++++
書き過ぎる、いや、書き足りない──過剰書字者ジャック・デリダの肖像
宮﨑 裕助
デリダの死からほぼ6年、今後これ以上の完成度をそなえたものは出てこないだろうと思わせる傑出した伝記が現われた。昨年日本語訳も刊行されたブノワ・ペータース『デリダ伝』は、そんな決定版と言える伝記である。
これまで一度ならずデリダ自身の著作に挑戦して挫折した人もいるかもしれない。本書は、デリダの私生活に踏み込むさまざまな新資料が駆使されているが、けっしてセンセーショナリズムに走ることのない、平明で抑制の効いた文体に貫かれている。そこにはまさしく等身大のデリダ像がある。これからデリダを読もうという人でも、凡百の入門書や早わかりに飛びつく前に、ぜひ本書を繙いてみてもらいたい。
模範的な伝記である本書は、アルジェリア生まれのユダヤ人少年が、反ユダヤ政策により市民権を奪われ、幾たびの挫折と苦悩を経て、パリのエリートとして立身出世する物語、さらには、高等師範学校でポストを得るもフランスの大学制度にいつまでも拒否されていると感じ続け、「脱構築」という旗印のもとアメリカに進出し、ついには世界的なスター哲学者へと登り詰めていく物語、そうした分かりやすい成功譚としてデリダの生涯を描くことを禁じているわけではない。
しかし本書を通読して得られる印象はそうした「物語」にはない。本書の魅力はもっと別の「細部」にある。たとえば、本書には私信からの多くの引用がある。デリダは家族、恋人、友人、知人をはじめとしたさまざまな宛先に夥しい数の手紙をしたためていた。デリダの筆まめは本書がくり返し強調するところであり、書簡のやりとりを通じてこそデリダがどれほど稀有な友情をとり結んできたのかをこの伝記は見事に明らかにしている。本書は、卓越した書簡作家としてのデリダを示す第一級の資料でもある。
他方でしかし興味深いのは、友情を導くこのマメさが、あらゆる災いの種にもなっているという点である。デリダにはつい過剰に書いてしまう「癖」があった。少年ジャッキー(「ジャッキー」はデリダの本名)は哲学に関しては十代から教師たちも目を見張る才能を発揮していた。しかし小論文の試験では求められている以上のことを過剰に書いてしまう。幾人かの教師は挑戦されたようにすら感じ、大きく減点するのであった。これはその後の入試の失敗の大きな要因になる。
あるいはデリダがのちの伴侶マルグリットとの結婚を彼女の両親に申し出るときのこと。デリダは結婚の許可を乞うのではなく、結婚についての自分のリベラルな考え方を開陳した長い手紙を送り、たいへんな不興を買った。また自分の伯父に返信するさいには相手の文面を一言一句事細かにとりあげて反駁してみせ、伯父を苛立たせるのだった。あまりに度が過ぎているので「四方八方から攻撃されていると思い込み、敵などいないのに空中をひたすら斬り続けている剣闘士のような状態だ」と心配されてしまうほどだった。
デリダは論争が絶えない哲学者だった。自分から論争を仕掛けることはあまりなかったが、論争がエスカレートする場合はたいてい書き過ぎるがゆえの「筆禍」のせいだと言ってよい。
典型的なのはアメリカの哲学者サールとの論争だ。デリダは、相手の論文のほぼ全文を引用して微に入り細に入り徹底的に論駁して、いったい誰と論争しているのかわからないぐらいに怪物的な反論文(「反論」文かつ反「論文」)を書き上げ、サールをいっそう激怒させた(というより呆れさせた?)のは有名なエピソードだ(『有限責任会社』参照)。自身の主張を単刀直入に提示すればいいものを、つねに一言二言余計に付け加えてしまい、結果誤解されて伝わってしまうのだった。
デリダの「書き癖」は、いつも車を運転しながら、またジョギングしながらでもメモをとってしまうというエピソードにもよく現われている(幸いそのせいで事故を起こしたことはなかったようだが)。私は「過剰書字(hypergraphia)」や「語漏症(logorrhea)」という言葉を思い出す。一般には、なにもかも強迫的かつ大量に書き付けて止まらなくなってしまう病気を指す言葉だ。しかしデリダに言わせればこれはたんなる病ではありえない。それは言葉(ロゴス)そのものが促す必然なのだ。
「私はそれをいわずにはいられない」。デリダは晩年のインタヴューで、物議を醸すことが分かっていても書いてしまう自分の言語活動について、半ば当惑しながらも確信をもってこの必然性を肯定してきたということを述べている。デリダによれば、それは「真理の欲動」でさえある。そこにはひとりの哲学者が生涯をかけて格闘した普遍的ななにかがある。
つねに書き足りず、つねに書き過ぎること。それはまさに「書くことの罪」であり苦悩そのものなのだが、デリダはこれを、個人の思惑を超えた「真理の命法」として断言することを選ぶ。それこそは「私」を、私というひとりのちっぽけな人間から解放しうるエクリチュール(書くこと)の力ではないだろうか。
デリダは意図するよりも先に筆が進んでしまうことに不安を感じながら、それに身を委ねることに喜びを見出していた。かくして『デリダ伝』の豊かな記述からひとりの印象的な人物像が浮かび上がる。それは一生涯書くことの二重性に引き裂かれながら、これを力強く肯定し、その分裂を幸福に生き抜くことのできた、そんな偉大な書き手の肖像である。
初出=『ふらんす』2015年11月号