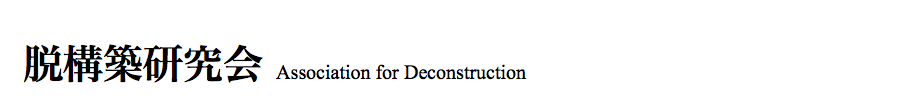Review

ポール・ド・マン著『読むことのアレゴリー──ルソー、ニーチェ、リルケ、プルーストにおける比喩的言語』土田知則訳(岩波書店、二〇一二年)書評
宮﨑 裕助
二〇世紀の文芸批評家のなかで、ポール・ド・マンほどしばしば語られてきたのにもかからず、その知名度に比して実際には読まれてこなかった存在も珍しいのではないだろうか。たしかに日本でド・マンの名は、多かれ少なかれ彼の影響を受けた柄谷行人や水村美苗といった突出した書き手を通じて以前から人口に膾炙していた。九〇年代には主要な論考の翻訳が『批評空間』のような雑誌に掲載されたこともあったし、その間いくつかの訳書も出ている。しかしながら、日本語でのド・マン受容はこれまで空回りの感があったことは否めない。その理由ははっきりしている。ド・マンの著作全体にとって二つの焦点をなしている生前の主著『盲目と洞察』(一九七一年)と本書『読むことのアレゴリー』(一九七九年)とがずっと未訳のままだったからである。
昨秋の『盲目と洞察』刊行に続き(拙訳で月曜社刊)、本書『読むことのアレゴリー』の翻訳がこのたび上梓されたことにより、原著出版以来ほぼ四十年にわたって続いていた空白がついに埋められることになった。本書の刊行をもって、まさしく「読むこと」について徹底的に思考したド・マンの著作を、ようやく日本語で「読むこと」のできる日が来たのである。
第一評論集『盲目と洞察』が、同時代の批評家や理論家を相手に殴り込みをかけるいわば闘争の書であり、ド・マンがイェール学派の首領として「脱構築批評」を率いるにいたった出世作だとすれば、本書は、ド・マンが自身の方法論をじっくり熟成させて名実ともに主著へと練り上げたものであり、批評家としてのキャリアを不動のものとした代表作だと言えよう。そうした点で本書が提示しているのは、なによりも「読むことの理論」(xiii頁)である。しかし、本書の企図はこの理論を体系として打ち立てることではない。そうではなく、本書が目論むのは、「読むことの理論」をひとつのプロセスとして敢行することなのである。
プロセスと強調したのは、ド・マンの「理論」が、文学という対象に対して、それを解釈するための道具のように用いられる方法論(メタ言語)をなすわけではないからだ。本書によれば「読むこと」の直面する「言語の修辞的・比喩的な潜在可能性」(一二頁)を追究することで、読者は、みずからの解釈をなすメタ言語が必然的に当の読解対象をなす言語に巻き込まれてしまうという循環に陥るのであり、そうした「読むこと」のプロセスそのものがみずからのメタ言語をつねに撤回せざるをえなくするのである。どういうことだろうか。
ド・マンは、例としてイェイツの詩「学童に交じりて」の最終連(「踊り子と舞踏をどうして切り離しえようか」)が修辞疑問(「両者は切り離すことができないほど調和している」)にも文法通りの疑問(「どうすれば両者を切り離しうるのか、教えてくれ」)にも受け取れることを取り上げている(一二頁以下)。この議論の核心は、同一文がたんに多義的だということではなく、双方の解釈が同一文でありながら互いの主張を論理的に斥け合うという背反関係に置かれるために、その解釈が決定不可能なアポリア(行き詰まり)に陥ってしまうという点である。
ド・マンはこうした状況を、字義的/比喩的、文法的/修辞的といった言語の二重性のうちに見出している。ド・マンは自身の企てを「修辞的読解」と呼んでいるが、誤解してはならないのは、それが文学作品にさまざまな型の比喩表現をみとめて修辞学的分類を打ち立てようとしているわけではないということだ(この点でジェラール・ジュネットやグループμの『一般修辞学』のような体系的試みとは異なる)。ド・マンは、実際の読解プロセスのただ中にあって、そのような言語の二重性が相互に反転し決定不可能となり、結果、意味の核そのものがくり抜かれてしまった水準において浮かび上がってくる言語の構造を探究するのであり、この言語(の探究)を「修辞(学)(レトリック)」と呼ぶのである。
しかしこの探究は一筋縄ではいかない。というのもそこから出てくる帰結が解釈の根本的なアポリアであるために「読むことの理論」どころか「読解不可能性の理論」に行き着いてしまうからだ。しかも、そのさい言われる「理論」とは、メタ言語の破綻を示す言語である以上、「読解不可能性の理論」自体の主張不可能性を(直接に語るのではなく)かろうじて示唆するだけにとどまる。かくして本書のタイトル「読むことのアレゴリー」が示しているのは、アレゴリー(寓意)の原義(allos[他なる] + agoreuein[公に語る])に即して、読解そのものがそうして「他なるものに託して語る」ことを余儀なくされた事態にほかならない。
ド・マンのこうした不可能性に不可能性を重ねたような「読むことの理論」は、解釈の不条理さそのものに淫したような不毛な企てのように映るかもしれない。しかしそれはまったくの誤解だ。読むことが真にその名に値する仕方で「読むこと」でありうるのは、実際には、読解不可能なものに直面してこそなのだ。国語の試験問題のような、あらかじめ読みうることをたんに読む行為は「読むこと」のうちには入らない。あるいは、理想化された「期待の地平」(ヤウス)へと意味の拡がりを収束させるような解釈学でさえ、読むことの出来事を十分に引き受けているとは言えない。ひとは読解不可能なものの試練を潜り抜けることによってこそ、予期せぬ仕方で、真に読むに値するものに遭遇することができるのであり、たんに恣意的でも意図的でもない仕方でテクストの新たな読解可能性を切り拓くことができるのである。この読解不可能性は、いうなれば、言語に内在する歴史や自由の条件そのものでさえあるのだ。
本書は、まさに読解不可能性の経験のなかで「読むことの理論」が実践されるプロセスをみずから提示してみせたものにほかならない。本書はそうした読むことの試練が課される特権的な舞台を、リルケ、プルースト、そしてなによりも、ニーチェとルソーのテクストに見出している。本書の企てをド・マンが論じている各テクストに即して丁寧に追跡してゆけば、読者は、たとえばニーチェの『悲劇の誕生』やフィクション論を、言語行為論の観点から再読する試み、あるいは、前著『盲目と洞察』でスタロバンスキーやデリダのルソー像をすら伝統的なルソー解釈者のそれにすぎないとして斥けたド・マンによるラディカルなルソー読解等々、「読むこと」の歴史的出来事となったいくつもの決定的な現場に立ち会うことができるだろう。
幸いなことに、本書は、ド・マンの高弟バーバラ・ジョンソンやショシャナ・フェルマンの翻訳も手がけてきた訳者の尽力によって、総じて正確で滑らかな訳文に仕上がっている。むろんド・マンの緻密で濃密な読解プロセスに併走していくことは、いかに優れた訳書といえども、初めは大変かもしれない。そうした読者にはまず、本訳書と同時刊行された訳者土田氏による『ポール・ド・マン』を繙き、そこに描き出されたド・マン的読解のキータームや主題群に馴染んでおくことをおすすめしたい。これは、日本語による初のド・マン研究の書であり、まずもって『読むことのアレゴリー』を読み始めるための副読本として活用することができる。その平易で明快な筆致は、格好のド・マン入門の役を果たしてくれるだろう。
「速く読みすぎても、ゆっくり読みすぎても、何もわからない」──これは本書の題辞として掲げられたパスカルの言葉である。「読むこと」は速読でも遅読でもない、テクスト固有のリズムにおいてはじめて成し遂げられる。高速を旨としたコミュニケーション・ツールが社会を一様に覆い尽くしつつある現在、「読むこと」をたんなる文字列の情報処理のごとき単調さに委ねないために、本書『読むことのアレゴリー』は、いわば、読むことの条件としてのテクストのリズムに注意深く耳を傾けてみるよう、原著刊行から三十余年の歳月を超えて、あらためてわたしたちを誘っているのである。
初出=『週刊読書人』2013年3月15日・第2981号