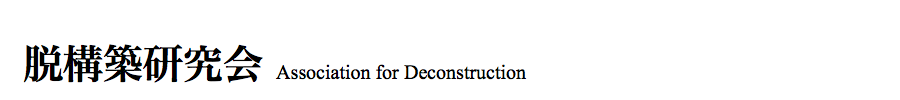Review

ジャック・デリダ『嘘の歴史――序説』西山雄二訳(未來社、2017年)
宮﨑 裕助
昨年末の合衆国大統領選でドナルド・トランプが当選して以降、「ポスト・トゥルース(脱真実)」「オルタナティヴ・ファクト(代替的事実)」といった言葉をあちこちで耳にするようになった。それらは客観的な事実や真理よりも、個人的な感情や信念が優先されてしまう現代政治の特徴を言い表した用語だとされている。
事実や真実に基づかない政治的メッセージは、これまでもデマゴギーやプロパガンダ等々、さまざまな言い方によって指し示されてきたし、いまなお警戒の対象であることに変わりはない。確かに政治には多かれ少なかれ嘘や欺瞞が付きものだろう。しかし単純化は禁物である。現在進行中のトランプの政治は措くとしても、現代ないし広く二〇世紀以降の政治において、いかなる意味で「嘘」が問題になるのだろうか。
このたび翻訳されたジャック・デリダの小著『嘘の歴史』は、そのような問いへの応答として読むことができる。そもそも嘘とはたんに虚偽や虚構を言うことではない。寓話や創作そのものは嘘ではない。嘘が嘘となるのは、自分が真実を知っていながら、相手を騙そうとして故意に虚偽を言うことに存している。したがって、これはたんに真か偽かという認識の問題ではなく、誠実か否かという信義の問題なのである。
本書がまず指摘しているのは、私たちのコミュニケーションがそうした意味で「嘘をついてはならない」という誠実性原則を前提すると考えられてきたという点である。プラトン、アウグスティヌス、ルソー、カントの嘘論の要点を簡潔にたどりながら、デリダはまず、歴史を超えて前提とされてきた嘘概念の基本的な定義を明確にしている。
しかしデリダが本書で議論の照準を合わせているのは、嘘のそうした形式的な前提には、なにがしかの歴史性が含まれているという点である。「嘘の歴史」という標題のもとにデリダが訴えかけようとするのは、そのような誠実性原則が中立的な形式的条件ではありえず、一定の歴史的条件のもとでくり返し問い直さねばならない性質のものだということにほかならない。とりわけ「政治における嘘」についてはそうなのだ。
本書の発端は一九九四─九五年の一連の講義にさかのぼる。戦後五〇年の節目にデリダが引き合いに出していたのは、ナチス占領下のフランスにおけるユダヤ人迫害(ヴェルディヴ事件)の過去であり、当時の大統領ジャック・シラクはそれがフランス国家が積極的に関与した罪であることをはじめて公式に認めたのであった。本書によれば、これは、ニュルンベルク裁判以後に確立した「人道に反する罪」という国際法上の概念のもとで戦争犯罪が認められるようになってきた趨勢のひとつである。デリダは日本のいわゆる村山談話もその一例に含めており、そうした広がりを「人類と国際法の、その学術と良心の歴史における進歩」とみなし、高く評価している。
そこからデリダが立てる問いとは次のようなものだ。シラクがはじめてフランスの国家的罪を認めたからといって、それまでのド・ゴールからミッテランにいたる大統領は、国家が関与した現実を否認し隠蔽していたことになるのだろうか。つまり嘘をついていたのだろうか。
彼らにしてみれば、この点で嘘か否かを追及されるのはほとんど無意味に思えただろう。法的には罪の事実そのものが存在しなかったと考えられるからだ。ここでの嘘を認定する「人道に反する罪」のような概念は、第二次大戦以前には知られておらず、戦後もそれを法的基準とすべきかどうかは不確かなままであった。
デリダによれば、実際に生じたのは逆の事態である。すなわちシラクは、そのような国家的な罪を認めることで、むしろ同時にそうした法的概念を尊重すべき基準として確証したのである。ここには嘘の概念があらかじめ準拠しうる事実は存在しない。実のところ歴史的出来事には「真理をつくり出す」次元があるということをデリダは(アウグスティヌスの言葉を引いて)強調するのである。
このような事例がひとつの「進歩」だとしても、しかしながら、これはつねに「退歩」へと反転しうる危うさと表裏一体である。ある時点で一国家がそうした戦争犯罪を認め公式的に謝罪をしたからといって客観的な真実そのものが確定するわけではない。そうした罪の事実を否認する歴史修正主義が回帰してくる余地もまた同様に残されたままである。嘘の概念自体が失効する次元があるという主張は、新たな修正主義と原理的に手を切ることができないという点を認めることを含意している。
本書によれば、ハンナ・アーレントが「現代政治における嘘」として考察していたのはまさにこの窮境である。アーレントが二〇世紀の政治の展開のなかで見抜いていたのは、現代では嘘の概念がひとつの臨界点に達して根本的な変容を被ったということである。すなわち、全体主義体制下における現実性の破壊、そしてこの破壊を支えるテクノロジーやメディア状況、そうした条件のもとで事実や真理は解明ないし検証の対象ではなくなり、もはやどうでもよいもの、それどころかはじめからなかったものにさえなるのである(その最終的な帰結がホロコーストにおける表象不可能性である)。
要するに、アーレントが「現代的な嘘」として危惧していたのは、嘘を嘘として定義しうる形式的条件そのものが成り立たなくなってしまう状況であり、現代の政治がそのなかでこそ進行しつつあるという事態なのだ。本書においてデリダはアーレントのみならず、アレクサンドル・コイレの嘘論を取り上げながらその危機感を共有するのであり、さらにアーレントやコイレが陥っているように見える楽観主義を超えて、この危機を尖鋭化させるのである。
デリダ独特のスタンスがせり上がってくるのはここからだ。その論点をざっと挙げておくなら、嘘の脅威を公共の透明性に訴えて斥けようとするコイレの議論に対して「秘密」を抵抗の権利として喚起する点、政治における「自己への嘘」を指弾するアーレントに対して自己に誠実たることが本当に可能なのかと問い質す点、あるいは両者に欠けているように思われる証言の問いの重要性を打ち出す点、等々である。
翻訳では百ページにも満たない本書は「序説(プロレゴーメナ)」と銘打たれている通り、残念ながら、そうした論点を十分に追究しているわけではない。しかし少なくともはっきりしているのは、本書が、現代にあっては嘘が避けがたく政治に関与する点とともに、従来の嘘概念が失効する臨界点をも見定めるものだということである。これは「嘘」という言葉がたんに無意味になったということではない。それどころか、ますます濫用されざるをえなくなったということを示しているのである。
「ポスト・トゥルース」や「オルタナティヴ・ファクト」といった言葉の流行は、私たちの時代におけるその兆候だろう。ならば、そのような状況に耐え得る、真/偽の対立や誠実/不誠実の対立に拠らない「嘘」の新たな概念とはどのようなものだろうか。そもそも歴史というものが「真理をつくり出す」次元、ある意味で嘘をつく可能性に依存していることを認めたうえでの新たな概念とは?──私たちがいま「嘘の歴史」のただ中を生きているのだとすれば、そのような問いのもとでこそ、本書を繙いてみなければならない。
初出:『図書新聞』2017年5月27日、第3304号