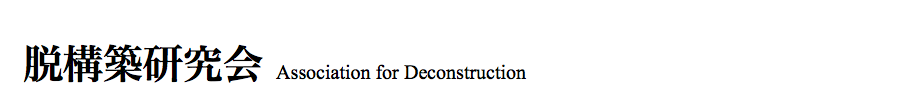Review

ジャック・デリダ『マルクスの亡霊たち』増田一夫訳(藤原書店、2007年)
鵜飼哲
「死者をして死者を葬らしめよ」。『マルクスの亡霊たち』の数ある可能な読み方の一つは、この書の全編を、イエスのものとされるこの言葉と、マルクスによる、さらにはマルクスの左翼的後継者の全世代による、その慣用的解釈とレトリック的使用に対する、慎重に準備され周到に組織された、そしてまた抑制された友愛に浸透されてもいる、深刻で精妙な留保の挙措と考えることかも知れない。なぜなら、この同じ言葉の同じ解釈は、当のマルクスに、本書刊行の年である一九九三年、いわゆる冷戦の終焉期のはるか前から、すでに、差し向けられていたからである。一九六八年の高潮ののち、自称・他称の「マルクス葬送派」は、一九七〇年代後半には、フランスでも、日本でも、すでに大きな潮流をなしていた。本書の終わり近くでデリダは言う。
「たとえそれを欲したとしても、死者に死者を葬ることを任せることはできないだろう。それは意味を持たず、不可能である。ただ死すべき者たちだけが、生き神ではない生ける者たちだけが死者を葬ることができるのである。生ける者だけが死者のために通夜をし、端的に注意をすることができる。幽霊たちもまたそれをすることができ、彼らは注意をしているいたる所にいるが、死者にはそれができない──それは不可能であり、できるようであってはならないだろう。
この無底の不可能事がそれでも場を持ちうるということ、それこそ逆に破滅もしくは絶対的な灰であり、思考すべき、そして依然として悪魔祓いしなければならない──違うだろうか?──脅威である。」(強調原文)
マルクス主義あるいは共産主義の「亡霊」に対する新自由主義的=新ヘーゲル主義的悪魔払い(フランシス・フクヤマ)に抗して、マルクス自身による「幽霊」の悪魔払いの諸相を分析すること―本書の企図のこの根本的な両義性は、一面では、この作業の歴史的な必然性に由来する。シェイクスピア『ハムレット』のある戦略的読解で幕を落とし、ブランショ「マルクスの三つの言葉」からマルクス的テクストの内的異他性と「厳命」のモチーフ(マルクスにおけるヘーゲルからカントへ回帰する線)を引き出し、ハイデッガー「アナクシマンドロスの言葉」の検討を通してThe time is out of jointというハムレットの嘆きの言葉を到来すべき正義の条件へと転化したうえで、現代世界の「傷口」を(『共産党宣言』、『出エジプト記』の十の災い、モーセの十戒、アリストテレスの範疇表、『ド・イデ』の十個の幽霊への五重の参照のもとに)十点に絞り込み、「新しいインターナショナル」到来への祈願に場を与え、メシア主義なきメシア性の思考とコーラの唯物論の必要性を説く―本書のこの長い助走は著作全体の半ばを超え、原書で実に一五〇頁に及ぶ。言い換えれば、本書でデリダが企図したのはマルクス思想の総体的検討というよりは、マルクス的テクスト、マルクス主義的出来事、そして今日的世界という三重の歴史的独異性の輻輳を凝視して選ばれた「亡霊」というモチーフを軸に、「マルクス主義はどこへ行くのか/衰退しているのか(W(h)ither Marxism)?」という、彼が参加を求められたコロックの表題をなす問いに、ある政治的かつ哲学的な言語行為をもって応答することであったと考えるべきだろう。
実際デリダは他の著作で、ここでは明示的に扱われていないマルクスの多くのテクストに触れており、その点だけからしても、本書をもってデリダのマルクス論の集大成とみなすことはできない。とはいえ、『共産党宣言』冒頭の一句に始まり、博士論文『デモクリトスとエピクロスの自然哲学の差異』の献辞において、ある父親的人物に向う情動が、すでに、「亡霊」と「精神」の間で、前者の召喚と追放を通して表明されていることの指摘を経て、『経済学批判要綱』『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』『ドイツ・イデオロギー』『資本論』へと至る読解の道は、「亡霊/幽霊」というモチーフのこのコンテクストにおける焦点化を、十分正当化するに足る説得力を備えている。
ここでは特に、『ド・イデ』におけるマックス・シュティルナーの『唯一者とその所有』に対する長大な批判を検討した箇所に注目したい。「ドイツ・イデオロギー内部論争」と呼ばれる思想史上の出来事の紹介および研究は、この国でも、一九八〇年代から九〇年代にかけて飛躍的に進んだが、デリダは早くから、おそらくアルチュセール(派)との微妙な緊張関係のなかで、この論争に対する関心を断続的に示していた。『弔鐘』(一九七四)で『経済学・哲学草稿』『聖家族』における「批判の母」としてのヘーゲル弁証法の位置づけが検討されたのち、『ド・イデ』におけるカール・グリューンの「真正社会主義」批判に哲学的ナショナリズムの最初の問題化の発見が試みられたこともある(「国民人間主義の存在神学」、一九九一)。いわゆる「シュティルナー・ショック」がマルクスとエンゲルスのフォイエルバッハからの離脱の契機となったことは現在ではほぼ定説だろうが、『ド・イデ』のシュティルナー批判に関しては、シュティルナーのように本質的普遍者(第二実体)ばかりでなく、シュティルナーが顕揚する唯一者(第一実体)をも、社会的諸関係からの抽象(「幽霊」)として退けるマルクスの立場を基本的に承認することがマルクス研究者の標準的解釈であるように思われる(例えば廣松渉『物象化論の構図』)。
この点でデリダは、むしろ、シュティルナー的問題構成の重要性を軽視するマルクスの、やや調子の外れた喜悦さえ含む性急な論難のうちに、論者(マルクス)の論敵(マックス)との競合的同一化、ヘーゲルの二人の「息子」、「兄弟」の間の抗争を見る。マルクスが一方では「精神」と「幽霊」の原理的区別に固執しつつ、他方では「霊」をも意味するGeistの両義性を論争の具として濫用していることは、デリダの目には問題化すべき徴候と映る。マルクスはシュティルナー的コギトを「歴史的構築物(Geschichtskonstruction)」と看取してその「脱構築」を図るのだが、彼が論敵から奪い取り投げ返す「幽霊」という語はそのとき単なる罵倒語の域を脱し、「精神」との「差延」において、ある奇妙な準—概念の様相を獲得する。ルソーのテクストに「代補」を、プラトンのテクストに「パルマコン」を見出したように、マルクスのテクストにデリダは「亡霊/幽霊」を見出す。この語=概念がマルクス的テクストのある層で一定の「恒常性」「一貫性」をもって機能していることの発見は、労働論にも、イデオロギー論にも、商品物神の分析にも、貨幣論にも、さらにはいわゆる「認識論的切断」をめぐる議論にも、少なくない重要な帰結を生まずにはいないだろう。
「幽霊」は、しかし、他面では、七〇年代半ば以降浮上した、デリダに固有な戦略的モチーフでもある。『絵画における真理』(一九七八)所収の諸論考には「幽霊」の語彙がすでに頻出し、『投機/思弁するーフロイトに(ついて)』(一九八〇)には『ド・イデ』における「幽霊」の軽視への言及もある。『弔鐘』以後、デリダはこのモチーフの現働化に踏み切ったように思われる。マルクスの亡霊たちとデリダの亡霊たちが出会い、混ざり合う場所で、かくして本書は成立した。本書でデリダが目指したのは、マルクス派にも反マルクス派にも、誰にも気に入られないだろうことを確信しつつ、反時代的な不協音を正しく響かせることだった。彼の著作のうちでも独特の取り組み難さを持つこのテクストと長い時間をかけて付き合い、正確で読み易い訳文を彫琢してくれた翻訳者の労に感謝したい。
(初出=『週刊読書人』、2721号、2008年1月18日)
宮﨑裕助
マルクスが読まれなくなった。そう述べることには、たんなる現状認識のみならず、マルクスを新たな読解の対象として復権しようとする期待がしばしば含まれている。だが、いまやそのような期待そのものが、消滅しつつあるように思われる。マルクス再生の要求は「マルクス主義の終焉」や「共産主義の死」が他方で喧伝される場合にはたしかになんらかの政治的な抵抗たりえただろう。ところが二一世紀に入り、冷戦終結後二十年に近い年月が経とうとしている現在、もはやマルクスをめぐるそうした対立に訴えること自体がなし崩しに失効してしまったかのようなのだ。
デリダが本書の元になる講演を合衆国で行ったのは、九三年に遡る。当時は、八九年のベルリンの壁崩壊に続く東欧・ソ連の共産圏諸国の解体とともに、文字通り「マルクス主義の終焉」であるかのような状況が生まれていた。アメリカ国務省のスタッフだったネオコンの論客F・フクヤマが著した『歴史の終わり』は、その時の政治情勢を象徴するものとしてよく知られている。要するにそれによれば、いまや資本主義が全世界を覆い尽くし、自由民主主義の勝利をもって、歴史が終わりを迎えた、ということになるのである。
本書をまずもって特徴づけているのは、このような主張に対してはっきりと異議を申し立てるべく、マルクスという思考の遺産を通じて状況介入しようとするデリダの強い切迫感である。第二章のフクヤマ(とその思想的源泉たるコジェーヴ)へのまとまった批判は、古典的テクストの精読を旨とするデリダとしては異例というべきものだろうし(デリダがフクヤマを取り上げたのは直接には講演を行った会議のプロトコルに導かれたからなのだが)、第三章で(先代ブッシュの打ち出した)「新世界秩序」への批判として、その綻びたる十の「傷口」を列挙することを通じて「新たなインターナショナル」の連帯を呼びかけるデリダの主張は、まさに『共産党宣言』でプロレタリア階級によるブルジョワ的生産関係への介入として掲げられた十箇条の再演ともみえる力強い調子に貫かれている。
そうした状況のなかで「亡霊」というモティーフを軸にデリダがマルクスを再読しようとしたことのねらいは、最も単純には次のように理解できるだろう。共産圏解体によってマルクス主義は過去の遺物として、マルクスは「死んだ犬」として厄介払いされようとしている。つまりマルクスの精神は、亡霊として祓い除けられようとしている。しかし注意しよう、マルクスはそもそも共産主義を亡霊としてこそ資本主義社会に取り憑かせていたのではなかったか。「亡霊がヨーロッパに取り憑いている──共産主義という亡霊が」。『共産党宣言』の劈頭に現われるこの一文は文字通りに受け取るべきだ。というのも、もし共産主義──マルクスの精神──がはじめから亡霊だったとするならば、それはたんに生きているのでも死んでいるのでもない、そのような精神゠霊(Geist)としてこそ効力を発揮すると考えられるからだ。実のところこの亡霊は、亡霊であるかぎりでむしろ共産主義にとってのチャンスではないだろうか。
このような展望をいささかのアイロニーもなしに受け入れること。このような企図が、おそらく本書をしてデリダに「愉しく喜劇的な本」と呼ばせるものにしている。それを達成するためにデリダが従事する読解の労働は甚大なものだ。というのも一方では、マルクス自身は見たところ幽霊嫌いであり、亡霊は、祓い除けるべき対象としてしか、あるいは、将来生き生きとした現前のもとで実現すべき対象としてしかみなしていないからだ。そこでデリダは、現前の形而上学に囚われているマルクスの存在論(ontologie)に代えて、《憑在論》(hantologie)を提唱する。
しかしこれは他方で、マルクスのテクストから引き出しうる議論なのである。そのことを示すために、デリダは『ドイツ・イデオロギー』におけるシュティルナー批判を取り上げ、幽霊退治をしようとしてますます多くの幽霊を召喚し幽霊に呪縛されるマルクスの窮境を描き出している。そこでは精神と亡霊が両者の相剋のなかで反転し合い、ついには判別不可能な関係に陥るのである(このシュティルナー/マルクスの関係は、ヘーゲルの影響下で『精神現象学』を『亡霊現象学』へと書き換える射程をも開くだろう)。
あるいは『資本論』における商品の物神的性格の批判のうちにデリダが読み取るのは、それなくしてはそもそも価値一般が可能にならなかったであろうようなフェティシズムの根本性格をマルクスが見抜いていたという洞察である。かくして物神崇拝を導く商品形態の亡霊的な仮象のうちに、デリダは『資本論』に潜む憑在論の所在を突き止めている(この視点からすれば、本書は、アルチュセールのイデオロギー論、グラムシのヘゲモニー論、廣松の物象化論と同様、下部構造を実体化した唯物論や経済主義に陥らない現代のマルクス論の系譜に合流するだろう)。
デリダの亡霊論の要諦は、幽霊を忌まわしいものとして懸命に祓い除けようとすればするほどいっそう多くの幽霊をおびき出し幽霊をそこかしこに取り憑かせてしまうという逆説的な論理を分析することである。重要なのはマルクスの再生ではない。そうではなく、マルクス(の精神)を、まさに死すべき者が生き延びるために依存せずにはいられないような亡霊として資本主義社会に遍在させることなのである。
このような展望をもつ亡霊論が、しかしながら、マルクス主義の終焉が叫ばれた時代への状況介入の刻印を帯びているのだとするならば、私たちにとっての困難は、いまやマルクスや共産主義を亡霊として追い払おうとする動きすらほとんど見当たらなくなっているということではないだろうか。もはやマルクス主義の終焉を喧伝することすら終わってしまったかにみえる現在、はたしてマルクスの亡霊はどこに潜んでいるのか。
本書は、おそらくそうした反問の地点から、あらためてマルクスとともに読み直される必要があるだろう。デリダは本書の結論部で、自身の亡霊論を、マルクスが切り開いた二つの問題系の交叉のうちに位置づけている。すなわち、宗教批判と、テクノロジーの問いである。本書の観点からすれば、自由民主主義の勝利が謳われるまさにそのときにこそ「宗教的なものの回帰」として暴力が噴出するという現代世界の構図(むろんこれは九・一一以後にも私たちが目にしていることだ)は、追い払おうとすればするほど自縄自縛に陥る亡霊的ロジックの観点から分析されるべき現象にほかならない。他方、現代のコミュニケーション状況を媒介するテレテクノロジー(遠隔技術)の展開が、公的/私的空間の境界線を不可視なものにし人間の諸関係を短絡させることで、予測不可能で制御不可能な政治状況をもたらしている。要するに現代社会のこの不安は、メディアの亡霊的作用(本書では「バイザー効果」と呼ばれている)を背景としているのである。
宗教とメディア゠テクノロジーの問いが切り結ぶ地点に、依然としてマルクスの亡霊たちが徘徊している。本書の亡霊論から浮き彫りになるのは、宗教批判と遠隔技術の思考としてのマルクスの可能性である。とはいえ、この問題設定をマルクスの遺産に即して継承し展開するには、本書はいまだ読解プログラムを素描したにとどまっている。こうした問いの追究は、デリダの他の著作へと引き継がれることになるが(とくに「信仰と知」および『テレビのエコーグラフィー』)、それらは必ずしもマルクスを焦点としているわけではない。マルクスをめぐる亡霊記述(スペクトログラフィ)の探究は、まだ途に就いたばかりである。
初出:「ジャック・デリダ『マルクスの亡霊たち』増田一夫訳(藤原書店、2007年)書評」『図書新聞』2008年2月16日、2858号。