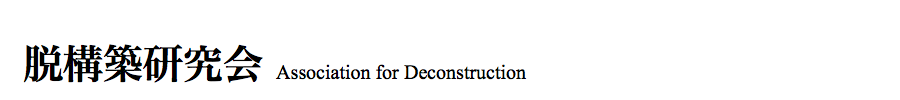Review
 _
_
ジャック・デリダ『グラマトロジーについて』
Jacques Derrida, De la grammatologie, Minuit, 1967.
日本語訳題『根源の彼方に』上・下巻、足立和浩訳、現代思潮社、一九七二年
宮﨑裕助
現代フランスの哲学者ジャック・デリダ(1930-)は、六〇年代初頭フッサール現象学の詳細な研究でデビューした後、六七年『エクリチュールと差異』『グラマトロジーについて』『声と現象』の三著を矢継ぎ早に公刊し、一躍世に知られることとなった。なかでも『グラマトロジーについて』は、エクリチュール(書かれた言葉、文字言語)に対するパロール(話された言葉、音声言語)の優位というモチーフを中心的な標的とし、プラトンからヘーゲル、ハイデガー、構造主義(ソシュール、レヴィ=ストロース)に至るまで、この優位に基づいて西洋思想全体が伝統的に組織されてきたということを、形而上学の歴史的な閉域(「現前の形而上学」「ロゴス中心主義」等とも呼ばれる)として徹底的に問い直そうとするものである。本書は、その企図の壮大さ、その影響の甚大さという点で、紛れもなくデリダの主著とみなすことができる。
そもそもグラマトロジーとは何か。グラマトロジーとは、グラム(gramme:書かれたもの)の学、すなわちエクリチュールの学、文字学のことである。しかし本書がもくろむのは、通常予想されるような、文字についての実証的な科学でも歴史学や考古学的な記述でもなければ、文字現象の社会科学的な考察でもない。その要諦はむしろ、エクリチュールの学が厳密には可能ではないということ、学としてのグラマトロジーの不可能性なのである。どういうことか。
本書が検討しているのは、まずもって、文字言語が特有の役割を果たしている形而上学の歴史的な時代(エポック)である。(1)このエポックは、みずからの問題提起の地平全体を「言語」として規定し、その地平の限界に文字言語を位置づけている。というのも(2)このエポックは、エピステーメー(真知)としての科学の本質をロゴス(言語=論理=理性)的と規定しつつ(ロゴス中心主義)、その達成のために、文字言語の表音化による音声言語の特権化、およびそれに伴う文字言語の副次化・外在化・周縁化を通して、言語のうちに真理一般の根拠を確保しようとするからである。文字(エクリチュール)は、話された言葉(パロール)の外的な反映であり、言語の意味理解を掻き乱しにやってくる余分な媒体にすぎない。言語の真なる意味は、発話者の現前のもとでパロールを通じて可能なかぎり直接的に聴き取られ理解されるべきものなのである(現前の形而上学)。しかし(3)当のエポックとは、エクリチュールに対するパロールの優位を指向するというまさにその運動によって、逆説的にも、エクリチュールがロゴス自身の他者として、ロゴスとしての学のリミットとして、いやましに突出してくるという、そうした時代にほかならない。
このように取り出された時代性のもとで、グラマトロジーの課題とは、文字の現象学や実証科学を打ち立てることでもなければ、音声言語に対する文字言語の復権を唱えることでさえもない。問題になるのは、エクリチュールを音声へ還元可能とみなすロゴス中心主義的な機制そのものがエクリチュールという他者への依存によって可能になっている構造を分析すること、そしてロゴスに還元不可能なこの他者を通して当の機制がみずからを解体し開放するに任せるよう、この構造のロジックを内側からたどり直してみることなのである。このときエクリチュールとは、厳密に言って、経験的に知られる文字(紙のうえに知覚されるインクの染みの連なり)のことではなく、音声化不可能なかぎりでのロゴスの他者、窮極的にはロゴスとしての学一般を破綻させる他者として否定的に指し示される名のことである。グラマトロジーは、まさしくそのようなエクリチュール=他者を「学の対象」として思考するという、それ自体不可能な試みとして名指されているわけだ。
以上が本書の「理論的マトリックス」とデリダが呼ぶものの要約である。もちろんこれだけでは抽象的な図式でしかない。本書──というよりデリダのどの著作をとってもそうなのだが——の醍醐味は、こうした図式が事前に用意された結論として適用されるのではなく、そこでデリダが実際に展開する読解の過程、すなわち、歴史的に規定された諸々のテクストの布置関係を標定しながら、問題となるテクストの各々を、非常に緻密かつ繊細な読解によって解きほぐしてゆく過程にある。「テクスト外なるものはない」──これは本書のなかの有名な一文だが、しばしば誤解されるように、テクスト外的な現実を無視して、図書館や書斎に堆く積まれたテクストの内に埋没することを推奨しているわけではない。それが言い表しているのは、まさにそのような「外的現実」が(コン)テクストの網目に搦めとられた産物でしかないこと、(コン)テクストの関係性のなかで格闘することを通じてしかそうした「外部」に遭遇できないということである。テクストを前にした弛まぬ読解の経験のみが、テクストの外、というより《外としてのテクスト》に到達する唯一の方途であることを、この一文は、デリダの厳格な方法論的仮説として断言しているのである。
では、先の「理論的マトリックス」は、本書においていかなる読解の経験として繰り広げられているのか。デリダが扱うテクストは、西洋形而上学の歴史全体を視野に入れた、きわめて広い範囲に及んでいるが、なかでもソシュールとルソーについての読解は質量ともに際立っており、重要である。以下では、両者に対するデリダの議論を再構成することで、本書の読解の内実を一瞥することにしよう。
1. ソシュールの『一般言語学講義』は、二〇世紀の構造主義の展開の端緒となった記念碑的なテクストである。デリダがそれを読むなかで第一に問い質しているのは、ソシュールがエクリチュールとパロールとのあいだに設定した「自然的な」関係である。ソシュールによれば、言語(ラング)とエクリチュールとは別次元に存しているが、後者は前者との「自然的な紐帯」につながれた代理物、前者の表象=再現像にすぎない。したがって言語学の対象は、エクリチュールから分離された「話された語」であるとされる(序説・第六章)。ここに認められるのは、エクリチュールが表音文字として過不足なく音声言語を写しとることができるという文字の表音化の自明視である。デリダにとってこれは西洋形而上学の伝統を無批判に反復している症候的な身ぶりなのだが、ソシュールの側からすれば、言語学を科学として打ち立てるために必要な前提であり、それが実際、ヤコブソン等へと引き継がれる言語学の音韻論主義に道を拓くことができたのであった。
ソシュールが表音文字の可能性を自明視しているからといって、デリダはそれを頭ごなしに非難するわけではない。デリダの読解が綿密に分析しているのは、その自明性を問いに付す反対の認識、つまり表音文字へと還元可能なエクリチュールは現実には存在しないという認識を、ソシュールのテクスト自身がもたらしているのだということである。
というのも、他方で「記号の恣意性」というソシュールの有名なテーゼから引き出される帰結のひとつは、パロールとエクリチュールとの関係が本質的に慣習=規約的なものだということであり、このテーゼが「文字が音声言語の像であることを禁止する」からである。音そのものが定義上可視的な外観を持たないのは言うまでもないが、ソシュールが自然のしるしとしての象徴を、言語学の対象としての記号から峻別したのは、記号の本質が外的な事物を何らかのかたちで反映した像では《ない》点に存するのだということを、ソシュールは知っていたからである。実際、表音文字が音素を指示するのは、それが音声的質料を可視的ないし象徴的に模倣しているからではなく、表音文字そのものを成立させている言語体系全体の網目の内部で、当の音の現象的形式を分節するからにすぎない(だからこそ言語体系が変われば、rとlの子音の判別が日本語の表音体系では不可能であるといった事態が生じることになる)。これは「記号の恣意性」の一例であるが、こうした理由から、エクリチュールとは言語体系を写しとる外在的な表象(自然な象徴)であるというソシュールの先の定義(序説・第六章)を、まさに「記号の恣意性」の名目のもとに斥けなければならないのである。
このときソシュールの言語学にとって重要なのは、質料的実体としての音声でも文字でもなく、それらをシニフィアン(意味するもの)の形式として分節する言語体系の全体である。よく知られるように、それは「積極的辞項なき諸差異しかない」と言われる純粋に示差的な体系にすぎず、もはや「自然的な紐帯」を決定的に欠いている(ゆえに恣意的である)。だが、こうした諸差異は何によってもたらされたのか。示差的な言語形式を産出する発生論的契機としてデリダが新たに名指すもの、それこそ「制定された痕跡」であり、言語の体系そのものを内的に構成するエクリチュール、「原(アルシ)エクリチュール」と呼ばれるものである。しかしそれはたんなる差異の発生の起源ではありえない。記号が恣意的であるかぎり、その起源=根源そのものへの遡行はあらかじめ禁じられている。そこで「痕跡」と言われるのは、もはや失われた根源の名残りとして、それ自体は自然的で実体的な核を持たないことが定義上含意されているからだ(痕跡の亡霊性)。したがって「痕跡」ないし「原エクリチュール」は、根源たりえないにもかかわらず、逆説的にも、示差的な体系の形式を付与しうるものとみなされた疑似-根源的なものの名であるだろう。
結論としてデリダのソシュール読解が主張するのは、一見文字言語の排除と音声言語の優位のもとに規定された言語学の対象が、まさにその中心テーゼたる「恣意性」ゆえに、当の言語形式を形成する契機としてのエクリチュールによって限界づけられているということである。
2. ルソーの名は、本書にとって前述の「現前の形而上学」に支配された歴史的エポックを検証するうえで、もうひとつの範例的な形象である。第二部では、ソシュールと並ぶ構造主義の始祖たるレヴィ=ストロースのルソー主義を経由して、『言語起源論』を中心としたルソーの著作についての包括的な読解が試みられている。
デリダのルソー読解が一貫して追究しているのは、ルソーのテクストにおける「代補(supplément)の論理」である。この「代補」は、たんにパロールとエクリチュールのあいだの代理=補足関係というだけではなく、より一般に、内部と外部の反転関係・相互依存関係、および両者を分かつ区別の決定不可能性として理解することができる。デリダの議論は、おおよそ次のようなものだ。
一方で、ルソーは直接的現前への欲望を《明言する》。直接的な現前としてルソーが欲しているのは、生命、自然、経験、情念、自己、起源といった本来的なものの現前である。これを固有で内的なものへの欲望とみなそう。この現前性は、言語に関しては、思考を直接に表現するパロールの充実性として追求される。このときエクリチュールとは、やはりパロールの充実性を掻き乱しにやってくる悪である。つまりソシュールの場合と同様、ルソーにとってもエクリチュールはパロールに対する外的な付加物として規定される。エクリチュールは、パロールにとって脅威であり、追放すべきものである。
他方、ルソーは直接的現前の欲望を明言するのと同じ身ぶりによって、当の現前の喪失を《記述する》。直接的な現前への欲望を語ろうとすればするほど、またその語りを劇的なものにしようとすればするほど、ルソーは、当の現前性が《どれほどまでに欠如していたか》ということを反面で強調せざるをえない。すなわち、パロールの充実性を達成し、この達成の語りを成就するためには、その分だけ効果的に、パロールの充実性はエクリチュールの外在性によってすでに毀損されていたことを示す必要が生じるのである。逆に言えば、そうした外的な脅威がなければ、諸々の直接的現前を欲望する必要すら生じなくなるだろう。この脅威が強大であればあるほど、充実性や現前性への欲望は切迫したものとなる。
もしエクリチュールが《たんに》外面的で副次的な付加物《にすぎず》、それ以上のものではないとすれば、はじめからパロールの充実性、内なるものの現前性を脅かすようなものですらなかったはずだ。実のところ、直接的な現前への欲望が生じるのは、内的なものの直接性や純粋性が、外的なもの(エクリチュール)によってアプリオリに汚染されているかぎりでのことである。つまり〈外部〉は単純に外的であるのではなく、構造上〈内部〉との関係を必然的にとり結び、内的なものを欲するための可能性の条件となっているのである。この点で、現前性への欲望を《明言》するルソーは、まさにその同じ身ぶりによって、その欲望があらかじめ断念されたものとして当の現前を《記述》せざるをえないのだ。
ルソーが明言していること(内部への欲望)は、ルソーが語ろうと望むこと以上のもの(この欲望を可能にする外部への依存)をつねに記述しているのだということ。こうした「明言」と「記述」の齟齬をデリダはルソーのテクストに即して丹念に追跡する。結果「代補の論理」として抽出されるのは、一見派生的で皮相にみえる〈外部〉がつねに〈内部〉との関係のうちにあるということ、そればかりでなく、この〈外部〉が〈内部〉の積極的な構成要素となっているということである。エクリチュールはパロールに外から付加されることによって逆説的にもパロールを駆動する力となる。それは「根源的代補」と呼ばれるだろう。このとき内部と外部との対立関係・ヒエラルキーは本質的に反転可能であり、その境界線は一義的に決定不可能である。かくしてデリダは、ルソーにおける「明言」と「記述」の齟齬、そしてそこに作用する「代補の論理」こそが、ルソーのテクストを紡ぎ出す一種の組成原理であることを突き止めるのである。
プラトンから構造主義に至るまで、文字言語に対する音声言語の支配(外部の内化作用)によってロゴスの主導権を確保しようとするまさにその運動が、かえってロゴスの他者としてのエクリチュールの解消不可能性を浮き彫りにし始めるという西洋形而上学の歴史的エポックを、デリダは「ルソーの時代」とも呼んだ。前述の「代補の論理」を通してデリダが企てているのは、外部が内化される作用を限りなく逆撫ですることで内部の内部に外部の名を書き込み、この内部/外部のトポロジー的な反転関係を通していわば「絶対的な外」を呼び込むという可能性を、「ルソーの時代」という歴史的な条件のもとで最大限押し開いてみることである。本書のこうした企図は、一般に「脱構築」と呼ばれるものの形式をなしており、この形式の射程の広さ、汎用性の高さは、本書が文学テクストの読解方法論として受容され(とりわけ七〇年代末以降の英語圏で)「脱構築批評」と呼ばれる流派を生み出すほどまで影響力を持つに至ったという事実によって裏付けられるだろう。この点で本書は、デリダが構造主義以降の哲学者として「脱構築」の思考を確立した決定的な著作であるということにいまだ変わりはない。
最後に、本書の初出稿が発表されてほぼ四十年が経とうとする現在から振り返ってみると、付記すべき点がいくつかある。デリダは後年の著作でも「脱構築」の企図を一貫して堅持し展開してきたと言えるが、本書の明示的な主題である「グラマトロジー」のモチーフについては、文字通りには放棄したことが分かる(私見では七八年のウォーバートン論「スクリブル」が最後だ)。その理由を推測するならば、一方で、本書のルソー読解に対するポール・ド・マンの厳しい批判(本書がルソーのテクストを「現前の形而上学」の枠内での範例的身分に縮減している点への批判)があったことが指摘されなければならないだろう。とはいえこの放棄に、デリダ自身の挫折や蹉跌の兆候を見てとるのは短絡的にすぎる。他方で強調されなければならないのは、はじめに述べたように、グラマトロジーがあらかじめ不可能な「学」として、ロゴスのリミットたる他者として構想されていたことである。脱構築という企図を一貫させるならば、ロゴス中心主義批判の帰結という意味で、デリダが文字(グラム)の学(ロゴス)としてはグラマトロジーに固執しなくなったことはむしろ当然であるとさえ言えよう。
しかしデリダ本人の関心とは別に、いまやグラマトロジーをめぐる一般的な状況は四十年前に比べると非常に大きな変化が生じているように思われる。当時すでにデリダは、サイバネティクスの問題が自然と生命の領域をエクリチュールの諸技術によって包括しつつあることを指摘していたが、今日では、たとえば携帯電話などの情報端末やインターネットなどの遠隔通信網が爆発的な発展と浸透を遂げているといった事象に見られるように、デジタルデータ化された文字情報がいっそう根本的な仕方でわれわれの身近な生活世界を規定しつつあることには疑いがない。エクリチュールを支えるこうした技術的な諸条件の一般的な変化は、パロールとエクリチュールの関係を分析するにあたって、旧来の理論的前提を量的にも質的にも希薄化させつつあるように見えるのだ。こうした視点からすれば、グラマトロジーを更新すべく、現在における「ルソーの時代」の相貌を描き直してみることは確かに興味深い作業となるだろう。もちろん本書の枠組みに照らして、この種の変化がどれほど変化と呼ぶに値するものなのかはそれ自体検討の余地がある。だが、新たなるグラマトロジーがロゴスの他者としてエクリチュールの可能性をこれまでになく解き放つものであるのか、あるいはその可能性をますます縮減し「現前の形而上学」のうちに幽閉してしまうものであるのか──その答えはデリダによっても、他の誰によってもいまだ与えられてはいないのである。
初出:「デリダ『グラマトロジーについて』解説」『現代思想』第32巻・第11号(2004年9月臨時増刊「ブックガイド60」)210-3頁。※本稿は、字数制限で一部割愛する以前のヴァージョンであり、掲載された版とは異なる。